28日(月)。時の流れは速いもので2月も今日で終わり、明日から弥生3月です 月末を迎えたので恒例により2月の3つの目標の実績をご報告します
月末を迎えたので恒例により2月の3つの目標の実績をご報告します ①クラシック・コンサート:13回(今夜の公演を含む)、②映画鑑賞:0回、③読書:7冊でした
①クラシック・コンサート:13回(今夜の公演を含む)、②映画鑑賞:0回、③読書:7冊でした ただし、②についてはNetflixで「父さんのヴァイオリン」「ウィンター・オン・ファイアー ウクライナ自由への闘い」「囚われた国家」の3本を観ました
ただし、②についてはNetflixで「父さんのヴァイオリン」「ウィンター・オン・ファイアー ウクライナ自由への闘い」「囚われた国家」の3本を観ました いずれにしても、個人的な映画館離れが続いています
いずれにしても、個人的な映画館離れが続いています
ということで、わが家に来てから今日で2606日目を迎え、北朝鮮は27日午前7時51分頃、北朝鮮の西岸付近から少なくとも1発の弾道ミサイルを東方向に発射した というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ウクライナばかりに目を向けてないで こっち向いて!という米国へのメッセージだ





池上彰 ✕ 佐藤優 共著「真説 日本左翼史 戦後左派の源流 1945~1960」(講談社現代新書)を読み終わりました 池上彰は1950年、長野県松本市生まれ。ジャーナリスト。慶應義塾大学卒業後、1973年にNHK入局。報道記者として活躍後、1989年に記者キャスターに起用され、1994年から11年にわたり「週刊こどもニュース」のお父さん役として活躍。2005年からフリーになり執筆活動を続けながら、テレビ番組等でニュースを分かりやすく解説し、幅広い人気を博す
池上彰は1950年、長野県松本市生まれ。ジャーナリスト。慶應義塾大学卒業後、1973年にNHK入局。報道記者として活躍後、1989年に記者キャスターに起用され、1994年から11年にわたり「週刊こどもニュース」のお父さん役として活躍。2005年からフリーになり執筆活動を続けながら、テレビ番組等でニュースを分かりやすく解説し、幅広い人気を博す 著書多数。一方、佐藤優は1960年、東京都生まれ。作家。元外務省主任分析官。1985年、同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省入省。在ロシア日本国大使館勤務などを経て、本省国際情報局分析第1課に所属。主任分析官として対ロシア外交の分野で活躍した。2005年に「国家の罠ー外務省のラスプーチンと呼ばれて」で鮮烈な作家デビューを飾る、著書多数
著書多数。一方、佐藤優は1960年、東京都生まれ。作家。元外務省主任分析官。1985年、同志社大学大学院神学研究科修了後、外務省入省。在ロシア日本国大使館勤務などを経て、本省国際情報局分析第1課に所属。主任分析官として対ロシア外交の分野で活躍した。2005年に「国家の罠ー外務省のラスプーチンと呼ばれて」で鮮烈な作家デビューを飾る、著書多数

池上氏は「はじめに」の中で、概要次のように書いています
「『社会主義と共産主義って、何が違うのか?』『右翼と左翼って、何?』と若い人からよく聞かれる ソ連崩壊から30年、ソ連のことを知らない人が増えているのも当然かもしれない
ソ連崩壊から30年、ソ連のことを知らない人が増えているのも当然かもしれない 2021年は中国共産党創設100周年、2022年は日本共産党創設100周年に当たる
2021年は中国共産党創設100周年、2022年は日本共産党創設100周年に当たる 中国共産党は、過去の自らの失敗を糊塗して、輝かしい歴史を偽造している
中国共産党は、過去の自らの失敗を糊塗して、輝かしい歴史を偽造している 日本共産党はどうか? 過去を正しく直視することが出来ているのか? そう思っているところに佐藤優氏から『日本でも社会主義が再評価されようとしている。ここで日本の左翼の歴史を振り返って、過去の功罪を再検討してみようではないか』と提案があった
日本共産党はどうか? 過去を正しく直視することが出来ているのか? そう思っているところに佐藤優氏から『日本でも社会主義が再評価されようとしている。ここで日本の左翼の歴史を振り返って、過去の功罪を再検討してみようではないか』と提案があった 本書では、第二次世界大戦後、1945年から1960年までの左翼運動の歴史を日本社会党と共産党の動向を柱に論じた
本書では、第二次世界大戦後、1945年から1960年までの左翼運動の歴史を日本社会党と共産党の動向を柱に論じた 」
」
本書は次の5つの章から構成されています
序 章「『左翼史』を学ぶ意義」
議論の準備①左翼とは何か?
議論の準備②共産党とは?社会党とは?
第1章「戦後左派の巨人たち」(1945~1946年)
第2章「左派の躍進を支持した占領統治下の日本」(1946~1950年)
第3章「社会党の拡大・分裂と『スターリン批判』の衝撃」(1951~1959年)
第4章「『新左翼』誕生への道程」(1960年~)
上記の通り、かなり広範囲に及ぶので、ここでは私が個人的に参考になった点(「左翼の定義」「共産党と社会党の違い」「書記長の位置づけ」など)についてご紹介しようと思います
「議論の準備①左翼とは何か?」の中で、佐藤氏は「左翼」の定義について次のように解説しています
「左翼はきわめて近代的な概念です。もともと左翼・右翼の語源は、フランス革命時の議会において、議長席から見て左側の席に急進派、右側に保守派が陣取っていた故事に由来します この左翼、つまり急進的に世の中を変えようと考える人たちの特徴は、まず何よりも理性を重視する姿勢にあります。(中略) 一方で右翼(保守派)の特徴は,、理性を認めないわけではないが、人間の理性は不完全なものだと考えている。左翼のように無闇にラディカルな改革を推し進めるのではなく、漸進的に社会を変えていこうと考えるのが本来の右翼です
この左翼、つまり急進的に世の中を変えようと考える人たちの特徴は、まず何よりも理性を重視する姿勢にあります。(中略) 一方で右翼(保守派)の特徴は,、理性を認めないわけではないが、人間の理性は不完全なものだと考えている。左翼のように無闇にラディカルな改革を推し進めるのではなく、漸進的に社会を変えていこうと考えるのが本来の右翼です 」
」
「議論の準備②共産党とは?社会党とは?」の中で、池上氏は次のように解説しています
「日本共産党は、日本で初めてマルクス・エンゲルスの『共産党宣言』を翻訳した堺利彦ら8人の社会主義者たちが、ロシア革命のような社会主義革命を日本でも実現するために結成したもので、私有財産制度を否定し君主制(天皇制)の廃止を掲げる共産党の主張は当時の日本政府にとって容認できないものだった 現在は合法政党となり全国に約27万人の党員を抱え、衆議院と参議院に議席を有しているが、現在も革命政党であることを綱領で謳っていることは変わっていない
現在は合法政党となり全国に約27万人の党員を抱え、衆議院と参議院に議席を有しているが、現在も革命政党であることを綱領で謳っていることは変わっていない 一方、日本社会党は戦時中に息を潜めていた非・共産党系の労働運動家や無産政党たちが戦後まもなく大同団結してできた政党だった
一方、日本社会党は戦時中に息を潜めていた非・共産党系の労働運動家や無産政党たちが戦後まもなく大同団結してできた政党だった ただ、この政党は国家観や社会観にかなりのバラつきがあった。左派は共産党とは違う方法論を志向していたものの、マルクス主義的な社会主義革命の実現を目指している点では同じで、多くは天皇制にも否定的な考えを持っていたのに対して、右派は反共産主義的な考え方を持つ人が多かった
ただ、この政党は国家観や社会観にかなりのバラつきがあった。左派は共産党とは違う方法論を志向していたものの、マルクス主義的な社会主義革命の実現を目指している点では同じで、多くは天皇制にも否定的な考えを持っていたのに対して、右派は反共産主義的な考え方を持つ人が多かった このため、右派と左派に分裂したり再統一したりを繰り返した。1996年に社民党(社会民主党)に党名を変更して現在も存続しているが、党員は1万454人(2019年現在)に過ぎない
このため、右派と左派に分裂したり再統一したりを繰り返した。1996年に社民党(社会民主党)に党名を変更して現在も存続しているが、党員は1万454人(2019年現在)に過ぎない 」
」
上記の解説について、佐藤氏は次のように補足説明を加えています
「現在の共産党は日本がまだ民主主義革命の途上、つまり一段階目であるという理由で主張を抑えているので革命政党であるという本質は見えづらくなっているが、彼らの究極的な目標が共産主義社会の実現であることは揺るがない 党の上から下まで、右から左までが一丸となって体制転覆を目指している政党は国会の中で共産党以外に存在したことはない
党の上から下まで、右から左までが一丸となって体制転覆を目指している政党は国会の中で共産党以外に存在したことはない 」
」
第1章「戦後左派の巨人たち」の中で、日本の左翼たちがGHQをどのような存在であると捉えていたかについて、池上氏は次のように解説しています
「(日本の敗戦を受け)1945年10月10日に徳田球一や志賀義雄などの戦前からの共産党幹部が一斉に釈放されているが、徳田と志賀はまもなく釈放されると知らされた10月4日に『人民に訴う』と題した出獄声明文を書き上げた この中で、『ファシズム及び軍国主義からの世界解放のための連合国軍隊の日本進駐によって、日本における民主主義革命の端緒が開かれたことに対し、われわれは深甚ある感謝の意を表する
この中で、『ファシズム及び軍国主義からの世界解放のための連合国軍隊の日本進駐によって、日本における民主主義革命の端緒が開かれたことに対し、われわれは深甚ある感謝の意を表する 米英及び連合諸国の平和政策に対してわれわれは積極的にこれを支持する』などと書いた
米英及び連合諸国の平和政策に対してわれわれは積極的にこれを支持する』などと書いた つまり、占領軍であるアメリカ軍を『解放軍』と規定してしまった。このアメリカへの追随ともいえる『解放軍規定』に対しては、当時でさえ『東京大空襲や広島・長崎への原爆投下で罪なき人民を虐殺したアメリカ軍を解放軍とはなにごとだ』という批判が党の内外から上がった
つまり、占領軍であるアメリカ軍を『解放軍』と規定してしまった。このアメリカへの追随ともいえる『解放軍規定』に対しては、当時でさえ『東京大空襲や広島・長崎への原爆投下で罪なき人民を虐殺したアメリカ軍を解放軍とはなにごとだ』という批判が党の内外から上がった 」
」
これは初めて知りました。自分たちはアメリカのお陰で釈放されたのだという感謝の気持ちが大きかったのだと思います 「アメリカの追随を止めろ
「アメリカの追随を止めろ 」と主張している現在の共産党からは想像ができません
」と主張している現在の共産党からは想像ができません
第2章「左派の躍進を支持した占領統治下の日本」の中で「ソ連ではなぜ国のトップが『書記長』だったのか」について池上氏は次のように解説しています
「ソ連共産党に書記局が作られたのは、もともとは初代の最高指導者であるレーニンを補佐する事務局としてであり、スターリンはその部署のトップだった 一般の会社で言うと総務部長のようなものだろう。しかし、現代の企業の総務部がそうであるように、ソ連共産党の書記局には人事に関する情報や党内のトラブルまであらゆる情報が集中した
一般の会社で言うと総務部長のようなものだろう。しかし、現代の企業の総務部がそうであるように、ソ連共産党の書記局には人事に関する情報や党内のトラブルまであらゆる情報が集中した スターリンはその情報を駆使することで党内をのし上がっていった。1922年にレーニンが脳梗塞で倒れた時も、レーニンへの連絡役を務めたのは事務方のトップのスターリンだった。この時スターリンはレーニンに対し徹底的に自分の都合の良い情報ばかりを吹き込む一方、党内のほかの実力者たちに対しては『レーニンの指示である』という体裁を取りながら自分の好きなように異動・左遷・粛清していった
スターリンはその情報を駆使することで党内をのし上がっていった。1922年にレーニンが脳梗塞で倒れた時も、レーニンへの連絡役を務めたのは事務方のトップのスターリンだった。この時スターリンはレーニンに対し徹底的に自分の都合の良い情報ばかりを吹き込む一方、党内のほかの実力者たちに対しては『レーニンの指示である』という体裁を取りながら自分の好きなように異動・左遷・粛清していった その結果としてスターリンはレーニンの後継者となり、スターリンの肩書である書記長もまた、共産党の最高指導者を指す言葉として定着していった
その結果としてスターリンはレーニンの後継者となり、スターリンの肩書である書記長もまた、共産党の最高指導者を指す言葉として定着していった 」
」
北朝鮮では国のトップである金正恩の肩書が「朝鮮労働党総書記」となっていますが、同じような考えですね
さて、この調子で紹介していったらきりがないので、「おわりに」の中で佐藤氏が書いていることを要約して終わりにしたいと思います
「本書はコロナ禍後の日本社会を強く意識して作られた コロナ禍後、格差が拡大する。それには2つの要因がある。1つ目は、従来の日本の経済・社会構造に起因する。格差の構造も重層的だ。階級間での格差が拡大する。特に非正規労働者のように構造的に弱い立場に置かれた人々は、賃金も低く、解雇されやすい
コロナ禍後、格差が拡大する。それには2つの要因がある。1つ目は、従来の日本の経済・社会構造に起因する。格差の構造も重層的だ。階級間での格差が拡大する。特に非正規労働者のように構造的に弱い立場に置かれた人々は、賃金も低く、解雇されやすい 地域間の格差も拡大する。富が東京に集中する傾向は今後、一層拡大するだろう。東京は富裕層と中間階級上層(世帯所得が2000万円以上)の人々と、人でなくてはできない仕事に従事するエッセンシャルワーカーや低賃金のサービス業に従事する人々に二極化していくだろう
地域間の格差も拡大する。富が東京に集中する傾向は今後、一層拡大するだろう。東京は富裕層と中間階級上層(世帯所得が2000万円以上)の人々と、人でなくてはできない仕事に従事するエッセンシャルワーカーや低賃金のサービス業に従事する人々に二極化していくだろう 2つ目の要因は、デジタル化の加速だ。AI(人工知能)はすでにビジネスに活用されているが、それが急速に広がり、現在 事務職のビジネスパーソンが従事していた経理、審査、営業などの人員が大幅に削減される。かつてホワイトカラーと呼ばれていた階層が解体され、そのうちごく一部の高度な専門知識もしくは管理能力を持つ人々が中間階級上層になり、大部分は低賃金のエッセンシャルワーカーかサービスに移動せざるを得なくなる
2つ目の要因は、デジタル化の加速だ。AI(人工知能)はすでにビジネスに活用されているが、それが急速に広がり、現在 事務職のビジネスパーソンが従事していた経理、審査、営業などの人員が大幅に削減される。かつてホワイトカラーと呼ばれていた階層が解体され、そのうちごく一部の高度な専門知識もしくは管理能力を持つ人々が中間階級上層になり、大部分は低賃金のエッセンシャルワーカーかサービスに移動せざるを得なくなる 同じ人間なのに産まれた家庭の経済力の差によって、子供たちの持つ可能性が異なってくる
同じ人間なのに産まれた家庭の経済力の差によって、子供たちの持つ可能性が異なってくる 社会主義という言葉が、ヨーロッパのみならず伝統的に社会主義に対する抵抗感の強い米国においても、最近頻繁に用いられるようになっている
社会主義という言葉が、ヨーロッパのみならず伝統的に社会主義に対する抵抗感の強い米国においても、最近頻繁に用いられるようになっている 日本でも近未来に社会主義の価値が、肯定的文脈で見直されると思う。その際に重要なのは、歴史に学び、過去の過ちを繰り返さないように努力することだ
日本でも近未来に社会主義の価値が、肯定的文脈で見直されると思う。その際に重要なのは、歴史に学び、過去の過ちを繰り返さないように努力することだ 日本における社会主義の歴史を捉える場合、共産党、社会党、新左翼の全体に目配りをして、その功罪を明らかにすることが重要だと考える
日本における社会主義の歴史を捉える場合、共産党、社会党、新左翼の全体に目配りをして、その功罪を明らかにすることが重要だと考える 」
」
「遇者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」と言ったのはビスマルクでしたが、現代における「格差問題」を考える上でも日本の「左翼」の歴史を正しく理解しておきたいと思います 本書はその手引きとなります
本書はその手引きとなります














 」
」 」
」
 1977年にレニングラード音楽院を卒業し、テミルカーノフの助手としてキーロフ劇場(現マリインスキー劇場)の指揮者となり、1988年同劇場の芸術監督に就任しました
1977年にレニングラード音楽院を卒業し、テミルカーノフの助手としてキーロフ劇場(現マリインスキー劇場)の指揮者となり、1988年同劇場の芸術監督に就任しました また、N響、読響、都響、日本フィル、東響などの在京オケをはじめ、バーンスタインが創設したPMFオーケストラを指揮しています
また、N響、読響、都響、日本フィル、東響などの在京オケをはじめ、バーンスタインが創設したPMFオーケストラを指揮しています



 私にとって最高の組み合わせプログラムです
私にとって最高の組み合わせプログラムです




 中盤で須田祥子のヴィオラ独奏で演奏された 哀愁を帯びた牧童の歌が 静かに染み渡りました
中盤で須田祥子のヴィオラ独奏で演奏された 哀愁を帯びた牧童の歌が 静かに染み渡りました この曲は指揮者にとっても演奏家にとっても「非常に困難な曲」であると同時に「都合の良い曲」ではないかと思います
この曲は指揮者にとっても演奏家にとっても「非常に困難な曲」であると同時に「都合の良い曲」ではないかと思います 実際、この日の公演もどこかで崩壊していたのかもしれません
実際、この日の公演もどこかで崩壊していたのかもしれません 第4機動隊出動
第4機動隊出動


 第3楽章ではホルン・セクションとチェロ・セクションの渾身の演奏が光りました
第3楽章ではホルン・セクションとチェロ・セクションの渾身の演奏が光りました 第4楽章は不思議な音楽です
第4楽章は不思議な音楽です この意味は何なのか? それまでの演奏を否定するかのようです
この意味は何なのか? それまでの演奏を否定するかのようです 何をそんなに急ぐのか、と言いたくなるような終わり方です。実に不思議な楽章です
何をそんなに急ぐのか、と言いたくなるような終わり方です。実に不思議な楽章です 何度かのカーテンコールのあと、井上は拍手を制して、「ショスタコーヴィチは19歳でこの曲を書いた。凄いことです
何度かのカーテンコールのあと、井上は拍手を制して、「ショスタコーヴィチは19歳でこの曲を書いた。凄いことです 井上道義がステージの上で倒れたのは、1999年9月30日にすみだトリフォニーホールで新日本フィルを指揮したマーラー「交響曲第1番」の第1楽章冒頭近くでの転倒以来、22~3年ぶりではないか
井上道義がステージの上で倒れたのは、1999年9月30日にすみだトリフォニーホールで新日本フィルを指揮したマーラー「交響曲第1番」の第1楽章冒頭近くでの転倒以来、22~3年ぶりではないか










 教え方が巧い講師のところには多くの学生が集まります。それにより給料が上がり生活が安定します(するはずです)
教え方が巧い講師のところには多くの学生が集まります。それにより給料が上がり生活が安定します(するはずです) 彼は格差拡大の原因を、1つの式で表している。それは『r > g』。つまり『資本収益率 > 経済成長率』。おおざっぱに説明すれば、『財産持ちの不労所得(利潤、利子、配当、賃料、株の売買益など)の方が、国民が働いて得た収入よりにかなり大きい』ということだ。21世紀は世界的に経済成長が鈍化しつつある時代だ
彼は格差拡大の原因を、1つの式で表している。それは『r > g』。つまり『資本収益率 > 経済成長率』。おおざっぱに説明すれば、『財産持ちの不労所得(利潤、利子、配当、賃料、株の売買益など)の方が、国民が働いて得た収入よりにかなり大きい』ということだ。21世紀は世界的に経済成長が鈍化しつつある時代だ )。1回目と2回目は大手町の自衛隊・大規模摂取会場でしたが、今回は豊島区のHPから予約を入れて近所の旧A中学校が取れたので近くて良かったです
)。1回目と2回目は大手町の自衛隊・大規模摂取会場でしたが、今回は豊島区のHPから予約を入れて近所の旧A中学校が取れたので近くて良かったです 今朝はまだ37.6度あるので今日は大人しく寝ていようと思います
今朝はまだ37.6度あるので今日は大人しく寝ていようと思います



 しかし、長男レイフ(ジョナサン・メジャース)と次男ガブリエル(アシュトン・サンダース)は生き残った。時は流れ2027年、地球は以前としてエイリアンたちの統治下にあり、体制に反抗的な人間は容赦なく殺されていた。それでも、エイリアンの強権的な支配に対抗すべく、レジスタンスを結成する人々もいたが、エイリアンたちは地下空間のどこかに隠れており、彼らの居場所を突き止めることも困難だった
しかし、長男レイフ(ジョナサン・メジャース)と次男ガブリエル(アシュトン・サンダース)は生き残った。時は流れ2027年、地球は以前としてエイリアンたちの統治下にあり、体制に反抗的な人間は容赦なく殺されていた。それでも、エイリアンの強権的な支配に対抗すべく、レジスタンスを結成する人々もいたが、エイリアンたちは地下空間のどこかに隠れており、彼らの居場所を突き止めることも困難だった
 」と思ったはずです。「 『24年の次期大統領選も視野に』ということでは、アメリカのバイデン大統領も同じ立場ではないか」と
」と思ったはずです。「 『24年の次期大統領選も視野に』ということでは、アメリカのバイデン大統領も同じ立場ではないか」と もしそうだとしたら、とんでもないことです
もしそうだとしたら、とんでもないことです いずれにしても、武力によって独立国家を脅かすのは許されない行為で、犠牲になるのは”普通の生活”を送っているウクライナ国民です
いずれにしても、武力によって独立国家を脅かすのは許されない行為で、犠牲になるのは”普通の生活”を送っているウクライナ国民です






 」と説得しますが、彼は起きる気配はありません
」と説得しますが、彼は起きる気配はありません 福川伸陽(N響)と藤田麻理絵(新日本フィル)のナチュラル・ホルンの演奏も素晴らしかったです
福川伸陽(N響)と藤田麻理絵(新日本フィル)のナチュラル・ホルンの演奏も素晴らしかったです


 それによると、前日のリハーサル終了後、夜9時半ごろ半田さんから電話が入り、急な胃腸炎のため出演できなくなったとの話があった
それによると、前日のリハーサル終了後、夜9時半ごろ半田さんから電話が入り、急な胃腸炎のため出演できなくなったとの話があった


 彼女は歌い終わると一旦引き上げ、渾身の管弦楽の演奏が続きます。すると今度はパイプオルガンの下手に小林が現れ、オケと共にフィナーレに向かいます
彼女は歌い終わると一旦引き上げ、渾身の管弦楽の演奏が続きます。すると今度はパイプオルガンの下手に小林が現れ、オケと共にフィナーレに向かいます


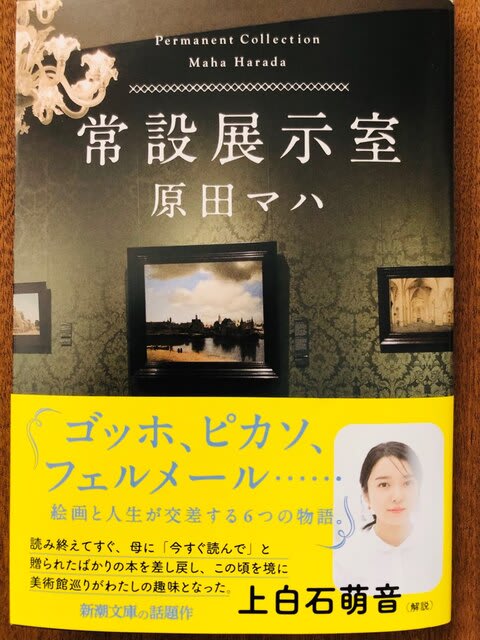
 そこへフランス語ペラペラの中年男性・御手洗が現れ、この色紙をネタになぜか多恵子に思わせぶりな態度を見せます
そこへフランス語ペラペラの中年男性・御手洗が現れ、この色紙をネタになぜか多恵子に思わせぶりな態度を見せます 1週間後、パスポートを受け取りに来た御手洗に誘われ一夜を共にします。パスポートがあるので身元はしっかりしているし、話によると親から受け継いだ有名な画家の絵を売ったお金で優雅に暮らしているということで、すっかり信じ込んでいました
1週間後、パスポートを受け取りに来た御手洗に誘われ一夜を共にします。パスポートがあるので身元はしっかりしているし、話によると親から受け継いだ有名な画家の絵を売ったお金で優雅に暮らしているということで、すっかり信じ込んでいました 「一芸に秀でる者は何とか」と言いますが、まさにマルチタレントと言えるかもしれません
「一芸に秀でる者は何とか」と言いますが、まさにマルチタレントと言えるかもしれません

 これからもよろしくお願い申し上げます
これからもよろしくお願い申し上げます



