29日(月)。わが家に来てから519日目を迎え、「2月も今日で終わりだねぇ 」と白ウサちゃんに声を掛けるモコタロです
」と白ウサちゃんに声を掛けるモコタロです

白ウサちゃん、君はいつもムクチだねぇ 六口・・・口が六つあるってか

 閑話休題
閑話休題 

昨日、ラ・フォル・ジュルネのチケットを追加で4枚買いました 新宿伊勢丹会館内のチケットぴあで買ったのは次の4公演です
新宿伊勢丹会館内のチケットぴあで買ったのは次の4公演です
①5月3日午前11:45~ ホールB7 公演番号122 シンフォニア・ヴァルソヴィア。シュターミッツ「交響曲ニ長調」他。
②5月3日午後3:30~ ホールC 公演番号144 新日本フィル。グローフェ「グランドキャニオン」。
③5月4日午後3:15~ ホールC 公演番号244 カンマー・アカデミー・ポツダム。ヘンデル「水上の音楽」。
④5月5日午後1:45~ ホールC 公演番号343 桐朋学園オケ。レスピーギ「ローマの松」他。
一番欲しかったのは4日午後5:15からの公演番号225(アンヌ・ケフェレック他。ベートーヴェン「スプリング・ソナタ」、ブラームス「雨の歌」)だったのですが、予想どおり売り切れでした
これで3日=5公演、4日=4公演、5日=5公演の合計14公演になりました。今年はもうこれでいいかなと思います

 も一度、閑話休題
も一度、閑話休題 

昨日、初台の新国立劇場でヤナーチェクのオペラ「イェヌーファ」を観ました キャストは、ブリヤ家の女主人にハンナ・シュヴァルツ、ラツァ・クレメニュにヴィル・ハルトマン、シュテヴァ・ブリヤにジャンルカ・ザンピエーリ、コステルニチカにジェニファー・ラーモア、イェヌーファにミヒャエラ・カウネほかです。バックを務めるのはトマーシュ・ハヌス指揮東京交響楽団、演出はクリストフ・ロイで、ベルリン・ドイツ・オペラで2012年に上演されたものと同じです
キャストは、ブリヤ家の女主人にハンナ・シュヴァルツ、ラツァ・クレメニュにヴィル・ハルトマン、シュテヴァ・ブリヤにジャンルカ・ザンピエーリ、コステルニチカにジェニファー・ラーモア、イェヌーファにミヒャエラ・カウネほかです。バックを務めるのはトマーシュ・ハヌス指揮東京交響楽団、演出はクリストフ・ロイで、ベルリン・ドイツ・オペラで2012年に上演されたものと同じです

話題のオペラの初日公演ということで、会場はほぼ満席です 私は2月2日に新国立劇場(中劇場)で、ヤナーチェクの生涯を描いたチェコ映画「白いたてがみのライオン」を観たので、このオペラを身近に感じることが出来ます
私は2月2日に新国立劇場(中劇場)で、ヤナーチェクの生涯を描いたチェコ映画「白いたてがみのライオン」を観たので、このオペラを身近に感じることが出来ます あらすじは次の通りです
あらすじは次の通りです
イェヌーファは義兄弟のシュテヴァの子を妊娠しており、彼に結婚を迫るが取り合ってもらえない 一方、シュテヴァの異父兄ラツァは彼女を愛している
一方、シュテヴァの異父兄ラツァは彼女を愛している イェヌーファは秘密裏に出産するが、彼女の継母コステルニチカは世評を恐れ彼女を家に匿い、外部の人間との接触を断つ
イェヌーファは秘密裏に出産するが、彼女の継母コステルニチカは世評を恐れ彼女を家に匿い、外部の人間との接触を断つ そして、世間体から、シュテヴァにイェヌーファと結婚してくれと頼むが拒否される。そこで、彼女はイェヌーファがラツァと結婚できるよう、赤ん坊を川に捨て、子どもは死んだとイェヌーファにウソをつく
そして、世間体から、シュテヴァにイェヌーファと結婚してくれと頼むが拒否される。そこで、彼女はイェヌーファがラツァと結婚できるよう、赤ん坊を川に捨て、子どもは死んだとイェヌーファにウソをつく 二人の結婚式の日、川から赤ん坊の死体が見つかる。人々は母親であるイェヌーファが殺したと疑うが、コステルニチカが真実を明らかにし、イェヌーファとラツァはお互いの愛を確認し、苦難を乗り越えて共に生きていくことを誓う
二人の結婚式の日、川から赤ん坊の死体が見つかる。人々は母親であるイェヌーファが殺したと疑うが、コステルニチカが真実を明らかにし、イェヌーファとラツァはお互いの愛を確認し、苦難を乗り越えて共に生きていくことを誓う

指揮者のトマーシュ・ハヌスが指揮台に上がり、さて幕開けか、と待っていると、会場の照明がすべて消され真っ暗になります 音楽も鳴らず、無音の中、小さな窓が開いて次第に広がっていくように舞台が明るくなっていき、音楽が始まります。この演出は斬新です
音楽も鳴らず、無音の中、小さな窓が開いて次第に広がっていくように舞台が明るくなっていき、音楽が始まります。この演出は斬新です
ステージは傾斜舞台になっており、白い壁の部屋に机と椅子があるだけのシンプルな舞台設定になっています これが、場面によって背面の壁が取り払われて外のシーンになったりしますが、それでもこれ以上ないほどのシンプルな舞台です
これが、場面によって背面の壁が取り払われて外のシーンになったりしますが、それでもこれ以上ないほどのシンプルな舞台です 「必要にして十分」「シンプル イズ ベスト」といったキャッチがピッタリの演出・舞台です
「必要にして十分」「シンプル イズ ベスト」といったキャッチがピッタリの演出・舞台です

タイトルロールのイェヌーファを歌ったミヒャエル・カウネは2010年「アラベッラ」のタイトルロールを歌って以来の新国立オペラ再登場です ハンブルク出身のソプラノですが、1997年からベルリン・ドイツ・オペラに所属し、2011年からベルリン宮廷歌手の称号を授与され、世界の歌劇場で活躍しています
ハンブルク出身のソプラノですが、1997年からベルリン・ドイツ・オペラに所属し、2011年からベルリン宮廷歌手の称号を授与され、世界の歌劇場で活躍しています 今回の「イェヌーファ」は全幕ほぼ出ずっぱりですが、美しい声で聴衆を魅了しました
今回の「イェヌーファ」は全幕ほぼ出ずっぱりですが、美しい声で聴衆を魅了しました
イェヌーファの継母コステルニチカを歌ったジェニファー・ラーモアはアメリカ出身のメゾソプラノですが、世界の主要なオペラハウスで歌っています 赤ん坊殺しの苦悩を見事に歌い演じていました
赤ん坊殺しの苦悩を見事に歌い演じていました
出番は少なかったものの、その存在感を見せつけたのはブリヤ家の女主人を歌ったハンナ・シュヴァルツです ハンブルク生まれのメゾソプラノですが、ワーグナーなどを中心に歌って活躍しています。深みのある声で会場を圧倒しました
ハンブルク生まれのメゾソプラノですが、ワーグナーなどを中心に歌って活躍しています。深みのある声で会場を圧倒しました
歌と演技で際立っていたのはラツァを歌ったヴィル・ハルトマンです 1996年から10年間ハノーファー州立歌劇場の専属歌手として活躍し、その後は世界の歌劇場に招かれ歌っています。この人は、歌に力があります
1996年から10年間ハノーファー州立歌劇場の専属歌手として活躍し、その後は世界の歌劇場に招かれ歌っています。この人は、歌に力があります
さて、今回、歌手以外で目立った働きをしたのは、チェコ出身の指揮者トマーシュ・ハヌスと東京交響楽団です ハヌスは「ヤナーチェクのオペラなら任せておけ
ハヌスは「ヤナーチェクのオペラなら任せておけ 」といった頼もしさを感じさせる指揮ぶりで、メリハリのある音楽づくりが際立っていました
」といった頼もしさを感じさせる指揮ぶりで、メリハリのある音楽づくりが際立っていました
終演後の長いカーテンコールは久しぶりでした この公演はシンプルな舞台づくりと相まって、日本のオペラの歴史に新たな1ページを加えるに相応しい素晴らしい公演でした
この公演はシンプルな舞台づくりと相まって、日本のオペラの歴史に新たな1ページを加えるに相応しい素晴らしい公演でした














 1冊目はオリヴァー・サックス著「音楽嗜好症~脳外科医と音楽に憑かれた人々」(早川文庫)です
1冊目はオリヴァー・サックス著「音楽嗜好症~脳外科医と音楽に憑かれた人々」(早川文庫)です
 日本のクラシック音楽は、山田耕作を抜きにしては語れません
日本のクラシック音楽は、山田耕作を抜きにしては語れません
 したがって、現在手元にあるRFJ音楽祭のチケットは次の10枚です
したがって、現在手元にあるRFJ音楽祭のチケットは次の10枚です


 餃子は冷凍ものです。娘と一緒の時はひき肉をこねるところから すべて手作りするのですが、一人だと手間が大変なので今回は勘弁してもらいます
餃子は冷凍ものです。娘と一緒の時はひき肉をこねるところから すべて手作りするのですが、一人だと手間が大変なので今回は勘弁してもらいます 焦げているように見えますか?・・・・・・そう見えたらあなたの目は正常です
焦げているように見えますか?・・・・・・そう見えたらあなたの目は正常です



 バッハの世俗カンタータ・シリーズ第7回公演です。プログラムは①オルガン協奏曲ト長調 BWV592」、②カンタータ「汝の果報を称えよ、祝福されしザクセンよ BWV215」、③カンタータ「静かに流れよ、たわむれる波よ BWV206」です
バッハの世俗カンタータ・シリーズ第7回公演です。プログラムは①オルガン協奏曲ト長調 BWV592」、②カンタータ「汝の果報を称えよ、祝福されしザクセンよ BWV215」、③カンタータ「静かに流れよ、たわむれる波よ BWV206」です
 今回から買わないことにしました
今回から買わないことにしました
 3つの大きな川=ヴァイクセル川をウィリアムズ、エルベ川をダニエルズ、ドナウ川を青木洋也が歌い(鈴木雅明氏いわく”青木ドナウ”)、ライブツィヒを流れる最も小さなプライセ川をブラシコヴァが歌います
3つの大きな川=ヴァイクセル川をウィリアムズ、エルベ川をダニエルズ、ドナウ川を青木洋也が歌い(鈴木雅明氏いわく”青木ドナウ”)、ライブツィヒを流れる最も小さなプライセ川をブラシコヴァが歌います この曲では、ブラシコヴァの美声が際立っていたのに加え、青木洋也の成長ぶりが頼もしく感じられました
この曲では、ブラシコヴァの美声が際立っていたのに加え、青木洋也の成長ぶりが頼もしく感じられました


 きっかけは当ブログの読者ゆえさんからの『お尋ねメール』です
きっかけは当ブログの読者ゆえさんからの『お尋ねメール』です
 ところで、公式サイトの『予告編』で 指揮者のヤンソンスが『ワン・トゥ』の掛け声で始める曲が印象的でしたが、誰の何という曲か分かりません
ところで、公式サイトの『予告編』で 指揮者のヤンソンスが『ワン・トゥ』の掛け声で始める曲が印象的でしたが、誰の何という曲か分かりません それはオランダの作曲家ヨハン・ワーヘナール(1862-1941)の序曲『じゃじゃ馬鳴らし』という曲でした
それはオランダの作曲家ヨハン・ワーヘナール(1862-1941)の序曲『じゃじゃ馬鳴らし』という曲でした
 というのは、現在 所有している約4,000枚のCDの中に「ニーベルングの指環」全4部作は1セットもないからです
というのは、現在 所有している約4,000枚のCDの中に「ニーベルングの指環」全4部作は1セットもないからです 」というので売り払ってしまったのです。したがって、生でワーグナーの歌劇や楽劇を聴くときは いつも予習なしの ぶっつけ本番という無謀なことを繰り返してきたわけです
」というので売り払ってしまったのです。したがって、生でワーグナーの歌劇や楽劇を聴くときは いつも予習なしの ぶっつけ本番という無謀なことを繰り返してきたわけです


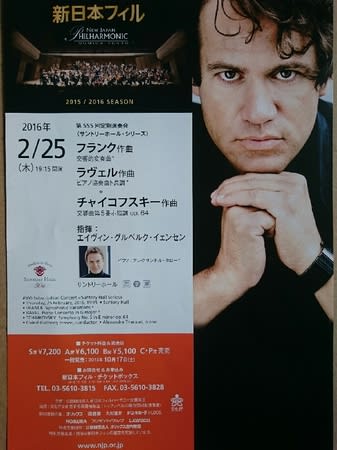

 最後の音が鳴り終わるや否や、拍手とブラボーの嵐です
最後の音が鳴り終わるや否や、拍手とブラボーの嵐です
 第2楽章はホルンの独奏が、運命には逆らえない”諦め”を表すかのように静かに響き、それを慰めるかのような音楽が続きます
第2楽章はホルンの独奏が、運命には逆らえない”諦め”を表すかのように静かに響き、それを慰めるかのような音楽が続きます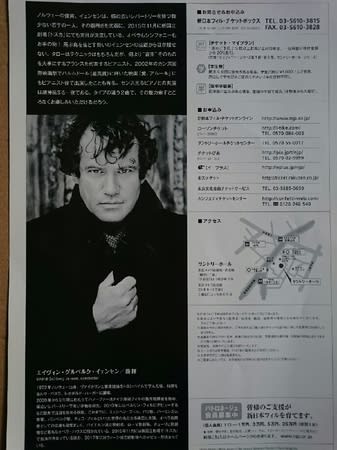
 戴いた後、「注意書き」にあった通り冷凍保存しておきました。さっそく今朝 今日が卒論の締め切りの息子と一緒にいただきましたが、『今まで飲んだ中で一番美味しいコーヒー
戴いた後、「注意書き」にあった通り冷凍保存しておきました。さっそく今朝 今日が卒論の締め切りの息子と一緒にいただきましたが、『今まで飲んだ中で一番美味しいコーヒー








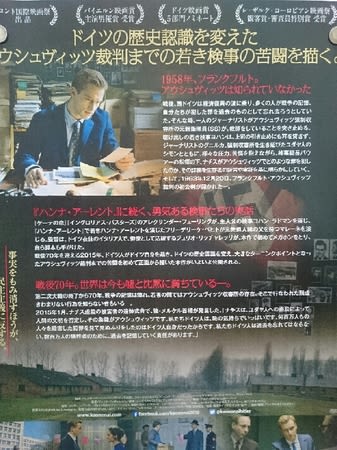
 」と一人で怒っています。その時は私も呆れて、「普段 送り迎えもしない母親が 急に病院に連れてったって、子どもは素直に言うことを訊かないだろうよ。子どもは正直だからね
」と一人で怒っています。その時は私も呆れて、「普段 送り迎えもしない母親が 急に病院に連れてったって、子どもは素直に言うことを訊かないだろうよ。子どもは正直だからね





 ヤマハ音楽教室出身者と言えばピアニストの上原彩子もそうですね
ヤマハ音楽教室出身者と言えばピアニストの上原彩子もそうですね





 エルディーティ弦楽四重奏団は、1989年東京藝術大学出身者4人で結成されました。第1ヴァイオリン=蒲生克郷、第2ヴァイオリン=花崎淳生、ヴィオラ=桐山建志、チェロ=花崎薫というメンバーです
エルディーティ弦楽四重奏団は、1989年東京藝術大学出身者4人で結成されました。第1ヴァイオリン=蒲生克郷、第2ヴァイオリン=花崎淳生、ヴィオラ=桐山建志、チェロ=花崎薫というメンバーです


 」と驚きを禁じえません。もっとも、メンデルスゾーンは16歳の時にあの名曲「弦楽八重奏曲」を書き、17歳の時に「真夏の夜の夢」序曲を書いたのですから、不思議でも何でもないのかも知れません
」と驚きを禁じえません。もっとも、メンデルスゾーンは16歳の時にあの名曲「弦楽八重奏曲」を書き、17歳の時に「真夏の夜の夢」序曲を書いたのですから、不思議でも何でもないのかも知れません










