31日(木)。早いもので1月も今日で終わり。あっという間の1か月でした。2月は28日しかないのでもっと速く過ぎ去ってしまうでしょう
昨夕、池袋の東京芸術劇場で日本フィルのコンサートを聴きました これは2013年都民芸術フェスティバルの参加公演です。プログラムは①チャイコフスキー歌劇「エフゲニー・オネーギン」より”ボロネーズ”、②リスト「ピアノ協奏曲第1番変ホ長調」(ピアノ=後藤正孝)、③ブラームス「交響曲第4番ホ短調」です。指揮は常任指揮者アレクサンドル・ラザレフです
これは2013年都民芸術フェスティバルの参加公演です。プログラムは①チャイコフスキー歌劇「エフゲニー・オネーギン」より”ボロネーズ”、②リスト「ピアノ協奏曲第1番変ホ長調」(ピアノ=後藤正孝)、③ブラームス「交響曲第4番ホ短調」です。指揮は常任指揮者アレクサンドル・ラザレフです
自席は1階P列18番、会場のど真ん中と言ってもよい席ですが、残念ながら通路側席ではありません 客席は9割方埋まっている感じです。オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスといったオーソドックスな態勢を取ります
客席は9割方埋まっている感じです。オケは左から第1ヴァイオリン、第2ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、その後ろにコントラバスといったオーソドックスな態勢を取ります 日本フィルを生で聴くのは本当に久しぶりです。コンマスの木野雅之さんのほかは一人も分かりません。定期会員ではないので仕方ないのですが
日本フィルを生で聴くのは本当に久しぶりです。コンマスの木野雅之さんのほかは一人も分かりません。定期会員ではないので仕方ないのですが
1曲目のチャイコフスキーの歌劇「エフゲニー・オネーギン」~ポロネーズは、公爵主催の舞踏会を導くための音楽です ラザレフはタクトを持たずに登場、振り向きざまに右手を振り下ろします
ラザレフはタクトを持たずに登場、振り向きざまに右手を振り下ろします 弦楽器などは慌てています。幸い冒頭は管楽器のみの演奏で間に合いましたが
弦楽器などは慌てています。幸い冒頭は管楽器のみの演奏で間に合いましたが ラザレフの指揮はパワフルです。指揮台の上で激しく動きます
ラザレフの指揮はパワフルです。指揮台の上で激しく動きます 何年か前、この曲を同じ日本フィルで西本智美の指揮で聴いたことがありますが、対極にある演奏でした
何年か前、この曲を同じ日本フィルで西本智美の指揮で聴いたことがありますが、対極にある演奏でした 西本智美のポロネーズはあくまでも華麗で美しく響きましたが、ラザレフのポロネーズは身体全体を使った”前進あるのみ”といったパワフルな音楽です。同じ曲、同じオケでこうも違うかと
西本智美のポロネーズはあくまでも華麗で美しく響きましたが、ラザレフのポロネーズは身体全体を使った”前進あるのみ”といったパワフルな音楽です。同じ曲、同じオケでこうも違うかと  です。
です。
センターにピアノが運ばれ、ソリストの後藤正孝がラザレフとともに登場します。後藤は2011年の第9回フランツ・リスト国際ピアノコンクールで満場一致の第1位を獲得、同時に聴衆賞を受賞しています 1985年生まれといいますから27~28歳ですが、小柄なため子供が登場したのかと勘違いしてしまいました
1985年生まれといいますから27~28歳ですが、小柄なため子供が登場したのかと勘違いしてしまいました
ところが、その子供のような小柄なピアニストの両手から紡ぎ出されるリストのコンチェルトの音楽は、気迫に満ちたパワフルなものでした 満場の拍手に応えてリストの「愛の夢第3番」をロマンチックに演奏しました
満場の拍手に応えてリストの「愛の夢第3番」をロマンチックに演奏しました 今後の課題はアマタいるピアニストの中でどう差別化して生き残っていくかです
今後の課題はアマタいるピアニストの中でどう差別化して生き残っていくかです
休憩後のブラームスの「交響曲第4番ホ短調」はブラームス最後の交響曲ですが、名曲中の名曲です。ラザレフはこの曲も身体全体を使って精力的に指揮をします。良く言えばパワフル、悪く言えばマイペースの指揮振りです 動きが激しいので彼を見ながら聴いていると、どうしても視覚が優先してしまい肝心の耳で聴くことがおろそかになってしまいます
動きが激しいので彼を見ながら聴いていると、どうしても視覚が優先してしまい肝心の耳で聴くことがおろそかになってしまいます こういう時には目をつむって音だけに集中するに限ります。音楽だけを聴く限り、よく流れていていい演奏です
こういう時には目をつむって音だけに集中するに限ります。音楽だけを聴く限り、よく流れていていい演奏です
ラザレフは、第4楽章のフィナーレで、観客席の方を向いて全曲を締めくくりました 満場の拍手とブラボーに、管楽器を立たせて賞賛し、自らも喜びを身体で表現します。気をよくした彼はアンコールにブラームスのハンガリー舞曲第4番を演奏しました
満場の拍手とブラボーに、管楽器を立たせて賞賛し、自らも喜びを身体で表現します。気をよくした彼はアンコールにブラームスのハンガリー舞曲第4番を演奏しました
途中で演奏が終わると見せかけて客席を振り返り、拍手が起こると”まだあるよ”と言わんばかりに再び演奏を続け、また終わると見せかけて、拍手が起こるとまた”まだまだあるぜ”と言わんばかりに再び演奏を続け、客席とキャッチボールしつつオケと一緒に楽しみながら演奏していました ラザレフはエンターティナーです
ラザレフはエンターティナーです 今の日本フィルにはこういう元気な”タレント”が必要なのだと思います
今の日本フィルにはこういう元気な”タレント”が必要なのだと思います
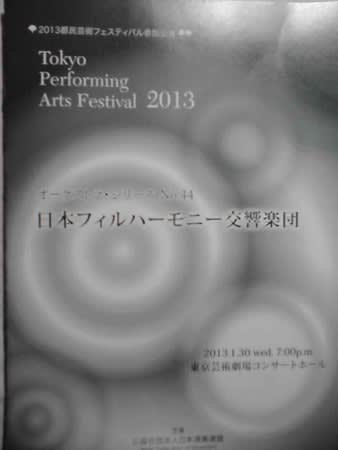

 閑話休題
閑話休題 

一昨年2月15日に始めたこのブログも今日=1月31日で777回の記念すべき回数を記録しました ここまで続けてこられたのもこのブログをご覧いただいた皆さん、とくにコメントを寄せて下さった”定期読者”の皆さんのご支援のおかげです
ここまで続けてこられたのもこのブログをご覧いただいた皆さん、とくにコメントを寄せて下さった”定期読者”の皆さんのご支援のおかげです ちなみにこのtoraブログの先週1週間(1/20~1/26)の訪問者数は2818人で1日平均402人、見られたページ数は6065ページビューで1日平均866ページ、訪問者数ランキングは181万7125ブログ中1506位となっています。これからも休むことなく毎日更新していきます。ご覧の上コメントをお寄せいただくと励みになります。よろしくお願いいたします
ちなみにこのtoraブログの先週1週間(1/20~1/26)の訪問者数は2818人で1日平均402人、見られたページ数は6065ページビューで1日平均866ページ、訪問者数ランキングは181万7125ブログ中1506位となっています。これからも休むことなく毎日更新していきます。ご覧の上コメントをお寄せいただくと励みになります。よろしくお願いいたします












 を2杯飲んで、寿司、おでん、蟹ピラフ、焼きそば、ホタテの貝柱、牡蠣フライ、デザートにメロンと苺、仕上げにコーヒーと、ほぼフルコースを平らげて会場を後にしました
を2杯飲んで、寿司、おでん、蟹ピラフ、焼きそば、ホタテの貝柱、牡蠣フライ、デザートにメロンと苺、仕上げにコーヒーと、ほぼフルコースを平らげて会場を後にしました 私は7時からすみだトりフォニーホールでコンサートがあるので、東京駅から総武線で錦糸町に向かいました
私は7時からすみだトりフォニーホールでコンサートがあるので、東京駅から総武線で錦糸町に向かいました
 その当時は”引きこもり”という言葉はなかったのですが、楽しみと言えば、レコード・ジャケットの解説を隅から隅までよく読むことでした。それが記憶に残っているのです。脊髄と口が直結していて、言葉が自然に出てしまうのです。決して頭がいいということではないのです
その当時は”引きこもり”という言葉はなかったのですが、楽しみと言えば、レコード・ジャケットの解説を隅から隅までよく読むことでした。それが記憶に残っているのです。脊髄と口が直結していて、言葉が自然に出てしまうのです。決して頭がいいということではないのです 」と発表されました。会場からオーッというどよめきの声が・・・・
」と発表されました。会場からオーッというどよめきの声が・・・・

 グールドはモーツアルトよりもハイドンを評価していたと言ってもよいかもしれません
グールドはモーツアルトよりもハイドンを評価していたと言ってもよいかもしれません


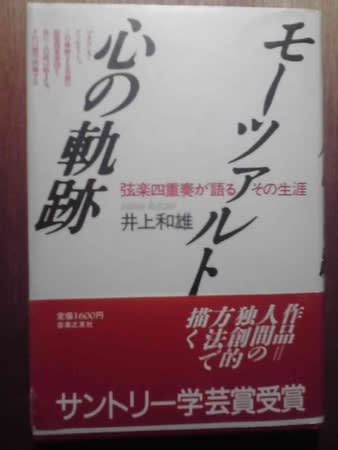
 これからじっくり読みたいと思います。趣味でブログを書いているに過ぎない、どこの馬の骨かも知れない私(篠原さんは私の名前も勤務先もご存じない)のために、時間をさいて絶版になった本を探してプレゼントしてくださったのです
これからじっくり読みたいと思います。趣味でブログを書いているに過ぎない、どこの馬の骨かも知れない私(篠原さんは私の名前も勤務先もご存じない)のために、時間をさいて絶版になった本を探してプレゼントしてくださったのです 幸い呼吸も安定していて顔色も良かったので一安心しました
幸い呼吸も安定していて顔色も良かったので一安心しました
 主催者は地元のNさんという私より1つか2つ年上のN自動車狭山工場に勤める青年とその奥さんで、公民館の許可を得て自分のスピーカーを持ち込んでレコード・コンサートを開いているという話でした
主催者は地元のNさんという私より1つか2つ年上のN自動車狭山工場に勤める青年とその奥さんで、公民館の許可を得て自分のスピーカーを持ち込んでレコード・コンサートを開いているという話でした



 何と筑紫氏は阿佐田哲也と「話の特集」編集長の矢崎泰久と歌手の井上陽水と何度か卓を囲んだことがあるというのです
何と筑紫氏は阿佐田哲也と「話の特集」編集長の矢崎泰久と歌手の井上陽水と何度か卓を囲んだことがあるというのです

 その素直で果敢で愛嬌ある精神こそがジャーナリストの本質だと、本書を読み終わったとき、私はしみじみと理解するのである
その素直で果敢で愛嬌ある精神こそがジャーナリストの本質だと、本書を読み終わったとき、私はしみじみと理解するのである



 しかし、亡霊たちが現われアエネアスに「イタリアへ」と促します。引きとめるディド―を振り切って出帆したアエネアスに失望したディド―は、自分は灰になって復讐者ハンニバルとして蘇る、と予言して自害して息を引き取ります
しかし、亡霊たちが現われアエネアスに「イタリアへ」と促します。引きとめるディド―を振り切って出帆したアエネアスに失望したディド―は、自分は灰になって復讐者ハンニバルとして蘇る、と予言して自害して息を引き取ります

 次のMETをしょって立つ一人になる可能性は極めて高いと言えるでしょう
次のMETをしょって立つ一人になる可能性は極めて高いと言えるでしょう
 その後、休憩時間に表に出て隣の会場(No2スクリーン)を確かめると山田洋次監督「東京家族」を上映していました
その後、休憩時間に表に出て隣の会場(No2スクリーン)を確かめると山田洋次監督「東京家族」を上映していました お二人はトロイアではなく東京に行くべきだったのですね
お二人はトロイアではなく東京に行くべきだったのですね
 をやらかしましたが、3人とも93点が最高で伸び悩みました。お店が用意してくれたバースデーケーキ
をやらかしましたが、3人とも93点が最高で伸び悩みました。お店が用意してくれたバースデーケーキ をいただき、X部長を中心にケータイで写真を撮りましたが、X部長にも家庭があるのでここに掲載することは控えます
をいただき、X部長を中心にケータイで写真を撮りましたが、X部長にも家庭があるのでここに掲載することは控えます さて、いったい誰が彼を殺したのか・・・・・・
さて、いったい誰が彼を殺したのか・・・・・・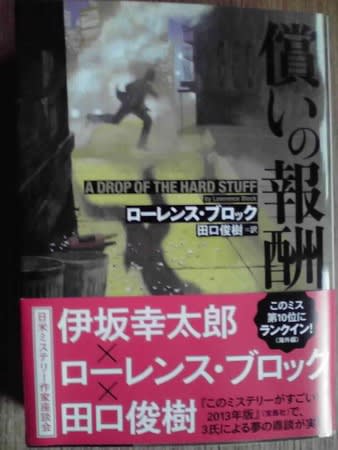

 ”と返さなくっちゃ」と言うので、二の句が告げられませんでした
”と返さなくっちゃ」と言うので、二の句が告げられませんでした
 ショスタコーヴィチは何に対して怒っているのでしょうか?社会主義レアリズムを強要したジダーノフでしょうか?最大の理解者を失った運命に対してでしょうか?いずれにしても、3人のアンサンブルは見事です
ショスタコーヴィチは何に対して怒っているのでしょうか?社会主義レアリズムを強要したジダーノフでしょうか?最大の理解者を失った運命に対してでしょうか?いずれにしても、3人のアンサンブルは見事です

 3.11大震災以降、どこのコンサートホールでもお馴染みの風景になっています
3.11大震災以降、どこのコンサートホールでもお馴染みの風景になっています

 もっとスマートな歌手だったら似合ったかもしれません
もっとスマートな歌手だったら似合ったかもしれません




 インタビューでルネ・フレミングが馬とポニーにニンジンをあげながら、「多くの馬の中からどういう馬を選ぶの?本番で馬が急に騒いたらどうするの?」と質問すると、飼育係は「多くの馬の中から落ち着いた馬を選びます。そのうえで、馬の近くで大きな音を出したり、オペラを大音響で聴かせたりして、大音響やオペラ音楽に耳を慣れさせます
インタビューでルネ・フレミングが馬とポニーにニンジンをあげながら、「多くの馬の中からどういう馬を選ぶの?本番で馬が急に騒いたらどうするの?」と質問すると、飼育係は「多くの馬の中から落ち着いた馬を選びます。そのうえで、馬の近くで大きな音を出したり、オペラを大音響で聴かせたりして、大音響やオペラ音楽に耳を慣れさせます



