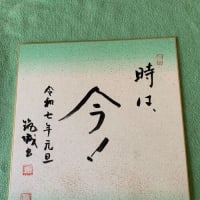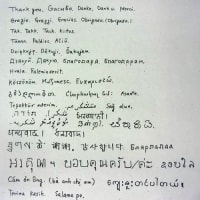解剖には、系統解剖、病理解剖、法医解剖とある。又、系統解剖学にも、ミクロの解剖(電子顕微鏡レベルの解剖学や、組織学など)とマクロの解剖(系統解剖など)、更には、発生学とある。
解剖には、系統解剖、病理解剖、法医解剖とある。又、系統解剖学にも、ミクロの解剖(電子顕微鏡レベルの解剖学や、組織学など)とマクロの解剖(系統解剖など)、更には、発生学とある。 系統解剖の実習に入る前に、金沢大学の解剖学教授の山田致知先生の書かれたエッセイ「解剖学実習の心得」を渡され、しっかりと読んでおくように言われた。以下は、その内容のほんの一部である。
解剖学実習の心得
金沢大学教授 山田致知
解剖学実習は、学生諸君が一生かけて取り組もうとする”人体”との劇的な出会いの場面であり、諸君が生まれて初めて経験する系統的な最大規模の探求事業となる。解剖学実習では、人体構造の知識を得る以外にも、判断力や処理能力を高めることが要求されるし、更に生命の尊厳や医学の倫理についても自分自身の考えを練る必要がある。それだけに、そして人体を解剖するという特殊性の故に、指導の責任と学生の規律とが特に重要視されなければならなくなる。
死体に対する態度
総ての死体解剖は、昭和24年制定の”死体解剖保存法”という法律に基づいて行われる。その第20条は、死体の取扱いに当たって特に礼意を失わないように注意しなければならないことを定めている。
法律は、総ての解剖に遺族の同意が必要であるとしている。いいかえると、我々は遺族の理解と協力によって”解剖させてもらえる”のであった、決して特権によって解剖できるのではない。大体、解剖することを特権だなどという考え自体が思想的に少々おかしいのではないだろうか。諸君は、実習体確保のためにどんな努力が払われ、関係者がどんなに苦慮しているかを知らないし、また知ろうともしないから、自分達のようなエリートには死体の方が集まってくるような錯覚に陥り易い。実習体確保という問題は、実習を担当する教室だけでどうこうする筋の問題でもなく、またできる問題でもない。それは医学の向上発達という大目的を達成する為に、医学関係者総員が節度を正して当たらなければならないことである。
兎に角、諸君が今日実習を開始できるのは、文字通り慈悲の固まりのような故人および遺族の善意の御蔭によるものである。もしもこの明白な因果が理解できない者がいたら、冷静に次のことを自問して見るがよい・・・君の両親が死亡した時、自分はかって一体の死体を解剖したからその恩返しにと肉親の遺体を実習の為に提供できるか、後述のような解剖体収集のキャンペ一ンに応えて諸君自身の肉体を実習用にと遺言することができるか、その際に、反対する身内の者を納得ゆくように説得できるか。而も法律は、学生の解剖を無条件に認めているのではない。学生は、全く解剖学担当教授または助教授の責任において解剖することができるのである。
解剖実習は医学専門課程のハイライトだといわれているが、それは医学を志す者が必ず通過しなければならない一つの難関であって、将来人命を預かる者が実際に人体に引き合わされる最初の機会でもある。我々が如何に無力であり無能であるかを先ず思い知らされ、ついで、我々のフシ孔のような観察力と型にはまった頭の働きによって一体何ができるかという能力検定の機会となるのが、解剖学実習である。
解剖とする対象は死体である。だからこれは人体解剖学ではなくて、死体解剖学”であるなどと反抗期的理論を宣伝する者があるのは困ったものである。成程と思う者が沢山あるであろうが、それは死んでいるのは実は彼の頭であると自白しているようなものである。死体の所見であっても、見る人の立場によっては、生き生きと躍動することを彼は気づかないのである。 学問の真髄はどの分科でも同じであるから、解剖学実習を実りあるものとして完遂できない者は、恐らく臨床医としての野心なども抱かないがよいだろう。要するに、死体は”聖書”であり、”活師”のなのである。
我々は初回に全員そろって黙祷をささげ、以後は各組ごとに礼拝、最終回には花束を手向けて冥福を祈り、感謝をこめて別れを告げるのが習わしである。
”死体を他人の遺体だと思うな。肉親を解剖する積もりになって、こうするのが当然だと思うように、絶えず自問しながら行動せよ。”