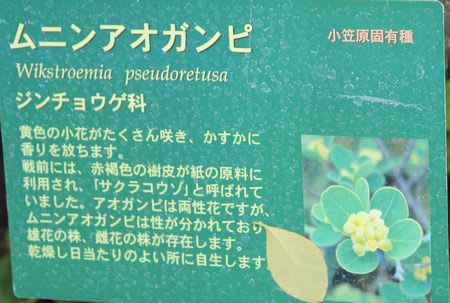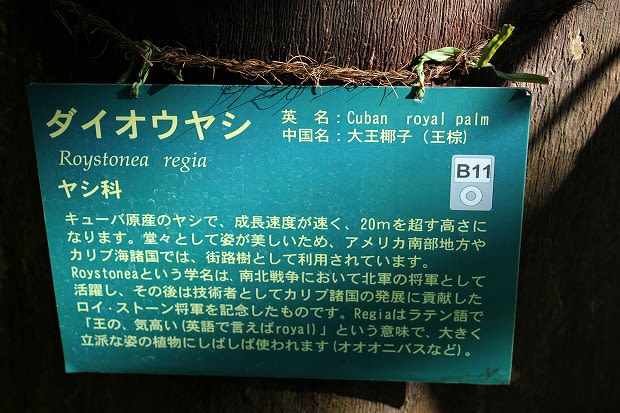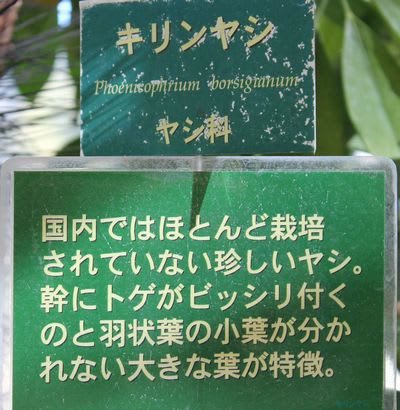じぐざぐじぐざぐ ラン♪ラン♪ラン♪ ☆ジグザグの木 名前も見た目そのものだった
学名を日本語読みしたら
デカリア マダガスカリエンシス だったのでマダガスカルに生える植物?
気になって調べたところマダガスカルの固有種ということが分かりました。ディディエレア科
ディディエレア科はマダガスカルのみにしか原産しないそうです。デカリア属で1属1種



この花 うちの多肉でも花を咲かせたのと同じ仲間みたい ☆ギバエウム ディスパー

亀の上に立派な葉 ☆ディオスコレア エレファンティペス 和名ツルカメソウ(鶴亀草)
多肉植物にこのような青々とした葉をつけるものがあったなんて!南アフリカ原産
ヤマノイモ科 ヤマノイモ属 ほかには亀甲竜(きっこうりゅう)という名前も!
エレファンティペス→「象のような足の」という意味だそうです。
表皮は硬いコルク質でおおわれて動物から食べられるのを防いでいるのだとか
淡い黄色の花を咲かせるそうです。




ドーム内で大きめな花を咲かせていたハナキリンがありました。
マダガスカル原産 トウダイグサ科 これも多肉植物といっていいのかしら・・・
花弁のように見える2枚の苞葉が可愛らしい♪





学名を日本語読みしたら
デカリア マダガスカリエンシス だったのでマダガスカルに生える植物?
気になって調べたところマダガスカルの固有種ということが分かりました。ディディエレア科
ディディエレア科はマダガスカルのみにしか原産しないそうです。デカリア属で1属1種



この花 うちの多肉でも花を咲かせたのと同じ仲間みたい ☆ギバエウム ディスパー

亀の上に立派な葉 ☆ディオスコレア エレファンティペス 和名ツルカメソウ(鶴亀草)
多肉植物にこのような青々とした葉をつけるものがあったなんて!南アフリカ原産
ヤマノイモ科 ヤマノイモ属 ほかには亀甲竜(きっこうりゅう)という名前も!
エレファンティペス→「象のような足の」という意味だそうです。
表皮は硬いコルク質でおおわれて動物から食べられるのを防いでいるのだとか
淡い黄色の花を咲かせるそうです。




ドーム内で大きめな花を咲かせていたハナキリンがありました。
マダガスカル原産 トウダイグサ科 これも多肉植物といっていいのかしら・・・
花弁のように見える2枚の苞葉が可愛らしい♪