NHKで竹内浩三と云う人の特集を見た。
彼の戦時下での振る舞いを見ると
手塚治虫のそれに似ているような気がした。
戦時下にありながらも、国家の大事をまるで
他人事のように、客観視することが出来
且つそれに対して、臆せず否定的な評価を
下せるということが、だ。
明治維新によって日本が近代化を迎えた、と
云っても、やはり当時の日本人は貧しく
近代的な個人足り得なかったのだろう。
だからこそ、多くの人が旧来通り
伝統にくびきをうたれ、自らを国家に
結びつけなければならなかったんだろう。
生きては行けなかったのだろう。
それ故の日清戦争であり、日露戦争であり
日比谷焼き討ちであり、2・26事件であり
盧溝橋事件であり、詰まる所太平洋戦争なんだろう。
そういった貧しい社会状況の中で
個人足り得たのは、国家から自らを
切り離すことが出来たのは
手塚や竹内のように明日の生活に追われない
経済的に恵まれた人々だけだったのだろう。
もっと云うと、映画や小説、演劇もしくは
漫画など芸術文化体験に恵まれた者たちであった
からこそ、国家から自立した個人足り得たのだろう。
この特集で挿入された軍国への憧れをまるで称えない
竹内や、『紙の砦』などで紹介される
戦時下、軍事工場でも漫画を描き続け
敗戦の知らせを聞いて。「漫画が描けるっ!」と
歓喜の声を上げた手塚のエピソードを
目の当たりにすると、そう考えたくなる。
彼の戦時下での振る舞いを見ると
手塚治虫のそれに似ているような気がした。
戦時下にありながらも、国家の大事をまるで
他人事のように、客観視することが出来
且つそれに対して、臆せず否定的な評価を
下せるということが、だ。
明治維新によって日本が近代化を迎えた、と
云っても、やはり当時の日本人は貧しく
近代的な個人足り得なかったのだろう。
だからこそ、多くの人が旧来通り
伝統にくびきをうたれ、自らを国家に
結びつけなければならなかったんだろう。
生きては行けなかったのだろう。
それ故の日清戦争であり、日露戦争であり
日比谷焼き討ちであり、2・26事件であり
盧溝橋事件であり、詰まる所太平洋戦争なんだろう。
そういった貧しい社会状況の中で
個人足り得たのは、国家から自らを
切り離すことが出来たのは
手塚や竹内のように明日の生活に追われない
経済的に恵まれた人々だけだったのだろう。
もっと云うと、映画や小説、演劇もしくは
漫画など芸術文化体験に恵まれた者たちであった
からこそ、国家から自立した個人足り得たのだろう。
この特集で挿入された軍国への憧れをまるで称えない
竹内や、『紙の砦』などで紹介される
戦時下、軍事工場でも漫画を描き続け
敗戦の知らせを聞いて。「漫画が描けるっ!」と
歓喜の声を上げた手塚のエピソードを
目の当たりにすると、そう考えたくなる。











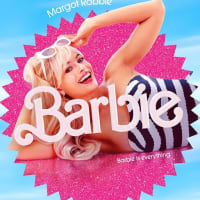








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます