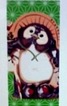この芝居のオープニング。
舞台が明るくなると、
弟子の由紀が下手くそな祭文を唱えている。
それを道子(私)が籐椅子に座って、
「うまくならんな~」みたいな気分で聞いている。
・・・こんなシーンからのスタートでした。
オープニングシーンなので、
そのずっと前から、まず私が、このあたりにスタンバってて、

けっこうギリギリに来る由紀と2人で、
じっと開演を待ちます。
この時間が、なんとも怖いんですよね~。
いくら長くやってても、ぜんぜん慣れません。
由紀役の響乃ちゃんがギリギリに来るのも、
変に緊張しないためだったようですし、
出の前の待ち時間は、役者それぞれ、
過ごし方が違います。
袖で、かなりダイナミックにストレッチする人もいますし、
壁をじっとさわっている人もいます。
一番多いのが、首を回したり、手をぶらぶらさせたり、
軽いストレッチをする人ですね。
これで身体の余計な力を抜いていきます。
私もこのパターンで、それに加えて、
台詞を口の中でブツブツ言いながら待っています。
そして暗転になったら、由紀と2人で出ていって、
所定の位置につきます。
このように、暗転中に位置について、
最初から舞台にいることを、
「板つき」といいます。
で、またまた話がそれちゃいますが、
こういう、暗転での板つきなどを、
現場で初めて体感するのが、
場当たり・・・つまり、
照明さん音響さん中心の最終チェックのとき。
場当たりでの重要案件のひとつが、
<暗転> なんですね。
暗転中、舞台上では、
役者の移動や物の移動が行われます。
真っ暗な中で、
例のカレンダーやら、お茶の入った湯呑みやら、
果ては置いてある名刺まで、
出したり入れたりします。
でも、見える人って見えちゃうんですってね。
ネコ目って呼ぶらしいんですが、
「この程度なら、舞台の端から端まで見えるよ」
とか、自慢げに言うヤツがいるんです!
だけどね、見えない人間は見えないんですよ。
私はものすごいトリ目で、
だから暗転が大の苦手で。
だからそれ故のネタはいくつもあるのですが、
これだけはどうしようもないんですよね。
何十年舞台をやっていても、
とにかく見えないものは見えないんだから。
で、暗転苦手役者の、何よりの味方が、
暗い中でも光る、畜光と呼ばれるシールで、
これを頼りに、暗闇の中を突き進みます。
(暗転の話はこのあたりにも書いています)
今回も、「畜光、まぶしいくらいだよね~」なんて、
他のキャストたちが言うほどチカチカだったのですが、
まるっきり見えん

その上、私の場合、すぐに方向を見失うという、
二重苦を背負っているもので


なのに・・・、
場当たりの時 舞台監督さんが言ったんです。
「ええと、オープニングの暗転は、
やってみなくても大丈夫かな?」
(つづく)
 ブログランキング参加中
ブログランキング参加中 
人気ブログランキング
よろしければ、
 クリックを!
クリックを!