
エルンスト・マイヤ
「これが生物学だーマイヤから21世紀の生物学者へ」(八杉貞雄、松田学訳)
エルンスト・マイヤ(Ernst Mayr:1904-2005) ドイツバイエルン州生まれの進化生物学者。鳥類の分類学、生態学で顕著な業績を挙げる。ハーバード大学教授。同大博物館館長。進化学における総合説を確立させ、種分化における「異所的種分化説」を唱えた。また「交雑可能」を基準とする生物学的種概念を提唱したので有名である。
このマイヤは、形態的基準は種の区分として信頼できないとして、生殖隔離(非交雑性)こそが重要な基準であるとした。これが平衡のとれた調和された遺伝子保護(すなわち種の実態保護)の制度と考えたのである。種間の形態的差異は生殖隔離の結果だと考えた。
マイヤの種概念における生殖隔離説は分かりやすくすっきりしており、現代の生物学者の間では、ほぼ主流をなしている。ダーウィンも、ある時期にこの「生物的種概念説」を唱えていたそうだ。しかし、最後には類型学的種概念説に戻った。何故だろうか。
次のように考えてみた。たまたまA種内に交雑不能な個体が生まれても、それに新たなニッチ獲得の優位性がなければ、たちまち消えてしまう。交雑不能という変異は、必ずしも新たな適応的なニッチ獲得を保証していない。資産のないドラ息子が親戚一同から勘当されているようなものだ。すなわち、単に交雑隔離が起こったとしても、あらたな種Bが種Aから生ずる可能性は限りなく小さい。
逆なんじゃないかと思える。すなわち環境への適応的変異の個体が突然変異で生ずる。それにともなって、体に様々な形態的な変化や生理的変化が生ずる。この突然変異は集団に広がるが、食い物の好みや種類も変わるかもしれない。その結果として、もとの変異の集団とは「相性が悪くなり」生殖隔離がおこる。αという環境に適応した種Aとβという環境に適応した種Bが交雑しても、不適な子孫ができて淘汰される。これは実験生物学的に検証できると思える。
マイアは、著書の中で「ダーウィンの転向」を「不思議なこと」と述べているが(p155)、ダーウィンも、最後はきっとこのように考えたんだと思う。種分化(種の起源)は、二つの条件(環境への適応変異とそれに引き続く生殖隔離)を潜り抜けてきた結果なのだ。異所的種分化も、この二つのプロセスが必要なのだ(単に住み場所が機械的に分かれたためではなく)。Great Bookの題が「種の起源(Orign of Species)]となっている所以である。

















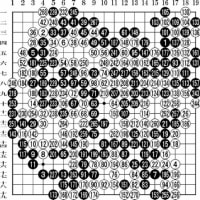








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます