2009年 韓国の最高裁判所で、植物状態にある70代の女性に対して初めて延命処置の中断を認める判決が下りたことを受けて「尊厳死と安楽死」という題でコラムを書いたことがあります。それから5年経った今、悪性の脳腫瘍で余命半年と告知されたアメリカの女性が、自ら死を選択することをネット動画上で発表し、その後医師から処方された薬を服用して死亡したことが世界中で話題になっています。この世に全く同一の人間が存在しないように、その死も一人一人すべて異なるものです。尊厳死、安楽死問題は、人間の死生観すべてに関わる問題だけに、最初にコラムを書いた当時から全く進歩せず、結論を出せずにいる自分がいます。
尊厳死と安楽死は混同されがちですが、定義としては全く異なるものです。尊厳死は、延命措置を断わって自然死を迎えることです。これに対し、安楽死は、医師など第三者が薬物などを使って患者の死期を積極的に早めることです。どちらも「不治で末期」「本人の意思による」という共通項はありますが、「命を積極的に断つ行為」の有無が決定的に違います。尊厳死に関しては、フランス、ドイツ、デンマークをはじめ欧州を中心にリビングウィル(Living Will、生前の意思)つまり治る見込みがなく、死期が近いときの医療についての希望をあらかじめ書面などで残し、尊重することで延命処置中止を認める法律が制定されています。韓国でも2009年の最高裁判決によりある程度認める方向にあるといえるでしょう。日本ではまだ明確な法的判断はなされていませんが、延命装置開始の有無などは個々の臨床現場で家族と医師の話し合いがなされているものと考えます。一方、安楽死に関しては合法化された国としては、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、そしてアメリカの一部の州のみで多くはありません。今回 アメリカ人の女性がわざわざ他の州から移り住んだオレゴン州もその一つです。やはり積極的な死の幇助は、どのようなケースであっても抵抗があるのは当然です。
「尊厳死」という言葉が存在するならば、その対極にあるのは「尊厳をもてない死」「みじめな死」でしょうか?誰も苦しみたくはないのは当然ですが、最後まで病気と闘うことも選択です。「人間の生は選択できないが死に方は選べる」というのが尊厳死を支持する人の主張ですが、医療や科学が高度に発達すれば、むしろ選ぶことが難しくなっているのかも知れません。














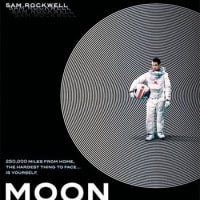
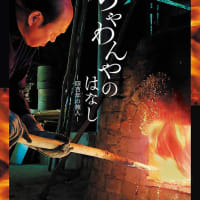










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます