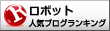大津の街をぶらつくと、面白い発見をすることがある。
これは昔の灯台だ。
夜になると灯を入れて、沖合を通る船の道標としたのだろう。
建立に貢献した町衆の名前が刻まれている。
しかし、今ではこの近くに渚はない。
はるか200mほど北へ移動している。
別に地面が盛り上がったわけではない。
琵琶湖を埋め立てたのだ。
人間は、時代時代で、自分たちの都合のよい解釈で自然を改変してきた。
今さらに元には戻せない。
最近、ISによる世界遺産の破壊がニュースとなっている。
人間が作ったものを、人間が破壊する。
もったいない話だが、それもありなのかもしれない。
逆に、そのような遺産を命がけで守ってきた人々もいた。
守る人は英雄と呼ばれ、破壊する人は悪魔と呼ばれた。
今を刹那的に生きる人と、未来に夢を託す人の違いだろう。
それだけ、ISが刹那的になってきている証でもある。
一方、自然が作ったものを、人間は破壊し利用してきた。
それは、人間が存在するための必然でもあるので、あまり厳しく問われてこなかった。
どこで折り合いをつけ、調和を図るのかが、問われている気がする。
破壊しつくした後に、どのような光景が広がっているのかが、私にはわからない。