
2011年10月20日、私はカナダの大学にいた。
ラバル大学に留学中の渡辺昌平さんの公聴会に出席するためだった。
6人の審査員の前で発表する昌平さんは緊張気味だった。
私も、海外の大学で学位を審査するのは初めてで、少し緊張していた。
主査は、友人であるビンセント教授だ。
ケベック州で最も古い大学であるラバル大学では、フランス語が必修だった。
しかし、昌平さんはあまり得意ではない。
そこで、アブストラクトだけフランス語で紹介し、あとは英語で発表した。
私はと言うと、もちろん、フランス語は分からない。
私が副査となったのは、彼の語学におけるマイナス面を正当化する意味もあったのかもしれない。
発表は、なかなかすばらしかった。
いつもそう思うのだが、学位の公聴会では、学生さんは自信満々で話をする。
居直っているのかもしれないが、緊張感と、晴れがましさが重なり合って、時にはほほえましくさえある。
発表が終わると、審査員が順に質問を行う。
主査が進行をするのは、日本の大学と同じだ。
私も当たりさわりのない質問をしたのだが、かれは少し戸惑っていたようだ。
発表が終わると、別室で審査が始まった。
ここでは、ラバル大学の副学長が議長を務めた。
学位論文の中身については問題なかったが、議長がこだわったのは、発表が英語だった点だ。
「大学の規則では、フランス語での発表が原則だ」
と彼は主張した。
他の審査員は、カナダ人が3名とアメリカ人、日本人だった。
アメリカの教授はもちろんフランス語はわからない。
日米共同で弁護する形となった。
しばらく議論をしてから、議長が折れて、学位を承認した。
なんだかセレモニー的だな、と思った。
全員が署名して、こうして昌平さんはめでたく学位をもらえることとなった。
後日談だが、数ヶ月してから、副学長から丁重なお詫びのメールが届いた。
申し訳なかったと率直にわびていた。
ビンセントが彼に、熊谷が怒っていたと吹き込んだらしい。
今、昌平さんはアメリカのタホ湖でポスドクをしている。
こうして日本の若者が海外で活躍することに、私は大きな期待を持っている。
因習にまみれた日本の閉鎖的な世界ではなく、広い社会で思い切り能力を発芽して欲しいものだ。
国際会議で顔を合わせる日が楽しみだ。










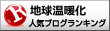







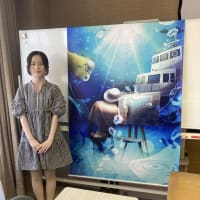









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます