関東大震災の朝鮮人虐殺 ラムザイヤーと藤野裕子 関川宗秀
1923年9月1日、関東大震災が発生した。
映画監督の黒沢明は当時13歳だった。「朝鮮人が井戸に毒を入れた」という噂が近所に広がっていた。白墨のしるしがある井戸が目印だという。ところがその印は以前、黒沢少年が落書きしたものだった。黒澤明本人が語った、関東大震災の思い出話だ。
ハーバード大学ロースクールのジョン・マーク・ラムザイヤー教授という政治経済の学者が、1923年関東大震災の朝鮮人虐殺事件を歪めた論文を発表していると、ノンフィクション作家加藤直樹が指摘している。(2021年7月5日の朝日新聞「論座」)
ラムザイヤーの問題の論文は、“Privatizing Police:Japanese Police,the Korean Massacre,and Private Security Firms”(「民営化する警察:日本の警察、朝鮮人虐殺、そして警備会社」)というタイトルで、2019年6月に書かれている。加藤によれば、ラムザイヤーは次のように、1923年の朝鮮人虐殺の史実を歪めているという。
朝鮮人虐殺事件に対するラムザイヤーの関心は、以下の引用部分にまとめられている(以下、本連載ではラムザイヤーの論文からの引用はグレー地の囲みで表記する)。
「問題はこれ(朝鮮人の重大犯罪と自警団の虐殺:加藤注)が起きたかどうかではない。どれだけの規模で起きたかだ。より具体的には、(a)震災の混乱の中で、朝鮮人はどのくらい広範に犯罪を行ったのか、そして (b)自警団は実際に何人の朝鮮人を殺したのか――である」
彼は、震災時に流言で語られたような朝鮮人の重大犯罪やテロが実際にあったと主張しているのである。その上、自警団の虐殺を朝鮮人の犯罪に対する「報復殺人」と規定している。
「朝鮮人による破壊行為の範囲を割り出そうとする際に陥る証拠の泥沼は、日本人による報復殺人の範囲を割り出そうとする際にも当てはまる」「彼ら(新聞)は朝鮮人の犯罪に関する異常なほど恐ろしい話や、日本人の報復に関する同様に恐ろしい話を報じた」
といった具合だ。
これに加えて、殺された朝鮮人の人数を推測する試みも行っているのだが、いずれにしろ、もはや論文のテーマからは完全に「逸脱」しているのはお分かりだと思う。
朝鮮人が重大犯罪やテロを行ったのは事実であり、自警団の殺人はこれに対する正当防衛だった――という議論は、ネット上でしばしば見受けられる。私はこれを「朝鮮人虐殺否定論」と呼んでいる。ホロコースト否定論という言葉が、単に「ガス室はなかった」という主張だけでなく、ホロコーストという歴史的事実の意味を、事実を歪めて矮小化しようとする試みを含めて名指す言葉として使われていることに倣ったものだ。ラムザイヤーの主張内容が、そういう意味で「朝鮮人虐殺否定論」であることは間違いない。
ラムザイヤーの論文の巻末には97本の参考文献が挙げられているが、うち6本が匿名の個人ブログだそうだ。美空ひばりのスキャンダルを取り上げた誰とも知れぬファンブログや、「大阪ニュース」「暴力団ニュース~ヤクザ事件簿」といったタイトルで新聞記事をまとめたものなどである。この点について、加藤直樹は次のように書いている。
先行研究の無視ということで言えば、参考文献で挙げられている震災関連の資料のなかに、山田昭次、姜徳相、琴秉洞、田中正敬、松尾章一といった虐殺研究の第一人者たちの、日本語による研究文献が一冊も含まれていない。山田の英文論文が一つ入っているだけだ。虐殺問題をめぐって日本政府がどう動いたかを検証した宮地忠彦『震災と治安秩序構想』(クレイン)も当然、入っていない。ラムザイヤーは、先行研究に学ぶことで得られる基本的な知識を欠いたままで、虐殺の様相や当時の日本政府の動向について議論を展開しているのである。その結果として、決定的な部分も含む至るところに一次史料の誤読が散見されるし、推論のみで提示される無理な主張も多い。参考文献の問題性としては、主張に関わる重要な数字の出典として匿名の個人ブログを挙げていたりする。
ラムザイヤーの論文は、先行研究の基本的な知識を欠き、一次史料の誤読、推論による無理な主張も多く、論文の体をなしていないと、加藤の指摘は手厳しい。
先日、『民衆暴力』(藤野裕子 2020年 中公新書)を読んだ。
世直し一揆や秩父事件、日比谷焼き討ち事件、関東大震災の朝鮮人虐殺など、江戸末期から大正期までの歴史的な民衆の暴力を、その行為者に即して理解を試みながら、権力への抵抗だったという安易な称揚にも与せず、「過去の民衆暴力を見る視線を研ぎ澄ませれば、現在を見る眼も磨かれる」という著者の思いに貫かれた良書である。
この本の第4章と第5章は朝鮮人虐殺にあてられている。地震の直後、「朝鮮人が暴動を起こした」「朝鮮人が井戸の毒を入れた」「放火した」などという噂が日本人の間に広まり、東京や神奈川で民間の自警団が2000以上できたそうだ。しかし、その噂はデマであり、実態のない想像上の産物に過ぎないと藤野裕子は断言している。
それでは、流言は本当に誤りだったのだろうか。これまでの研究は、この点についても丁寧に検証している(山田昭次『関東大震災時の朝鮮人虐殺』)。
司法省の「震災後に於ける刑事事犯及之に関連する事項調査書」のうち、罪を犯したとされる朝鮮人は140人いる。そのうち、氏名不詳・所在不明・逃亡・死亡とされる者が約120人、86%にのぼる。
後述するように、東京では自警団が各地域に検問所を設けて、通行人を誰何し、教育勅語を言わせるなどして、朝鮮人かどうかを判断した。裏返せば、そうでもしない限り、朝鮮人か日本人かを見た目だけで判断することは困難だった。この司法省の発表に対し、同時代のジャーナリスト石橋湛山は、「所謂鮮人の暴行は、漸く官憲の発表する所に依れば、殆ど問題にするに足らぬのである。〔中略〕官憲の発表に依れば、殆ど皆風説に等しく、多分は氏名不詳、たまたまその明白に氏名を掲げあるものも、現にその者を捕まえたるは少ない。かくては、その犯罪者が果たして鮮人であったか、内地人であったかも、わからぬわけである」と批判している。(『東洋経済新聞』1923年10月27日)。犯人の名前がなく、捕まってもいないのに、朝鮮人の犯罪として統計に数えられていることが、同時代にも批判されていた。
残りの20人ほどのうち、3人は判決が確定してなく、残る16人、15件が有罪となっている。罪状は窃盗・横領・贓物(ぞうぶつ)運搬などである。東京市だけでも、震災後三ヵ月間で約4400件の窃盗があったというから、そのうちの15件が朝鮮人の犯行だったとしても、それだけで朝鮮人が暴動を起こそうとしていた証拠にはならない。(『民衆暴力』P148)
朝鮮人暴動はなかったという論証に続いて、その誤情報を政府が流していた事実が記されている。警察を管轄する内務省警保局は、「震災を利用し、朝鮮人は各所に放火し不逞の目的を遂行せんとし現に東京市内で爆弾を所持し石油を注ぎて放火するものあり」と全国の地方長官に通達を出している。この通達は9月3日のことだ。
政府は震災翌日の9月2日、東京市と周辺地域に戒厳令を施行している。この戒厳令の目的は「人心の安定」であり、「朝鮮人暴動」への対応ではなかったとする説もあるそうだが、流言が広まる中、警察が出動し、全面的に治安の維持を担ったことで、朝鮮人が暴動を起こしているという噂に信憑性を与え、「軍隊・警察・民衆が朝鮮人を殺害することへのためらいが払拭された」と藤野裕子は書いている。
そして9月5日、山本権兵衛内閣は、一転して事態の収拾を図るべく、朝鮮人迫害を諫める告諭(「民衆自ら濫に鮮人に迫害を加ふるが如きこと」を戒める)を発出する。その告諭の中には、「諸外国に報ぜられて決して好ましきことに非ず」という文言もあったという。そして告諭は、地方長官に対して流言を流布する新聞記事の差し止め・差し押さえを命じている。
さらに、虐殺された朝鮮人を焼くときに「数がわからないようにしろ」という埼玉県本庄署などの隠蔽工作まで『民衆暴力』は教えてくれる。
このような政府の対応を追っていくと、朝鮮人の暴動というデマの肥大化に政府が加担していたこと、そして政府の混乱ぶりがよくわかる。
『民衆暴力』は、膨大な一次史料、二次史料から、歴史の検証を行っている。藤野裕子は本書のあとがきで、「大学生にも手に取ってもらえるように願って書いた」と述べているが、新書版ながら本書の内容は研究書としても堪え得る、読み応えのあるものだ。
ラムザイヤーを論難する加藤直樹の記事に対し、「論座」に投稿された読者のコメント見ると、朝鮮人虐殺について正しい歴史の検証を求める声が多いように感じる。が、「従軍慰安婦問題を捏造した」などというステレオタイプの言葉で、加藤の記事を批判しているものも散見され、うんざりする。
『民衆暴力』のあとがきで著者は、そもそも本書をまとめる決意のきっかけは、「前著の刊行以後、歴史修正主義が行政にまで入り込んでいることを痛感せざるを得なかったこと」だと書いている。
「前著」とは『都市と暴動の民衆史』(有志舎 2015年)という専門書である。
2015年といえば、憲法の解釈を変え、集団的自衛権を可能とした安保法制が作られた年だ。
また、この2015年は、戦後70年談話(安倍談話)が発表された年でもある。50年談話(村山談話)、60年談話(小泉談話)などで使用された4つのキーワード(「植民地支配」「侵略」「痛切な反省」「お詫び」)を安倍晋三も使用したが、それは日本がこれまで繰り返し反省とおわびを表明してきたことを間接的に引用したものだった。
そして、「あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」と明記している。今後、際限なく謝罪を続けることはない、という意思表示も明確に行った。
さらに、「日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました」とした。これは、日本の対外侵略の歴史を修正し自己肯定的にとらえようとするものだ。
その前年の2014年1月に、新しくNHKの会長に就任した籾井勝人が、就任会見で、旧日本軍の従軍慰安婦について、「戦争をしているどこの国にもあった」などと発言して、物議を醸していた。
2017年、東京都の小池百合子知事が、毎年9月1日に開催されている「関東大震災朝鮮人犠牲者追悼式」に、知事名の追悼文を送らない決定をした。過去の知事は送ることが通例となっており、それを覆すことの政治性が問題になった。2020年の追悼式まで連続4年、小池百合子知事は追悼文を送っていない。(追記 小池百合子は2021年も追悼文を送らなかった)
2015年ごろを少し振り返っても、歴史修正主義者たちの動きは、藤野裕子の言葉の通り、より露骨になってきていると言わざるを得ない。
私たちは、さまざまな、今日的な課題に直面している。
そのとき、私たちに示唆と勇気を与えてくれるのは、書物や芸術作品など、先人の知的営為だろう。
先人が、逆境の中にあって、その諸問題といかに取り組み、思考していったのか。先人の学問的、芸術的な取り組みは、困難な事態に立ち向かい、未来を志向しようとする者に、様々なことを教えてくれる。
藤野裕子の労作も、そんな先人たちの知的営為の積み重ねのその先端で、2021年の今、震えている。











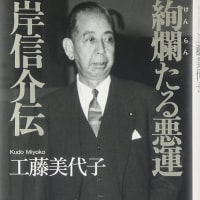
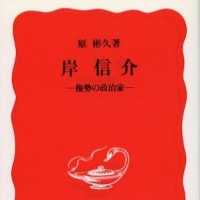

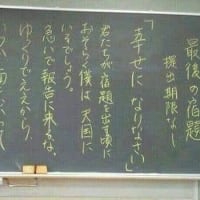

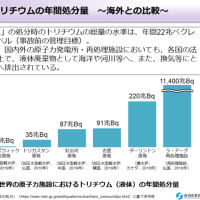
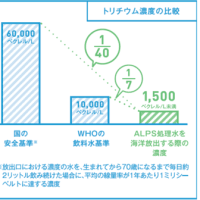
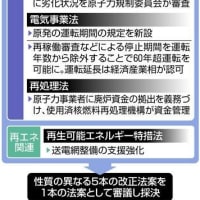








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます