秋風や寄れば柱もわれに寄り 鷹羽狩行
風が吹く。秋風が吹く。そぞろに淋しい風が渡る。仮に旅吟としよう。柱は寺のものとしよ
う。奈良は唐招提寺、そのエキゾチックなエンタシスならばなおよい。遠く異国唐天竺を、天
平の昔を思う。秋風はそこから吹いてくるとしたい。風雪を経た柱の存在感を目で確かめ、美
しさを心にとめ、響いてくるものを見つめる。目に触れ、肌に触れ、ふと柱に寄りかかる。旅
のつれづれに生まれた時間の空白にもたれかかる。太くたくましく、歴史を刻んだ柱である。
千年余を柱として存在し、その前の数百年を樹木として存在し、合わせて二千年余の命を保っ
てきた時間に寄りかかり、旅情に浸る。木の柱のほのかな温もりが肌に伝わってくる。木の肌
から我が肌へ互いの体温が行き来する。抱かれるかのような安堵感が兆す。物としての柱が自
分に情を示してくれるように感じる。旅の多い作者の定住漂泊の日常から旅吟としてみたが、
一般家屋の柱を想定しても柱の素材、年輪、季節などから同様の鑑賞ができる。










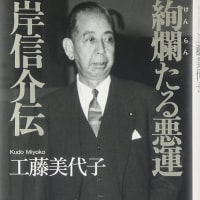
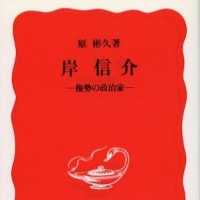

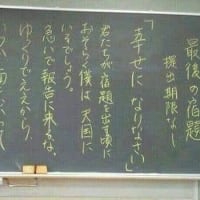

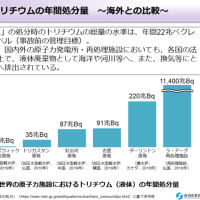
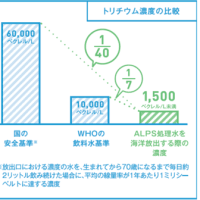
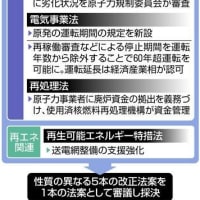








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます