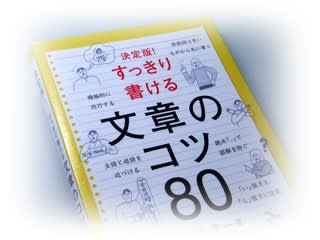【2015.05.10(sun)】
★分かり易い“文章のコツ”
・図書館で本を物色していて、この本が目に留まりました。
・日頃文章を書く機会が多い人、少ない人様々だと思いますが、機会の多少はあっても誰も“書く”行為から逃ることは出来ないと思います。巷に出ている文章作法の本は大家が書かれたものが多くて敷居が高い。
・著者の高橋俊一氏は記者出身。
この本では最初に文章を書く為の「最強の6か条」が掲げられ“その具体的なコツ80個”が示されています。平易で歯切れがよく理解し易い本だと思う。

・当たり前のこと、分かりきった内容、余分な言葉など、省略が可能なら削るとのこと。

・意味もなく飾らないこと、と書かれています。
文例の中の“すべからく”は本来の意味と違う解釈で使われている。
すなわち“当然”という意味で使うべきであり“全て”と言う意味ではない。
思い込みによる誤用は怖いです。
間違いは誰にも起こりうるので気をつけなくては…私も勉強になりました。

・無駄な言葉、意味不明の言葉は使わない。
これは自分にも当てはまります。耳が痛い。

・接続語はたいてい省ける。確かに言えます。
私の文章も添削して頂くと、接続語が無くなることが殆ど。

・この事は日頃うすうす感じていましたが、
このようにスッキリ直された文例を見ると改めて納得します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・“具体的なコツ80個”は徐々にステップ・アップ出来るよう順番が配慮されているようです。
写真のように“こつ”“もやもや例文”“スッキリ例文”“ポイント”が見開きで解説されていて
とても分かり易い。
・思いつくがままに文章を書いていました。既に自分も理解し消化していた箇所もありましたが、
認識を新たにした内容の方が遥かに多く役に立ちました。お薦めです。
・作法以外で文章を書く時に困るのは、未知の事柄が実に多いということです。
“聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥”と言われますが、
今は聞く相手はネットワークで良いのでこっそりと調べて、恥をかくことも無くなりました。
全くいい時代になったものです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Better to ask the way than go astray.
See you.
I.O
★分かり易い“文章のコツ”
・図書館で本を物色していて、この本が目に留まりました。
・日頃文章を書く機会が多い人、少ない人様々だと思いますが、機会の多少はあっても誰も“書く”行為から逃ることは出来ないと思います。巷に出ている文章作法の本は大家が書かれたものが多くて敷居が高い。
・著者の高橋俊一氏は記者出身。
この本では最初に文章を書く為の「最強の6か条」が掲げられ“その具体的なコツ80個”が示されています。平易で歯切れがよく理解し易い本だと思う。
【最強の6か条】
1.文は短く
2.一点に集中して
3.誰が読んでも同じ意味に
4.同じ言葉、同じ内容は不要
5.句読点をしっかり打つ
6.積極的に改行する
1.文は短く
2.一点に集中して
3.誰が読んでも同じ意味に
4.同じ言葉、同じ内容は不要
5.句読点をしっかり打つ
6.積極的に改行する

・当たり前のこと、分かりきった内容、余分な言葉など、省略が可能なら削るとのこと。


・意味もなく飾らないこと、と書かれています。
文例の中の“すべからく”は本来の意味と違う解釈で使われている。
すなわち“当然”という意味で使うべきであり“全て”と言う意味ではない。
思い込みによる誤用は怖いです。
間違いは誰にも起こりうるので気をつけなくては…私も勉強になりました。


・無駄な言葉、意味不明の言葉は使わない。
これは自分にも当てはまります。耳が痛い。


・接続語はたいてい省ける。確かに言えます。
私の文章も添削して頂くと、接続語が無くなることが殆ど。


・この事は日頃うすうす感じていましたが、
このようにスッキリ直された文例を見ると改めて納得します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・“具体的なコツ80個”は徐々にステップ・アップ出来るよう順番が配慮されているようです。
写真のように“こつ”“もやもや例文”“スッキリ例文”“ポイント”が見開きで解説されていて
とても分かり易い。
・思いつくがままに文章を書いていました。既に自分も理解し消化していた箇所もありましたが、
認識を新たにした内容の方が遥かに多く役に立ちました。お薦めです。
・作法以外で文章を書く時に困るのは、未知の事柄が実に多いということです。
“聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥”と言われますが、
今は聞く相手はネットワークで良いのでこっそりと調べて、恥をかくことも無くなりました。
全くいい時代になったものです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<南大山観峰展望Pより2015.04.30>
Better to ask the way than go astray.
See you.

I.O