サービス提供責任者
7月から受講していた介護福祉士実務者研修。ネット学習と通学。ネット学習のテストは全部で1000問ぐらい答えたかな。通学は合計7日。今日で、無事通学7日目をおえて、終了。そして、修了。おわりという漢字の終了と、おさめたという漢字の修了。
6日目と7日目は実技の試験があったけど、なんとか、ガイドヘルパーさんに私の目の代わりになってもらって、無事実技もクリア。これで、来年には修了証が届くね。
目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。4月に豊中市役所をやめて、無職になったので、次の仕事として、自らヘルパー事業所をひらこうと決意。そのためには、サービス提供責任者が必要。だれか人を雇う余裕などないので、よし、私が、サービス提供責任者もやろう。サービス提供席に社であり、利用者。そんなヘルパー事業所をつくろう。お世話になっているヘルパーさんをヘルパーとしてお願いし、私の家事援助や同行援護をやってもらおう。障害者自身がヘルパーをたちあげ、そして自分にもっともよい形のサービスを受ける。これは、ヨーロッパのほうで実施されている障碍者福祉制度、パーソナルアシスタントという制度と似ている。障碍者が直ヘルパーを雇用し契約するという制度。ヘルパー事業所や行政をいったんかますよりも、よりダイレクトに障害者の意思を反映させることができるね。直接雇用なので、中間搾取もないね。より多くヘルパーに報酬をはらえて、障碍者はもっと自由にヘルパーを使える。
日本でこのパーソナルアシスタント制度はないので、それを実現させるためには、障碍者自身がヘルパー事業所を立ち上げないといけないのよね。
ヘルパー事業所を立ち上げるには。3つの条件がいる。
まずは、ヘルパー事業所は法人でないといけない。株式会社や、社団法人や、NPOなどなんらかの法人じゃないとヘルパー事業所は運営できない
そして、人員では、サービス提供責任者という資格をもったものが一人はいる。介護福祉士の資格をもっている人が原則だけど、介護福祉士実務者研修修了者っでもなれる。
そして、最後3つ目は、事務所があるということ。物理的なスペース、事務所がないとヘルパー事業所はひらけない。
以上の3つ、法人格、サ責、事務所、この3つが、結構大きなハードル。
まずは、そのひとつ、サ責、サービス提供席に社の資格を私がとったことで、のこる大きなハードルは2つだね。これから地道にクリアしていこう。
デスペア的全盲視覚障害者が介護福祉士実務者研修を受講して終了するポイント
1、専門学校
私が、介護福祉士実務者研修を受講したのは、三幸福祉カレッジ大阪駅前校。ネット学習と通学7日で、修了できて、立地もいいので交通アクセスもいいね。大阪駅前第2ビルの15階にあるので、私でも一度だれかにつれていってもらえれば、2度目からはひとりでいける。便利な橋にある。
2、費用
費用は142,670円。初任者研修なら5万円ぐらいで受講できるけど、その上位資格である実務者研修はこんなに高いのよね。ただ、これは、私が介護職員初任者研修を受講していなくて、何の資格ももっていなかったため、一番受講料がたかかった。初任者研修資格をもっていれば9万円とかでいいのかもね。
あと、本来なら、なんらかの割引が2万円ていどあったのだけど、例えば、事前に説明会に参加するとか、だれかの紹介とか、早期割引とかあったのだけども、私は、それは受けられず。カレッジのほうから割引なしでお願いしたいととお願いされたので、それを了承。
3、合理的配慮
全盲視覚障害者の私がどんな合理的配慮おを受けたか。大きく3つ。
1つは、テキストデータの提供。誓約書を提出し、オリジナルテキストをPDFデータで提供してもらえた。そのおかげで、ずいぶん、自宅ネット学習はスムーズにおこなえた。講義終了後は、データは返却。
2つ目は、アシスタント講師をつけてくれたこと。通学5日目までは、ケーススタディーで、事例にもとづいて、いろいろシートに分析して記入する。その記入が私は難しいということで、当初は、私がガイドヘルパーをつれてこないといけなかったのだけど、なぜか、私専属のアシスタント講師をつけてくれた。なぜここまで、配慮してくれたのかなぞ。
当初、カレッジと私と、大阪府障害者差別解消担当の障害福祉企画課権利擁護グループの職員との三者懇談では、盲人ウエカジさんがガイドヘルパーを用意するのなら、研修参加は認めますとのことだったけど、結局5日間は、アシスタント講師がついてくれた。
おそらく、これは、講師の研修もかねていたんだろうね。
最後3つ目は、マンツマン授業。通学6日目と7日目は、たん吸引や、経管栄養という、実技の科目。たん吸引のながれを、順番通りにまちがいなくやらないといけない。医師の指示所を確認し、手を洗い、物品をそろえて、本人に確認、説明と同意を市、たん吸引をするという一連の流れを5回やって、5回で全部、おぼえてひとりでやらないといけない。
本来なら、受講生12人がひとりの講師から、この実技科目をおそわるのだけども、目の見えない私は、説明に時間がかかる、評価、実技試験に時間がかかるということで、なんとマンツーマン。受講生はたった私ひとり、そして講師もひとり。朝9時30分から夕方4時30分までマンツーマン授業。
これはほんとありがたかったね。マンツーマンの講義だけど、私のとなりには、ガイドヘルパーさん、私がいつもお世話になっているガイドヘルパーさん。がいてくれて、実技試験で、目盛りをよんでもらったり、立ち位置を確認してもらったりした。私の目のかわりになって、私の指示にしたがって、情報をおしえてくれたガイドヘルパーさん。こういった実技試験では、盲人ではなく、ついついガイドヘルパーがでしゃばってしまうものだけど、それがまったくなかった。なので、ちゃんと盲人の実技試験という形になった。ありがたいね。
実技の1日目は、大阪府の権利擁護グループの職員2人も見学にきて、はたして、盲人が実技試験をクリアできるのか視察。マンツーマン講義ということもあり、しっかり実技を覚えられた私は、なんなく5回目のトライアルで無事クリア。職員も感心していた。
以上のように、テキストデータ、アシタント講師、マンツーマン実技。この3つの合理的配慮をしてくれたカレッジ。ありがたいね。
カレッジは、特別に合理的配慮をさせてもらうので、受講料の割引はなしで、定価でおねがいしたいということだった。割引がなかった分で、アシスタント講師や、マンツーマン実技を実現してもらえたので、こっちとしてはとってもお得だったね。ありがたい。
今回、私のクラスは、おそらく私が最年長49歳。ほかの受講生はだいたい20代。みんな優秀だね。そして、介護の仕事をしているので、みんな人当たりが良いし、コミュニケーション能力が高い稲。これにはびっくり。私以外の人は、来年の介護福祉士の国家試験を受験するよう。みんなはそれが目的。でも、私は、それができない。介護福祉士の試験を受けるには実務経験が3年以上ないとだめ、なので、私はとりあえず、実務者研修修了の資格でサービス提供席に社になろっと。
あとは、同行援護の応用家庭を終了すれば、同行援護のサービス提供席に社にもなれるね。これで障害福祉サービスで私が利用している家事援助、通院等解除、身体介護、同行援護の4つの事業の事業所をひらけることができるね。来年、同行援護の応用家庭の講義を受ける予定なので、それまでは、どんな法人がよいか、いろいろ勉強しなくちゃ。今は一番、合同会社、昔でいう有限会社がいいのかもと思っている。
こううやって、全盲視覚障害者がヘルパー事業所を立ち上げるために奮闘しているけども、北欧の福祉制度、パーソナルアシスタント制度があれば、こんな苦労しなくていいんだよね。いつか、日本にもパーソナルアシスタント制度が導入してほしいな。そのためには、政治の力が必要だね。
そして、私がこの研修を受けるために、どうしても必要だった実技試験のガイドヘルパーは、私の自腹。豊中市に同行援護の追加支給を申請しても、それは豊中市が定めているガイドラインの月基準をうわまるっているという理由だけで追加支給は拒否。豊中市に対しては、また、同行援護裁判をおこさないといけないね。ほんと目が見えないと、いろいろやるべきことが多い。人生1回だけだと足りないね。
7月から受講していた介護福祉士実務者研修。ネット学習と通学。ネット学習のテストは全部で1000問ぐらい答えたかな。通学は合計7日。今日で、無事通学7日目をおえて、終了。そして、修了。おわりという漢字の終了と、おさめたという漢字の修了。
6日目と7日目は実技の試験があったけど、なんとか、ガイドヘルパーさんに私の目の代わりになってもらって、無事実技もクリア。これで、来年には修了証が届くね。
目の見えない私、網膜色素変性症な私、盲人ウエカジ。4月に豊中市役所をやめて、無職になったので、次の仕事として、自らヘルパー事業所をひらこうと決意。そのためには、サービス提供責任者が必要。だれか人を雇う余裕などないので、よし、私が、サービス提供責任者もやろう。サービス提供席に社であり、利用者。そんなヘルパー事業所をつくろう。お世話になっているヘルパーさんをヘルパーとしてお願いし、私の家事援助や同行援護をやってもらおう。障害者自身がヘルパーをたちあげ、そして自分にもっともよい形のサービスを受ける。これは、ヨーロッパのほうで実施されている障碍者福祉制度、パーソナルアシスタントという制度と似ている。障碍者が直ヘルパーを雇用し契約するという制度。ヘルパー事業所や行政をいったんかますよりも、よりダイレクトに障害者の意思を反映させることができるね。直接雇用なので、中間搾取もないね。より多くヘルパーに報酬をはらえて、障碍者はもっと自由にヘルパーを使える。
日本でこのパーソナルアシスタント制度はないので、それを実現させるためには、障碍者自身がヘルパー事業所を立ち上げないといけないのよね。
ヘルパー事業所を立ち上げるには。3つの条件がいる。
まずは、ヘルパー事業所は法人でないといけない。株式会社や、社団法人や、NPOなどなんらかの法人じゃないとヘルパー事業所は運営できない
そして、人員では、サービス提供責任者という資格をもったものが一人はいる。介護福祉士の資格をもっている人が原則だけど、介護福祉士実務者研修修了者っでもなれる。
そして、最後3つ目は、事務所があるということ。物理的なスペース、事務所がないとヘルパー事業所はひらけない。
以上の3つ、法人格、サ責、事務所、この3つが、結構大きなハードル。
まずは、そのひとつ、サ責、サービス提供席に社の資格を私がとったことで、のこる大きなハードルは2つだね。これから地道にクリアしていこう。
デスペア的全盲視覚障害者が介護福祉士実務者研修を受講して終了するポイント
1、専門学校
私が、介護福祉士実務者研修を受講したのは、三幸福祉カレッジ大阪駅前校。ネット学習と通学7日で、修了できて、立地もいいので交通アクセスもいいね。大阪駅前第2ビルの15階にあるので、私でも一度だれかにつれていってもらえれば、2度目からはひとりでいける。便利な橋にある。
2、費用
費用は142,670円。初任者研修なら5万円ぐらいで受講できるけど、その上位資格である実務者研修はこんなに高いのよね。ただ、これは、私が介護職員初任者研修を受講していなくて、何の資格ももっていなかったため、一番受講料がたかかった。初任者研修資格をもっていれば9万円とかでいいのかもね。
あと、本来なら、なんらかの割引が2万円ていどあったのだけど、例えば、事前に説明会に参加するとか、だれかの紹介とか、早期割引とかあったのだけども、私は、それは受けられず。カレッジのほうから割引なしでお願いしたいととお願いされたので、それを了承。
3、合理的配慮
全盲視覚障害者の私がどんな合理的配慮おを受けたか。大きく3つ。
1つは、テキストデータの提供。誓約書を提出し、オリジナルテキストをPDFデータで提供してもらえた。そのおかげで、ずいぶん、自宅ネット学習はスムーズにおこなえた。講義終了後は、データは返却。
2つ目は、アシスタント講師をつけてくれたこと。通学5日目までは、ケーススタディーで、事例にもとづいて、いろいろシートに分析して記入する。その記入が私は難しいということで、当初は、私がガイドヘルパーをつれてこないといけなかったのだけど、なぜか、私専属のアシスタント講師をつけてくれた。なぜここまで、配慮してくれたのかなぞ。
当初、カレッジと私と、大阪府障害者差別解消担当の障害福祉企画課権利擁護グループの職員との三者懇談では、盲人ウエカジさんがガイドヘルパーを用意するのなら、研修参加は認めますとのことだったけど、結局5日間は、アシスタント講師がついてくれた。
おそらく、これは、講師の研修もかねていたんだろうね。
最後3つ目は、マンツマン授業。通学6日目と7日目は、たん吸引や、経管栄養という、実技の科目。たん吸引のながれを、順番通りにまちがいなくやらないといけない。医師の指示所を確認し、手を洗い、物品をそろえて、本人に確認、説明と同意を市、たん吸引をするという一連の流れを5回やって、5回で全部、おぼえてひとりでやらないといけない。
本来なら、受講生12人がひとりの講師から、この実技科目をおそわるのだけども、目の見えない私は、説明に時間がかかる、評価、実技試験に時間がかかるということで、なんとマンツーマン。受講生はたった私ひとり、そして講師もひとり。朝9時30分から夕方4時30分までマンツーマン授業。
これはほんとありがたかったね。マンツーマンの講義だけど、私のとなりには、ガイドヘルパーさん、私がいつもお世話になっているガイドヘルパーさん。がいてくれて、実技試験で、目盛りをよんでもらったり、立ち位置を確認してもらったりした。私の目のかわりになって、私の指示にしたがって、情報をおしえてくれたガイドヘルパーさん。こういった実技試験では、盲人ではなく、ついついガイドヘルパーがでしゃばってしまうものだけど、それがまったくなかった。なので、ちゃんと盲人の実技試験という形になった。ありがたいね。
実技の1日目は、大阪府の権利擁護グループの職員2人も見学にきて、はたして、盲人が実技試験をクリアできるのか視察。マンツーマン講義ということもあり、しっかり実技を覚えられた私は、なんなく5回目のトライアルで無事クリア。職員も感心していた。
以上のように、テキストデータ、アシタント講師、マンツーマン実技。この3つの合理的配慮をしてくれたカレッジ。ありがたいね。
カレッジは、特別に合理的配慮をさせてもらうので、受講料の割引はなしで、定価でおねがいしたいということだった。割引がなかった分で、アシスタント講師や、マンツーマン実技を実現してもらえたので、こっちとしてはとってもお得だったね。ありがたい。
今回、私のクラスは、おそらく私が最年長49歳。ほかの受講生はだいたい20代。みんな優秀だね。そして、介護の仕事をしているので、みんな人当たりが良いし、コミュニケーション能力が高い稲。これにはびっくり。私以外の人は、来年の介護福祉士の国家試験を受験するよう。みんなはそれが目的。でも、私は、それができない。介護福祉士の試験を受けるには実務経験が3年以上ないとだめ、なので、私はとりあえず、実務者研修修了の資格でサービス提供席に社になろっと。
あとは、同行援護の応用家庭を終了すれば、同行援護のサービス提供席に社にもなれるね。これで障害福祉サービスで私が利用している家事援助、通院等解除、身体介護、同行援護の4つの事業の事業所をひらけることができるね。来年、同行援護の応用家庭の講義を受ける予定なので、それまでは、どんな法人がよいか、いろいろ勉強しなくちゃ。今は一番、合同会社、昔でいう有限会社がいいのかもと思っている。
こううやって、全盲視覚障害者がヘルパー事業所を立ち上げるために奮闘しているけども、北欧の福祉制度、パーソナルアシスタント制度があれば、こんな苦労しなくていいんだよね。いつか、日本にもパーソナルアシスタント制度が導入してほしいな。そのためには、政治の力が必要だね。
そして、私がこの研修を受けるために、どうしても必要だった実技試験のガイドヘルパーは、私の自腹。豊中市に同行援護の追加支給を申請しても、それは豊中市が定めているガイドラインの月基準をうわまるっているという理由だけで追加支給は拒否。豊中市に対しては、また、同行援護裁判をおこさないといけないね。ほんと目が見えないと、いろいろやるべきことが多い。人生1回だけだと足りないね。











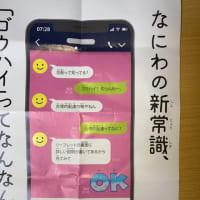
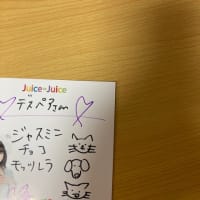
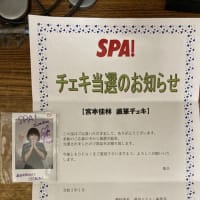

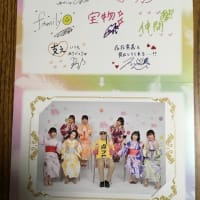









貴重な経験談を残してくださり、ありがとうございます。
私は全盲で、介護福祉士ではまだないです、介護福祉士実務者研修修了者です
ラインのオープンチャント 全盲ヘルパー事業所連絡会
にもぜひご参加を!