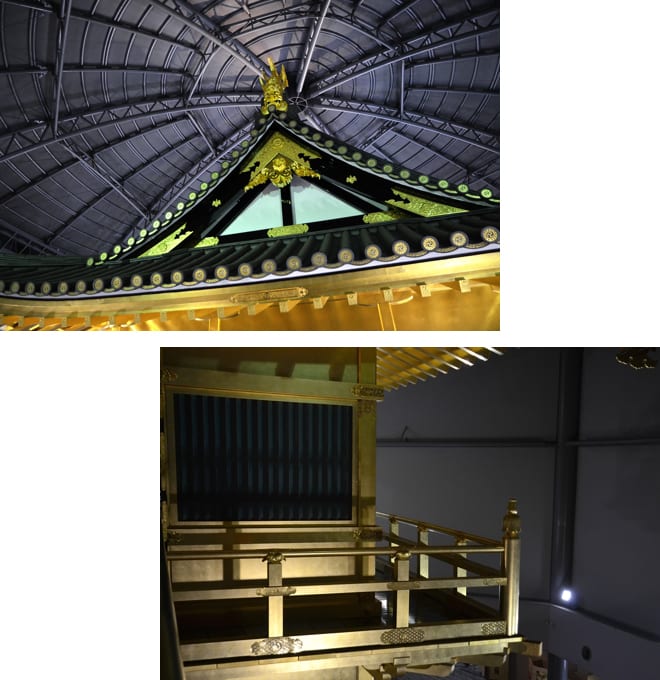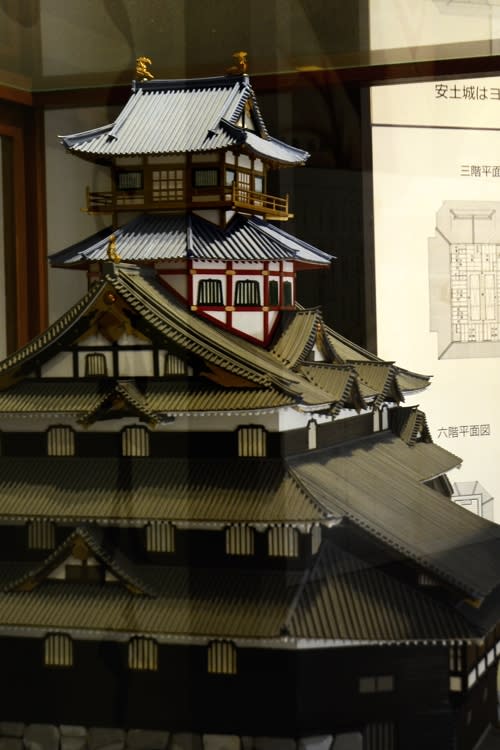木之本を出て、びわ湖東岸の湖岸道路を南下。2時間程の快適ドライブ♪
「水車橋」と書かれた信号を左折して川沿いに走ると、びわ湖の内湖のひとつ
伊庭内湖(いばないこ)に面した公園に到着します。

『能登川水車とカヌーランド』という名称のレジャー施設で、関西最大級の
水車が回っています。
広~い芝生広場の公園にポツンと、しかしデッカイ水車が・・・
ところで「能登川」って名前の川があるんだと思っていたら、そんな川は
存在しないんですよね。
能登川町を流れているのは須田川、伊庭内湖からびわ湖に流れる川は
大同川って言います。この川の南北には愛知川(えちがわ)町の愛知川、
西湖から流れている長命寺川には長命寺町があるし。普通は何とか川って
地名には同じ名前の川があるものですよね。
ここも大昔、一時期だけ瓜生川(うりゅうがわ)を能登川と呼んだ記録が
あるそうですが・・・今は能登川って河川はありません。



この地域は、琵琶湖の内湖の一つ「大中の湖」とその周辺の「小中の湖」の
干拓がすすめられ、1966年に大中の湖干拓事業が完成しました。
その時の一部が水路として残されたのが今の伊庭内湖と大同川です。
7世紀前半に大陸から伝えられたという「能登川水車」かつてはこの地域に
40基近くもあったようです。全て撤去されてしまっていたのを、平成3年に
着工した公園整備と同時に、直径13mの水車として復元されたとのこと。



ひたすら回り続ける大水車、何か悠久の時の流れを遡るかのようです。



そろそろ陽が落ちてきました・・・
『能登川水車とカヌーランド』、広大な芝生広場に水遊び体験エリア、
カヌー基地、水車資料館などが併設されています。
公園利用は無料、駐車場も無料。ただしボートの貸出しなどは有料です。
ここは水車資料館(入場無料)、レストハウス「みずぐるま」にも
なっていますが、私らが行った時にはもう閉店していました。

そうそう此処にも水車がありました。

公園のアイドル? 典型的な公園ネコですね。∧_∧



伊庭内湖、大同川ではフィッシングも楽しめますが、びわ湖は全域で
ブラックバスやブルーギルなどの外来魚のリリースは禁止ですからね!
回収ボックスや回収いけすに入れて帰って下さい。
なお、外来魚の密放流は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、
あるいはそれらが併科されます。



帰り道、湖東平野は収穫期を迎えた広大な黄金色の麦畑と水田は田植えが
始まっていました。

2014.5/18、能登川にて。
「水車橋」と書かれた信号を左折して川沿いに走ると、びわ湖の内湖のひとつ
伊庭内湖(いばないこ)に面した公園に到着します。

『能登川水車とカヌーランド』という名称のレジャー施設で、関西最大級の
水車が回っています。
広~い芝生広場の公園にポツンと、しかしデッカイ水車が・・・
ところで「能登川」って名前の川があるんだと思っていたら、そんな川は
存在しないんですよね。
能登川町を流れているのは須田川、伊庭内湖からびわ湖に流れる川は
大同川って言います。この川の南北には愛知川(えちがわ)町の愛知川、
西湖から流れている長命寺川には長命寺町があるし。普通は何とか川って
地名には同じ名前の川があるものですよね。
ここも大昔、一時期だけ瓜生川(うりゅうがわ)を能登川と呼んだ記録が
あるそうですが・・・今は能登川って河川はありません。



この地域は、琵琶湖の内湖の一つ「大中の湖」とその周辺の「小中の湖」の
干拓がすすめられ、1966年に大中の湖干拓事業が完成しました。
その時の一部が水路として残されたのが今の伊庭内湖と大同川です。
7世紀前半に大陸から伝えられたという「能登川水車」かつてはこの地域に
40基近くもあったようです。全て撤去されてしまっていたのを、平成3年に
着工した公園整備と同時に、直径13mの水車として復元されたとのこと。



ひたすら回り続ける大水車、何か悠久の時の流れを遡るかのようです。



そろそろ陽が落ちてきました・・・
『能登川水車とカヌーランド』、広大な芝生広場に水遊び体験エリア、
カヌー基地、水車資料館などが併設されています。
公園利用は無料、駐車場も無料。ただしボートの貸出しなどは有料です。
ここは水車資料館(入場無料)、レストハウス「みずぐるま」にも
なっていますが、私らが行った時にはもう閉店していました。

そうそう此処にも水車がありました。

公園のアイドル? 典型的な公園ネコですね。∧_∧



伊庭内湖、大同川ではフィッシングも楽しめますが、びわ湖は全域で
ブラックバスやブルーギルなどの外来魚のリリースは禁止ですからね!
回収ボックスや回収いけすに入れて帰って下さい。
なお、外来魚の密放流は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、
あるいはそれらが併科されます。



帰り道、湖東平野は収穫期を迎えた広大な黄金色の麦畑と水田は田植えが
始まっていました。

2014.5/18、能登川にて。











































































































































 〈Google Mapより〉
〈Google Mapより〉