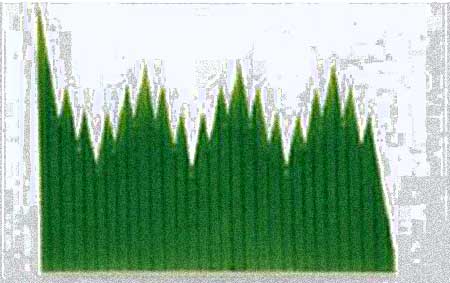人はどんな時に和ろうそくを灯すのだろう?
和ろうそくを知ってから、時折その事を考えてきました。
前回の記事で、ろうそく電灯があるのなら、和ろうそくの出番は?という問いかけで終わってしまいましたが、続きを書きたいと思います。
正徳芯和ろうそくを初めて販売したのが2007年9月。八女の祭りの時です。それ以来、様々な催事やイベントで商品を並べては、お客様と言葉を交わしてきました。その中で一番多い意見がこれ。
「和ろうそくは高いもんね。」
これですよ、これ。ともかく値段が高いから買おうという気がしない。観光地で和ろうそく職人の実演を見て、たまたま気が向いたというか、気が違ったというか、買う気がなかったのについ買ってしまった場合、家に帰った後、もったいなくて灯せません。何年も箪笥の肥やしになって、ついには忘れ去られて、肝心の仏事のチャンスが訪れても、結局灯さないパターンです。
かえって食べ物みたいに消費期限があれば、期限前にあわてて灯すかもしれませんが、和ろうそくに消費期限はありません。先日、大正時代の和ろうそくを灯したという方が言われました。
「ちゃんと普通に燃えたよ。きれいやった。」
最新鋭の電化製品は目まぐるしく葬り去られていくのに、ほぼ半永久的に使えてしまう和ろうそく。喜ばしいことなのかどうか複雑な気持ちになりました。
あわてて使う必要がないって状況では、人はますます和ろうそくを灯さないではありませんか。
人はどういう時に、和ろうそくを灯す行動をするのだろう?
和ろうそくに関わって以来、命題のようにのしかかるこのテーマが私の頭から離れません。
この答えがわかれば、人は和ろうそくを灯し、原料である櫨蝋が増産され、櫨の実の収穫が増え、櫨の木が植えられるはず。そうすると各地に櫨の風景が蘇ることは決して不可能な夢ではありません。
もちろん耳納山にも。
↓押してくださると励みになります。

人気blogランキングへ
和ろうそくを知ってから、時折その事を考えてきました。
前回の記事で、ろうそく電灯があるのなら、和ろうそくの出番は?という問いかけで終わってしまいましたが、続きを書きたいと思います。
正徳芯和ろうそくを初めて販売したのが2007年9月。八女の祭りの時です。それ以来、様々な催事やイベントで商品を並べては、お客様と言葉を交わしてきました。その中で一番多い意見がこれ。
「和ろうそくは高いもんね。」
これですよ、これ。ともかく値段が高いから買おうという気がしない。観光地で和ろうそく職人の実演を見て、たまたま気が向いたというか、気が違ったというか、買う気がなかったのについ買ってしまった場合、家に帰った後、もったいなくて灯せません。何年も箪笥の肥やしになって、ついには忘れ去られて、肝心の仏事のチャンスが訪れても、結局灯さないパターンです。
かえって食べ物みたいに消費期限があれば、期限前にあわてて灯すかもしれませんが、和ろうそくに消費期限はありません。先日、大正時代の和ろうそくを灯したという方が言われました。
「ちゃんと普通に燃えたよ。きれいやった。」
最新鋭の電化製品は目まぐるしく葬り去られていくのに、ほぼ半永久的に使えてしまう和ろうそく。喜ばしいことなのかどうか複雑な気持ちになりました。
あわてて使う必要がないって状況では、人はますます和ろうそくを灯さないではありませんか。
人はどういう時に、和ろうそくを灯す行動をするのだろう?
和ろうそくに関わって以来、命題のようにのしかかるこのテーマが私の頭から離れません。
この答えがわかれば、人は和ろうそくを灯し、原料である櫨蝋が増産され、櫨の実の収穫が増え、櫨の木が植えられるはず。そうすると各地に櫨の風景が蘇ることは決して不可能な夢ではありません。
もちろん耳納山にも。
↓押してくださると励みになります。

人気blogランキングへ