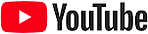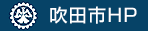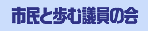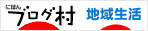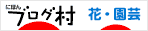未来にまっすぐ、市政にまっすぐ。まっすぐな人、池渕佐知子。無党派、市民派の前吹田市議会議員です。
未来にまっすぐ(池渕 佐知子のブログ)
学生に混じって
阪大工学部の大学院生に混じって講義を受けています。
社会人の受講生も私以外に数人いますが、私以外のみなさんは製造業の管理部門の人やコンサルタントの人なので、実際の企業の状況とかもご存知の人ばかりです。
私といえば、大学卒業後、少し製薬会社に勤めましたが、それ以降は、市役所の非常勤職員をしたぐらいなので、行政の仕組みはある程度わかっていたり創造できたりしますが、メーカーの実情はよくわかりません。
そんな中、事業を進める中で起こるリスクを最小にするためのマネジメント、コントロールの手法を学び、実際にどうなるのか?ということを考えていくのは、正直、しんどいところがあります。
ただ、現実の社会をわからないのは学生も同じなので、その学生たちが今行っている研究のことから、現実社会の状況を想像しつつ、マネジメントを学んでいますので、私も負けていられません。
リスク評価やリスクマネジメントを本業にしている講師の話を聞きながら、今の私の仕事に少しでも活かせるものはないか、探っているところです。
講義の本論もさることながら、講義の合間に話してもらえる、「今、こんなことがあってね」みたいな裏話がとても興味深いし、勉強になります。
たとえば、今日の余談では、
骨髄移植用・採取キットを製造している外国企業が事情により製造ストップになり、日本はその企業のキットしか承認していないので、キットが入手できないとなると骨髄移植そのものがストップしてしまう可能性があるので、他のメーカーのキットをできるだけ早く承認しないといけないけれど、そう簡単にはいかないという話をしてくれました。
幸い、厚労省が事の重大さを考慮し、異例の対応をとったことで、なんとか骨髄移植手術のストップは免れたようです。
詳しくは以下のURLに記事があります。
http://cancernavi.nikkeibp.co.jp/report/090303_01.html
でも、こういうことって、つまり承認されている移植キットが一社しかないということは、その唯一のものが今回のような事情で供給されなくなると、骨髄移植しか生命を守れない人の命を奪うことになるという、リスクになります。
つまりリスクを軽減、回避するためには、複数のものを承認するということが必要となります。
話を聞けば「な~んだ。最初からそうしておけばよかったのに」というようなことができていないのが現実には多く、だからこそ、リスクマネジメントが必要なんですよね。
社会人の受講生も私以外に数人いますが、私以外のみなさんは製造業の管理部門の人やコンサルタントの人なので、実際の企業の状況とかもご存知の人ばかりです。
私といえば、大学卒業後、少し製薬会社に勤めましたが、それ以降は、市役所の非常勤職員をしたぐらいなので、行政の仕組みはある程度わかっていたり創造できたりしますが、メーカーの実情はよくわかりません。
そんな中、事業を進める中で起こるリスクを最小にするためのマネジメント、コントロールの手法を学び、実際にどうなるのか?ということを考えていくのは、正直、しんどいところがあります。
ただ、現実の社会をわからないのは学生も同じなので、その学生たちが今行っている研究のことから、現実社会の状況を想像しつつ、マネジメントを学んでいますので、私も負けていられません。
リスク評価やリスクマネジメントを本業にしている講師の話を聞きながら、今の私の仕事に少しでも活かせるものはないか、探っているところです。
講義の本論もさることながら、講義の合間に話してもらえる、「今、こんなことがあってね」みたいな裏話がとても興味深いし、勉強になります。
たとえば、今日の余談では、
骨髄移植用・採取キットを製造している外国企業が事情により製造ストップになり、日本はその企業のキットしか承認していないので、キットが入手できないとなると骨髄移植そのものがストップしてしまう可能性があるので、他のメーカーのキットをできるだけ早く承認しないといけないけれど、そう簡単にはいかないという話をしてくれました。
幸い、厚労省が事の重大さを考慮し、異例の対応をとったことで、なんとか骨髄移植手術のストップは免れたようです。
詳しくは以下のURLに記事があります。
http://cancernavi.nikkeibp.co.jp/report/090303_01.html
でも、こういうことって、つまり承認されている移植キットが一社しかないということは、その唯一のものが今回のような事情で供給されなくなると、骨髄移植しか生命を守れない人の命を奪うことになるという、リスクになります。
つまりリスクを軽減、回避するためには、複数のものを承認するということが必要となります。
話を聞けば「な~んだ。最初からそうしておけばよかったのに」というようなことができていないのが現実には多く、だからこそ、リスクマネジメントが必要なんですよね。
コメント(0)|Trackback()
?