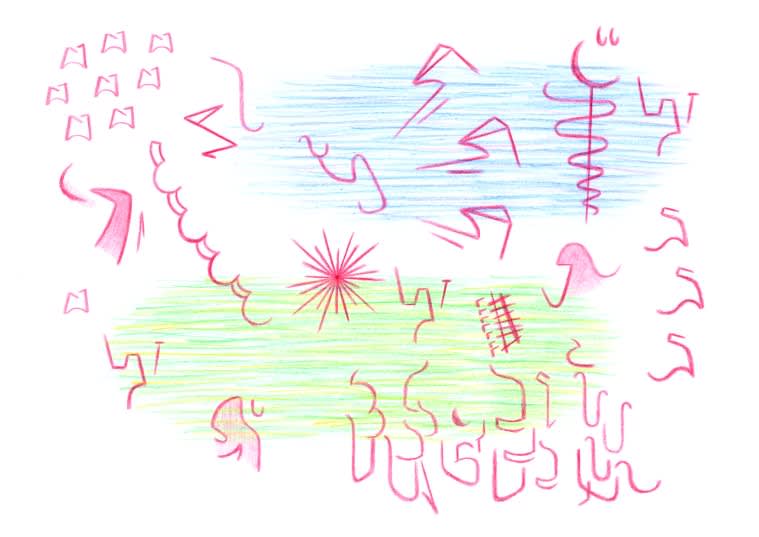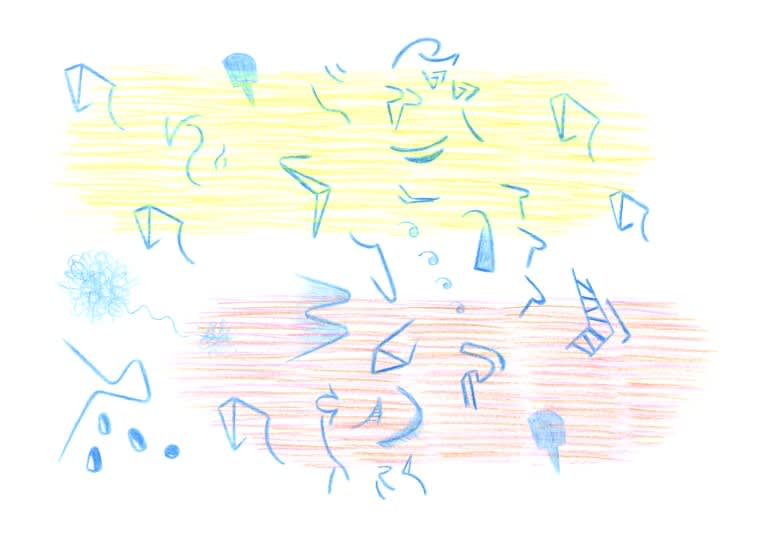今日はサク山さん家のチョコ次郎君です。

知らないうちに誕生し、いつの間にかメジャーなお菓子になっていたサク山チョコ次郎。ミルククリームをチョコレートとビスケットでサンド。間違いのない組み合わせ。ビスケットがサク山ですね。
僕は以前、イベント運営のアルバイトをしていました。野球とかサッカーとかコンサートなどのイベントが開催されたとき、接客を行う仕事です。
ある年の冬、福岡ドームでポケモンのイベントが開催されました。野球のシーズンオフの期間には、よくこの手のイベントが開かれるのです。
ポケモンの遊具があったり、グッズが販売されてたり、ゲームのレアキャラクターを入手できたりするイベントでした。期間中は、ピカチュウがやってくることになっていました。言うたら、着ぐるみですね。
しかし、前の会場で着ぐるみが破損してしまっており、修復が間に合っていませんでした。そのため、「着ぐるみ修復中につき、ピカチュウ来場できず」という状況になっていたのです。
仕事前に、社員からそのことについて注意がありました。
もし大人からピカチュウ不在について尋ねられたら、「着ぐるみが破損して、修復が間に合っていない」と、事実をそのまま伝えていい。でも子供に訊かれたら、「ピカチュウがドームに来る途中で敵に襲われた」と答えるように、と。
大人と子供で説明を変えろという注意でした。なるほどと思いましたね。
でもひとつ疑問に思ったのが、「ピカチュウが敵に襲われた」と聞かされた子供は不安にならないのか、ということです。ピカチュウは大丈夫なのかと動揺しないか。心配するあまり、泣き出してしまわないか。「道に迷ったらしい」くらいの説明のほうがよかったのではないか。そんなことを思いました。
しかしまあ、ものは言いようですね。
言い方、といって思い出すのが、引き算です。小学一年で引き算を習ったとき、すんなりと理解できませんでした。
たとえば、38-15とかならすぐにできたんですけど、42-27みたいなのをどうやって解けばいいのか、なかなか呑み込めませんでした。
ネックになったのが、「借りてくる」というやつです。一の位、2だけだと7引くことができないから、十の位から借りてくる。そして12-7にする。
その理屈を理解するのに手間取ったのです。先生の説明を何度か聞いて、ようやく吞み込めました。
今にして思うのですが、この「借りてくる」という説明、正確とは言えないのではないでしょうか。
だって、「借りる」のであれば、常識的・礼儀的には返さなければなりませんが、借りられた十の位は、返ってくることはないのですから。
借りられたら、借りられたまんま。借りっぱなしです。けっして返されることはない。借りパクです。
だから、「借りてくる」じゃなくて、「もらう」って言うべきじゃないかと思うんですよ。そのほうが正確でしょ?
子供に引き算教えるのにも、そのほうが理解されやすいんじゃないでしょうか。返さないのに「借りる」なんて、おかしいじゃないですか。そこのおかしさに引っかかってしまう子供もいるかもしれません。そこに気を取られることで、引き算の理解が遅れてしまう。そんなこともあるかもしれないのです。
だから、より正確に引き算を理解するために、「借りる」じゃなくて「もらう」にすべきではないかと思うのですよ。
なんか、この「借りる」って言葉、日本的なおためごかしが潜んでいるような気もするんですよね。
お金のやり取りでも言うじゃないですか、「借りる」って。でも、多くの場合、貸したお金は戻ってきませんよね。だから実質、それは「もらっている」のです。借りているわけではない。
借り手はほとんどの場合、返すつもりなく「貸して」と言っている。貸し手も、うすうすお金は返ってこないと気づいている。その暗黙の了解の上で貸し借りは行われるのです。
借り手は、「ちょうだい」と言うより、「貸して」と言ったほうがお金が手に入りやすいことを見越して、「貸して」と言う。貸し手は、借り手に返す気がないことを察しつつも、お金がないとコイツは困るだろうと、相手を思いやって貸す。そんなふうにして「貸し借り」は成立するのです。
表向きは「貸し借り」、実情は「譲渡」です。
この、「返す気がないのに貸してと言う」ような、事実の湾曲というか、遠回しな表現というか、そんな言い方って、いかにも日本的ですよね。ハッキリとものを言わない。できるだけボヤかす。
そのほうが角が立たないということなのか。人間関係を円滑にするための工夫なのか。大人の分別なのか。
そして、この日本的遠回し表現が、引き算の説明にも入り込んできているのではないでしょうか。
まあ一概に否定するつもりはないですけどね。でも日本以外の国では引き算どのように説明してるのかが気になりますね。日本と同じように「借りてくる」と言っているのか、正確に「もらう」と言っているのか。
よく外国(おもに欧米)の方から、「日本人は言ってることとやってることが違う」みたいな批判を受けますけど、それってこの湾曲表現が原因ですよね。それを踏まえて考えると、日本以外では「もらう」と言っているのではないかと思います。
そのへんをご存じの方、いらっしゃいましたらご一報ください。

知らないうちに誕生し、いつの間にかメジャーなお菓子になっていたサク山チョコ次郎。ミルククリームをチョコレートとビスケットでサンド。間違いのない組み合わせ。ビスケットがサク山ですね。
僕は以前、イベント運営のアルバイトをしていました。野球とかサッカーとかコンサートなどのイベントが開催されたとき、接客を行う仕事です。
ある年の冬、福岡ドームでポケモンのイベントが開催されました。野球のシーズンオフの期間には、よくこの手のイベントが開かれるのです。
ポケモンの遊具があったり、グッズが販売されてたり、ゲームのレアキャラクターを入手できたりするイベントでした。期間中は、ピカチュウがやってくることになっていました。言うたら、着ぐるみですね。
しかし、前の会場で着ぐるみが破損してしまっており、修復が間に合っていませんでした。そのため、「着ぐるみ修復中につき、ピカチュウ来場できず」という状況になっていたのです。
仕事前に、社員からそのことについて注意がありました。
もし大人からピカチュウ不在について尋ねられたら、「着ぐるみが破損して、修復が間に合っていない」と、事実をそのまま伝えていい。でも子供に訊かれたら、「ピカチュウがドームに来る途中で敵に襲われた」と答えるように、と。
大人と子供で説明を変えろという注意でした。なるほどと思いましたね。
でもひとつ疑問に思ったのが、「ピカチュウが敵に襲われた」と聞かされた子供は不安にならないのか、ということです。ピカチュウは大丈夫なのかと動揺しないか。心配するあまり、泣き出してしまわないか。「道に迷ったらしい」くらいの説明のほうがよかったのではないか。そんなことを思いました。
しかしまあ、ものは言いようですね。
言い方、といって思い出すのが、引き算です。小学一年で引き算を習ったとき、すんなりと理解できませんでした。
たとえば、38-15とかならすぐにできたんですけど、42-27みたいなのをどうやって解けばいいのか、なかなか呑み込めませんでした。
ネックになったのが、「借りてくる」というやつです。一の位、2だけだと7引くことができないから、十の位から借りてくる。そして12-7にする。
その理屈を理解するのに手間取ったのです。先生の説明を何度か聞いて、ようやく吞み込めました。
今にして思うのですが、この「借りてくる」という説明、正確とは言えないのではないでしょうか。
だって、「借りる」のであれば、常識的・礼儀的には返さなければなりませんが、借りられた十の位は、返ってくることはないのですから。
借りられたら、借りられたまんま。借りっぱなしです。けっして返されることはない。借りパクです。
だから、「借りてくる」じゃなくて、「もらう」って言うべきじゃないかと思うんですよ。そのほうが正確でしょ?
子供に引き算教えるのにも、そのほうが理解されやすいんじゃないでしょうか。返さないのに「借りる」なんて、おかしいじゃないですか。そこのおかしさに引っかかってしまう子供もいるかもしれません。そこに気を取られることで、引き算の理解が遅れてしまう。そんなこともあるかもしれないのです。
だから、より正確に引き算を理解するために、「借りる」じゃなくて「もらう」にすべきではないかと思うのですよ。
なんか、この「借りる」って言葉、日本的なおためごかしが潜んでいるような気もするんですよね。
お金のやり取りでも言うじゃないですか、「借りる」って。でも、多くの場合、貸したお金は戻ってきませんよね。だから実質、それは「もらっている」のです。借りているわけではない。
借り手はほとんどの場合、返すつもりなく「貸して」と言っている。貸し手も、うすうすお金は返ってこないと気づいている。その暗黙の了解の上で貸し借りは行われるのです。
借り手は、「ちょうだい」と言うより、「貸して」と言ったほうがお金が手に入りやすいことを見越して、「貸して」と言う。貸し手は、借り手に返す気がないことを察しつつも、お金がないとコイツは困るだろうと、相手を思いやって貸す。そんなふうにして「貸し借り」は成立するのです。
表向きは「貸し借り」、実情は「譲渡」です。
この、「返す気がないのに貸してと言う」ような、事実の湾曲というか、遠回しな表現というか、そんな言い方って、いかにも日本的ですよね。ハッキリとものを言わない。できるだけボヤかす。
そのほうが角が立たないということなのか。人間関係を円滑にするための工夫なのか。大人の分別なのか。
そして、この日本的遠回し表現が、引き算の説明にも入り込んできているのではないでしょうか。
まあ一概に否定するつもりはないですけどね。でも日本以外の国では引き算どのように説明してるのかが気になりますね。日本と同じように「借りてくる」と言っているのか、正確に「もらう」と言っているのか。
よく外国(おもに欧米)の方から、「日本人は言ってることとやってることが違う」みたいな批判を受けますけど、それってこの湾曲表現が原因ですよね。それを踏まえて考えると、日本以外では「もらう」と言っているのではないかと思います。
そのへんをご存じの方、いらっしゃいましたらご一報ください。
今日は遊具です。


あみじゃががあってぼうじゃががある、それはいい。しかしポテコがあるのになげわがあるとは?何がどう違う?その必然性は?
いくら輪投げをしてもわからない。誰か教えてください。
輪投げとはつまりゲームのこと。ゲームについて話しましょう。
子供のころ、町内のイベントかなんかで遠足に行ったことがありました。参加者は、小学生が8割、引率の大人が2割くらい。大きめの公園が目的地でした。
その公園で、主催者によるゲームが開催されました。
最初に行われたのは、「焼きイカゲーム」でした。どんなゲームかというと、親がひとりいて、その親が、「焼きイカ焼きイカ焼けたかな、ジュッ」と歌いながら踊る。ほかの人たちはその呼びかけに応じて、まだ焼けてないなと思ったら「まだ焼けない」、焼き上がったと思ったら「もう焼けた」と答える、というもの。みんなが「もう焼けた」と答えたら終わりになるのです。
極めてシンプルなルールです。普通のゲームには備わっている、偶然性やギャンブル性がありません。「鬼が交代する」といったこともないので、一回で終了します。
「これ面白いのか?」という疑問とともに、ゲームがスタートしました。
主催者兼ゲームの提唱者のおじさんが、「焼きイカ焼きイカ焼けたかな、ジュッ」とリズミカルに歌いながら、コミカルなダンスを披露しました。一回目なんで、みんな「まだ焼けない」と答えました。
おじさんは、二回三回と「焼きイカ焼きイカ焼けたかな、ジュッ」をくり返しました。みんな「まだ焼けない」と答えました。
だんだん面白くなってきました。子供たちの間に、「何度くり返しても「まだ焼けない」と答えたほうが面白い」という空気ができあがっていきました。
おじさんにひたすらダンスをくり返させたほうが面白い。だから絶対に「もう焼けた」とは言わない。子供たちは、誰が言い出すでもなく、みんなそう思い始めていました。
みんな、何度も何度も「もう焼けない」と答えました。おじさんはそのたびに、「焼きイカ焼きイカ」と踊りました。
あまりにもイカが焼き上がらないので、とうとうおじさんは「もう終わり!」と言って、ゲームを打ち切りました。疲れたからでもあるでしょうが、子供たちの様子から、「もう焼けた」と言いそうにないと察したのでしょう。
おじさんはゲームの失敗に落胆し、子供たちは大ウケしていました。
その次に、「てんかたいへい」というゲームが行われました。漢字で「天下太平」か「天下泰平」だと思います。
どんなゲームかというと、まず、みんなで輪になって座る。帽子を2つ用意して、輪の中のひとりにそのひとつをかぶせ、少し離れたところのもうひとりに、もうひとつをかぶせる。
帽子をかぶっている人は、「てんかたいへい」と言いながら、手を3回叩く。それがすんだら、帽子を右隣の人にかぶせる。
みんなが「てんかたいへい」と言いながら、帽子を隣の人にパスしていくのです。2つ目の帽子が、1つ目に追いついてしまったら、その時点で帽子をかぶっていた人の負け、というルールです。
これはけっこう盛り上がりました。みんな2つ目の帽子に追いつかれないよう、早口で「てんかたいへい」と叫んでいました。
でも、僕はふと思いました。「みんな同じスピードで2つの帽子を回していたら、いつまでたっても追いつかないのではないか」と。
実際2つの帽子は、ずっと同じ距離を保っていました。これでは、いつまでたっても終わりません。
そこで僕は一計を案じました。1つ目の帽子が自分のところに来たとき、超スローペースで「てぇんかぁたぁいへぇい」と言ったのです。右隣のおばさんが焦って、「ちょっとアンタ、はやくせんね!」と叫びました。
そして2つ目の帽子が来たときは、ハイスピードで「てんかたいへい」を言いました。少しは距離が縮まりましたが、ほかの人たちは2つとも同じスピードでやっていたので、結局2つの帽子は重なりませんでした。負けが出ることなく、みんなが体力を使い果たすとともにゲームは終了したのです。
おかしなゲームを2つ体験した、そんな遠足でした。
そのインパクトが強かったため、ゲーム以外のことは覚えていません。
皆さんも、ヒマでヒマでしょうがないことがあれば、一度やってみてください。人生を浪費するはずですから。
あ、あとゲームと言えばですね、玉入れについて思うことがあるんですよ。運動会の定番競技、玉入れ。
あれの大人がチーム組んで競う大会があるじゃないですか。アマチュアのスポーツ大会みたいな。
その参加選手がやってる、最初に玉をかたまりにして垂直に投げ入れるテクニックがありますよね。見たことあります?玉10~20個くらいを筒状のかたまりにして、カゴの真下から投げるやつです。あっという間に全部の玉を入れちゃうじゃないですか。
あれ、何が楽しいんでしょうね?
玉入れなんて、何も考えずに「ウキャー」って叫びながら投げまくるのが楽しいんじゃないですか。それをあんな、機械が淡々と作業をこなすような入れ方して、何が面白いというのか。
勝つことだけを考えたらそれが最善なんでしょうけど、競技としての楽しさは死んでますよね。なんの喜びもなく、勝利のためだけに黙々と玉を放っているようにしか見えません。コンピューターが玉入れしてんのか?ロボット甲子園なのか?
誰が考え出したか知りませんけど、あのやり方がとにかく早い、確実に勝てるとなったら、みんな真似せざるを得なくなったんでしょうね。で、玉が全部入る時間は格段に短縮されたけど、機械的に作業をこなすだけなので、楽しさは失われてしまった。
競技としての玉入れはアップグレードされたけど、つまらないものになってしまった。そんな悲しい「革新」だったのでしょう。
玉入れの楽しさを取り戻すには、もうあのやり方を禁止するしかないですね。「ウキャー」と叫んで投げまくる、あの原始的な玉入れを復活させるしかないでしょう。
余計なお世話ですかね。


あみじゃががあってぼうじゃががある、それはいい。しかしポテコがあるのになげわがあるとは?何がどう違う?その必然性は?
いくら輪投げをしてもわからない。誰か教えてください。
輪投げとはつまりゲームのこと。ゲームについて話しましょう。
子供のころ、町内のイベントかなんかで遠足に行ったことがありました。参加者は、小学生が8割、引率の大人が2割くらい。大きめの公園が目的地でした。
その公園で、主催者によるゲームが開催されました。
最初に行われたのは、「焼きイカゲーム」でした。どんなゲームかというと、親がひとりいて、その親が、「焼きイカ焼きイカ焼けたかな、ジュッ」と歌いながら踊る。ほかの人たちはその呼びかけに応じて、まだ焼けてないなと思ったら「まだ焼けない」、焼き上がったと思ったら「もう焼けた」と答える、というもの。みんなが「もう焼けた」と答えたら終わりになるのです。
極めてシンプルなルールです。普通のゲームには備わっている、偶然性やギャンブル性がありません。「鬼が交代する」といったこともないので、一回で終了します。
「これ面白いのか?」という疑問とともに、ゲームがスタートしました。
主催者兼ゲームの提唱者のおじさんが、「焼きイカ焼きイカ焼けたかな、ジュッ」とリズミカルに歌いながら、コミカルなダンスを披露しました。一回目なんで、みんな「まだ焼けない」と答えました。
おじさんは、二回三回と「焼きイカ焼きイカ焼けたかな、ジュッ」をくり返しました。みんな「まだ焼けない」と答えました。
だんだん面白くなってきました。子供たちの間に、「何度くり返しても「まだ焼けない」と答えたほうが面白い」という空気ができあがっていきました。
おじさんにひたすらダンスをくり返させたほうが面白い。だから絶対に「もう焼けた」とは言わない。子供たちは、誰が言い出すでもなく、みんなそう思い始めていました。
みんな、何度も何度も「もう焼けない」と答えました。おじさんはそのたびに、「焼きイカ焼きイカ」と踊りました。
あまりにもイカが焼き上がらないので、とうとうおじさんは「もう終わり!」と言って、ゲームを打ち切りました。疲れたからでもあるでしょうが、子供たちの様子から、「もう焼けた」と言いそうにないと察したのでしょう。
おじさんはゲームの失敗に落胆し、子供たちは大ウケしていました。
その次に、「てんかたいへい」というゲームが行われました。漢字で「天下太平」か「天下泰平」だと思います。
どんなゲームかというと、まず、みんなで輪になって座る。帽子を2つ用意して、輪の中のひとりにそのひとつをかぶせ、少し離れたところのもうひとりに、もうひとつをかぶせる。
帽子をかぶっている人は、「てんかたいへい」と言いながら、手を3回叩く。それがすんだら、帽子を右隣の人にかぶせる。
みんなが「てんかたいへい」と言いながら、帽子を隣の人にパスしていくのです。2つ目の帽子が、1つ目に追いついてしまったら、その時点で帽子をかぶっていた人の負け、というルールです。
これはけっこう盛り上がりました。みんな2つ目の帽子に追いつかれないよう、早口で「てんかたいへい」と叫んでいました。
でも、僕はふと思いました。「みんな同じスピードで2つの帽子を回していたら、いつまでたっても追いつかないのではないか」と。
実際2つの帽子は、ずっと同じ距離を保っていました。これでは、いつまでたっても終わりません。
そこで僕は一計を案じました。1つ目の帽子が自分のところに来たとき、超スローペースで「てぇんかぁたぁいへぇい」と言ったのです。右隣のおばさんが焦って、「ちょっとアンタ、はやくせんね!」と叫びました。
そして2つ目の帽子が来たときは、ハイスピードで「てんかたいへい」を言いました。少しは距離が縮まりましたが、ほかの人たちは2つとも同じスピードでやっていたので、結局2つの帽子は重なりませんでした。負けが出ることなく、みんなが体力を使い果たすとともにゲームは終了したのです。
おかしなゲームを2つ体験した、そんな遠足でした。
そのインパクトが強かったため、ゲーム以外のことは覚えていません。
皆さんも、ヒマでヒマでしょうがないことがあれば、一度やってみてください。人生を浪費するはずですから。
あ、あとゲームと言えばですね、玉入れについて思うことがあるんですよ。運動会の定番競技、玉入れ。
あれの大人がチーム組んで競う大会があるじゃないですか。アマチュアのスポーツ大会みたいな。
その参加選手がやってる、最初に玉をかたまりにして垂直に投げ入れるテクニックがありますよね。見たことあります?玉10~20個くらいを筒状のかたまりにして、カゴの真下から投げるやつです。あっという間に全部の玉を入れちゃうじゃないですか。
あれ、何が楽しいんでしょうね?
玉入れなんて、何も考えずに「ウキャー」って叫びながら投げまくるのが楽しいんじゃないですか。それをあんな、機械が淡々と作業をこなすような入れ方して、何が面白いというのか。
勝つことだけを考えたらそれが最善なんでしょうけど、競技としての楽しさは死んでますよね。なんの喜びもなく、勝利のためだけに黙々と玉を放っているようにしか見えません。コンピューターが玉入れしてんのか?ロボット甲子園なのか?
誰が考え出したか知りませんけど、あのやり方がとにかく早い、確実に勝てるとなったら、みんな真似せざるを得なくなったんでしょうね。で、玉が全部入る時間は格段に短縮されたけど、機械的に作業をこなすだけなので、楽しさは失われてしまった。
競技としての玉入れはアップグレードされたけど、つまらないものになってしまった。そんな悲しい「革新」だったのでしょう。
玉入れの楽しさを取り戻すには、もうあのやり方を禁止するしかないですね。「ウキャー」と叫んで投げまくる、あの原始的な玉入れを復活させるしかないでしょう。
余計なお世話ですかね。
大澤真幸の『経済の起源』(岩波書店)を読んだ。
これは社会学者の大澤が、経済とは何か、贈与交換から商品交換(貨幣経済)への転換はどのようにして起こったのか、貨幣はどのようにして生まれたかなど、経済の謎を解くために、幾つもの文献にあたりながら、東西の文化に触れ、歴史を辿った探究の書である。この中の第5章「ヒエラルキーの形成――再分配へ」で、贈与に関して、興味深い事例が紹介されている。
十九世紀から二十世紀の初頭にかけて、アマゾンやアフリカの狩猟採集民の社会に入った宣教師や探検家をたいへん驚かせたことがある。定型的な筋をもっているのだが、その代表として、イギリス人宣教師たちがコンゴで体験したことを紹介しよう。現地人の一人が重い肺炎にかかったので、宣教師たちは、彼を治療し、濃いチキンスープなどを与えた。おかげで、この病人は命をつなぎとめた。宣教師たちが、次の目的地へと向けて旅立つ頃には、彼はすっかり回復していた。宣教師たちが旅支度をしていると、この男がやってきて、なんと宣教師たちに贈り物を要求してきたのだ。宣教師たちはびっくりして、これを拒否すると、男の方も同じくらい驚き、大いに気分を害した。宣教師が、贈り物によって感謝を示すべきはあなたの方ではないかと言うと、彼の方は、「あなた方白人は、恥知らずだ!」と怒って言い返してきた。
このエピソードは、二十世紀前半の哲学者リュシアン・レヴィ゠ブリュールの著書から引いたものである。レヴィ゠ブリュールは、「未開社会」の人々が、「われわれ」とは異なる論理で思考し、行動していることを示す証拠として、似たような報告事例をたくさん蒐集している(Lévy‐Bruhl 1923)。溺れていた男を救ってやったところ、その男から高価な服を要求されたとか、トラに襲われて大けがを負った人を治療してやったところ、さらにナイフを欲しいと言われたとか、である。これらはすべて、西洋人側が現地の人に対して、贈与に相当することを行い、西洋人の観点からは現地の人の方からお返しの贈与があってしかるべき、と思われていたところが、逆に、現地の人の方からさらなる贈与を要求されている。これをどう説明したらよいのだろうか。
とてつもない忘恩のようにも思えるのだが、そうではない。忘恩であれば、わざわざ追加的な贈与を要求したりはしない(単純に無視し、関係を断とうとするはずだ)。次のように解釈すればよい。宣教師によって肺炎を治してもらった男は、当然、宣教師に感謝している。彼は、宣教師との親密な関係を維持したい。とりわけ、彼は、宣教師を自分にとっての「主人」のようなものとして尊敬したいと思っている――そして、そのことは宣教師側にとっても喜ばしいことだと想定している――のではないか。
ここで、主人とは何か、がポイントになる。主人とは、従者に対して、(価値あるものを)与え続ける者である。言い換えれば、従者は、主人に対して、いつまでも消えない負債の感覚をもちたいのだ。彼の方から何かをお返しして、負債を無化してしまえば、宣教師を主人として仰ぎ続けることが不可能になる。彼は、宣教師になおいっそう負債を負い、負債感を維持したいがために、さらなる贈り物を要求したのだ。当然主人たる宣教師が喜んで、何かを贈ってくるだろう、と予期して。
うーん、面白い。
このような贈与のありかたは、現代の日本にも馴染まない。贈り物をすべきは助けられたほう、というのがゆるぎない常識としてある。
だが、上の事例の狩猟採集民の感覚から眺めてみれば、助けてもらった相手に贈り物をすることは、相手との関係を断つ方向に働いていると言える。贈り物をして、感謝を伝える。そうすればそこで貸し借りは清算され、負い目を感じる必要はなくなる。そうなれば、それ以上相手との関係を維持する必要はなくなるのだ。
もちろんその後も関係を保ち続けることはできる。だが、贈り物をしてしまえば、そこで関係を絶ったとしても非礼とは見做されない。助けてもらった相手への贈り物は、基本的には関係を維持するのではなく、清算する方向に働くのだ。助けてもらった相手に贈り物をしたいと思う、その背後には、「貸し借りをなくしたい」「関係を清算したい」という願望も貼りついているのではないか。
その点を合わせて考えると、助けてもらった相手に贈り物を求める文化圏は、そうでない文化圏よりも、人間関係が密になるのは間違いない。だとすれば、「助けてもらった相手に贈り物を求める習慣」を日本に定着させれば、日本人の人間関係は今よりも密になるだろう。引用文にあるように、それは主従関係を基調としているので、「平等」を原理主義的に追求している日本社会からは反発されるかもしれないが。それに、恐らくは「助けてもらった相手に贈り物をする」のが日本社会の長年の常識だったはずで、それに反する習慣を易々と受け入れられるのか、という問題もある。(平等という点をさらに突っ込んで考えてみると、平等という観念があまり発達していない原始社会ほど、上下関係・主従関係に抵抗がないから、「助けてもらった相手に贈り物を求める」文化的傾向があり、平等の観念が浸透するほど上下関係・主従関係に抵抗が生まれ、「助けてもらった相手に贈り物をする」ほうに逆転していくのかもしれない)
なので、日本社会にこのような贈与の感覚を根付かせるのは難しいかもしれない。それでも、このような贈与のありかたもあるということ、現代日本の贈与のありかただけが唯一の形ではないことを知るのは、ひとつの希望のように感じられるのではないか。
少なくとも、僕はそう感じた。異なる視点を導入することで、自分の属する文化を相対化し、今とは違うありかただってあるのだと知る。こことは違う文化、違う時代には異なる常識があって、それはけっして非現実的なものではなく、自分たちの文化に移植することも可能かもしれないと気づく。それは思考の風通しをよくして、ほんのわずかでも社会の息苦しさを解消してくれる効果があるだろう。
ところで、助けてもらった相手に贈り物をする動因、恩返ししたいという願望は、「負債感」によって基礎づけられるものだ。この負債に関してもまた、大澤は鋭い考察を加えている。
人は長い間、そしてときには今日でも、「金を貸す人間」は邪悪な人物の典型であるかのように考えてきたのだ。もし負債こそが罪の中の罪であるとすれば、貸す者には何の問題もないはずだ。逆に借りながら、まだ返していない者こそが悪い。それなのに、金貸しは、いつも悪人である。
世界文学や民間説話を振り返ってみるとよい。金を貸す善人が描かれていたためしがない。『ヴェニスの商人』のシャイロックのように、金を貸す者は常に邪悪な側にいる。考えてみれば、この戯曲で、負債を清算していないのは、ヴェニスの貿易商人のアントーニオの方なのに、彼は善人として描かれている。『罪と罰』では、金貸しは被害者であって、罪を犯すのは苦学生のラスコーリニコフだが、読者は、ラスコーリニコフによって殺されたのが金貸しであることで、少しだけ安心しているはずだ。あんなババアは殺されても仕方がなかったんだ、と。(中略)
一般には、贈与交換における互酬こそが、正義の原型と見なされている。この通念に従えば、「互酬が未だに実現していない状態に対して責任があること」こそが、要するにお返しをせずに、負債を残していることこそが、罪の原型である。実際、ニーチェをはじめとする多くの思想家・哲学者が罪を、「負債の一般化」として理解してきた。
(中略)
贈与は、他者にとってポジティヴな価値のあるモノを、その他者にもたらすことである。それゆえ、一般に、贈与は、倫理的には善きこととして評価される。しかし、同時に、贈与には否定的な意味も宿る。なぜなら、贈与は、与え手が受け手を支配する力を生み出してしまうからだ。受け手側の負債の意識を媒介にして、贈与は、与え手が受け手を支配することを可能にする。
受け手の方に負債の意識が生ずる原因は、贈与が、一般に、互酬化されることへの強い社会的圧力を伴うことにある。与えた側は、ほとんどの場合、お返しがあって当然だと思っている。そして受け手の側は、お返しすることを義務だと感じている。お返しが実現するまでは――つまり互酬的な交換が未了のうちは――、受け手側は、与え手に対して負い目がある。このとき、受け手はどうしても、与え手が喜ぶように行為しなくてはならない、あるいは少なくとも、与え手に不快なことはできない、と思うことになる。与え手を喜ばすことだけが返済に近づくことであり、逆に、与え手を不快にすることは負債を大きくするからである。
このように、贈与は、他者に価値あるモノをもたらしながら、そのことを通じて、その他者を拘束する力を発生させる。「金を貸す人間」が邪悪な人物として描かれるのはこのためである。
この負債感は、助けてもらった相手を主人として仰ぎ見たい、という負債感とは異なり、ネガティヴなものである。助けてもらった相手に贈り物を求める、狩猟採集民のそれを「ポジティヴな負債感」と定義するなら、金を貸す人間を邪悪な者と感得するのは、「ネガティヴな負債感」と言えるだろう。
このネガティヴな負債感は、金貸しという職業が確立していないと生じない。金融経済がある程度発展し、金貸しが職業として確立していることを前提としている。なのでこの感覚は、金融経済が成り立っていない狩猟採集民などの原始社会には存在しないだろう。
また、この「負債感=金を貸すほうが悪」という感覚は、「助けてもらった相手には贈り物をしないと落ち着かない」という感覚とパラレルだと思われる。「負債を清算する=借金を返す」ということと、「恩返しをする=贈り物をする」という行為は、ともに上下関係・主従関係を均して平等にしたい、という願望によって駆動されているのだ。
だとすると、金を貸すほうを悪と見做すのと同様に、助けてもらった相手に対しても、少なからず嫌悪感を抱いてしまう、ということがあり得るのではないか。「借金=負債感」によって受け手が拘束されるように、「恩義」もまた負債感として感得され、それが返済されないうちは心理的な拘束として働く(世の中には、借りを作ることを極度に嫌う人がいるが、それはこの心理的拘束に対する抵抗感が人一倍強い、ということなのだろう)。だから早く恩を返したい、と思う。恩返しをしないうちは、助けた側は、助けてもらった側を拘束する。そうなると、恩義だけでなく、同時にわずかながら憎しみの感情も抱いてしまうのではないか。
恩人に対する、アンビバレントな感情。恩を返したいと思うそのとき、関係を平等にしたいとも、憎しみを抹消したいとも願っている。恩返しをして、恩義に報いることができたと喜ぶとともに、主従関係を解消できた、もう相手を憎まなくていいと安心してもいるのだ。
人の感情というのは複雑だ。だからこそ面白い。
これは社会学者の大澤が、経済とは何か、贈与交換から商品交換(貨幣経済)への転換はどのようにして起こったのか、貨幣はどのようにして生まれたかなど、経済の謎を解くために、幾つもの文献にあたりながら、東西の文化に触れ、歴史を辿った探究の書である。この中の第5章「ヒエラルキーの形成――再分配へ」で、贈与に関して、興味深い事例が紹介されている。
十九世紀から二十世紀の初頭にかけて、アマゾンやアフリカの狩猟採集民の社会に入った宣教師や探検家をたいへん驚かせたことがある。定型的な筋をもっているのだが、その代表として、イギリス人宣教師たちがコンゴで体験したことを紹介しよう。現地人の一人が重い肺炎にかかったので、宣教師たちは、彼を治療し、濃いチキンスープなどを与えた。おかげで、この病人は命をつなぎとめた。宣教師たちが、次の目的地へと向けて旅立つ頃には、彼はすっかり回復していた。宣教師たちが旅支度をしていると、この男がやってきて、なんと宣教師たちに贈り物を要求してきたのだ。宣教師たちはびっくりして、これを拒否すると、男の方も同じくらい驚き、大いに気分を害した。宣教師が、贈り物によって感謝を示すべきはあなたの方ではないかと言うと、彼の方は、「あなた方白人は、恥知らずだ!」と怒って言い返してきた。
このエピソードは、二十世紀前半の哲学者リュシアン・レヴィ゠ブリュールの著書から引いたものである。レヴィ゠ブリュールは、「未開社会」の人々が、「われわれ」とは異なる論理で思考し、行動していることを示す証拠として、似たような報告事例をたくさん蒐集している(Lévy‐Bruhl 1923)。溺れていた男を救ってやったところ、その男から高価な服を要求されたとか、トラに襲われて大けがを負った人を治療してやったところ、さらにナイフを欲しいと言われたとか、である。これらはすべて、西洋人側が現地の人に対して、贈与に相当することを行い、西洋人の観点からは現地の人の方からお返しの贈与があってしかるべき、と思われていたところが、逆に、現地の人の方からさらなる贈与を要求されている。これをどう説明したらよいのだろうか。
とてつもない忘恩のようにも思えるのだが、そうではない。忘恩であれば、わざわざ追加的な贈与を要求したりはしない(単純に無視し、関係を断とうとするはずだ)。次のように解釈すればよい。宣教師によって肺炎を治してもらった男は、当然、宣教師に感謝している。彼は、宣教師との親密な関係を維持したい。とりわけ、彼は、宣教師を自分にとっての「主人」のようなものとして尊敬したいと思っている――そして、そのことは宣教師側にとっても喜ばしいことだと想定している――のではないか。
ここで、主人とは何か、がポイントになる。主人とは、従者に対して、(価値あるものを)与え続ける者である。言い換えれば、従者は、主人に対して、いつまでも消えない負債の感覚をもちたいのだ。彼の方から何かをお返しして、負債を無化してしまえば、宣教師を主人として仰ぎ続けることが不可能になる。彼は、宣教師になおいっそう負債を負い、負債感を維持したいがために、さらなる贈り物を要求したのだ。当然主人たる宣教師が喜んで、何かを贈ってくるだろう、と予期して。
うーん、面白い。
このような贈与のありかたは、現代の日本にも馴染まない。贈り物をすべきは助けられたほう、というのがゆるぎない常識としてある。
だが、上の事例の狩猟採集民の感覚から眺めてみれば、助けてもらった相手に贈り物をすることは、相手との関係を断つ方向に働いていると言える。贈り物をして、感謝を伝える。そうすればそこで貸し借りは清算され、負い目を感じる必要はなくなる。そうなれば、それ以上相手との関係を維持する必要はなくなるのだ。
もちろんその後も関係を保ち続けることはできる。だが、贈り物をしてしまえば、そこで関係を絶ったとしても非礼とは見做されない。助けてもらった相手への贈り物は、基本的には関係を維持するのではなく、清算する方向に働くのだ。助けてもらった相手に贈り物をしたいと思う、その背後には、「貸し借りをなくしたい」「関係を清算したい」という願望も貼りついているのではないか。
その点を合わせて考えると、助けてもらった相手に贈り物を求める文化圏は、そうでない文化圏よりも、人間関係が密になるのは間違いない。だとすれば、「助けてもらった相手に贈り物を求める習慣」を日本に定着させれば、日本人の人間関係は今よりも密になるだろう。引用文にあるように、それは主従関係を基調としているので、「平等」を原理主義的に追求している日本社会からは反発されるかもしれないが。それに、恐らくは「助けてもらった相手に贈り物をする」のが日本社会の長年の常識だったはずで、それに反する習慣を易々と受け入れられるのか、という問題もある。(平等という点をさらに突っ込んで考えてみると、平等という観念があまり発達していない原始社会ほど、上下関係・主従関係に抵抗がないから、「助けてもらった相手に贈り物を求める」文化的傾向があり、平等の観念が浸透するほど上下関係・主従関係に抵抗が生まれ、「助けてもらった相手に贈り物をする」ほうに逆転していくのかもしれない)
なので、日本社会にこのような贈与の感覚を根付かせるのは難しいかもしれない。それでも、このような贈与のありかたもあるということ、現代日本の贈与のありかただけが唯一の形ではないことを知るのは、ひとつの希望のように感じられるのではないか。
少なくとも、僕はそう感じた。異なる視点を導入することで、自分の属する文化を相対化し、今とは違うありかただってあるのだと知る。こことは違う文化、違う時代には異なる常識があって、それはけっして非現実的なものではなく、自分たちの文化に移植することも可能かもしれないと気づく。それは思考の風通しをよくして、ほんのわずかでも社会の息苦しさを解消してくれる効果があるだろう。
ところで、助けてもらった相手に贈り物をする動因、恩返ししたいという願望は、「負債感」によって基礎づけられるものだ。この負債に関してもまた、大澤は鋭い考察を加えている。
人は長い間、そしてときには今日でも、「金を貸す人間」は邪悪な人物の典型であるかのように考えてきたのだ。もし負債こそが罪の中の罪であるとすれば、貸す者には何の問題もないはずだ。逆に借りながら、まだ返していない者こそが悪い。それなのに、金貸しは、いつも悪人である。
世界文学や民間説話を振り返ってみるとよい。金を貸す善人が描かれていたためしがない。『ヴェニスの商人』のシャイロックのように、金を貸す者は常に邪悪な側にいる。考えてみれば、この戯曲で、負債を清算していないのは、ヴェニスの貿易商人のアントーニオの方なのに、彼は善人として描かれている。『罪と罰』では、金貸しは被害者であって、罪を犯すのは苦学生のラスコーリニコフだが、読者は、ラスコーリニコフによって殺されたのが金貸しであることで、少しだけ安心しているはずだ。あんなババアは殺されても仕方がなかったんだ、と。(中略)
一般には、贈与交換における互酬こそが、正義の原型と見なされている。この通念に従えば、「互酬が未だに実現していない状態に対して責任があること」こそが、要するにお返しをせずに、負債を残していることこそが、罪の原型である。実際、ニーチェをはじめとする多くの思想家・哲学者が罪を、「負債の一般化」として理解してきた。
(中略)
贈与は、他者にとってポジティヴな価値のあるモノを、その他者にもたらすことである。それゆえ、一般に、贈与は、倫理的には善きこととして評価される。しかし、同時に、贈与には否定的な意味も宿る。なぜなら、贈与は、与え手が受け手を支配する力を生み出してしまうからだ。受け手側の負債の意識を媒介にして、贈与は、与え手が受け手を支配することを可能にする。
受け手の方に負債の意識が生ずる原因は、贈与が、一般に、互酬化されることへの強い社会的圧力を伴うことにある。与えた側は、ほとんどの場合、お返しがあって当然だと思っている。そして受け手の側は、お返しすることを義務だと感じている。お返しが実現するまでは――つまり互酬的な交換が未了のうちは――、受け手側は、与え手に対して負い目がある。このとき、受け手はどうしても、与え手が喜ぶように行為しなくてはならない、あるいは少なくとも、与え手に不快なことはできない、と思うことになる。与え手を喜ばすことだけが返済に近づくことであり、逆に、与え手を不快にすることは負債を大きくするからである。
このように、贈与は、他者に価値あるモノをもたらしながら、そのことを通じて、その他者を拘束する力を発生させる。「金を貸す人間」が邪悪な人物として描かれるのはこのためである。
この負債感は、助けてもらった相手を主人として仰ぎ見たい、という負債感とは異なり、ネガティヴなものである。助けてもらった相手に贈り物を求める、狩猟採集民のそれを「ポジティヴな負債感」と定義するなら、金を貸す人間を邪悪な者と感得するのは、「ネガティヴな負債感」と言えるだろう。
このネガティヴな負債感は、金貸しという職業が確立していないと生じない。金融経済がある程度発展し、金貸しが職業として確立していることを前提としている。なのでこの感覚は、金融経済が成り立っていない狩猟採集民などの原始社会には存在しないだろう。
また、この「負債感=金を貸すほうが悪」という感覚は、「助けてもらった相手には贈り物をしないと落ち着かない」という感覚とパラレルだと思われる。「負債を清算する=借金を返す」ということと、「恩返しをする=贈り物をする」という行為は、ともに上下関係・主従関係を均して平等にしたい、という願望によって駆動されているのだ。
だとすると、金を貸すほうを悪と見做すのと同様に、助けてもらった相手に対しても、少なからず嫌悪感を抱いてしまう、ということがあり得るのではないか。「借金=負債感」によって受け手が拘束されるように、「恩義」もまた負債感として感得され、それが返済されないうちは心理的な拘束として働く(世の中には、借りを作ることを極度に嫌う人がいるが、それはこの心理的拘束に対する抵抗感が人一倍強い、ということなのだろう)。だから早く恩を返したい、と思う。恩返しをしないうちは、助けた側は、助けてもらった側を拘束する。そうなると、恩義だけでなく、同時にわずかながら憎しみの感情も抱いてしまうのではないか。
恩人に対する、アンビバレントな感情。恩を返したいと思うそのとき、関係を平等にしたいとも、憎しみを抹消したいとも願っている。恩返しをして、恩義に報いることができたと喜ぶとともに、主従関係を解消できた、もう相手を憎まなくていいと安心してもいるのだ。
人の感情というのは複雑だ。だからこそ面白い。