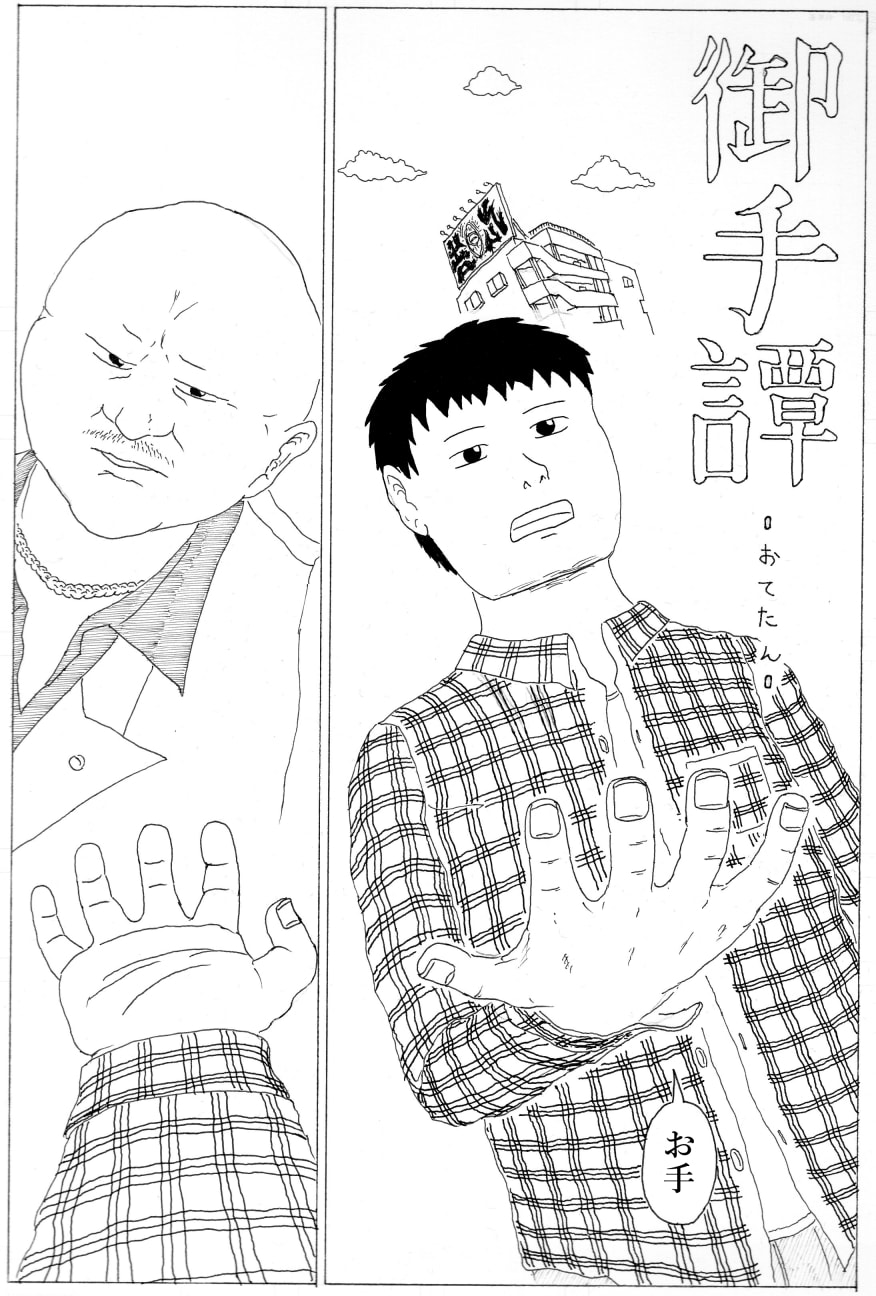(前編からの続き)
価値を媒介する貨幣が、価値そのものと誤解されることによって起こるのが、貯蓄それ自体を目的とした貯蓄、つまり「退蔵」であるが、それでは、退蔵によって引き起こされるのは何か。
いくら稼いでいるか、いくら蓄えられるかは、人によって違ってくるので、退蔵からは「格差」が生まれる。
格差からは、持てる者と持たざる者の二分化がもたらされる。この二分化は、「雇う者」と「雇われる者」へと転化する。
ここからさらに生まれてくるのは何か。雇う者と雇われる者との力関係が強固になることで、支配の構図も現れるだろうし、労働力の搾取も行われうるし、雇う者が、差益をさらなる投資に回すことで、ますます持てる者となってゆく、という面もあるだろう。
教科書通りの人類の歴史。つまり、退蔵からは資本主義が発生するわけだ。
ところで、退蔵の対義語は何か。
それは、「蕩尽」である。
退蔵の対極の現象を眺めることで、資本主義の裏面が見えてくるだろう。
ここでご登場いただくのは、文化人類学者御用達の「ポトラッチ」である。
今はもう廃れてしまっているようだが、北米先住民の間で、昔から行われていたポトラッチと呼ばれる習慣がある。これは、新しい首長が選ばれた時のお披露目や、重要な人物の子供の結婚祝いに、他の村人を招いて行われるもので、招いた側も、招かれた側も、膨大な贈り物をする。お返しをする際には、受け取ったぶんより、さらに多くの物を贈らねばならないとされており、さながら、「贈り物合戦」のようになっている。で、注目すべきはさらにその先で、贈り物を行う際に、自分達の気前の良さを証明するために、相手の前で、貴重品を破壊して見せることがあるという。
せっかく蓄えた財を破壊するとは、なんてバカげたことを。…と思われるだろうか。
だがそれは、資本主義マインドに染まりきった我々の、一面的な見方でしかない。退蔵だけが正しい振る舞いというわけではないのだ。
蕩尽を行う文明には、当然ながら、退蔵は起こらない。
そうすると、「格差」は発生しないし、持てる者と持たざる者との二分化ももたらされないし、搾取も行われない。
つまりポトラッチは、資本主義の発生を防いでいるのである。
ポトラッチを行っている人々が、どれだけそのことに自覚的であるか、はわからない。意図的に構築されたシステムではなく、たまたまそうなっているだけなのかもしれない。だが、狙ってやっているにせよ、図らずしてそうなっているにせよ、ポトラッチがそのような働きを有しているのは事実なのである。
で、言うまでもないことだが、資本主義社会は多くの問題を抱えており、我々退蔵を行う文明の側が、「ポトラッチなんかバカげてる」と揶揄したとして、蕩尽を行う文明からは、「財を蓄えることで、様々な苦しみや不条理が生まれてるじゃないか」という答えが返ってくるだろう。
実際、資本主義社会は、環境破壊によって滅び去る恐れがあるけれど、蕩尽を行う文明は――資本主義社会の巻き添えを食わない限り――これから先も変わらず存続し続けるだろう。
安定度は、蕩尽を行う文明の方が、遥かに高いのである。
と、いうわけで……多くの問題を抱えて行き詰まりつつある、現在の資本主義を打開するには、ポトラッチしかない!
さあ、みんなで蕩尽しよう!
蓄えた財産を、徹底的に費消しつくそう!
むやみに溜め込んだ物を吐き出しきってこそ、新しい経済体制への活路は開けるのである。
いざ、ポトラッチ!
(こんな結びでいいのか、と自問しつつ了)
オススメ関連本・藻谷浩介『里山資本主義――日本経済は「安心の原理」で動く』角川oneテーマ21