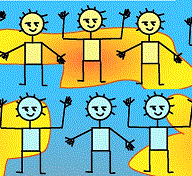けさの朝日新聞『be』に、「ダメなことを叱るのではなく、よい行動を褒める」教育を唱える奥田健次の紹介が載っていた。
奥田健次は言う。
「『正しいこと』ことを言うといつも殴られた。5歳から継父から殴られ、教師からは『出て行け』。同級生からもいじめられた。」
すさまじい人生である。彼は虐待を受けていた。よく心がゆがまなかったと感心する。
私が親に叱られたことがあったか、この歳になると、よく覚えていない。叱ることが教育上必要なのかどうかを私は疑っている。
私は幼稚園に行っていない。私がたぶん叱られたのは、小学校に行く寸前に、親が近所の男の子たちに私を紹介した、その日ぐらいである。
その日、子どもたちだけで遊んだ後、斜め向かいの町内会会長の子が、子どもたちを近所の瀬戸物屋の前に連れて行き、石を投げ入れた。私にとってはじめてのことで、何がなんだかわからずに、立ち尽くした。私を置いて、みんな逃げたのである。瀬戸物屋の主人は私を家に連れて行き、父親に叱られた。なんと言われたか覚えていないが、この世に非常に不当なことがあると感じた。
それ以来、近所の男の子たちと遊ばなくて、よくなった。
小学校に上がると、男の子たちが二手に分かれ、掃除の箒やはたきやバケツをもって、毎朝、先生が教室に来るまで、喧嘩をした。その一方のガキ大将が町内会会長の子だった。
私はその喧嘩に参加しなかった。私は暴力が嫌いだ。私が大人しいから、いつも女の子から遊びに誘われた。小学校高学年になるまで、友達はすべて女の子であった。
いまどきの女の子は、暴力をふるうのだろうか。
私は教師から叱れた記憶もほとんどない。
私は、中学2年のとき、教室の子たちを扇動して、年老いた女の教師の国語の授業を集団で抜け出した。そのことで、教室担任に叱られた。じつは、本当に扇動したかどうか、記憶が定かではないが、私は扇動したと教室担任に申し出た。扇動することがカッコいいと思っていたのである。女の教師に気の毒なことをした、と今は思っている。高校にはいったとき、祝いに彼女から古文の参考書を贈られた。私は彼女に好かれていたのだ。
高校にはいってからも教師に対する私の悪ふざけはつづいた。高校2年のとき、教育実習にきた学生をいじめたと国語教師に叱られた。「いじめ」と言っても暴力をふるったわけではない。質問という形で教える側の権威をからかったつもりだったが、いじめと受けとめられたのだ。もちろん叱られたと言っても、国語教師にいやみを言われただけである。しかし、それ以来、国語という教科は好きではない。
権威に逆らいたくなるのは今も続いている。
人間を含め、生き物は生き方を学習する。たぶん、奥田健次は、効率的な学習指導を提唱しているのであろう。学習を良い方向に導くのに暴力はいらない。暴力に肉体的なもの以外に言葉の暴力がある。叱ったとしても、なぜ叱られたかが伝わらければ意味がない。なぜ叱られたかがわかるには、叱られる側の一定程度の知性が熟していないといけない。褒めるほうが効果的である。
私がNPOで担当してきた「発達障害」の子どもたちの半数は知的に遅れがある。下手に叱るのは、心に歪みを生じさせるだけである。ただ、危険な行為は即座に止めるべきだ。自傷行為は、理屈を述べるよりも、直ちに止めるほうが、愛情が伝わる。もちろん、止めると同時に声掛けがあったほうが、その子に愛情として記憶される。
先日読んだ、アリス・マンローの『ディア・ライフ』(新潮社)に、80年前の教育や子育てのとんでもない暴力描写がでてくる。こんなことは、現在では見られないはずである。
「それからごっこ遊びがあり、誰かが先生になって、さまざまな違反や愚行を理由にほかの子たちの手首を叩き、相手に泣く真似をさせるのだった。」p.331
「母は納屋に行って父にわたしのこと〔口答え〕を言いつけるのだ。すると父は仕事を中断してわたしをベルトで殴らなくてはならない(当時これはごくありふれた懲罰だった)。」p.369
わたしの子ども時代には、日本の敗戦のおかげで、もはや、このような暴力は軍国主義の遺物として否定されていた。現在も指導という暴力があれば、それは犯罪である。叱ることも上から目線の行為で、暴力につながる。