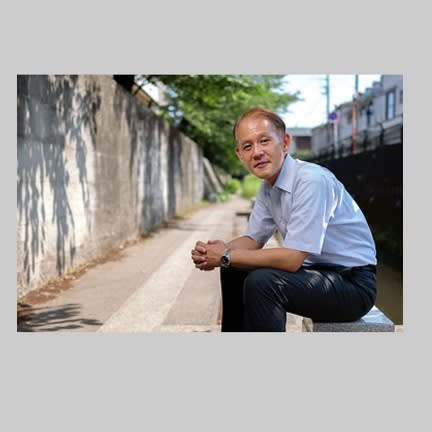
宇野重規の『西洋政治思想史』(有斐閣アルマ)を病室のベッドで読んでいて、結章で気になる一節に出くわした。
〈共和政が「公共の利益が支配する政治」であるとすれば、デモクラシー(民主政)は「社会の多数を占める、貧しい人々の利益が支配する政治」にほかならなかった。〉
西洋政治思想の歴史の中でデモクラシーが否定的意味合いで使われてきた、と宇野は言いたいのであるが、上の言明は私にはとても唐突に感じた。
共和政が「公共の利益が支配する政治」というのは、たぶん、ローマの政治思想を肯定的に捉えた風潮を指すのだろう。
デモクラシーは「社会の多数を占める、貧しい人々の利益が支配する政治」というのが理解しがたい。本当にそういう風潮が西洋政治思想にあったのだろうか。
考えてみるに、アリストテレスの政治学の読み違えではないかと思う。そこで、アリストテレスは、寡頭政(oligarchy)は少数者による支配、デモクラシーは多数者による支配、富者は少数、貧者は多数と言っている。しかし、「貧しい人々の利益が支配する政治」とは言っていない。
多数者による支配と貧者のための政治と別ものと考える。
デモクラシーはあくまで一人や少数の人たちが支配する政体ではないということである。トマス・ホッブズは『リヴァイアサン』で〈集まる意思のあるすべての者の合議体の場合は《民主政》(デモクラシィ)あるいは人民のコモンウェルス〉と定義し、〈「民主政」のもとで苦しんでいる人々は、これを「無政府」(アナキィ)〔統治の欠如の意〕と呼ぶ〉と言っている。
安定したデモクラシーの実現は容易ではない。
多数の人々が1つの政治的意思をもつというのは明らかに難しい。したがって、多数の人々が1つの政治的決断にいたるには、説得や妥協などのコミュニケーションの技術がいる。
宇野は『西洋政治思想史』のなかで、〈トクヴィルが言うデモクラシーとは、単なる政体分類の1つではなく、平等な諸個人からなる社会状態のことを指す〉と書いている。この言明がわかりにくい。
宇野は『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社選書メチエ)につぎのように書いている。
〈アメリカ社会では政府の存在は強く感じられず、あたかも「統治の不在」のごとくであるが、にもかかわらず社会は正常に機能している。その背景にあるのは、社会の底辺における自然発生的な「デモクラシー」なのではないかというのが、トクヴィルの観察であった。〉
宇野が言いたいのは、デモクラシーが政体として機能するには平等な諸個人からなる社会状態がいるということであろう。政治家だから偉い、高級官僚だから偉い、大学教授だから偉いと人々が思っているようでは、デモクラシーが機能するのは難しい。













