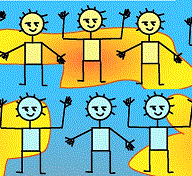
長く就職先が決まらない子がようやく去年の末に面接に受かり、この4月から毎日仕事に出かけている。24歳になる。この夏に有給休暇を取らずに一所懸命働いたと彼は自慢気に私に語った。うれしい話である。
その子は、成績優秀ではないが、知的障害でもない。いわゆる「発達障害者」である。どこか変な子で、扱いにくい子である。小学校で教室から排除されたためか、人との付き合いがとても下手である。家の外での会話が少なかったためか、言葉の意味を取り違えているケースがときどきある。もう少し早くから、インクルージョン教育が公立学校で普及していればと思う。
先日、その子の保護者と面談しているとき、職場の管理者から持て余していると言われたという。私のところでの彼の振る舞いと大きく違うから、職場の管理者が私たちがどのように指導しているか、知りたいという。メールでのやりとりよりも、直接あって話した方がいいと思って、コンファレンスを設定してもらった。
その子の職場は、倉庫のようなビルの3階にあった。屋内農園型障害者雇用支援サービス会社の施設を10社が利用していた。その1つが彼の就職した会社である。それぞれ会社が「障害者」を雇って、同じ大部屋で水耕栽培をやっている。休憩室も10社共有である。
コンファレンスには、私のNPOから私と同僚2人が参加した。向こうは、彼を雇用している会社側の管理者一人と支援サービス会社の職員一人である。コンファレンスでびっくりしたのは、管理者が障害者を雇うということを全然理解していないことである。オーバーリアクションをしている。それに対し、支援サービス会社の職員は一言も言葉を挟まなかった。
彼の管理者は、もとは営業マンで、60歳になったので、現在の職場に配置されたと言う。彼がその管理者にいちいち指示や判断を求めると私たちに文句を言う。就業時間が終わってもさっさと帰らないから、施設の入り口まで送らないといけないと言う。どうして彼のような手間のかかる子を雇ったのか会社には文句を言ったが、チャレンジ―だと突っ返されたとその管理者は言う。
彼と同時に雇ったダウン症の子を「自主退職」という名目で解雇したと私を脅す。雇用契約は1年であると言う。会社の名を汚さなければ、自分が定年になるまでの5年間、雇ってあげると言う。
管理者は、会社が教育や訓練のために彼を雇用しているのでないと言う。会社は彼に月14万円ほどを支給している。昇給はない。時間給はみんな同じだ。仕事では成果を求めていない。それはそのはず、障害者の法定雇用率を満たすために、会社は「障害者枠」で彼を雇っているだけである。水耕栽培での収穫物は売っていない。会社のビジネスに何も貢献していない。
(注)法定雇用率は2024年度に2.5%になった。26年度には2.7%になる。
この支援サービス会社は障害者雇用「代行ビジネス」会社の1つである。障害者の法定雇用率を満たしたい会社に、水耕栽培の施設を提供している。しかし、障害者にどのような配慮をすべきかを利用会社に指導していない。利用会社がこの支援サービス会社にいくらを支払っているか私は知らない。しかし、ずいぶん払っているのではないか。
これら代行ビジネスの会社は、法定雇用率を満たさないと罰金を払うことになり、会社名を公表される、結果として会社のブランド・イメージが下がると、講演してまわり、いま、全国的に急成長している。しかし、障害者の適切な雇用の場が見つからなければ、国に罰金を払うほうが健全ではないか、と私は思う。国はその徴収したお金を、福祉団体の就労継続支援事業所(いわゆる「作業所」)や市町村の就業支援センターにまわした方が良い。
最後に、障害者の雇用の促進等に関する法律から、その理念と事業主の責務を掲げてこのブログを終える。
(基本的理念)
第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
第四条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。
(事業主の責務)
第五条 すべて事業主は、障害者の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、障害者である労働者が有為な職業人として自立しようとする努力に対して協力する責務を有するものであつて、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るように努めなければならない。













