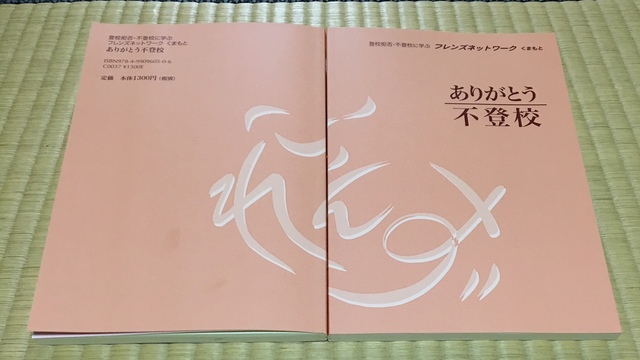・参 考
◆今年4月7日、岐阜市に不登校児専門の公立中学校が開校されました。その学校の方針はwすべての授業はオンラインも併用のため通学してもしなくてもいい。w担任は生徒側の選択制。w時間割は教師と生徒が相談しながら決める。w職員室は生徒に開放。等、とても革新的なもののようです。
その学校は出来たばかりでまだまだ未知数ですが、開校除幕式での塩瀬隆之氏(京都大学総合博物館准教授)のスピーチが「会場を涙させた」としてネットにあがっていました。その一部をご紹介します。
▼私が、世界中、それから日本中、理想的な学校がどういうところなのかというのを調べる中で、魅力的な学校に共通すると感じることがあります。それは「学びの選択肢がたくさんある」ことです。好きな場所で学ぶことができたり、好きなことを学ぶことができたり、学ぶ内容を選べたり、さらには学びの設計図である「時間割」を先生と一緒につくることができる学校こそが、子どもたちにとって本当によい学校なのではないか、と思うようになりました。
しかし、子どもたちがこれを選ぶというのはなかなかに難しく、しかも、そういう環境はほとんどありません。大人は、時間割も、教室も、担任の先生も、9教科も、よかれと思って子どもたちに与えます。子どもたちに必要だと思うから与えるのです。
でもこれを子どもたち自身が自分で選べるチャンスというのは、どうすれば作ることができるのか。みんな同じように同じペースで学ばないといけない、これができることが大人になるために必要だ、と大人は考えます。そのためには我慢をしないといけないし、耐えなければならない。
しかし、本当にそうでしょうか!? 我慢して、耐えることだけが、子どもたちに必要なことで、これを6・3・3の12年間、さらに4年間足して16年間耐え続けられた人だけが大人になれるのでしょうか。私は、そうでない場所、を作ることが大事だと思います。
子どもたちが勘違いしている言葉の一つに、「義務教育」という言葉があります。子どもたちのほとんどは「学校に行かなければいけないのは義務だ」と感じています。どんなに苦しくても、どんなにしんどくても、行かなければいけないのが「義務教育」だと勘違いをしています。
大人はここで声を大きくして、それが間違いであることを伝えないといけないと思います。子どもたちが持っているのは「学習権」です。「学びたいと考えたときに、学んでいいという権利」です。義務を負っているのは大人で、その子どもたちが学びたいと言ったときに、(大人は)学ぶ方法すべてを提供しなければなりません。
教室の中に、正方形のタイルのようにまっすぐ並ぶことのできた子だけが学んでいいという、そういう条件付きの学びではなく、子どもたちが、いつ、どこで、だれと、何を学びたいのか、そのすべてを選んでもいいはずで、その環境を提供できることこそが、大人に課せられた使命だと思います。
「義務教育」の意味を誤解しているのは、子どもばかりではありません。まだまだそういう思いに引っ張られている大人は多いと思います。知識として知っているだけでは、よく分かっていることにはなりません。
そして「正方形のタイルのようにまっすぐ並ぶことのできた子」という表現、現状をよく表していると思います。そんな学校で「正方形でない子」が無理やり正方形になるよう個性的な形を削られるとしたら、それはとってももったいないことだと思います。