どうもです。
前日は一日中、家に籠って“積ん読”になっている文庫本の消化を
試みていて、今日は外出する予定でいたんですが、朝起きたら雨模様。
仕方がないので、今日も家で昨日の続きということで。
昨日・今日で完読したのが、順に『鷹の羽城』『生きのびる』『海狼伝』
(以上すべて白石一郎)と『GEN 「源氏物語」秘録』(井沢元彦)の4冊。
白石一郎氏の作品は、古本屋で見かけて何気なく買ってみた『切腹』
を読んだのが始めで、それ以降は意識的に、氏の文庫本を探してきて
は読み漁ってます。2004年9月に亡くなられていて、未完の作品が
いくつかある訳ですが、入手可能な作品の、およそ9割は入手、完読
できたんではないかと。
今回読んだ『生きのびる』は、侍稼業に嫌気がさした主人公が、開港
して間もない横浜で荷揚げ人足をしつつも、町で起きる外国人との
トラブルや事件を解決していくという「横浜異人街事件帖」シリーズの
第2弾です。表題作「生きのびる」で登場する、侍社会の不条理に
よって死を強要されている男の台詞に、人が生きることとは…云々、
というのが出てきて、今までのシリーズ作品と(白石作品全体の雰囲気
とも)違う何かがあるように感じていたんですが、解説を読んで納得。
この「生きのびる」と次作(最終話)「情けねぇ」は亡くなる直前、病床で
書かれたものであるとのこと。物語中の男は自分の信条に従った行動
によって生きのびることができなかったんですが、死を目前にして導き
出された作者の死生観が、そのまま活字にされたものなのかなぁ、と
解説の後に改めて読み返して思いました。
しかしそれでいて、最終話では主人公、衣笠卯之助と(内縁の妻で
ある)おゆみとの間に新しい命が芽生えたところで幕が引かれていて、
これまで死に急ぐような生き方をしてきた卯之助が、生きのびるための
縁[よすが]を手にして終わる辺りに、すごく清々しい読後感を覚えたり。
作品世界は歴史的には幕末の、第二次長州征伐の頃から江戸開城
までになるんですが、主人公たちのいる舞台がそういった流れからは
全くと言っていいほど隔絶した処にあって、そうした歴史的な事象が
すべて伝聞調でしか語られてなくて、慣れない手法に作者も苦労された
とか。
ガンダム学(笑)者にとっては、MSVの頃から見慣れてきた手法
なんですけどね。
次に読んだ『海狼伝』は、対馬に生まれ、さまざまな経緯から瀬戸内
の村上海賊衆の一員となった主人公が新造帆船を手にして南方の
外洋へ出るまでの話。海戦のシーンなどは川原正敏氏の『海皇紀』の
イメージで補完しつつ読んでいたりして。事の正否はともかくとして、
ビジュアルイメージがあるのはやっぱり強いよなぁ、とも思ったり。
『海皇紀』の連載が終わったら、白石一郎作品のコミカライズをやって
くれないかな、川原氏も。講談社文庫でも結構な冊数が出てるんだし。
『海狼伝』には続編『海王伝』があり、そちらの文庫本も確保してある
はず(*1)なんだが、“積ん読”の山に埋もれてしまっているのか、一向に
見当たらない。仕方がないので(ヲイ)、井沢元彦氏の『GEN』を読む。
副題に~「源氏物語」秘録~とあり、「源氏物語多作者説」による
「原・源氏物語」が登場するんですが、それはとっかかりのようなもので、
むしろ「南朝正統論」と「足利義満皇位簒奪計画」の方が本題のような
構成になってます。一応、自殺に見せかけた殺人事件の謎を追う推理
ものではあるんですが。
井沢氏の小説は、その多くが歴史上の謎を題材としつつ、近・現代を
舞台としたミステリーものなんですが、歴史の謎に迫る自説の開陳に
紙数の多くがとられていて、殺人に使われたトリックが強引だったり、
物語の幕引きが定型的だったり。『逆説の日本史』を読んでいる分には
面白いんですが、そこに殺人ミステリー的ストーリーが混じると、興が
削がれるというか何というか。
次にこれだけ纏まった時間がとれるのはいつになるか判りませんが、
その時のために『海王伝』を探してきます。
////////////////////////////////////////////////////////////
*1:携帯電話のメモ機能を使って購入リストを作成(そうしないと以前に買った本を
ダブって買いかねないから・・・、というか実際何度かやってしまってるし)、確認
しているので、間違いはないんだが・・・・orz
前日は一日中、家に籠って“積ん読”になっている文庫本の消化を
試みていて、今日は外出する予定でいたんですが、朝起きたら雨模様。
仕方がないので、今日も家で昨日の続きということで。
昨日・今日で完読したのが、順に『鷹の羽城』『生きのびる』『海狼伝』
(以上すべて白石一郎)と『GEN 「源氏物語」秘録』(井沢元彦)の4冊。
白石一郎氏の作品は、古本屋で見かけて何気なく買ってみた『切腹』
を読んだのが始めで、それ以降は意識的に、氏の文庫本を探してきて
は読み漁ってます。2004年9月に亡くなられていて、未完の作品が
いくつかある訳ですが、入手可能な作品の、およそ9割は入手、完読
できたんではないかと。
今回読んだ『生きのびる』は、侍稼業に嫌気がさした主人公が、開港
して間もない横浜で荷揚げ人足をしつつも、町で起きる外国人との
トラブルや事件を解決していくという「横浜異人街事件帖」シリーズの
第2弾です。表題作「生きのびる」で登場する、侍社会の不条理に
よって死を強要されている男の台詞に、人が生きることとは…云々、
というのが出てきて、今までのシリーズ作品と(白石作品全体の雰囲気
とも)違う何かがあるように感じていたんですが、解説を読んで納得。
この「生きのびる」と次作(最終話)「情けねぇ」は亡くなる直前、病床で
書かれたものであるとのこと。物語中の男は自分の信条に従った行動
によって生きのびることができなかったんですが、死を目前にして導き
出された作者の死生観が、そのまま活字にされたものなのかなぁ、と
解説の後に改めて読み返して思いました。
しかしそれでいて、最終話では主人公、衣笠卯之助と(内縁の妻で
ある)おゆみとの間に新しい命が芽生えたところで幕が引かれていて、
これまで死に急ぐような生き方をしてきた卯之助が、生きのびるための
縁[よすが]を手にして終わる辺りに、すごく清々しい読後感を覚えたり。
作品世界は歴史的には幕末の、第二次長州征伐の頃から江戸開城
までになるんですが、主人公たちのいる舞台がそういった流れからは
全くと言っていいほど隔絶した処にあって、そうした歴史的な事象が
すべて伝聞調でしか語られてなくて、慣れない手法に作者も苦労された
とか。
ガンダム学(笑)者にとっては、MSVの頃から見慣れてきた手法
なんですけどね。
次に読んだ『海狼伝』は、対馬に生まれ、さまざまな経緯から瀬戸内
の村上海賊衆の一員となった主人公が新造帆船を手にして南方の
外洋へ出るまでの話。海戦のシーンなどは川原正敏氏の『海皇紀』の
イメージで補完しつつ読んでいたりして。事の正否はともかくとして、
ビジュアルイメージがあるのはやっぱり強いよなぁ、とも思ったり。
『海皇紀』の連載が終わったら、白石一郎作品のコミカライズをやって
くれないかな、川原氏も。講談社文庫でも結構な冊数が出てるんだし。
『海狼伝』には続編『海王伝』があり、そちらの文庫本も確保してある
はず(*1)なんだが、“積ん読”の山に埋もれてしまっているのか、一向に
見当たらない。仕方がないので(ヲイ)、井沢元彦氏の『GEN』を読む。
副題に~「源氏物語」秘録~とあり、「源氏物語多作者説」による
「原・源氏物語」が登場するんですが、それはとっかかりのようなもので、
むしろ「南朝正統論」と「足利義満皇位簒奪計画」の方が本題のような
構成になってます。一応、自殺に見せかけた殺人事件の謎を追う推理
ものではあるんですが。
井沢氏の小説は、その多くが歴史上の謎を題材としつつ、近・現代を
舞台としたミステリーものなんですが、歴史の謎に迫る自説の開陳に
紙数の多くがとられていて、殺人に使われたトリックが強引だったり、
物語の幕引きが定型的だったり。『逆説の日本史』を読んでいる分には
面白いんですが、そこに殺人ミステリー的ストーリーが混じると、興が
削がれるというか何というか。
次にこれだけ纏まった時間がとれるのはいつになるか判りませんが、
その時のために『海王伝』を探してきます。
////////////////////////////////////////////////////////////
*1:携帯電話のメモ機能を使って購入リストを作成(そうしないと以前に買った本を
ダブって買いかねないから・・・、というか実際何度かやってしまってるし)、確認
しているので、間違いはないんだが・・・・orz












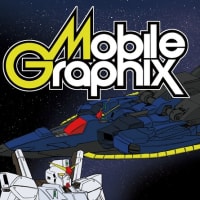







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます