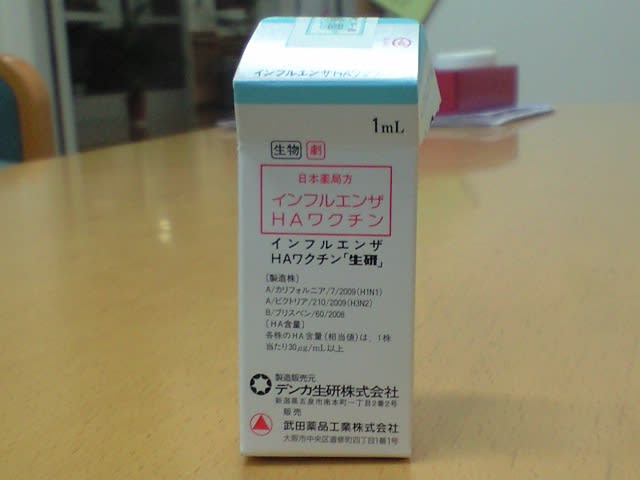8月24日に厚生労働省が発表した資料(『認知症高齢者数について』)によれば、平成24年の認知症高齢者数は推計305万人とされています。
この数は65歳以上の人口の約10%となりますので、10人に1人が認知症を有していることになります。
因みに85歳以上では4人に1人が認知症を有していると言われています。
ただ、「認知症」の基準というのが難しいため、今回の調査では介護認定調査における「認知症高齢者の日常生活自立度」というものを使った上で、その基準のⅡ以上の人数を算出しています。
当然ながら、認知症を有しながら介護認定を受けていない人は含まれていません。
しかしながら、「認知症高齢者の日常生活自立度」と言われても、高齢者福祉に携わっている人でなければ、よく分からないと思われますので、数字だけが独り歩きすることも考えられます。
因みに「認知症高齢者の日常生活自立度」というのは下記の表を参考にしてもらえればと思います。
ランク |
判断基準 |
見られる症状・行動の例 | |
Ⅰ |
何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している |
| |
Ⅱ |
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる |
| |
|
|
Ⅱa |
家庭外で上記Ⅱの状態がみられる |
たびたび道に迷う、買い物や事務、金銭管理などそれまで出来たことにミスが目立つなど |
Ⅱb |
家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる |
服薬管理が出来ない、電話や訪問者の対応などひとりで留守番ができないなど | |
Ⅲ |
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどきみられ、介護を必要とする |
| |
|
|
Ⅲa |
日中を中心として上記Ⅲの状態がみられる |
食事、排泄、更衣が上手にできない・時間がかかる、やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
Ⅲb |
夜間を中心として上記Ⅲの状態がみられる |
ランクⅢaに同じ | |
Ⅳ |
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする |
ランクⅢに同じ | |
M |
著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患がみられ、専門医療を必要とする |
せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 | |
現在、認知症サポーター養成や啓発活動などを通じて、認知症を有する人たちが自宅で暮らしながら日常生活を送れるようにしていこうという取り組みが進められています。
もし、こういった取り組みによって社会が認知症の人たちを受け入れる体制が整っていけば、認知症を有する人も、そして家族の人もずいぶんと救われるのではないでしょうか。