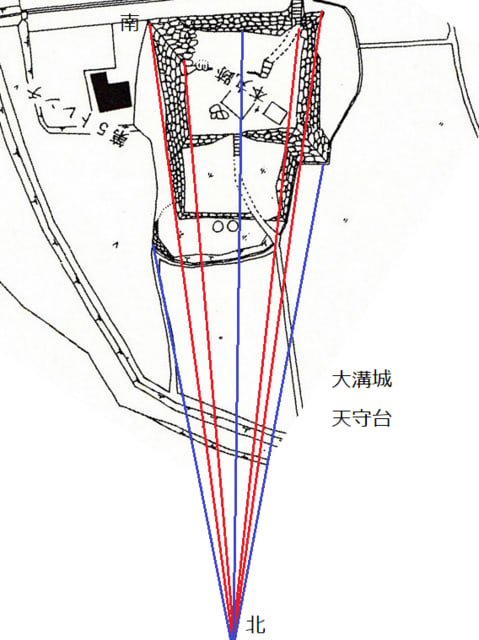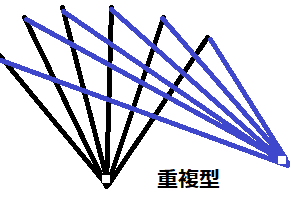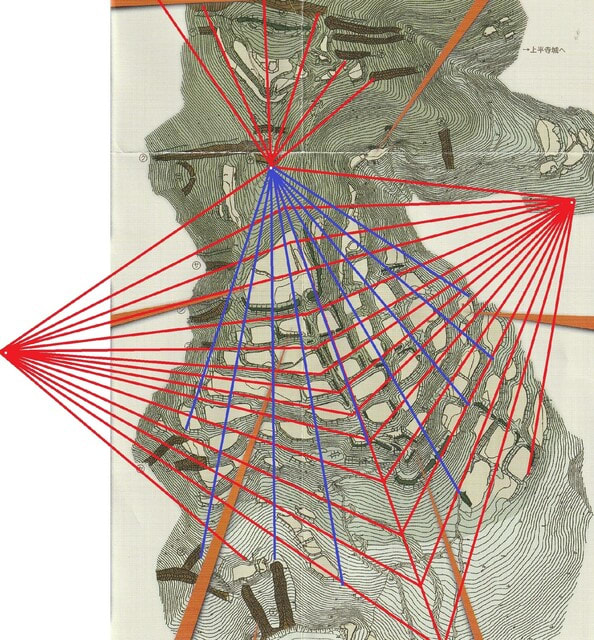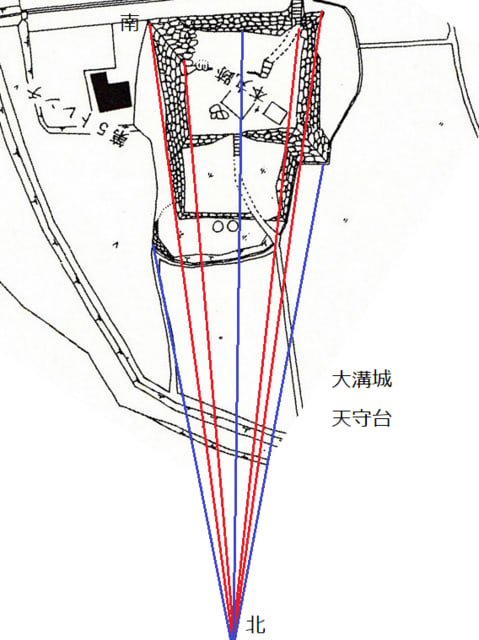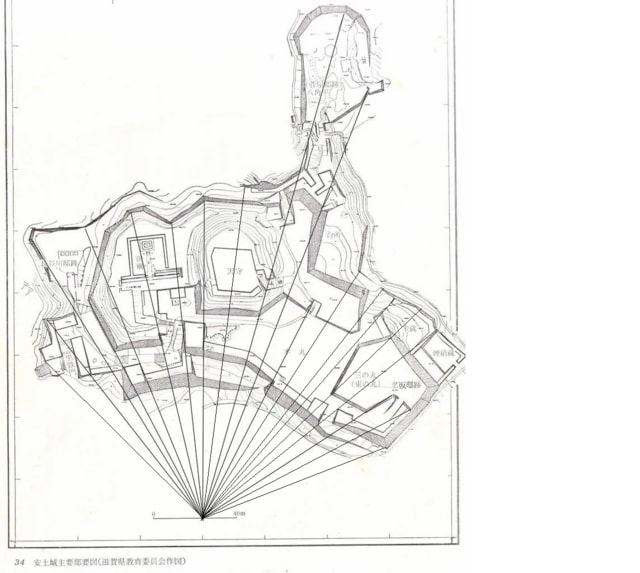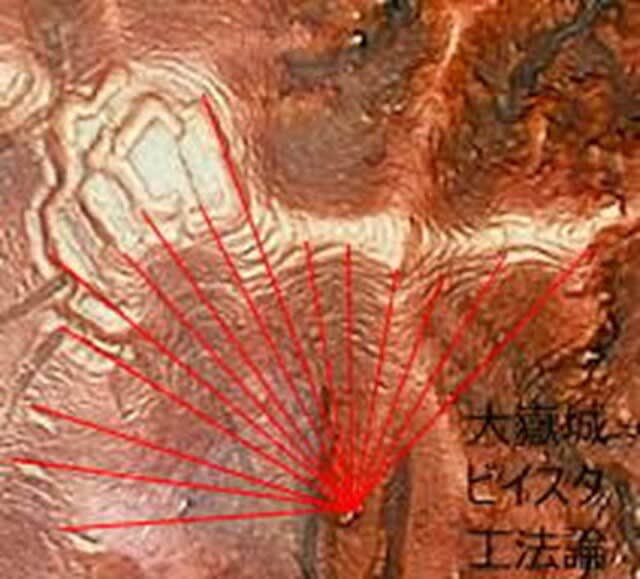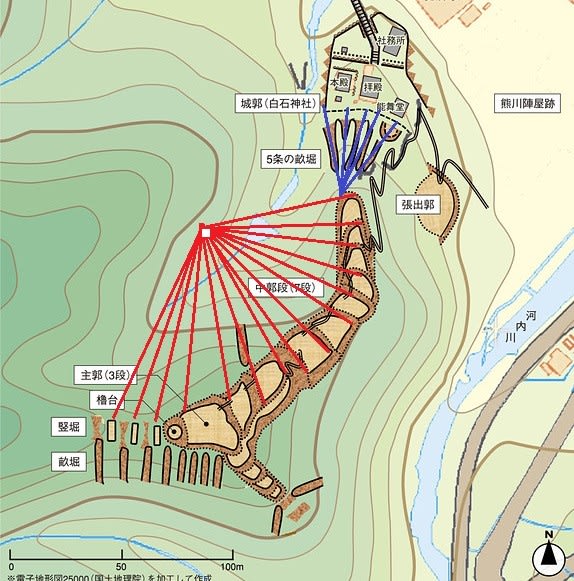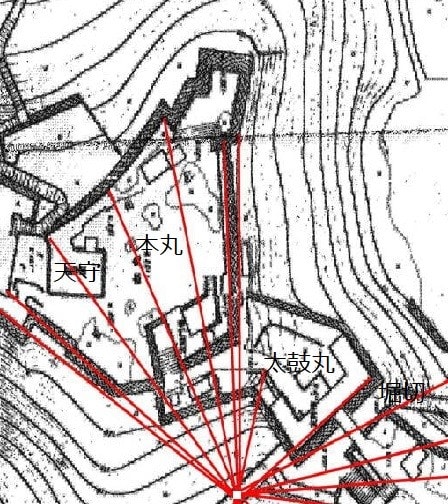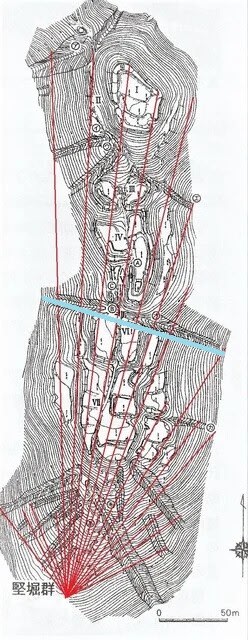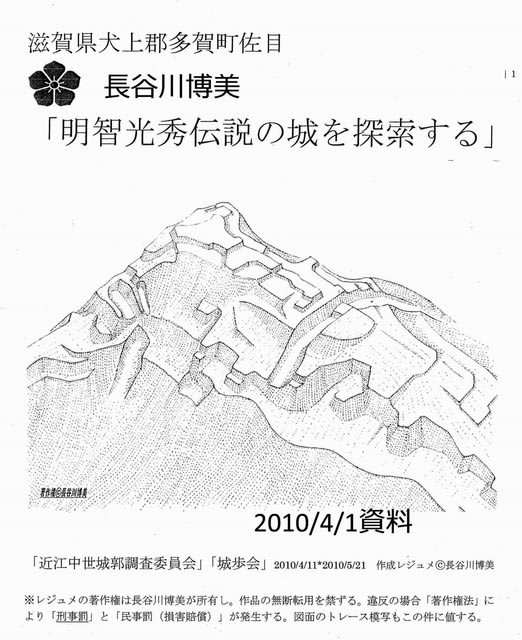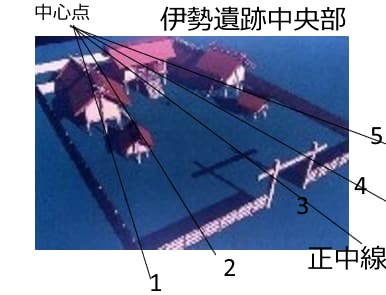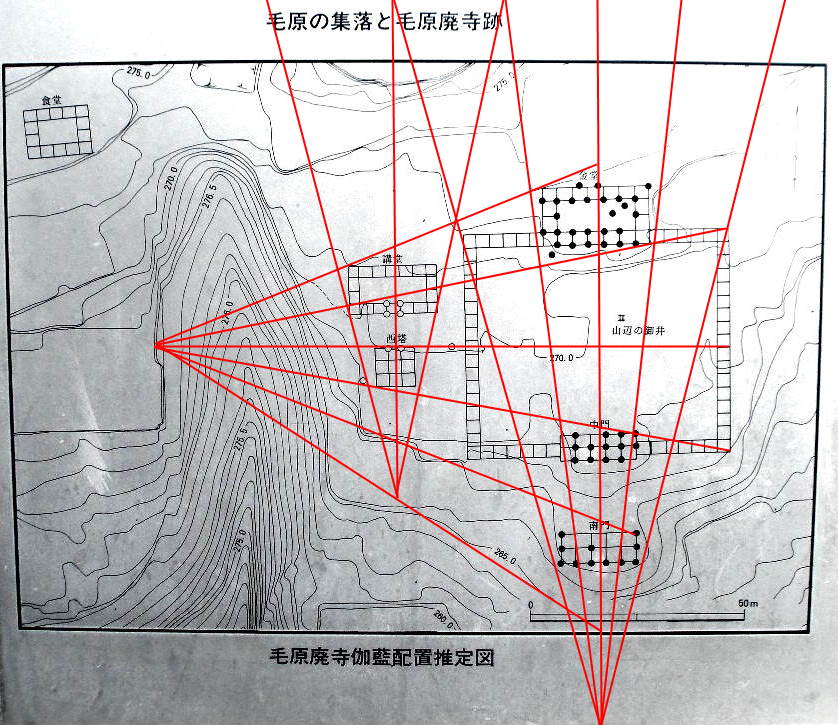城郭遺跡見学講師 信長公記講師 お城イベント案内 民俗学講師 神道思想史講師 などの情報を発信して行きます。
近江高島郡田中の城 ビイスタ工法
◆一般者
城郭ビイスタ論動画が巷間で
話題になっていると聞いてお
り視聴数が3100人との事です。
◆長谷川
図形には基本基準として
1 方眼紙状グリッド線
2 放射腺状グリツド腺
3 円弧腺状グリッド線
などは世の古今東西に存在
その中で測量台測量盤を設
けて分度を利用し放射状に
計測する測量法2は現在で
も普遍的に用いられいます。
◆一般者
でも織田信長の安土城の設計線
たる安土城ビイスタ工法を発見
された事は戦前戦後を通し最大
の功績、未曾有の発見と見解!
◆対談者
二次資料で地誌『淡海温故録
』には近江犬上郡佐目に明智
十兵衛光秀の伝説が記されて
いますが多賀町佐目の城に現
在日本全国で話題騒然の城郭
ビイスタ工法が読取れますか?
◆長谷川
明智十兵衛光秀近江犬上郡出
身説の真偽は今回述べません。
◆対談者
では多賀町佐目の城に城郭ビ
イスタ工法が読取れますか?
◆長谷川
中世城郭のクサビ型形状城郭
ビイスタ工法は読み取れます。
城郭遺構として凹凸メリハリ
少ない中世城郭ながらも堀切
など小字「腰越」の急峻な山
頂に小刻みに郭を繊細に配置
したセンスある中世城郭です。

◆質問者
近江高島大溝城は織田信長の甥
織田信澄の城として信澄の妻の
父、明智光秀が大溝城の縄張を
担当したとして伝承されていま
すが大溝城の中心部天守台には
ビイスタ工法が読取れますか?
◆長谷川
意外にも大溝城天守台及びその
付帯する附け櫓石垣は正方形で
なく私の分類するクサビ型ビイ
スタに分類されると思います。
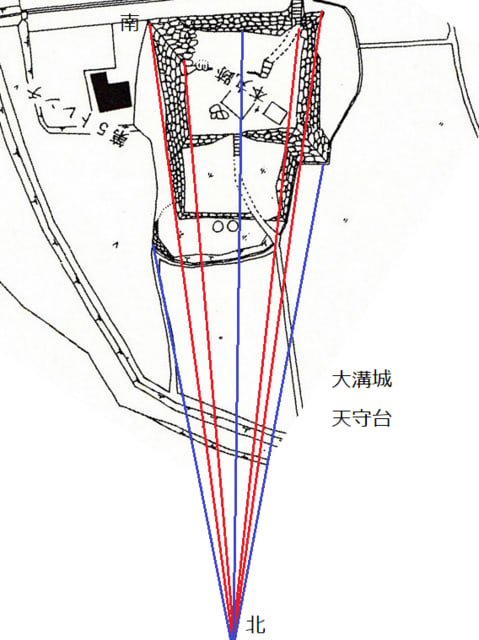

◆長谷川
一次資料には近江高島田中の城が
文献『信長公記』に3度登場します。
1回目、元亀元年(1570)4月20日
信長が京都から越前へ向う際に高島郡
田中の城に織田信長の宿泊記録がある。
2回目元亀3年(1572)3月11日
信長が高島郡で浅井・朝倉軍を攻撃
した際の記録で信長家臣の明智光秀
や丹羽長秀らが木戸・田中両城を看視
しています。
3回目元亀4年(1573)7月26日、
信長が大船で湖上から高島郡を攻撃、
陸からも木戸・田中両城を攻撃した
記録木戸・田中両城を信長から明智
光秀下賜されています。
二次資料として
熊本藩の家老米田家に伝わる医学
書『針薬方』永禄9年奥書に「明智
十兵衛尉高嶋田中籠城之時口伝也」
とある田中城と光秀に関する伝承
ですが、二次資料口伝の範疇です。
◆質問者
近江高島田中の城にビイスタ工法
が明智関係の城として存在する?
◆長谷川
山頂部の詰め城部分に重複型の
城郭ビイスタ工法読み取れます。
見事な中世城郭構図と言えます。

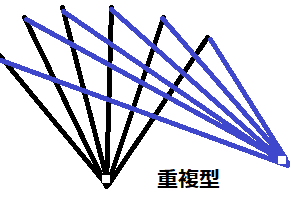
◆一般者
長谷川先生!この投稿は明智光秀
を考える上で非常に重要な投稿!
◆長谷川
興奮しないで下さい!誤解しない
で下さい!私は空偶然明智関係の
城のビイスタ工法を取り上げる訳
であり明智が占有してビイスタの
法則駆使した事を述べる訳でなく
『近江輿地志略』の高島の項目に
「上寺村の上の山に在り」と簡略
に記さてるだけで、上寺城であり
田中の城と未だに確定できない。
先ず高島七寺のひとつ松蓋寺遺跡
として全山の寺院ビイスタ工法を
検討致しましょう。所在地滋賀県
高島氏安曇川町田中大畑平安時代
の遺跡である事を認識しましょう。
▼松蓋寺遺跡本堂を中心とする図
松蓋寺本堂跡を中心の寺院城郭
ビイスタに該当致します。

▼武者隠しから見た城郭ビイスタ図
この城は山頂の城、中腹の城そし
て城下集落の三部構成の城ですね

◆長谷川
近江坂田郡の伊吹七寺のひとつ
とされる弥高寺跡遺跡も典型的
山岳寺院ビイスタ縄張ですよ。
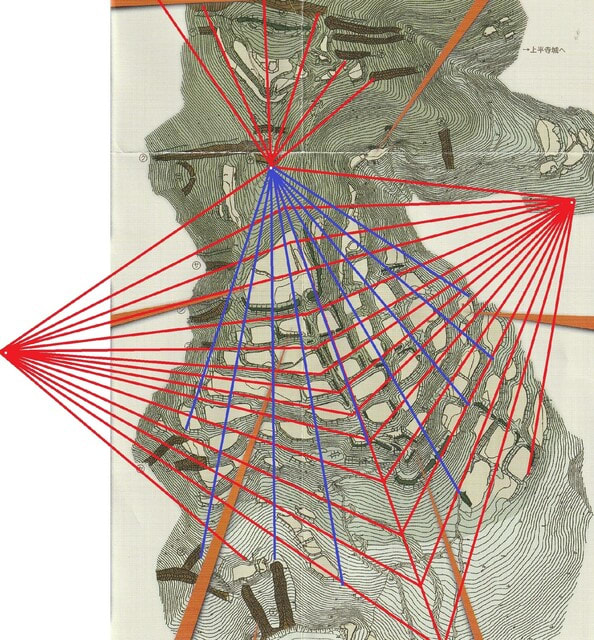
◆対談者
しかし佐目城、田中の城、大溝
城に日本の城郭の基準とも言え
るクサビ型ビイスタ工法が存在
する事自体が新しい城郭論です
城郭ビイスタ法が如何に革新的
令和の先駆的城郭研究論である
と巷では評判が高いのです!
▼明智伝説の城 多賀町

▼明智伝承の城 高島市

▼明智光秀縄張伝承 大溝城 高島市
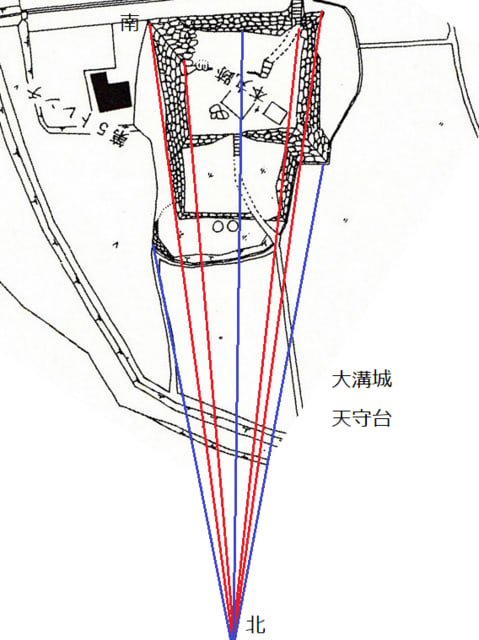

▼長谷川
ここで近世の城郭の開祖とも
評判の高い安土城なのですが
信長安土城以前にも中川重政
が旧土城に在番していた記録
は『信長公記』にありその先
は佐々木六角配下の目賀田氏
の城であつた事やその前身の
安土寺まで遡って安土城縄張
を考えなければなりません。
安土の縄張が最新鋭の縄張で
はなく旧城郭の様式を踏襲し
た日本の寺院城郭の延長線上
であつた可能性も考慮すべき
です。安土城には六角氏寺院
江南寺御殿や甲賀寺仏塔など
旧材を集めたリサイクル城郭
の要素もあった事も考慮する。
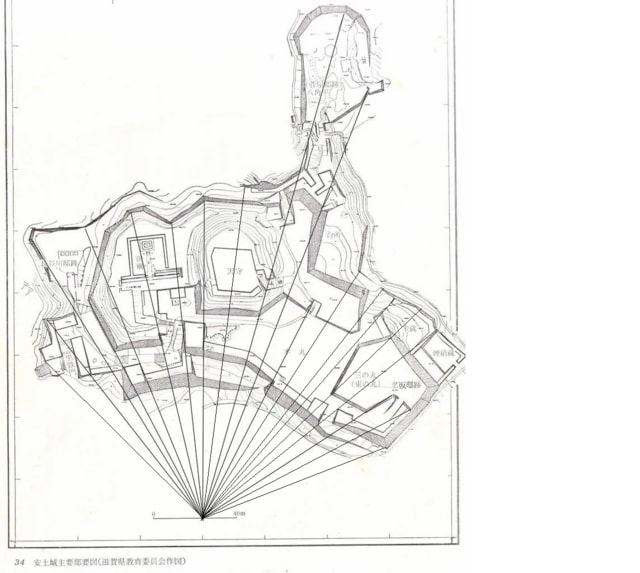
◆長谷川
小谷城最高峰の大嶽城ビイスタ
も山岳寺院『大嶽寺』ビイスタ
の可能性も考えておく事が大切
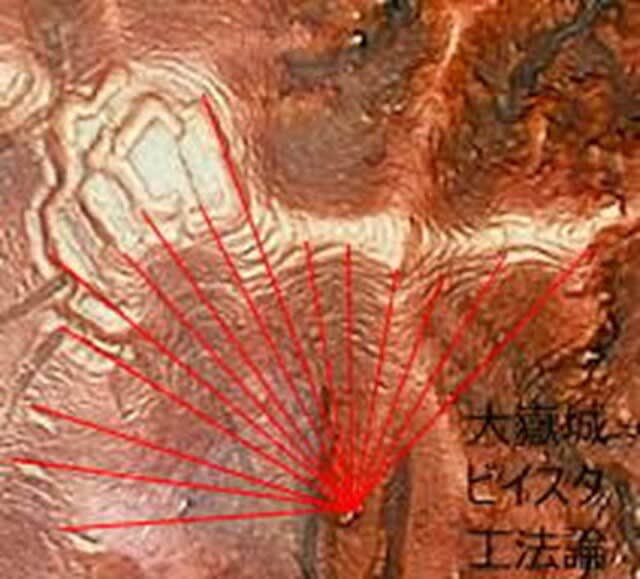
◆対談者
長谷川先生の研究視点とは
深淵ですね本当に深堀です。
◆一般者
室町幕府の要職にあった細川
藤孝の正妻は若狭熊川城主の
沼田氏でした。また熊川城に
関しては明智光秀の書簡など
も発見されており若狭方面と
明智光秀の関係は深いですね。
◆長谷川
元亀元年『信長公記』に若狭
で活動する明智光秀が記録さ
れています。「明智十兵衛
丹羽五郎左衛門 両人若狭
に差し遣わされ、武藤上野
人質執候て参るべきと」記
さて若狭方面の明智の動向
を知る事が出来ます。
◆対談者
若狭熊川城には城郭ビイスタ
は存在するのでしょうか?昔
の城の縄張の仕方や選地には
最近の城郭ビイスタ論の評価
が非常に高く話題騒然です!
◆長谷川
山城城郭自体中世城郭とし
て弓なりに縄張しています
もう解りますね!扇状ビイ
スタ工法です。赤腺の畝堀
もビイスタ工法と言えます。
▼若狭熊川城ビイスタ工法
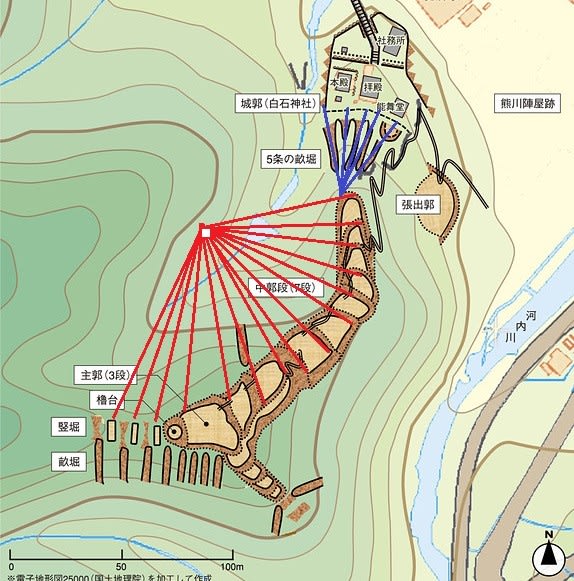
◆長谷川
主郭の南にある連続竪堀も
みどり色の上から2本目の
ビイスタ腺に従って中世
城郭としての縄張を展開
しております。

◆一般者
余計な質問を致します。
明智光秀の丹波亀岡城
にビイスタ工法は存在
しましたか?
◆長谷川
複数のビイスタ工法が存在
致します。

▼亀岡城本丸のビイスタ工法

◆長谷
今回の投稿を通してこの様な
元亀元年頃の世相を考えます
越前朝倉義景
↓
足利義昭を奉じての上洛不履行
↓
足利義昭
美濃の織田信長を頼み上洛成就
↓
足利幕府再興を望む利潤探求者
↓
前将軍足利義輝に従属して利権
を得て生計を立てていた奉行集
↓
織田信長義昭を室町将軍に擁立
↓
室町幕府 臣下細川藤孝の立身
↓
細川藤孝の正室は若狭もと熊川
城主の沼田氏出身
↓
熊川城は若狭松宮玄番が奪取
↓
沼田家は熊川領奪還を目指す
↓
元亀年間越前朝倉は若狭国へ
侵攻を繰り返していた
↓
細川氏や室町幕府方の意向と
して若狭国の室町的秩序回復
↓
幕臣から信長家臣へ傾く細川
↓
細川の妻 沼田氏から若狭領
問題を細川氏へ伝達された。
↓
細川は沼田氏の旧領復帰や
若狭武藤氏の領域侵犯を信
長に要請細川は織田信長へ
日本海側の動静を報告する
役目を帯びていた。内面で
縁戚明智をも牽制的に目付
の役目を信長から得ていた。
↓
信長は若狭秩序回復を名目
に朝倉氏の敦賀郡まで侵犯
↓
江北浅井氏は信長の湖北の
塩海産物の供給源の敦賀へ
の派兵を危惧し朝倉に回帰
ライフライン、商業圏確保
↓
信長は急遽敦賀金ケ崎から
朽木を通り挟撃の危機回避
京都に駆着やがて岐阜回帰
↓
姉川合戦
浅井朝倉VS織田徳川
日本海 太平洋
物流資本 物流資本
↓
元亀元年志賀の陣勃発
↓
天正10年
本能寺の変の際の細川家の
冷酷な反応、信長死すとも
織田家の体制の中で明智を
牽制する役目を継続し続け
明智光秀娘を一時幽閉して
細川家は明智光秀に加担せ
ず。
志賀の陣(しがのじん)は、元亀元年
(1570年)9月16日から12月17日にかけて
発生した、織田信長と浅井長政、
朝倉義景、比叡山延暦寺の戦いを言う。
↓
天正元年北陸物流勢力
浅井朝倉勢力が滅亡へ
◆『信長公記』元気元年引用
江北浅井備前手の反履の由、追々
其注進候。
然共、浅井は歴然御縁者たるの上
、剰江北一円に仰付けらるゝの間、
不足これあるべからざるの条、
虚説たるべきと思食候処、方々よ
り事実の注進候。是非に及ばず、
の由候て、金か崎の城には木下
藤吉郎残しをかせられ、四月晦日、
朽木越をさせられ、朽木信濃守馳
走申し、京都に至つて御人数打納
れられ、是より、明智十兵衛
・丹羽五郎左衛門両人若州へ差遣
はされ、武藤上野人質執候て参る
べきの旨御諚候。
◆ウイッキペデイア若狭松宮玄番引用
松宮 清長(まつみや きよなが)は、
戦国時代から安土桃山時代にかけての
武将。若狭武田氏の家臣。長講堂領
吉田荘の代官を務めた[1]。
若狭国守護・武田義統に仕えた。
遠敷郡東部に勢力を張り、膳部山城主
の他、瓜生城主として瓜生・井ノ口・
天徳寺、熊川を領す[2]。松宮氏被官だっ
た沼田氏が沼田清延の時代に熊川城を
築くと、永禄12年(1569年)、沼田一族
を攻め、子・左馬亮を熊川城主とした。
結果、新道・河内・熊川を得て三宅庄
まで進出し、近江国から若狭へ入る街道
筋を掌握した[3]。元亀元年(1570年)4月
22日、織田信長が朝倉義景討伐のため越前
へ侵攻する際(第一次越前侵攻)、若狭国
内の諸将と共に信長を出迎え、熊川城を
「若州熊川松宮玄蕃所」として提供する[4]。
粟屋勝久らと共に敦賀の手筒山城攻めを始
め信長軍として活躍し、元亀4年(1575年)
の朝倉義景攻め(第二次越前侵攻)に参陣
。天正3年(1575年)7月1日、武田元明に
随従して上京、相国寺にて信長に謁見した[5]。
同年8月の越前一向一揆討伐戦に若狭衆と
して参加。海賊衆を率いて一揆と戦う。
その後の消息は不明だが、明智光秀の乱に
与し武田元明と共に没落したとの説もある。
◆対談者
私城郭ビイスタ論動画は30人視聴
したら大成功と思っていましたが
先生のブログを見たら3000回視聴
がありこ何かの?間違いだと思う。
◆反論者
城郭ビイスタ動画など絶対見るな!
◆忠告者
何故貴方は毎回否定論を先行する?
全人未踏の日本の城郭新論の地平が
広がっているのに何故城郭ビイスタ
論いや日本の城郭研究の進歩進捗を
阻止する為のシャッターを閉める様
な陰鬱で陰険な精神を持ってるの?
◆質問者
彦根城天守閣って何故魅力的に
見えます?美の秘密の根源は?

◆長谷川
天守閣自体に美的均衡に配慮し
たビイスタ工法を採用してます。
簡単に言うなら建築デザイン!


◆一般者
上からでも下からでも放射線状に
均整均衡のとれた美しい建築図案
が検討されているので彦根天守が
美しい訳なんですね勉強なった!
◆対談者
日本国に上半身も下半身も均整が
取れた武士の正装は存在しますか?

◆長谷川
羽織袴、裃「かみしも」姿とは
日本人が持つちあわせた調った
概念が存在致します。この装束
の場合人間のヘソがビイスタの
中心という民俗学や服飾の観点
から見た柔軟見解と言えます。
特に裃の折り目こそビイスタ!
◆質問者
彦根城石垣にもビイスタ工法を
使ってると長谷川先生の指摘が
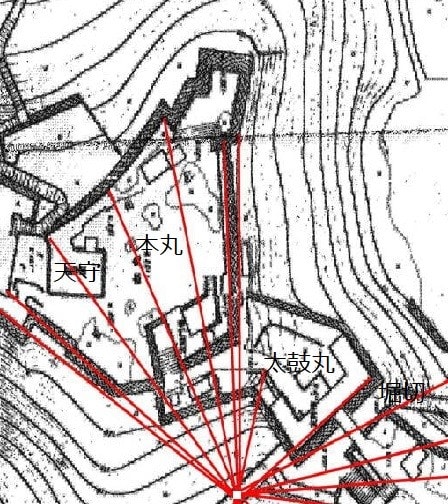

◆反論者
こんなビイスタ工法が存在する事を
俺れは50年も知らず弟子達に彦根城
教えてたんだが!俺様こそ一番だ!
◆対談者
1番2番3番は競技の世界の順位!
学問は新しい法則や定理の発見!
固定概念に固執して進歩は無い!
定説とは覆される為にある虚説!
日本城郭史パラダイム固定概念
は令和の世にパラダイムシフト
し新しい日本新城郭研究が出発
する。天運は我らの頭上にあり!

◆長谷川
私は柔和で穏やかな性格人間性
を好みます過激な言葉を控えて

◆質問者
姫路城大天守閣に裃のような肩が
いかったようなデザインで日本的
美観に従った意匠が存在しますか?
◆反論者
V字が日本の文化とでも言うか?
くだらん考え方をする学者だよ!
◆長谷川
銅鐸に描かれた人はV型字です。
日本人に通底するVの文化論!

▼突然消えた日本の銅鐸文化も
クサビ型ビイスタ逆ビスタです

古墳の周囲に配された円筒
埴輪のV型も日本の美です。

前方後円墳の前方部もV

古墳時代の円筒埴輪も

中世城館のビイスタも

遊具羽子板も日本の文化です。

佐和山城下から出土した符丁も
日本の伝統文化として捉える事
佐和山城天守の行方
城郭研究家 長谷川博美さん を検索下さい。

▼近江図書館に陳列されたV定規も

◆長谷川
天守閣のプラニング設計構図とし
は三階大入母屋屋根や四階千鳥破
風等に上に行くほど大きい様相の
意匠配置がなされて10カ所の鯱の
位置もビイスタ工法で配置してる
勿論土中から計測している訳では
なく一度設計図面を作成している。

◆長谷川
日本の熨斗飾の意匠も日本人の
持つ美観や概念に従い作られて
います。日本の城郭は和の美術
此処で私が述べたいのは日本国
の美的センスの比較研究文化論

◆長谷川
楔型ビイスタの中間には必ず
中仕切り中の切りが存在する
賤ケ岳城にいってもちやんと
現地で緑色のビイスタの中切
を説明したりしてるのですよ。

◆反論者
そんなの誰も聞いて無いわ解んない!
◆長谷川
そう言わずに、上平城に何度も昔から
行きました「中切」の説明しても知ら
ん顔されていて本当に残念なんですよ。
▼上平館

◆長谷川
この城も何度も見学会致しまた。
リクエスト無いので行きません。
▼苅安尾城 中切の堀 水色
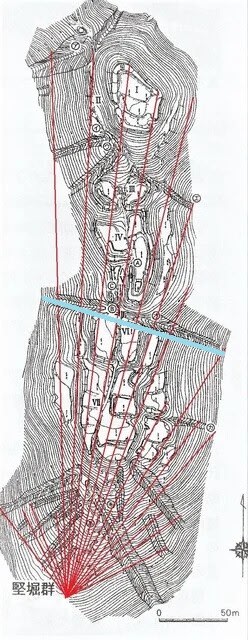
◆長谷川
清水谷の水堀も中切なのです。


◆佐目の城に中切はありますか?
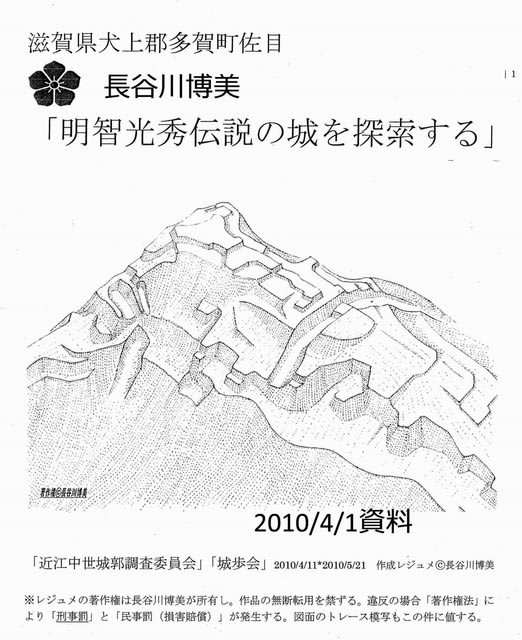
◆長谷川
もう説明しなくても貴方なら解る。
城ってこんな風に設計されている。
多賀町佐目の城はセンスある城で
築城術を理解した人の理知的な城

◆長谷川
姫路城大天守は御覧の如く
非の打ちどころない和の美
的要素「ハエ」ビイスタ法
法に準拠した完璧な建築美
構成美を十二分考慮楼閣で
十二分に見栄がする姫路城

◆一般者
これは素晴らしいですね!長谷川
先生のビイスタ論動画が3000回を
超えているのは中世や戦国や近世
に限定した城郭論と言う狭視野に
とどまらない広範な歴史視座です。
奈良纏向弥生宮殿遺跡のビイスタ

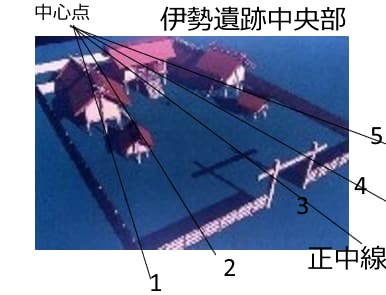
▼大和毛原廃寺のWビイスタ
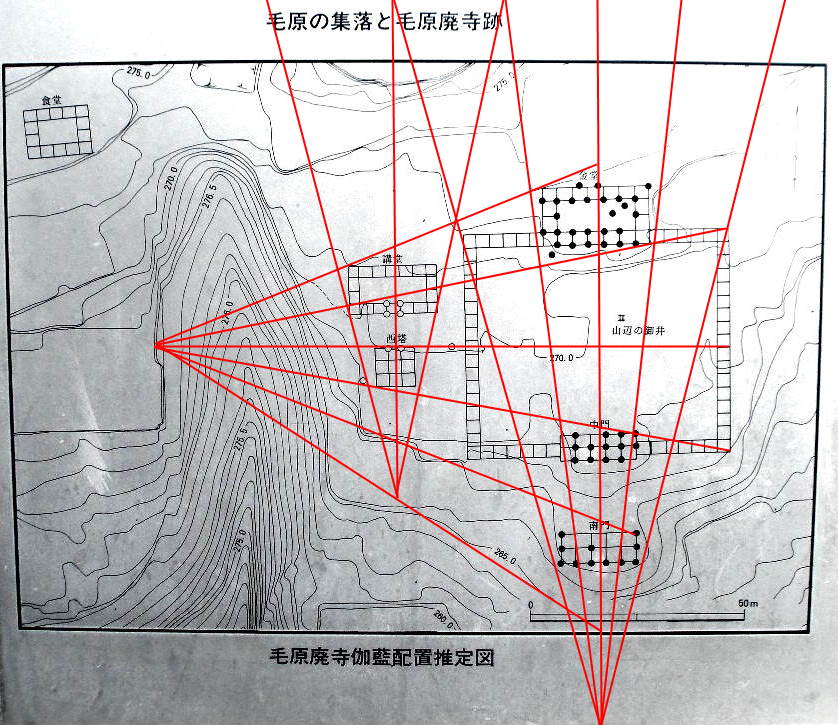
日本の建築測量文化の大観!
をされているから動画視聴数
が30でなく3000に到達した訳
である事を私は今更ようやく
解ってきましたこれ面白い!
◆反論者
馬鹿な事を言うな姫路城にビイスタ
工法存在する訳がなかろう非常識な
◆対談者
城郭は感情や怒気ではなく冷静な
分析をする人々の所に新研究解明
の女神が知恵の恵みを与えるもの
◆長谷川
姫路城には様々なビイスタ工法が
存在それが原因で様々な方向から
の素晴らしい景観が現代も楽しむ
事が可能です。これが姫路城の美
▼主郭部の扇型ビイスタ

▼各所のビイスタ工法

▼主郭部と西の丸のビイスタ工法

▼三国堀を中心とする中央ビイスタ

益田市七尾城対談
◆対談者
益田市七尾城には城郭ビイスタ
工法が存在するのでしょうか?
◆長谷川
青 大ビイスタ
赤 中ビイスタ
薄青〇小ビイスタ
と大中小のビイスタ工法が存在
致します。基本は自然地形です
が地選地取段階にビイスタ工法
適用し易い地形を選択したもの
▼上を東に見た図

▼下を北に見た図

以下ウイッキペデイア益田城引用
七尾城(ななおじょう)は島根県
益田市七尾町にあった日本の城。
城跡は、同市三宅町にある三宅
御土居跡とともに国の史跡「
益田氏城館跡」に指定されている[1]。
七尾城は、石見国の国司として
鎌倉時代(建久年間)に益田荘を
本拠とした益田氏の城。歴代の
益田氏が居館とした三宅御土居など
[2]の詰めの城として、標高約120
メートルの七尾山に築かれた。
山頂の本丸跡(標高約118メートル)
からは益田平野から日本海までを
一望できる。なお、三宅御土居跡
とは、益田川を挟み870メートル
の距離がある。発掘調査により、
大小40あまりの曲輪・空堀・土塁・
井戸跡などが発掘された[3]。さらに、
戦国時代後期のものとされる礎石建
物や遺物が多く出土しており、毛利
元就と対立した頃には益田藤兼と
家臣たちが居城とするなど、戦時
のみに使われる城郭という従来の
山城のイメージを塗り替えるもの
である[4][5]。
築城時期は諸説あるが、通説では
建久4年(1193年)に益田兼高が
築城したとされる[6][7]。史料に登
場するのは南北朝時代で、延元元
年(1336年)に南朝方の三隅氏が
「北尾崎木戸」(当時の大手口[8])
を急襲したことが益田家文書に
残る[6]。
戦国時代後期、益田氏は陶氏と
縁戚関係にあり、大寧寺の変で
も陶隆房(後の陶晴賢)に協力
していたが、その陶晴賢が天文
24年(1555年)の厳島の戦いで
毛利元就に敗れると、当時の益
田氏当主・益田藤兼は毛利勢の
攻撃に備えて城を大改修した[6]。
この時、藤兼とその家臣たちは、
三宅御土居を出て七尾城内に移
住したとされる。その後、藤兼
は元就の軍門に降って毛利氏の
家臣となり、藤兼の子・益田
元祥は三宅御土居に居館を戻し
た[9]。慶長5年(1600年)、関
ヶ原の戦いに敗れた毛利輝元は
周防国・長門国の2ヶ国へ減封
されると、益田元祥も毛利氏に
従って長門須佐へと移り、七尾
城は廃城となった。
◆日野町民様
先週投稿の滋賀県日野町鎌掛
城のビイスタ工法には驚愕を
いたしました素晴らしい研究
家の存在を令和に知りました。
滋賀県蒲生郡日野町の場合
▼山頂を中心とするビイスタ

▼中腹を中心とする鎌掛城ビイスタ

◆有識者
僕は梯郭式、連郭式、円郭式、連
郭式、曲輪論、虎口論、考古論を
中心に学んできた優等生タイプ人
間ですが安土城ビイスタ論に驚く
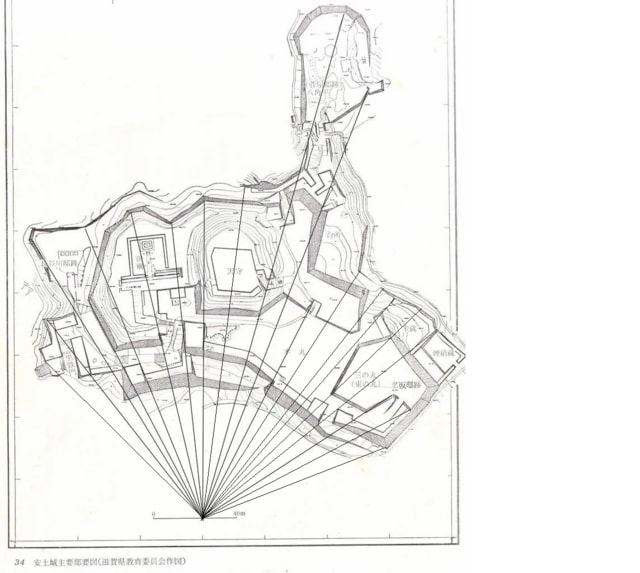
◆対談者
僕が会得してきた城郭論は僕が
図書や講演や講座で取得した知識
既知理論、既成概念論の上に醸造
バイヤス上の昭和平成城郭理論で
それと異なる全く新しい城郭幾何
学理論ビイスタ工法動画の台頭は
本当に驚異的とも言えるものです。
▼姫路城 扇型ビイスタ

▼肥前名護屋城 ビイスタ論図

◆米原市民様
最初鎌刃城ビイスタ論を鼻先で
私は笑って失笑したものですが
長谷川さん御指摘を冷静に傾聴
する新しい城の世界知るべき時
節と考え始めました。時代とと
もに研究視点や会社は変わてく
ものと最近考えている所です。

◆長谷川
思いもよらぬ方に推薦を先年
賜り地元米原学びあいステー
ションの講師として招聘され
て自分自身が驚いております。
私が講演に行く所とは名古屋
岐阜三重兵庫と県外である事
が多かったので米原町内講座
は誠に夢の様にもに感じます。
米原市内での講座ご案内です。
◆日時 令和4年7月28日木曜
御前10時~11時30
◆場所 滋賀県米原市下多良三丁目
◆施設 米原学びあいステーション
◆☎ 0749ー52-2240
◆講師 滋賀民俗学会理事 長谷川博美
◆参加費 500円