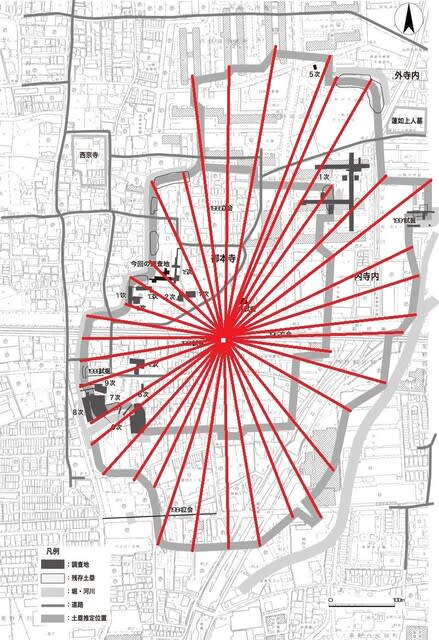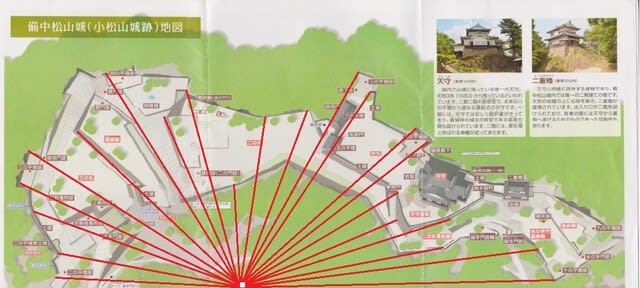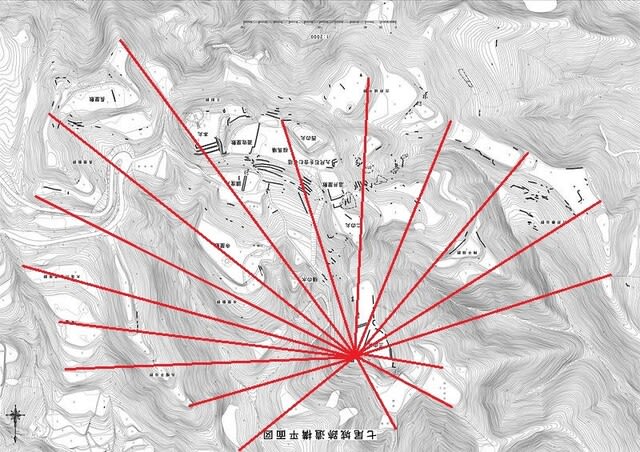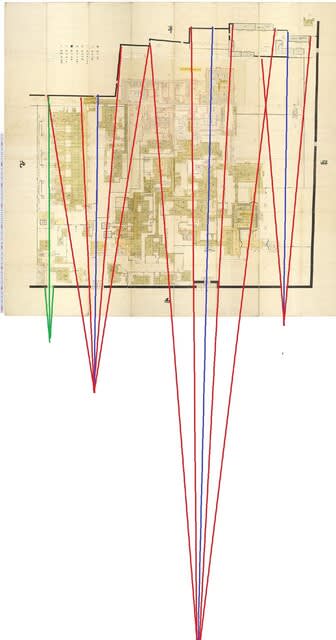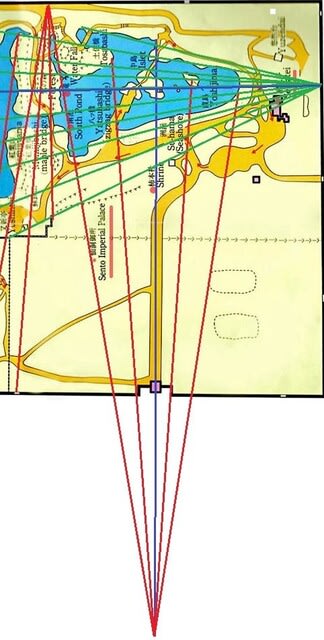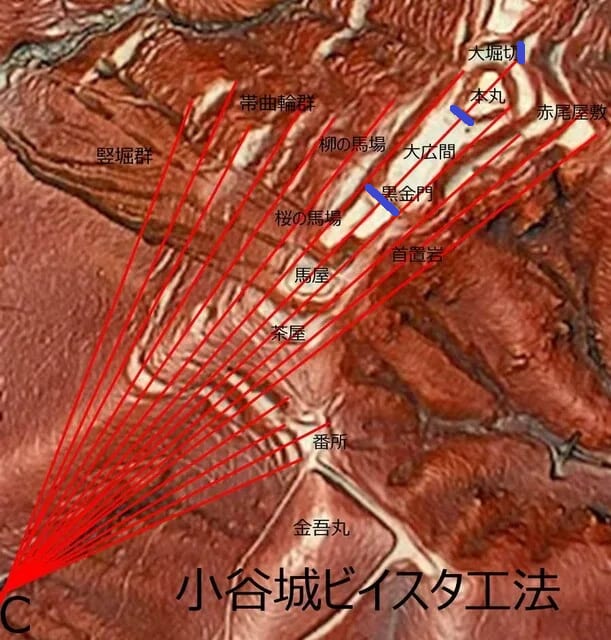城郭遺跡見学講師 信長公記講師 お城イベント案内 民俗学講師 神道思想史講師 などの情報を発信して行きます。
◆質問者
守護職能登畠山氏の巨城と
言われる七尾城のビイスタ
を、この投稿の後半に是非
解説して頂きたい思います。
令和の現代ではビイスタを
知らずば城知らずと言われ
るとか?最近特に話題です。
◆長谷川
能登畠山氏は北近江余呉町
にも別業を持っていました
文献『江北記』には、東蔵
畠山殿として京極氏の与力
の様な形で記録されていま
す。東蔵とは言うまでも無
く「一切経」を護る役職の
事で「一切経」は余呉菅山
寺に保管されていた一部を
徳川家康の命令で江戸上野
寛永寺に所蔵された経典!
また余呉菅山寺城には堀切
残っており既に見学会済み

◆対談者
前例の無い城郭測量痕跡を
考察する事により新しい城
の研究視点を長谷川先生が
動画で提示された事が話題
を呼んでいます。私達とし
は駄目動画ボツ動画にしか
見えない動画が何故3400人
もの視聴があるのか全く理
解に苦しみます私に解らず。
◆有識者
明治大正昭和平成令和に至る
まで城郭測量法に着目して城
郭の設計施工に所謂土木設計
原点に回帰した城郭遺跡分析
が成されていなかった現実は
城郭研究において大きな盲点
だと言えます。長谷川さんの
研究家として力量は半世紀前
から非常に高かった私達現代
人が知り得ぬ城郭縄張の奥義
を知る人としてその道の特殊
な人間であったと言えますが
しかし近年非常に優秀な一部
の方々が長谷川さんの城郭に
対する造詣の深さを洞察して
更に城郭遺跡の見学の仕方を
根本から学び直すと言う機運
が萌芽し始めていると言えま
す。長谷川さんの山科本願寺
城の分析は城郭研究史におい
てとてっもない高いレベルで
論述された研究視点である事
には驚愕せざるを得ません!
▼山科本願寺城のビイスタ論 扇型

▼山科本願寺城のビイスタ論 放射型
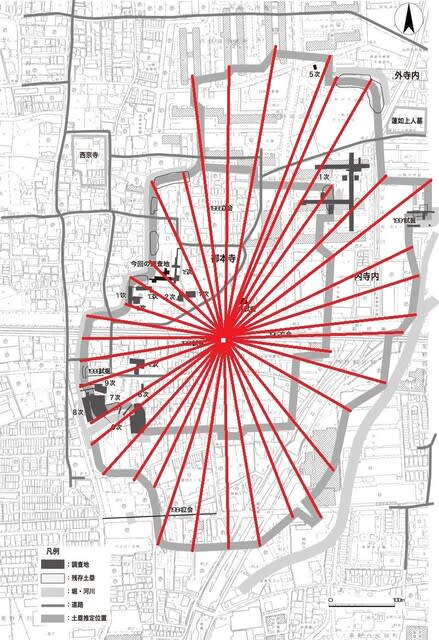
◆有識者
加えて城郭構造の画期とも言
われる安土城の縄張分析等も
従来の城の研究手法を完全に
凌駕する城郭研究のデッド壁
を突き破るほどの衝撃を含む
ものだったのです。私大学院
で教鞭を取っていた経験ある
者ですが長谷川さんを兄とも
呼んで支障なき学兄に相当し
一般社会から過小評価された
眠れる未知の逸材たる人です。
▼安土城 ビイスタ工法図説

◆対談者
私はその辺の学問の深淵までは
理解できません。ただ言える事
はビイスタ工法で縄張された城
が日本全国に次々と登場して来
た普遍性、蓋然性、必然性には
次々に私は目を見張っています。
私観光で備中松山城行きました
こんな縄張だと夢にも思わず私
の城見学の人生観さえ変化した。
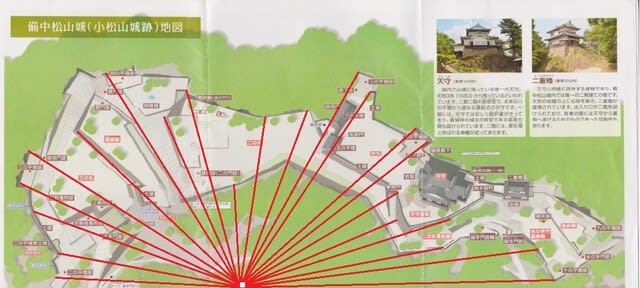
◆長谷川
能登七尾城概略をウイッキ
ペデイアより引用致します
別名 :松尾城、末尾城
城郭構造 :連郭式山城
天守構造 :なし
築城主 :畠山満慶
築城年 :1428年 - 1429年(正長年間)
主な改修者 :畠山義綱、上杉謙信
主な城主 :畠山氏、上杉氏、前田氏
廃城年 :1589年(天正17年)
遺構 :郭、石垣、土塁、堀切、虎口、
指定文化財 :国の史跡
室町三管領家の七尾畠山氏の初代当主
で能登国守護の畠山満慶が正長年間
(1428年~1429年)頃にこの地に築いた
と思われるが、当時の七尾城は砦程度の
規模と見られ、行政府である守護所も
府中(現七尾市府中)に置かれていた。
次第に拡張、増強され、以後約150年間
にわたって領国支配の本拠となり、五代
当主である畠山慶致の頃には守護所も
府中(七尾城山の麓)から七尾城へと
移されたという。その後、畠山義続・
畠山義綱の頃に能登では戦乱が続いた
ために増築され、最大の縄張りとなっ
たと言われる。1576年(天正4年)に
能登国に侵攻した上杉謙信に包囲され
るが、一年にわたって持ちこたえた。
しかし、重臣同士の対立の末に擁立
されていた若年の当主畠山春王丸が
長続連、遊佐続光、温井景隆らの対立
を収めることができず、結果七尾城は
孤立し、最終的には遊佐続光の内応に
よって徹底抗戦を主張した長氏一族が
殺害され、同年9月13日に開城された
(七尾城の戦い)。越中国と能登国を
繋ぐ要所である七尾城は、のちに織田
氏によって領され、城代として菅屋長頼
が入って政務にあたった後に前田利家が
入るが、既に山城の時代ではなく、拠点
を小丸山城に移したため、しばらく子の
前田利政が城主となっていたが、のち、1
589年(天正17年)廃城となった。
Wikipedia
◆質問者
城郭ビイスタ論は日本の城郭
研究論の中でも戦前戦後を通
しても最高峰の研究論と言わ
れておりますがこの理論とは
城郭の基礎が身に付いてない
人には全く解らないとも言わ
れている基礎に立脚した理論
能登七尾城のビスタ解説を!
◆長谷川
あまりに巨大な城郭遺跡です
その一部しか検討できません
本丸、桜馬場、西の丸、温井
屋敷、二の丸など真に見事な
扇型ビイスタの縄張がみられ
ます。調度丸が測量起点です。

本丸と西の丸の間は青腺で
測量腺のビイスタで縄張が
なされております私は此を
重複型ビイスタ工法と呼称

◆長谷川
全山の曲輪を放射状に配置
した放射型ビイスタも読み
取れます。当時の測量術は
谷を越えても施工されてい
ます。測量櫓をくみ上げて
の縄張だと推測されます。
▼扇型ビイスタ工法 複数

◆長谷川
また思わぬ所からも測量が
実施された事にも驚きます。
▼中央型ビイスタ工法 Ⅰ類

▼中央型ビイスタ工法 Ⅱ類
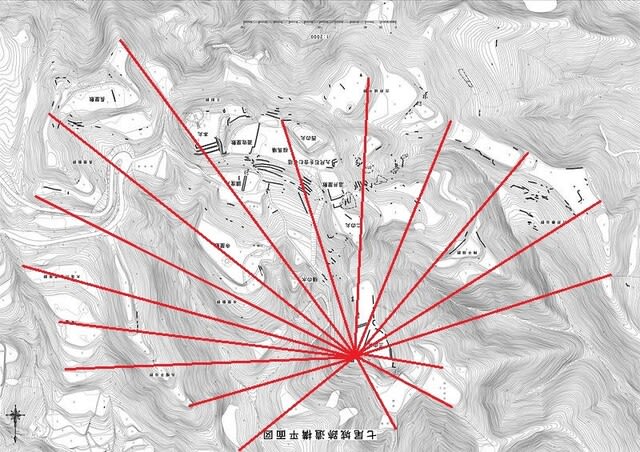
▼各所に潜在する扇型縄張

◆参加者
米原学びあいステーシヨンでの
長谷川先生の講義は従来にない
柔軟性あふれる講座が好調です。

◆対談者
犬山城天守閣の楼閣ビイスタの
解説に斬新さを私は感じました。
◆長谷川
私自身取り立てて斬新な講座と
考えておりません。柔軟にもの
事を考える事が新しい発見や研
究の進化に繋がると私は思いま
す。
▼山科本願寺城の縄張

▼安土城の縄張

◆質問者
京都西本願寺様の楼閣「飛雲閣」
に楼閣ビイスタ工法は存在しま
すか?

◆長谷川
左右対称を定型とする特殊な
楼閣「アンシンメトリカル」
な三重の楼閣と認識してまし
たが日本人の美の琴線に響く
安定したビイスタ「建築」で
あり日本語で言う「見栄え」
を考慮した優美な楼閣である
事が読取れると私は思います。
◆質問者
奇妙な質問をし申し訳ありま
せんが、地上から上へと設計
された建築見栄えやバランス
整合性ある整いの設計思想は
飛雲閣には存在するのですか?

◆長谷川
一見アンバラスな外観に感じる
飛雲閣ですが練りに練った楼閣
の見栄えは流石に用意周到なる
構図に裏打ちされた建造物です
西本願寺飛雲閣黄鶴台から寛永
五年三月から寛永六年八月迄の
墨書が発見され高台院屋敷すな
わち秀吉の京都新城の遺構だと
する説も最近は存在致します。
◆長谷川
一般の大工は図面道理手本通り
に建築物を作れば良いしかし人
が建物を見る角度を考慮する事
はケース、バイ、ケースであり
工匠や棟梁と呼ばれる人々は型
から脱したアーテステック芸術
的優美な建物を設計するアート
感覚を身に着けているものです
大工さんではなくデサイナー!

▼飛雲閣の家相 長谷川加筆

◆質問者
飛雲閣の語意や意味は何です?
◆長谷川
中世「山」は比叡山の隠語で
「松」は内裏、皇室の隠語で
「雲」は皇居、内裏に昇殿が
許された高位高官の事、殿上
人を「雲客」と言いますので
身分高き人のみ登閣許された
風流や茶事の為の建築名と私
は考えています飛雲閣黄鶴台
と言う地名の台」は古くから
東洋の府都に設置された為政
の為の国見櫓の意味があろう
かと私は個人的に思います。
◆質問者
徳川幕府により京都仙道御所寛永4
年(1627)年後水野尾天皇御退位に伴
う仙道御所建設では御所の平面設計
「縄張」にはビイスタ工法が活用さ
れたのでしょうか?
▼創建当時の仙道御所

◆長谷川
私にはこの件に関して正確に答え
られません、ビイスタ工法の研究
課題とし試論的に考察させて頂き
ます、複数のクサビ型ビイスタで
縄張した可能性があると思います
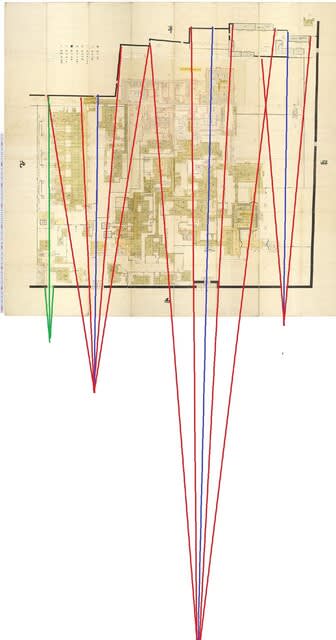
▼安土城表門複数門のビイスタ

◆長谷川
仙道御所は天皇が退位された後
の上皇や法王が居住される殿舎
を言います創建当初の仙道御所
▼山科本願寺のクサビ型ビイスタ 長谷川分析

◆質問者
現代の京都仙道御所の南池近辺
が小堀遠州の作庭と巷間で言わ
れてますが、南池近辺には庭園
ビイスタが存在しますか?
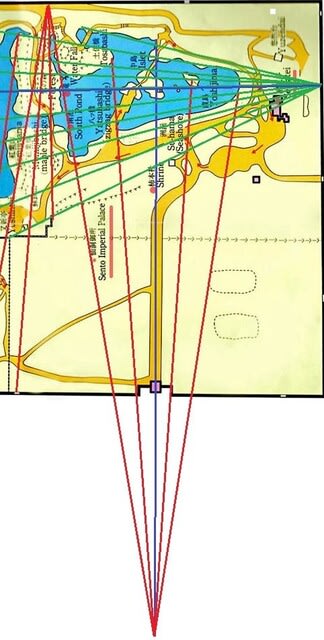
◆長谷川
小堀遠州や片桐石州の家系
は近江浅井家の被官として
出発しております。浅井氏
居城小谷城は文献『信長
公記』では天正3年まで
羽柴秀吉が居住していた
記録あり小谷城ビイスタ
も時に考え併せましょう。
▼小谷城ビイスタ工法
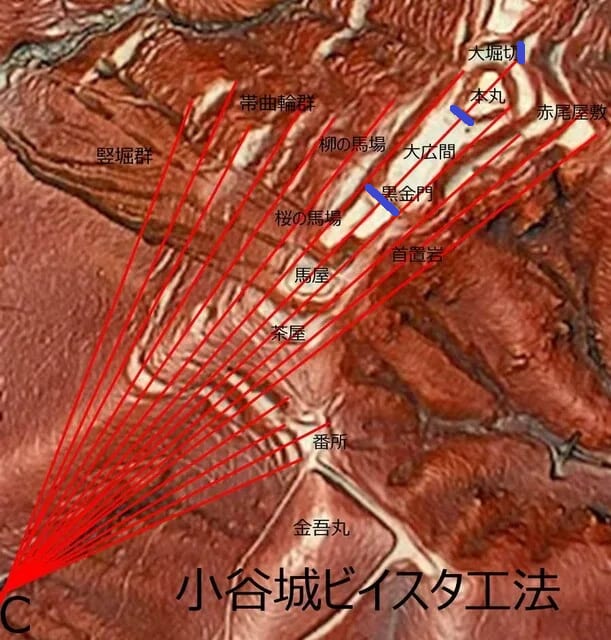
▼尾張 小牧山城の複数ビイスタ

◆一般者
ビイスタ論ってスゴイ理論です!
◆ベテラン様
長谷川さんの幾何学論
城郭ビイスタ論動画が
3400回も視聴されてる
事に異常さを感じる!
長谷川さんは城を楽し
んでおられない「楽」
ではなく「学」です!
◆対談者
器に盛られた旬の物
を頂いて味覚を賞味
する事も日本食文化
とも言えますtaste
味わいですが一方で
その器の造詣自体を
深く精神的に鑑賞を
する事も重要だと私
は思います。織部焼
にも様々な工夫設計
が成されいて日本の
器の文化として親し
み楽しむ事が織部焼
を鑑賞する楽しみ。


◆長谷川
山科本願寺も日本の幾何学
文化の通過点として捉える
事が寺院城郭を鑑賞する為
の和の心ではないですか?
山科本願寺を巨大な幾何学
の「織部焼」のような日本
文化論として考えましよう
器「うつわ」は食品を入れ
る容器、曲輪は人々を戦乱
から守る「くるわ」です。
◆山本様【匿名】
長谷川先生の城郭ビイスタ論
動画が巷間で大変な話題です
京都の山科本願寺城址は平城
で1世紀前に近代城郭の要素を
含むと『中世城郭辞典』には
「城郭史上、特筆すべき城郭
跡といえる」と解説されてま
す。城郭研究史上重要な城な
のですか?
▼山科本願寺城 主要部

◆長谷川【著者】
山科本願寺城は(1532年)の
『経厚法印日記』に「山科
本願寺ノ城ヲワルトテ」と
記録され六角氏と法華宗が
落城させています。縄張は
100年進んだ横矢の配置で
近世城郭縄張の基礎が既に
萌芽している優れた縄張の
寺院城郭と言えます。山科
本願寺の創築自体は天文10
年1478年1月29日に開始さ
れています。
◆山本様【匿名】
蓮如さんが布教活動された
代表的な場所は何処です?
◆長谷川
堅田、吉崎、山科、石山何れも
天険の要害と水陸の交通の要衝
に選地して築城しておられる事
を考えると城郭を作る然るべき
要害の地を「見立て」選び取る
センスは日本城郭史においても
稀有の資質を持ち合わせた人で
地勢経営学の達人とも言える人
築城の事を「経始」と言います。
◆山本様【匿名】
大坂城は大坂石山本願寺の跡に
羽柴秀吉が自らの根城とし築城
しますが先生のビイスタ分析に
よりますと中央型ビイスタ工法
との事で私個人は大変驚きます。
▼天正大坂城

◆長谷川
織田信長の永禄6年1563年築城
小牧山城も中央ビイスタ型です

◆山本様
山科本願寺城は(1532年)
落城していますが中央に
ビイスタ工法が存在しま
すか?
◆長谷川
天文期に既に横矢配置や巧妙
な曲輪配置が存在する事自体
が非常に驚くべき事と思います
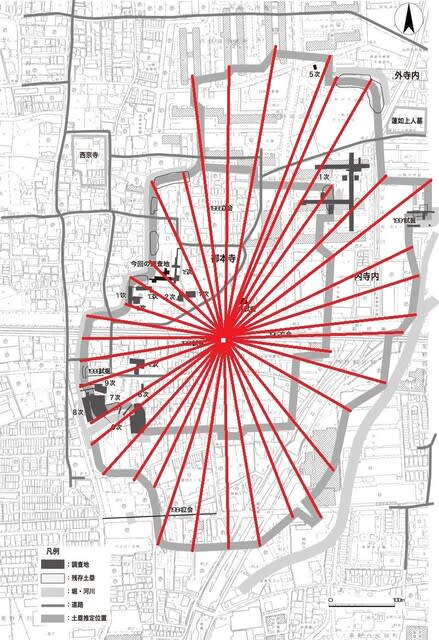
◆長谷川
家相学 方位学 四神相応
に計画された寺院城郭でも
あり正しく法城に相応しい
縄張設計がなされています。

▼ 仏城 曼荼羅 参考資料

◆山本様
この優れた幾何学や測量術
を保持していた縄張技能集
団は真宗教団自体ですか?
◆長谷川
山科本願寺自体の縄張を
実施した人名を私は知り
ません。山科本願寺後身
の石山本願寺では天文21
年1553年松田三郎入道と
呼ばれる加賀の国の城作
りが招聘されて築城され
ていますから山科本願寺
も加賀の国の職能集団が
縄張を担当した可能性が
あると私は考えています。
◆山本様
天正4年段階で織田信長は
安土城に扇型の縄張を採用
した事は長谷川先生の研究
で既に全国に知れ渡ったて
います。山科本願寺城にも
扇型ビイスタ工法は存在す
るのですか?
▼安土城 扇型ビイスタ工法

◆長谷川
見事な扇型ビイスタが安土と
同じく方位軸「北」を中心に
読み取れる事が可能です。

◆長谷川
航空写真で分析しますと御本寺
内寺内、外寺内、蓮如も生活し
た南殿も含めて扇型ビイスタで
縄張された本願寺の都市計画が
読み取れます。

◆一般様
長谷川先生!これだけ大論
を解説出来る城郭研究家は
日本国屈指の城郭研究家だ
◆長谷川
私は残念なから
著書一冊も無し
仕事は一切無し
支持者全く無し
肩書も勿論無し
◆対談者
重複型ビイスタ工法は存在
しますか?
◆長谷川
南と東から存在致します。

◆長谷川
また北から南に向けた様々な
ビイスタ工法も存在致します。
特に下図赤線放射状ビイスタ
は御本寺を中心とする扇型の
寺内通路とも密接に関連して
います。

◆対談者
小ビイスタ、緻密ビイスタは
存在しますか?
◆対談者
扇型やクサビ型ビイスタ存在
致します。

◆長谷川
方角を変えると様々な
大小のビイスタ工法が
存在に気付きます。

◆長谷川
西から東へのビイスタも
見事なものがあります。

以下ウイッキペデイアより引用
造営され、約6年間で建設
されたと言われている。
(旧音羽川)の合流地点で、
この地域は東海道から宇治
街道へ抜ける分岐点、交通
の要所であった。
山科本願寺がどのような寺院、城郭であっ
たかについて、天文元年(1532年)8月24日
『二木水』の条では
四、五代に及び富貴、栄華を誇る。寺中は
広大無辺、荘厳ただ仏の国の如しと云々、
在家また洛中に異ならざるなり、居住の者
おのおの富貴、よつて家々随分の美麗を嗜む