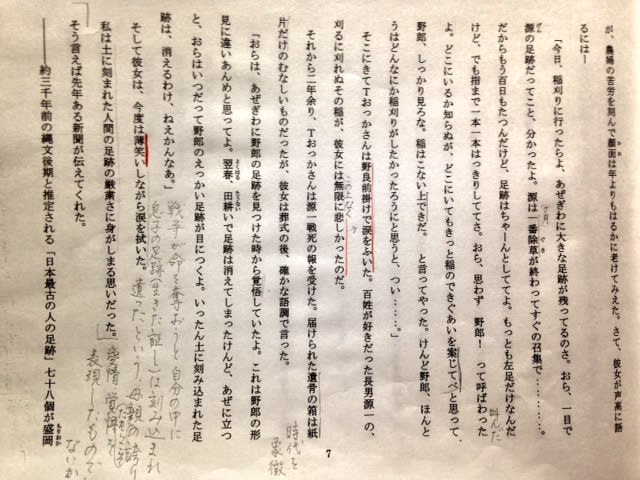
今日の読書会は、農民作家住井すゑのエッセイ『足跡』
少し長いので要約すると、
《ある日テレビを観ていた作者は、畑を裸足で遊ぶ2~30人の子供たちの足首の白さが気になる。
それは生まれてこのかた、土はおろか空気にさえもろくには触れることがなかった足首だ。
社会が合理化されるにつれ、農村でも裸足の人はいなくなった。
このまま進めば人間の足裏は土の感触を失うのではないか、と作者は不安に思う。
昔はぬかるみの道には幾つもの足跡が刻まれていたものだと。
作者は一人の農婦を思い出す。
農婦は、田植え後に召集された息子の足跡が、畦ぎわにくっきり残っていたと、涙する。
そして2年後、戦死の報を受ける。農婦は葬式後しっかりした言葉で語る。
「野郎の足跡を見つけた時から覚悟はしていたよ。
足跡は消えてしまったけんど、畦に立つといつだって野郎の足跡が目に付くよ。
いったん土に刻み込まれた足跡は、消えるわけねえかんなあ。」
そして彼女は、薄笑いしながら涙を拭いた。》
ここで、『薄笑い』とはどういう心境なんだろうか?と生徒から質問が出た。引っかかる表現ではある。
が、皆の意見や、先生の解説を合わせると、
『戦争が命を奪おうと、自分の中には息子の足跡=生きた証しが刻み込まれている。
母親なればこその誇り、愛情、覚悟を表現したものではないか。』ということだった。
エッセイはこの後、遺跡から発見された3000年前の人の足跡について語り、
《足跡は嘘のない歴史である。あの足首の白い子供たちにも歴史に足跡を残してもらいたい。》
と述べている。
歴史に足跡を残す。それは何もノーベル賞を獲れ、というのではない。
大地に根を張って生きることである、と今日の先生のお話でした。

























