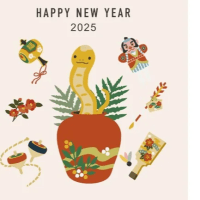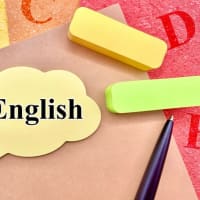以下の文章は全てNHKのあさイチのホームページからのものです。
具体的に知りたい方は是非HPを見て写真も見てください。
腰痛やひざの痛みの原因はふくらはぎや太ももの筋肉をほぐすといいようです。
また、肩こりやだるさには寝てのストレッチや横隔膜の運動、呼吸法が良いようです。これで、ウエストも引き締まるとか!
今回のスゴ技Qは、今までに放送したスゴ技Qの中から、カラダをスッキリさせる技を、再構成でお送りした特別編。
冬の間に硬くなって、腰痛がおきがちなカラダや、年齢を重ねるにつれて増えてくるひざの痛みを、「拮抗筋ストレッチ」で改善する技を紹介しました。あわせて春のハイキングに役立つ、歩き方のポイントも紹介しました。 そして、「横隔膜」を使うことで、肩凝り・だるさ・息切れの改善に効果が期待できるエクササイズ。準備運動から、横隔膜を鍛える動きの初心者編から上級者編まで、一挙お届けしました。
腰痛改善ストレッチ
腰痛がなかなか治らないとお悩みの方。腰痛が治らない原因は、実は太ももの後ろ側の筋肉の柔軟性が関係しているかもしれません。
太ももの後ろ側の筋肉がやわらかいと骨盤が前に傾くので、股関節から曲がります。しかし、筋肉が硬いと骨盤が傾かず、腰の骨(腰椎)から曲がってしまうので、腰に負担がかかり、腰痛を起こす原因となります。
そこで、太ももの後ろ側の筋肉の柔軟性を高め、腰痛を改善するストレッチを徳島大学教授で整形外科医の西良浩一さんに教えてもらいました。ストレッチのポイントは、太ももの後ろ側の筋肉の拮抗筋である「太ももの前側の筋肉」に力を入れて縮めることです。
番組に登場した、腰痛でお悩みだった中村さんの場合、ストレッチをする前は立位体前屈で床から約11センチ離れていましたが、10日間、腰痛改善のストレッチを行ったところ、床に手のひらがつくようになり、腰痛も軽減したと話していました。
取材協力:西良浩一さん(徳島大学 整形外科 教授)
西良さんオススメ!
腰痛改善ストレッチ
足を少し開いて、しゃがむ。
足首の後ろを持ち、太ももとおなかを離さないようにし、 かつ、太ももの前側の筋肉に力を入れて、できる限りひざを伸ばす。 ※最も重要なポイントは、太ももとおなかを離さないこと。 股関節の角度が変わらず、太ももの前側の筋肉を縮めた状態に保つことができます。
その状態で前側の筋肉に力を入れると、太ももの後ろ側の筋肉をさらに伸ばすことができます。
目標回数・・・1回10秒間×5セットを朝と晩に行う。
(10秒間がつらい方は、短い秒数でもいいので、毎日行うことがオススメです。)
※1 呼吸を止めずに行ってください。
※2 反動をつけたり、人に無理に押してもらったりしないようにしてください。
※3 常に腰に強い痛みがある方、足にしびれを感じる方、前屈の姿勢で腰に痛みを感じる方は行わないでください。
※4 妊娠中の方は、腹圧がかかるので行わないでください。
取材協力:西良浩一さん(徳島大学 大学院 教授 整形外科医)
ひざの痛みを解消するストレッチ
NHKネットクラブで行ったアンケートで、女性500人にひざが痛み始めた年代を聞いたところ、40代からひざの痛みを感じ始めた人が最も多くいました。
整形外科医師の高井信朗さんによると、高齢者に多い、関節が削れて痛む「変形性ひざ関節症」とは違い、40代の“ひざ痛”は、大きな原因として、太ももの前側の筋肉の衰えが考えられるといいます。
なかでも注目すべき筋肉は「大腿直筋」。太もも前側の筋肉の中で唯一、骨盤とひざの下を結びつけている筋肉です。この大腿直筋が硬くなると、骨盤とひざが引っ張られるため、骨盤が前に傾き、ひざが曲がった姿勢になります。そして、ひざのお皿の骨が筋肉とつながった部分が常に引っ張られるので、ひざの痛みにつながるのです。
そこで、「あさイチ」でおなじみの筋肉トレーニングの達人、岡田隆さんに、40代女性でも簡単にできる大腿直筋のストレッチを教えてもらいました。
取材協力:高井信朗さん(日本医科大学 整形外科学 主任教授・医師)、
岡田隆さん(日本体育大学 体育学部 准教授・理学療法士)
40代女性にオススメ!
大腿直筋のストレッチ
横向きに寝る。
床に接していない側の脚を背中側に曲げ、同じ側の手でつま先を持つ。
手でひざを後ろに引っ張り、太もものつけ根から大腿直筋を伸ばす。
さらに伸ばしたい場合は、床についている方の足のかかとを伸ばしている脚のひざに当て、後ろに押す。
目安は左右それぞれ15秒ずつ、1回以上。
※妊娠中の方やこの動きで強い痛みが出る方は行わないでください。
ひざの痛みを改善する 太ももの前側の筋肉を鍛える“拮抗筋ストレッチ”
大腿直筋を含めた太もも前側の筋肉の筋力低下も、“ひざ痛”の原因のひとつです。 ひざ部分の骨は、太もも前側の筋肉に引っ張られることで、正しい位置に収まります。しかし、筋力が弱まると、正しい位置で安定せずに痛めやすくなります。
そこで、岡田隆さんが筋トレ初心者にもオススメしている「片足を前に出したスクワット」を教えてもらいました。両ひざを横に開いて曲げる一般的なスクワットよりもバランスがとりやすいので安全なうえ、体のほかの部分に余分な力が入りにくいので、前に出した脚の、太ももの前側の筋肉を効率よく鍛えることができます。
初心者にオススメ!
太ももの前側の筋肉を鍛える“拮抗筋ストレッチ”
手を腰に当てて、片足を一歩前に出し、さらに2足分、脚を前に進める。
体は地面に対して垂直になるように保ちながら、真下に腰を落としていく。
前足のひざがつま先よりも前に出ないように注意し、太ももが床と平行になるまでゆっくりとひざを曲げて腰を落とし、ゆっくりと戻す。
(痛みを感じる場合はひざを曲げる角度を浅くしてください。それでも痛い場合は中止してください。)
目安は、同じ脚を続けて10回動かし、左右を入れ替えて10回動かすのを1セットとして、2セット行う。
※妊娠中の方や、この動きで強い痛みが出る方は行わないでください。
※ふらつく場合は、何かにつかまって倒れないようにご注意ください。
取材協力:高井信朗さん(日本医科大学 整形外科学 主任教授・医師)、
岡田隆さん(日本体育大学 体育学部 准教授・理学療法士)
ひざに負担をかけない 坂道&階段の歩き方のコツ
あさイチアンケートでは、「階段や坂道」を下りるときに、“ひざ痛”を感じるというお悩みが多く寄せられました。そこで、登山ガイドの鈴木桜子さんに、坂道や階段を下りるときに、ひざへの負担を減らすスゴ技を伺いました。ポイントは2つです。
足裏全体を地面につけるようにして、狭い歩幅で歩く。 上下運動が少なくなり、ひざへの衝撃を減らすことができます。 ※地面の変化に気をつけて、転ばないように注意してください。
重力に任せてスタスタとはやめに歩く。
筋肉の負担が減って疲れにくくなり、ひざを痛めにくくなります。
一方、一歩一歩ゆっくり歩くと、足をつくたびに、太ももの筋肉が前に進もうとする力を止めようとしっかりと収縮します。その結果、疲労がたまって硬くなり、ひざ部分の骨とつながる部分が引っ張られるので、痛みが出やすくなります。
※足元に気をつけて、いつでも止まれる程度の、制御できるスピードで歩いてください。 小股でスタスタ歩く方法は、階段や舗装された坂道を下りるときにもオススメです。
取材協力:鈴木桜子さん(登山ガイド)
横隔膜を動かす体作りの第一歩・肩ほぐしエクササイズ
息切れや、慢性的な肩凝りの原因を解明してくれたのは、呼吸器を専門に診て25年の山本和男さんです。通常の女性の場合、呼吸すると横隔膜が3~4センチ動くのに対し、今回出演していただいた視聴者の大箭さんは1.8センチ。息を吐く速さは、なんと75歳レベルでした。これを解決するために、まず必要なのは、肩まわり、胸まわりの筋肉の硬さをやわらげること。その硬い筋肉をほぐすスゴ技を教えてくれたのは、フェンシングの世界選手権で日本人初の金メダルを獲得した太田雄貴さんと、そのトレーナーの牧野講平さんです。
<横隔膜を動かす 肩ほぐしエクササイズ>
クルクル丸めたバスタオルを背筋に当ててあおむけになる。
手のひらを上に向け、腕を30度ほど開き、上下させる。
牧野さんのオススメは、指先を意識して動かすこと。肩をほぐしたいのに肩を意識してしまうと、力が入って緩みにくいので、ほぐしたい肩から最も遠い指先に意識を集中するのがオススメとういことでした。
取材協力:山本和男さん(都立広尾病院 呼吸器科)、
牧野講平さん(トレーナー)、太田雄貴さん(元フェンシング選手)
第2ステップ 胸をほぐすエクササイズ
メダリストの太田さんに、試合前に必ずやっていたという、胸しなやか金メダルエクササイズを伝授していただきました。
<太田さんオススメ エクササイズ>
ひざの下にクッションを入れ、頭の下にタオルを入れる。
クッションに載せたひざを動かさないようにして、骨盤をなるべく固定するのがポイント。
前で合わせた手を出来るところまで開いていく。
このとき、顔も手を見るようにして動かすのが大切。
※動かす範囲は、痛みが出ない範囲に留めてください。
胸を開くときに息を吐くのもポイント。息を吐くと、おなかの筋肉に力が入って固定されるので、胸の部分の動きが大きくなり、筋肉がほぐれやすくなるんだそうです。
取材協力:牧野講平さん(トレーナー)、太田雄貴さん(元フェンシング選手)
ストローを使った横隔膜のトレーニング
横隔膜を鍛える方法を教えてくれたのはボイストレーナーの安ますみさんです。安さんの教え子たちは、横隔膜をちゃんと使って呼吸すると、代謝がアップして痩せると言います。
まずは肩の位置と耳の位置をそろえるように、姿勢を正します。
次に、太めのストローを使って、横隔膜をトレーニングします。ストローを通して、手のひらに息が当たっているのを確認します。ストローを使って呼吸すると、少しずつしか空気がとおりません。そのため、吸うときは、横隔膜を強く縮めるトレーニングに、吐くときはおなかの筋肉を収縮させるトレーニングになります。さらに、長く吸って長く吐くと、ストローを使っても、最後まで息を吐ききることができ、横隔膜を大きく動かすことができるため、トレーニングの効果が上がると言うことでした。
また、苦しくても目をしっかり開けることも、最後まで息を吐ききるためのポイントでした。
慣れてきたら、ストローをはずして同じように呼吸します。このとき、口をすぼめるのに加え、おなかの筋肉を使って横隔膜を持ち上げ、肺の中の空気を全部出す意識で息を吐きます。うまく吐けないときは、両ひじを抱えてみぞおちの辺りに押しつけるとよいそうです。
取材協力:安ますみさん(ボイストレーナー)
横隔膜を使ったトレーニング 上級編
俳優や画家として活躍する片岡鶴太郎さん。その活力の源は、毎朝行うヨガの呼吸法にあるといいます。その方法は、鼻から息をする、腹式呼吸。息を吐くときには、おなかを引き込んでいます。
鼻を使って呼吸をするには、狭い管に多くの空気を通す必要があります。そのためには、おなかの筋肉(腹横筋)をしっかり使って、横隔膜を押し上げなくてはなりません。
その結果、強度の高い横隔膜トレーニングになるのです。
片岡さんは、この呼吸方法を始めてから2年間で体重が2キロ減り、ウエストは63センチになったといいます。
そんな鶴太郎さんに一般向けのオススメ横隔膜トレーニングを教えてもらいました。
<片岡鶴太郎さんオススメ 究極のドローイン>
イスに座っておなかに力が入らない姿勢になる。
おなかを引き込み、その勢いで息を吐く。
強く吐くと、強く吸えるので、横隔膜に瞬間的に強い力がかかり、負荷が大きくなります。
息を吐くのを速いテンポで行うと、より横隔膜を鍛え上げることができます。
テンポが速いほど、瞬間的に横隔膜にかかる負荷は大きく、それが短時間で何度も繰り返されるので、トレーニングの効果が高まります。
※腹圧がかかるため、妊娠中の方は行わないでください。
取材協力:片岡鶴太郎さん(画家・俳優)
専門家ゲスト:佐野みほろさん(日本医科大学 整形外科医)、山本和男さん(都立広尾病院 呼吸器科)
ゲスト:金子貴俊さん(俳優)、城之内早苗さん(歌手)、村上知子さん(森三中 タレント)、
マキタスポーツさん(タレント)、鈴木拓さん(タレント)、益子直美さん(タレント)
プレゼンター:宮下純一さん(タレント・元水泳選手)