11月9日(水)晴
最近の学生は体育会系のクラブ活動を敬遠していると良く云われます。実は僕の母校でも体育会系のヨット部は部員が1名か2名の年があってクラブ活動の存続が危ぶまれています。合宿生活、練習の厳しさ、メンテナンスのつらさ、どれをとっても逃げたくなることがありました。楽に楽しく過ごしたい欲望はわからない訳ではありませんが、ただ肉体的制約や精神的制約の中で”ものごとに耐える力”と言った”こらえ性”が形成されて行くような気がします。最近の若い人たちの起こす事件を見ていると、まったく”こらえ性”のないが故の事件が多いのです。簡単に止めてしまったり、簡単に離婚したり、豊かさの裏返しとして、我慢する力が弱まっています。
石原慎太郎氏の本の中にコンラッド・ローレンツの動物行動学論で述べられている言葉の引用部分があります。「幼い時期に肉体的苦痛を味わうことのなかった人間は長じて必ず不幸な人間になる」ここで肉体的苦痛と言っているのは肉体的制約、精神的制約のことだと思いますが、厳しいトレーニングや折角のデートのチャンスも合宿で逃してしまうような制約を乗り越えなくては人間として一人前にはなれないと言うことだと思います。このことは別にスポーツだけでなく芸術でも学問でも同じことです。社会生活を余儀なくしなければならない人間として、一番大切なことは、我欲を制約する能力を養うことです。戦後の豊かさがお金さえあれば何をしてもよいような風潮を作ってしまったことに一因があるような気がしてなりません。お金で掴んだ快楽や幸福は一過性です。苦労して、耐え忍んで掴んだ楽しさや幸せはいつまでも心に残るものです。きっと苦労して頑張っている若い人たちもいっぱいいるとは思いますが、目の前の豊かさに溺れず、自分の足で歩いて行く人がより多い国であってほしいものです。
もっとも僕も偉そうなことが言える身分ではありません。学生のころヨット部をやめてしまおうと思った時期がありました。合宿にも参加せず何も手に着かなかったのです。幸い同じクラブの先輩や友人が訪ねて来てくれて、徹夜で議論したり、飲みに行ったりしてヨット部に復帰したことがありました。おかげで迷いが消えて、結局この年になるまでヨットを続けていられます。犠牲にしたものも多かったけど、得たものはもっと多かったような気がします。一人で耐えられたら、それはそれですばらしいことですが、耐えられなくなった時、まわりの友人や関係する人達に思いをぶつけてみることも若いうちなら許されるような気がします。
何かまとまりがつかなくなってしまいました。少しは言いたかったことがわかるでしょうか?それではまた。
最新の画像[もっと見る]
-
 しんさんのよもやま話
5ヶ月前
しんさんのよもやま話
5ヶ月前
-
 しんさんのよもやま話
5ヶ月前
しんさんのよもやま話
5ヶ月前
-
 しんさんのよもやま話
5ヶ月前
しんさんのよもやま話
5ヶ月前
-
 しんさんのよもやま話
6ヶ月前
しんさんのよもやま話
6ヶ月前
-
 しんさんのよもやま話
6ヶ月前
しんさんのよもやま話
6ヶ月前
-
 しんさんのよもやま話
7ヶ月前
しんさんのよもやま話
7ヶ月前
-
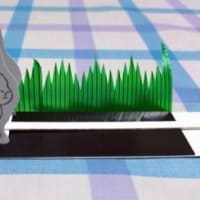 しんさんのよもやま話
7ヶ月前
しんさんのよもやま話
7ヶ月前
-
 しんさんのよもやま話
8ヶ月前
しんさんのよもやま話
8ヶ月前
-
 しんさんのよもやま話
9ヶ月前
しんさんのよもやま話
9ヶ月前
-
 しんさんのよもやま話
9ヶ月前
しんさんのよもやま話
9ヶ月前











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます