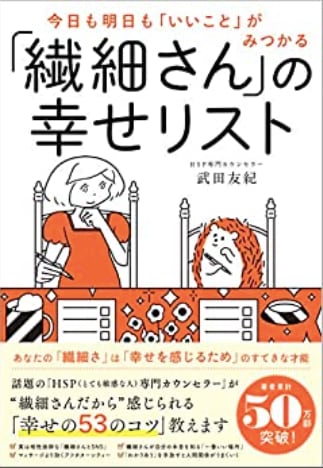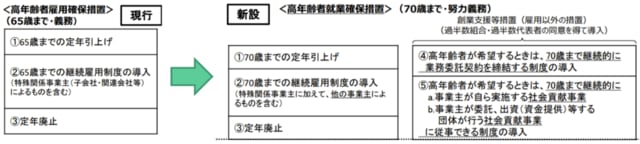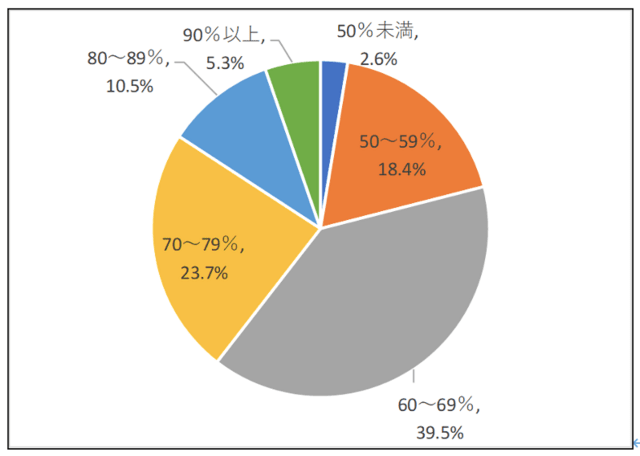皆さん、こんにちは。(有)人事・労務の金野です。
皆さんは「EAP」をご存知でしょうか。
従業員支援プログラム EAP は、もともとはアメリカで生まれた制度ですが、日本の企業でも大企業を中心に取り入れられるようになりました。
アメリカでEAPという概念が生まれた背景も相まって、日本でも主にメンタルヘルス対策として取り入れられるのが一般的ですが、これからは「個が主体的にキャリアを築く」時代。
働く個々がキャリアを歩む上で直面する複雑な課題を解消するスベとして、自ら選択してEAPのサービスを活用していく時代に変化していくのでは、ということで、新たな時代のEAPの導入・活用について、お伝えしたいと思います。
働き方改革を経てこのコロナ禍では、リモートワークや時差出勤など働くかたちが変容しました。
在宅勤務時のオンライン会議に子供や犬猫が加わったり、自宅から職場のオンライン忘年会に参加したり、これまでは”通勤”というアクションを通して区切られてきた「職場と家庭との境目」が必然的に変化し、線引きし直したり融合したりしています。

その変化に自然となじんでいる人もいれば、何らかの負荷を受けている人も多いはずです。
副業解禁や自律分散型組織への注目の高まりなど、「個としての主体的な生き方・働き方」が社会全体で後押しされ、「会社に雇われて働いてお給料をもらう」という受け身な感覚から、「仕事を通してキャリアを重ね成長・変容していく」という能動的な感覚で仕事人生を歩んでゆく流れが、これから先ますます強まって来るのではないかと感じます。
EAP(Employee Assistance Program)においても、単なる福利厚生的な意味合いではなく、キャリアデザインやライフスタイルなども含めた「社員一人ひとりの“はたらき方と生き方”」全般を取り上げ、それらにおいて生じる問題を解消し、専門分野を組み合わせながら解決の道筋を示すプログラムとしての役割へとニーズが変化しているのではないかと思うのです。
例えば、社員個人からの相談に上司や人事部だけが対応するのではなく、介護や育児、キャリアアップなど生き方全般に対して、外部のEAPサービスを活用しながら対話を進め問題解消していく、というものです。
そこにはまず、「本人〜会社〜EAP機関」という三者の信頼関係が必要です。せっかくEAPサービスを利用して相談しても、結果その会社を退職することになった、となれば、会社にとっては大きな損失です。かといって、そのような懸念があるために本人から相談の機会を奪ってしまっては、より悩みが深くなり結局退職する、ということになっては元も子もありません。
会社は、社員を囲い込むのではなくオープンマインドでソトに出していく。社員は、自社のメンバーとしての軸はぶらさずに社会性を高める機会として、うまくソトの機関も使いながら、抱える課題の解消に時間を費やしてみる、ということが大切になってくるのです。
そして、EAPのサービス自体も変化していく必要があります。
・業務の優先順位の付け方や意思決定の仕方など、”良い仕事”をするためのスキルや心がまえの学び
・「育児休業を経て職場復帰する際の心がまえ」であったり「介護に直面した時に家庭内でどのような話し合いを持てば良いのか」など、”暮らす”と”働く”に関わる相談
・病気を抱える家族との暮らしかたアドバイス
等々。
個人の人生観(ライフスタイル)や仕事観(ワークスタイル)まで、社内においては上司やメンター役、人事担当者、社外においてはEAP機関や属するコミュニティのメンバーなど、接点あるところから必要な情報を得て、自らのキャリアを考えていく時代になってきているのです。
この観点からとらえると、私たちもこれまで2万人近い方々にEAPサービスを行なってきました。
そこには、自社に属しながらも二拠点の働き方や本業以外の地域活動をしていきたい人、独立・起業を考えている人、親の介護や育児、障がいを持った子どものこと等なかなか職場の中では話せないが心理的負荷になりつつある案件を抱えている人、など、さまざまな「課題」が存在していました。
「個人的なことはあまり人前で言わない方が良い」「職場と家庭は別」といったこれまでの日本社会に流れる常識から、会社の中では悩みを吐露できぬままに、根深い課題となり、何らかの制約となってやむを得ずキャリアを諦めたり悲観的になってしまっている人も、相当数いるはずです。
このような状態に関して、「ワークライフバランスの推進を」と一言でくくるのでなく、「今の社員の多くは“仕事も暮らしもまぜこぜの中で人それぞれの事情を抱えている”」という前提を理解した上で、仕事=働く内容や働きぶりのみを判断材料に組織変革を推し進めるのではなく、EAPの視点から個々の暮らし方・生き方に関しても問いかけを重ねながら、組織として対応できる解決の道筋を示していくことが重要ではないかと思います。

ある対談番組の中で、哲学者の國分巧一朗さんは、医師の熊谷晋一郎さんの言葉を引用し、
「自律する、というのは、依存先が少なくなることではなくて、依存先が増えてどこに依存しているかすらもあいまいな状態がふわっと現れてきている段階を指す」
と述べ、それを受けて評論家の荻上チキさんは、心理学における「コーピング」という考えを紹介する場面がありました。
ストレスを受けた時に気晴らしをして気分を良くすることをコーピングと言いますが、そのコーピングは「質より量」。つまり、小さなこと(窓を開けて新鮮な空気を吸う、コーヒーを淹れるなど)でも良いからたくさんのコーピングのレパートリーを持っておくことで、ストレスの溜め込みを防ぐことができる、と。
特定のものの道が失われても別の選択肢がある、と切り替えることができる、という点は、「マルチアイデンティティ」の考えにも置き換えることができます。
人にはさまざまな切り口があり、例えば家庭では「母親」、職場では「上司」、地域活動では「一メンバー」、趣味で「陶芸の職人」等々、複数の役割をもち、そこでの顔を持っているわけです。そのようなマルチアイデンティティな自分を認識できると、國分さんや荻上さんが話すように複数の依存先を得ることができ、例えば、「しばらくは職場と家庭中心の時間の過ごし方になるけれどもたまに趣味の時間でリフレッシュしてエネルギーを高める」「一時期だけ異なる働き方を選んで無理なく働きながら生活していく」といった選択肢をもつことができます。
外部EAPサービスの利用は、そのような「しなやかに暮らし働いていく上での依存先の一つ」になり得るのではないかと思います。
企業規模の大小や年代にかかわらず、今や働く誰もが多様な課題に直面する時代。
持続的なキャリアを実現するためにも、課題にも柔軟に対応できるしなやかさをもった組織を実現するためにも、EAPを活用してみてはいかがでしょうか。