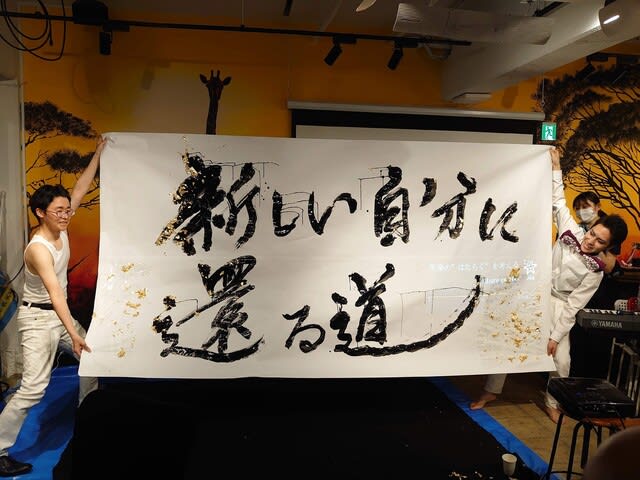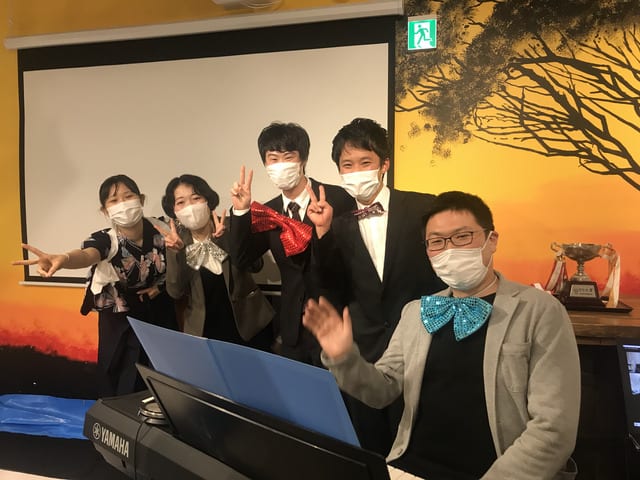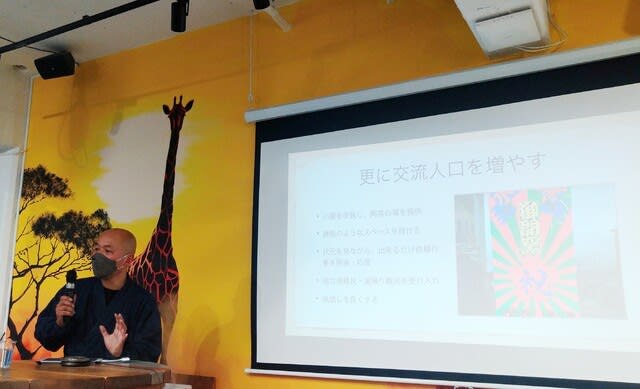皆さん、こんにちは!有限会社人事・労務の志村です。
先日4月16日(土)17日(日)、ワーカーズさんのご縁で、903シティファーム推進協議会が「Earth Day Tokyo 2022」に出店致しました!
せっかくの素敵な機会!
コミュニティを実践する仲間である、ウェルファイアカデミー卒業生にお声掛けして、
「あやせのえんがわ」の森川さん
「Share Re Green」の瀬戸山さん
と共に『ウェルファイな森』として共同出展。

私たち903シティファーム推進協議会のコンセプトは、「農と食を通して、90分圏内にもう一つの居場所を持ち、3割程度のお金に依存しない自律した生き方を体現する」です。
お金中心の社会から、つながりがめぐる社会の実践。
田心カフェでは、土づくりからこだわり、自然農法や固定種栽培をされているお野菜を販売しました。
農家さんの思いや、私たち903の思いや活動に共感して、お野菜を手に取ってくださる方が大変多かったと感じています。

自然農法に興味を持つ方が私たちに声を掛けてくださり、農業を通して多様な生物が暮らしやすい持続的な社会を醸成していく取り組みを色々と教えてくださったり、若い方々も予想以上に関心を持つ方がたくさんおり、様々な交流が生まれました。
今後は、自然農法や自然栽培の野菜を仕入れるだけではなく、実際に学びながら田心ファームで実践していこうと考えています!

循環畑の吉原さんとのご縁から自然農法の中でも「菌ちゃん農法」という農法があると知りました。
菌ちゃん農法とは、
森の生態系のように、落ち葉や木の枝や、枯れた草木などが土に戻り、微生物の力を活用して植物が育つ。そんな自然の循環に沿って育てる方法です。
畑では発酵させた生ごみまたは雑草と発酵を促す微生物たちを一緒に投入し、畝に雑草マルチをかけて、外部から雑菌が入りにくい状態にします。
すると、土壌全体が発酵の方向に働くようになり、土着の菌たちが一緒になって生ごみを発酵分解し、様々な有用な成分を作りだしていきます。そうなると、土はますます完全な発酵状態に近づき、野菜は化学肥料なしに、青々と育ち、病気も虫の害も少なくなり、元気で美味しく育ちます。
管理された畑とは違い雑草も野菜も皆が共生する。

雑草か野菜かを分けているのは人間のモノサシで決めていることで、本来は共生しお互いの良さを引き出し、ダメなところを補いながら暮らしています。
現代のような個で力を持ち、効率性即金性を重視した分断を生む関係性ではなく、お互い複雑に関わり合いながら、おかげさまの関係性を土と腸の関係から学びます。

これは私たちが目指しているコミュニティの在り方そのもので、一人では出来ないことを実現していくために、自分の弱みをみせ、そこを補ってもらったり、逆に相手の苦手な部分を、自分の得意でフォローする。
そんなお互い共生し合う生命体のような組織をつくる実践をしています。
仲間との活動を通して、人と繋がりを持つことの温かさや、自分の能力や人間性の成長を実感し、本来のはたらく豊かさを感じることができる。
私たちは「菌ちゃん農法」を通して、一人一人が主体的に行動し、自律した働き方を体現するようなコミュニティに成長して行ければと考えています。
▼ぜひ少しでもご興味があればホームページを覗いてみてください。
https://hatarakuba.com/903cityfarm/
※参考文献:
吉原史郎さんの循環畑の考え方
『ソース・プリンシプル理解の大前提【その4】!ティール組織実践で重要な概念を理解しよう』
https://nol-blog.com/sourceprinciples_4/
NPO法人大地といのちの会・菌ちゃんふぁーむ 吉田俊道さんの資料
https://www.town.matsukawa.lg.jp/material/files/group/6/danryuukouzou.pdf
NPO法人大地といのちの会・菌ちゃんふぁーむ 吉田俊道さんのYouTube動画
https://www.youtube.com/channel/UCB4l2ruSdpcNVRA8BvmP9uw
『腸と森の「土」を育てる~微生物が健康にする人と環境~』 桐村里紗、光文社新書
『完全版 生ごみ先生が教える「元気野菜づくり」超入門』吉田俊道、東洋経済新報社