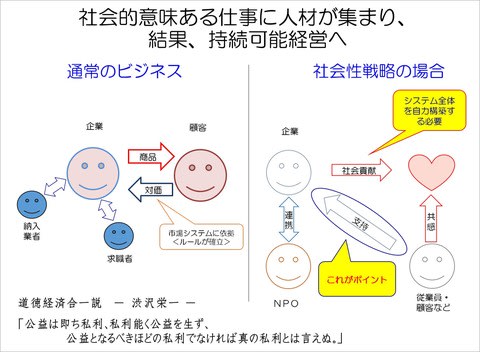こんにちは。
人事・労務の井上です。
コミュニティと一つの言葉でも、職場も一つのコミュニティ、私自身は母として会う所謂ママ友のコミュニティ、家族のつながりのコミュニティと様々なコミュニティに属しております。
コミュニティの役割とは他者との関係性の中での他者を通して自己を知る場でもあるように思います。
先日、高校時代の友人である家富万里さんが主催する「元ギャルがつくるやさしいコミュニティ作りのすすめ方」に参加させていただきました。
友人は、卒業後も友人の結婚式など定期的に顔を合わせる間柄ではありましたが、突然岩手へ移住し、何をしているのか詳しくは知りませんでした。
岩手では豚を飼って、その豚を食べたりしてると聞き、かなりインパクトがありつつも自然の中で何かを感じつつ過ごしているんだなという緩やかなイメージを持っていました。

彼女は、東日本大震災を経て、東京の脆さを感じ本能的な危機感を感じたそう。
様々な場所へ旅へ行き、色々な人に出会い、今のNext Commons Lab(以下NCL)の代表と出会い、立ち上げから携わっていたそう。
NCLのコーディネーターとして彼女は何をしているのかというと、岩手の伝統芸能を学んだり、地域に入り込みながらコミュニティ作りを行なっています。
彼女自身、中学時代のいじめや家庭での不和から学校や家庭以外の居場所を探し求めていた経験から、居場所づくりを行うコーディネーターへの道へと進んでいます。
若い頃のやり場の無い怒りをギャルとしての表現でエネルギーを解放していたよう。
そもそも同じ高校にいながら、昔の彼女の写真を見ると中々本格的なギャルだったなあという懐かしい思いと共に、その裏側にある彼女の葛藤や思いについては全く知らなかったと思いました。
学校という場での繋がりはありつつも深い話をする仲間はまた違う繋がり方をしていたなとも認識しました。

どこにも居場所がないと感じていたギャル時代は、渋谷のセンター街と出会うことで多様のスタイルの人々がいることも知り、自分がありのまままでいていいという場所があることを知りました。
それからは、センター街が安心の場であり、通っては仲間と集う日々だったよう。
センター街というコミュニティでの自己を解放できたことで徐々に彼女の精神面でも変化があり、安心できる居場所があることで自分と向き合い整えていくことができたそうです。
大学は美大の建築科へ進学し、コミュニティのあり方を考える空間デザインについて学び、震災を経て、生きる力を学ぶ為に岩手の遠野へ移住。
農山村を支援する活動に参加したことで野菜の成長を見ながら食の成り立ちを知り、自分がどう生かされているのか知る経験になったそう。
そんな彼女は今東北にセンター街を作る活動をしている。多様な大人と子供が行き交う場所つくりを通して、新しい価値観や目指すべきロールモデルに出会うきっかけ作りを行いたいと。
彼女の今までの生きてきた過程での痛みや葛藤や想いが重なり今の彼女エネルギーの源になってるんだなと感じました。

自己の属するコミュニティの中で自分の主観を伝えられる環境であるということは安心感のある場であると思います。
それが家庭であっても、また別の場所にあっても良い、どこかの自己の属するコミュニティにおいて肯定感を持ちつつ、生きることができる場というのは大切だと改めて感じました。
更に大人になり過ごす時間が多く仕事を通した場においても、主観を伝え合える安心の職場作りということはどのように出来てくるのかも日々考えることが多いです。
弊社では定期的に行うイロドリ会議でその期間での個人の主観を述べる場があります。特に大きく共感し合うことが目的でもなく、主観を聞く、個人を知る機会です。大人になり社会に出て自己の意見を素直に伝えていい、というのは、今までの社会人経験の中であまり無かったなと感じます。知らぬ間に、仕事はこういうもので、決まった型にある程度収まらなくてはいけないという固定観念に縛られていたようにも思います。
そのような他者の意見を聞いて、相手を知り、また主観を述べる、大きな否定も肯定もなくとも、双方向で素直に意見を話せるというのは肯定感や安心感に繋がります。そうした、安心感ができることが業務においての関係性にも緩やかに変化をもたらしてくれるようにも思います。
コミュニティを通した対話の大切さを感じつつ、今いるコミュニティや生かされている場に感謝をしながら日々過ごさなければいけないなと感じました。
人事・労務の井上です。
コミュニティと一つの言葉でも、職場も一つのコミュニティ、私自身は母として会う所謂ママ友のコミュニティ、家族のつながりのコミュニティと様々なコミュニティに属しております。
コミュニティの役割とは他者との関係性の中での他者を通して自己を知る場でもあるように思います。
先日、高校時代の友人である家富万里さんが主催する「元ギャルがつくるやさしいコミュニティ作りのすすめ方」に参加させていただきました。
友人は、卒業後も友人の結婚式など定期的に顔を合わせる間柄ではありましたが、突然岩手へ移住し、何をしているのか詳しくは知りませんでした。
岩手では豚を飼って、その豚を食べたりしてると聞き、かなりインパクトがありつつも自然の中で何かを感じつつ過ごしているんだなという緩やかなイメージを持っていました。

彼女は、東日本大震災を経て、東京の脆さを感じ本能的な危機感を感じたそう。
様々な場所へ旅へ行き、色々な人に出会い、今のNext Commons Lab(以下NCL)の代表と出会い、立ち上げから携わっていたそう。
NCLのコーディネーターとして彼女は何をしているのかというと、岩手の伝統芸能を学んだり、地域に入り込みながらコミュニティ作りを行なっています。
彼女自身、中学時代のいじめや家庭での不和から学校や家庭以外の居場所を探し求めていた経験から、居場所づくりを行うコーディネーターへの道へと進んでいます。
若い頃のやり場の無い怒りをギャルとしての表現でエネルギーを解放していたよう。
そもそも同じ高校にいながら、昔の彼女の写真を見ると中々本格的なギャルだったなあという懐かしい思いと共に、その裏側にある彼女の葛藤や思いについては全く知らなかったと思いました。
学校という場での繋がりはありつつも深い話をする仲間はまた違う繋がり方をしていたなとも認識しました。

どこにも居場所がないと感じていたギャル時代は、渋谷のセンター街と出会うことで多様のスタイルの人々がいることも知り、自分がありのまままでいていいという場所があることを知りました。
それからは、センター街が安心の場であり、通っては仲間と集う日々だったよう。
センター街というコミュニティでの自己を解放できたことで徐々に彼女の精神面でも変化があり、安心できる居場所があることで自分と向き合い整えていくことができたそうです。
大学は美大の建築科へ進学し、コミュニティのあり方を考える空間デザインについて学び、震災を経て、生きる力を学ぶ為に岩手の遠野へ移住。
農山村を支援する活動に参加したことで野菜の成長を見ながら食の成り立ちを知り、自分がどう生かされているのか知る経験になったそう。
そんな彼女は今東北にセンター街を作る活動をしている。多様な大人と子供が行き交う場所つくりを通して、新しい価値観や目指すべきロールモデルに出会うきっかけ作りを行いたいと。
彼女の今までの生きてきた過程での痛みや葛藤や想いが重なり今の彼女エネルギーの源になってるんだなと感じました。

自己の属するコミュニティの中で自分の主観を伝えられる環境であるということは安心感のある場であると思います。
それが家庭であっても、また別の場所にあっても良い、どこかの自己の属するコミュニティにおいて肯定感を持ちつつ、生きることができる場というのは大切だと改めて感じました。
更に大人になり過ごす時間が多く仕事を通した場においても、主観を伝え合える安心の職場作りということはどのように出来てくるのかも日々考えることが多いです。
弊社では定期的に行うイロドリ会議でその期間での個人の主観を述べる場があります。特に大きく共感し合うことが目的でもなく、主観を聞く、個人を知る機会です。大人になり社会に出て自己の意見を素直に伝えていい、というのは、今までの社会人経験の中であまり無かったなと感じます。知らぬ間に、仕事はこういうもので、決まった型にある程度収まらなくてはいけないという固定観念に縛られていたようにも思います。
そのような他者の意見を聞いて、相手を知り、また主観を述べる、大きな否定も肯定もなくとも、双方向で素直に意見を話せるというのは肯定感や安心感に繋がります。そうした、安心感ができることが業務においての関係性にも緩やかに変化をもたらしてくれるようにも思います。
コミュニティを通した対話の大切さを感じつつ、今いるコミュニティや生かされている場に感謝をしながら日々過ごさなければいけないなと感じました。