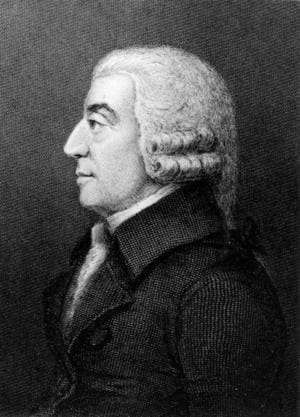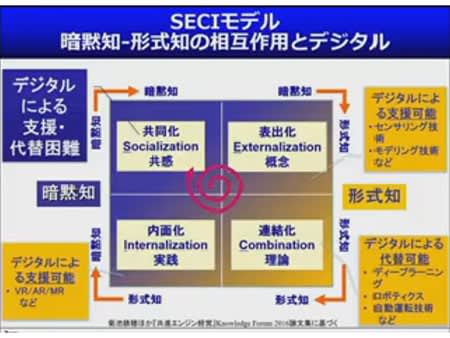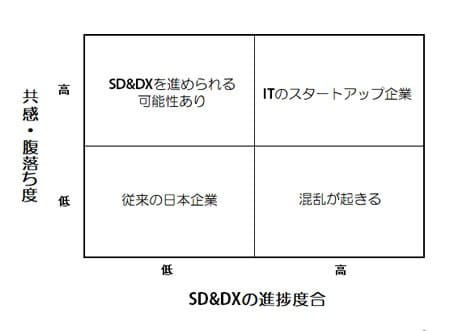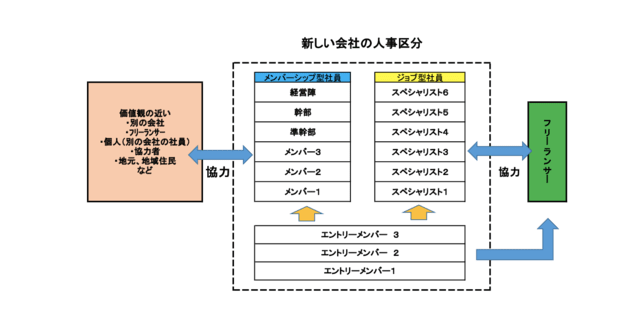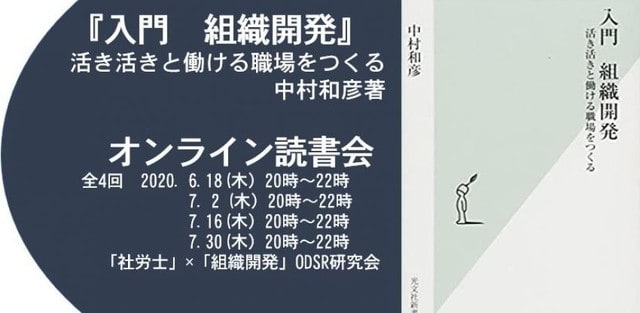こちら会社で採用をいただいてから、現在まで様々なことを学ばせていただきました。
入社させて頂いてから、約1ヶ月経過しました。過ごす時間はとても濃いもので、感覚的には3倍もの時間に感じます。
そんな濃い生活の中で、私が衝撃を受けた社内風土がいくつもございました。本日はその中で私が一番衝撃を受けた社内風土を「三つ」お話ししたいと思います。

一つ目は「迷惑はかけるもの」という価値観です。
私は幼い頃から、人様に迷惑をかけないで生きるよう教わりました。が、
社内では「迷惑をかけるもの」だとご指導いただきました。
例えば、
お電話をいただき、それに対応をしている際、メンバーがおしゃべりをしておりました。
私の価値観ではおしゃべりをしていた方が静かにします。
ですが、そのおしゃべりをしている方が静かにするのではなく、電話をしている方がオフィスから出ていくのです。
これを見たときの衝撃は尋常なものではありませんでした。
なぜ出ていくのか?
私の解答としましては、
心理的な距離を縮め、仲間の絆を強めるためだと思いました。
よく考えてみれば、家族にはたくさんの迷惑をかけます。他人には絶対にしないであろう言葉遣いや行為、頼みごとをしてしまいます。
これは心理的な距離が近いからで、この状態を家族以外で作るのは迷惑をかけ続けることが効率がいいと思いました。
ダメな部分や自分の秘密を相手に知られると、その人のことを信用してしまうという性質と似ていて、自分のプライベートや最近興味のあることを話すことで自然に絆が深まります。
もう一つ大きな効果があると思っておりまして、
対話の回数が多いほどアイデアや改善点が思いつきやすく見える化します。
これは私自身が実感したことで、たわいもない雑談から着想を受け、業務の効率化ができたり、お客様により良いサービスを提供できることに繋がったことがありました。
入社する前までありえない常識でしたが、今では当たり前になりつつあります。こちらの方が生きやすく、ストレスが少ないと感じる日々でございます。

二つ目は「組織とは一つの生命体である」という価値観です。
生命体???人が集まったものが生命体???スイミーのような理解なのか?
最初は言っている意味がわかりませんした。
ですが、腑に落ちる体験がございました。
私はIT部門で採用をいただき、RPAの開発やFacebookライブの設営&運営などを業務として行なっております。
その中で、IT部門以外の方に私たちの業務を手伝っていただいたことがありました。
その時、再度このお話を頂戴し「なるほど!そういうことだったのか!」と体感致しました。
”生命体にはそれぞれの役割を行う臓器がある。肺は酸素を取り入れ、心臓はその酸素を身体中の臓器にエネルギーと一緒に届ける。
ここで、心臓が肺の動きをしては生命体は死んでしまう。臓器にはそれぞれ役割があり、その役割をこなすことが最優先事項だ。”と
ですが、ここで混乱するのが「迷惑をかけるのは良い」です。
一つ目で申し上げましたが、迷惑はかけるものなのです。
どういうことなのか?
これのキーワードは「対話」でした。

生命体が危機に瀕した時、オートファジーというのが起こると聞いたことがあります。
臓器同士が話し合い、「今はここにエネルギーを送るのが一番良いよ!」という対話を行い、そこにエネルギーを集中的に投下するのです。
これに似ていると私は思いました。組織内でもどうしても自分だけで解決できないことはメンバーの方々に頼ることの方が効率が良いのです。
「生命体」と「対話」という考え方は本当に衝撃的でした。
三つ目は「無理ではなく、どうすればできるのかを考えよ」という価値観です。
これは知識としては理解していましたが、実際にその価値観で行動すると衝撃を受けました。
困難な業務でもメンタルが安定し、一定のスピードで一定の成果が挙げられるのです!
マインドや自分が発する言葉で、業務効率や達成速度が大きく変わりました。
本当に度肝を抜かれました。
冒頭でもお話致しましたが、私はIT部門でRPAツールを使い、ロボットを作るという業務を任せていただいております。
1ヶ月前までRPAという存在すら知らず、それを開発するとなったころ、不安しかありませんでした。
教材や教えてくださる方もおらず、独学する必要があり、開始3日目には納品物を任せていただきました。
業務の負担が重くなっていくにつれて、精神的に疲弊していきました。
その中で、プロジェクトリーダーから、この言葉をいただきました。
言われた直後は、あまりその価値観について考えることはありませんでした。
ですが、家に帰った時、「明日、業務完了させるの難しいかも、でもやらないとな」と心に負担を感じました。
そんな時、この言葉が頭に浮かび、スッと心が軽くなりました。

「無理」と考えると、こなせないと思っているのにやらなければならない。
心と行動がチグハグになってしまいます。そうなると、心の負担になってしまいます。
人は断わるだけでも心理的に相当なストレスを感じてしまうと聞いたことがあります。
この考え方はそんなストレスをなくしてくれます。
さらに、「無理」というより「どうすればできるのか?」という建設的な問いで話を進めた方が、結果もより良いものにできますし、何より気持ちがいいです。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
まだまだ不甲斐ない面や学ぶことが多い私ですが、これからも組織全体と自分自身の成長に邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。