本日、ピー・シー・エー株式会社様主催の給与計算、社会保険手続き実務セミナーに私 梅津が登壇させて頂きました。
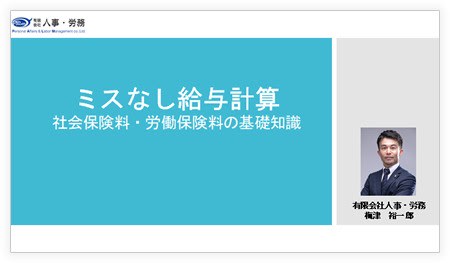
英オックスフォード大学でAI(人工知能)などの研究を行うマイケル・A・オズボーン准教授が発表した「あと10年でなくなる仕事(2014年)」に見事(?)ノミネートされてしまった「給与計算・福利厚生関係の仕事」。AIやRPAの台頭と電子政府への取組みを考えるとタイミングはさておき、省力化、自動化の流れはまず間違いないと私も見ています。
でもみなさん、
みなさんは給与明細に列挙されている様々な数字が持っている意味をひとつひとつ正確に理解されていますか?
「色々書いてあるけど、一番下の欄に表記されている自分の口座に振り込まれる金額を確認して終わり」という方が大多数ではないでしょうか?
私は給与明細に記載されている情報は「人事情報の宝庫」だと思っています。
そしてこれらの情報群を理解し、その仕組みを改善することで組織のポテンシャルは飛躍的に高まるのです。

給与明細が持つ情報は大きく分けて2つ。
ひとつは「社会保障制度等を享受する資格の情報」。
仕事中のケガや、プライベートでの病気、ご家族がいらっしゃる方はご家族の医療負担、失業保険、年金等々様々な保障を受けるための財源が保険料や税金としてみなさんのお給料から引かれています。
そして2つ目、実はこれがとても大切です。それは「仕事量と成果に対するあなたへの評価に関わる情報」。これが給与の構造を理解することで一目瞭然となります。
当たり前の話ですが、会社は何もしなければ潰れてしまいます。また、「今まで通りのやり方を続けていけばとりあえず現状維持できる」という考え方も、ニーズの多様化、グローバル化、ITの加速度的な進化をふまえるとかなり怪しいと私は見ています。
社員のみなさんの雇用を維持し、生活の基盤である給与をしっかりと支給する。これは会社の維持、あるいは成長にダイレクトに繋がります。

そこで逆転の発想。
これからは会社が利益(成果)を生み出すビジネスモデルを構築するのではなく、利益(成果)を生み出す社員が自然と生まれる組織を作る。
「利益=給与原資」という意識を高めれば自ずとこの答えにたどり着きます。
その為にはまず給与計算のロジックを法律の理解から初め、その範疇で許容されるあらゆる手法を独自に発想していく必要があります。
本日のセミナーはその第一歩として、給与事務のご担当者を中心に、労働基準法の基礎知識と具体的な手続きのポイントについて演習を交えての内容でしたが、近い将来、参加された皆様には是非そのような発想を持って頂き、「給与計算で会社を変える!」人財へと成長して頂きたいと思います。
これからの給与担当者のミッションは情報処理(計算業務)ではなく、組織を活性化させるしくみをデザインすることなのです。
給与計算担当者の未来は明るい!!
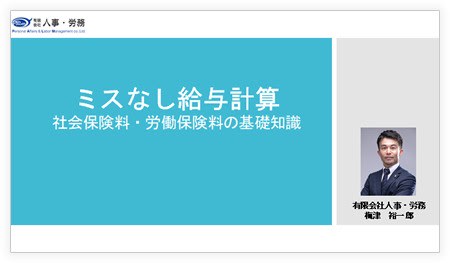
英オックスフォード大学でAI(人工知能)などの研究を行うマイケル・A・オズボーン准教授が発表した「あと10年でなくなる仕事(2014年)」に見事(?)ノミネートされてしまった「給与計算・福利厚生関係の仕事」。AIやRPAの台頭と電子政府への取組みを考えるとタイミングはさておき、省力化、自動化の流れはまず間違いないと私も見ています。
でもみなさん、
みなさんは給与明細に列挙されている様々な数字が持っている意味をひとつひとつ正確に理解されていますか?
「色々書いてあるけど、一番下の欄に表記されている自分の口座に振り込まれる金額を確認して終わり」という方が大多数ではないでしょうか?
私は給与明細に記載されている情報は「人事情報の宝庫」だと思っています。
そしてこれらの情報群を理解し、その仕組みを改善することで組織のポテンシャルは飛躍的に高まるのです。

給与明細が持つ情報は大きく分けて2つ。
ひとつは「社会保障制度等を享受する資格の情報」。
仕事中のケガや、プライベートでの病気、ご家族がいらっしゃる方はご家族の医療負担、失業保険、年金等々様々な保障を受けるための財源が保険料や税金としてみなさんのお給料から引かれています。
そして2つ目、実はこれがとても大切です。それは「仕事量と成果に対するあなたへの評価に関わる情報」。これが給与の構造を理解することで一目瞭然となります。
当たり前の話ですが、会社は何もしなければ潰れてしまいます。また、「今まで通りのやり方を続けていけばとりあえず現状維持できる」という考え方も、ニーズの多様化、グローバル化、ITの加速度的な進化をふまえるとかなり怪しいと私は見ています。
社員のみなさんの雇用を維持し、生活の基盤である給与をしっかりと支給する。これは会社の維持、あるいは成長にダイレクトに繋がります。

そこで逆転の発想。
これからは会社が利益(成果)を生み出すビジネスモデルを構築するのではなく、利益(成果)を生み出す社員が自然と生まれる組織を作る。
「利益=給与原資」という意識を高めれば自ずとこの答えにたどり着きます。
その為にはまず給与計算のロジックを法律の理解から初め、その範疇で許容されるあらゆる手法を独自に発想していく必要があります。
本日のセミナーはその第一歩として、給与事務のご担当者を中心に、労働基準法の基礎知識と具体的な手続きのポイントについて演習を交えての内容でしたが、近い将来、参加された皆様には是非そのような発想を持って頂き、「給与計算で会社を変える!」人財へと成長して頂きたいと思います。
これからの給与担当者のミッションは情報処理(計算業務)ではなく、組織を活性化させるしくみをデザインすることなのです。
給与計算担当者の未来は明るい!!













