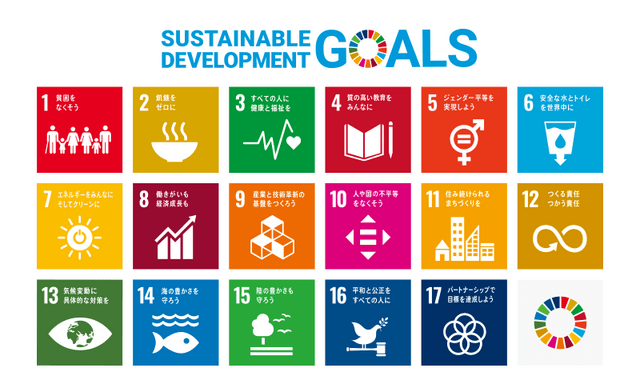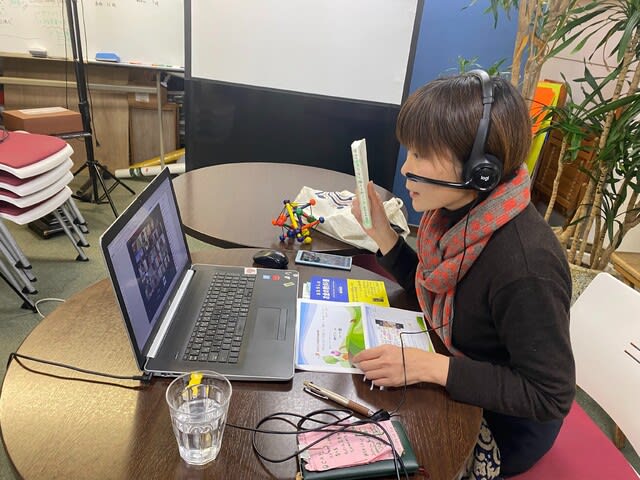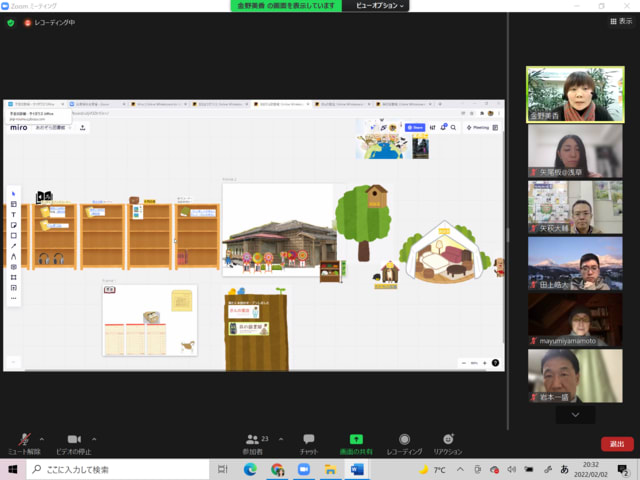今回は新井和宏さんの著書「幸せな人は『お金』と『働く』を知っている」の内容の第2回目の読書会になります。

第3章・第4章の内容について、有限会社人事・労務チーフコンサルタントの畑中義雄さんにご紹介頂きました。生きていく上での本当の「幸せ」とはどのようなものなのか。どんな幸せを感じることが、本当の意味での“幸福”になるのでしょうか考えていきたいと思います。

今回の著者新井和宏さんは株式会社eumo(ユーモ)の代表取締役として会社を経営されています。社名の“ユーモ”は「Eudaimonia(ユーダイモニア)」という言葉の略称となっており、「持続的幸福」という意味があります。
幸せは「Hedonia(ヘドニア)」と「Eudaimonia(ユーダイモニア)」の大きく分けて2つあります。
「Hedonia(ヘドニア)」は感覚的快楽のことで、“美味しいものを食べる”“欲しいものを手に入れる”のような一時的な楽しい時を過ごして感じる幸せのことです。このような幸せは、慣れにより感じなくなり、さらなる大きな幸せを求めるようになることが科学的に証明されているため、結果的に継続した幸せを感じる事が難しくなります。
これに対し、「Eudaimonia(ユーダイモニア)」は自己実現や更なる、自己超越などの生きがいを感じることで得られる幸せの事で、自分の強みを活かした行動や「身近な人を喜ばせたい」「幸せにしたい」という思いが原動力になって行った行動によって得られるものです。
「持続的幸福」とは、自己実現や生きがいを感じることで得られる幸せであり、この会社に関わる人々に、持続的幸福に気づく機会を提供して行きたいとの願いが込められています。

新井さんは幸せについて、利己と利他の一致(自己満足が人の役に立ってしまうこと)、つまり、主体が自分自身にあるという事が重要で、それにより人は見返りを求めなくなり、強くなれると考えています。つまり、「自分がやりたい事」が「相手がされて嬉しい事」であり、その時の“自分”は“満たされている”=見返りを求めない状態になります。これこそ、本当の意味でのWIN:WIN(お互いがお互いを幸せにしている関係)だと思います。
ここで、アダム・グラントの著書「GIVE&TAKE 与える人こそ成功する時代」の内容に出てくる3人の登場人物「ギバー(与える人)」「テイカー(受け取る人)」「マッチャー(バランスを取る人)」が浮かんできました。本のタイトル通り、人は大きく3パターンに分けられ一見、与えられている「テイカー」が得や幸せになりそうなのですが、本のタイトル通りギバーが幸せを感じたり、巡り巡って見えないかたちで得や成功するというような内容になっています。
ここで鍵となるのが「マッチャー(バランスを取る人)」で、この人物は“与えていた方が(ギバー)後から得をする”ということを考えて、与えるという「見返りを見越してのGIVE」をするタイプです。私は行動をしていると「自分はギバーになりたいマッチャーなのではないか」と、ふと自分の行動に自信が持てない時があります。
しかし畑中さんは、人間は「良い部分(心・勇気・能力・努力)」と「邪悪で弱い部分」があり、「良い部分を発揮できる場所」「良い部分を発揮させてくれる場所」に身を置くことがポイントとなってくると話していました。そして、この「自分の良い部分が出せる環境」で仕事をすることで幸せに結びついていくため「働く」と「幸せ」は密接に関係しているということでした。

この話を聞いて、「誰しも悪の部分はある」こと、そしてそこを覆い隠すのではなく“自分が輝ける場所”で生きていけばいいのだと思えました。
今回は著書「幸せな人は『お金』と『働く』を知っている」の4章までを読み深めてきました。次回は5章「あなたらしい幸せの見つけ方」6章「社会を形作るもの全てに感謝を」の内容になります。一人一人違う幸せの形を知り、どのように生きていくと良いのかについて考えていきます。次回もとても楽しみですね。