水門を閉めたら腐敗臭漂う海になった、というリポートは鮮明に覚えているなぁ。
●国に排水門開放命じる=諫早湾干拓訴訟
国は『漁獲量減少は事業以前からの傾向で「閉め切りの影響による被害の発生は認められない」と反論していた』訳ですが、それがどの程度の統計的資料を基したものかは、報道では解りません。
しかし原告側は別の記事で大幅減になったと主張しています。
諫早干拓訴訟…漁業者ら「開門が待ち遠しい」と期待の声
『タイラギの漁獲量は年々減少。1997年の潮受け堤防閉め切りで、タイラギのほか、取っていたアサリも死がいが目立つようになった。』
これだけだと国の主張にそう感じですが、タイラギもアサリも、貝類は壊滅状況になりました。
『アサリ養殖場がある。堤防閉め切り後、毎年春にまく稚貝約5トンの半数は夏ごろ死んでしまうようになった』
『2002年、国が1か月間排水門を開けた短期開門調査の後は貝の生育が順調で、03年春に稚貝をまこうとしたところ、約10トンの稚貝がすでに生まれていたという。翌04年のアサリは夏に全滅』
排水門を開けたら稚貝が生育し、閉めたら全滅。
『クルマエビやタイ、ヒラメの水揚げは堤防閉め切り後、それ以前の3分の1から4分の1以下に激減。見たことのない赤潮を島原市近郊の海で見るようになった』
漁獲高の大幅減少と水質悪化は明らかだと言えるでしょう。
ただしwikipediaによると、水質汚濁は水門閉鎖による物だけでなく、『海苔業者が消毒目的に散布した酸、および化学肥料による影響があったとも考えられている』。
一方沿岸の農業では用水問題などで干拓事業が必要とされている。
しかし減反が進められている現在、沿岸の水田は免罪符というか、切り札として祭り上げられているような気もする。自給分の米作を補償するのはともかく、商品作物としての米は大幅な生産調整を行っているのであり、政策に矛盾を感じる。
しかし矛盾はあったとしても農業の視点で見ると水の確保などで利点はあるので、農民対漁民で対立しています。
なおこの干拓事業はJST失敗知識データベースにも収録されています。
●国に排水門開放命じる=諫早湾干拓訴訟
国は『漁獲量減少は事業以前からの傾向で「閉め切りの影響による被害の発生は認められない」と反論していた』訳ですが、それがどの程度の統計的資料を基したものかは、報道では解りません。
しかし原告側は別の記事で大幅減になったと主張しています。
諫早干拓訴訟…漁業者ら「開門が待ち遠しい」と期待の声
『タイラギの漁獲量は年々減少。1997年の潮受け堤防閉め切りで、タイラギのほか、取っていたアサリも死がいが目立つようになった。』
これだけだと国の主張にそう感じですが、タイラギもアサリも、貝類は壊滅状況になりました。
『アサリ養殖場がある。堤防閉め切り後、毎年春にまく稚貝約5トンの半数は夏ごろ死んでしまうようになった』
『2002年、国が1か月間排水門を開けた短期開門調査の後は貝の生育が順調で、03年春に稚貝をまこうとしたところ、約10トンの稚貝がすでに生まれていたという。翌04年のアサリは夏に全滅』
排水門を開けたら稚貝が生育し、閉めたら全滅。
『クルマエビやタイ、ヒラメの水揚げは堤防閉め切り後、それ以前の3分の1から4分の1以下に激減。見たことのない赤潮を島原市近郊の海で見るようになった』
漁獲高の大幅減少と水質悪化は明らかだと言えるでしょう。
ただしwikipediaによると、水質汚濁は水門閉鎖による物だけでなく、『海苔業者が消毒目的に散布した酸、および化学肥料による影響があったとも考えられている』。
一方沿岸の農業では用水問題などで干拓事業が必要とされている。
しかし減反が進められている現在、沿岸の水田は免罪符というか、切り札として祭り上げられているような気もする。自給分の米作を補償するのはともかく、商品作物としての米は大幅な生産調整を行っているのであり、政策に矛盾を感じる。
しかし矛盾はあったとしても農業の視点で見ると水の確保などで利点はあるので、農民対漁民で対立しています。
なおこの干拓事業はJST失敗知識データベースにも収録されています。














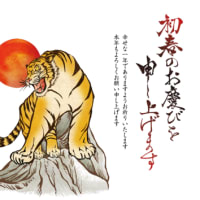





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます