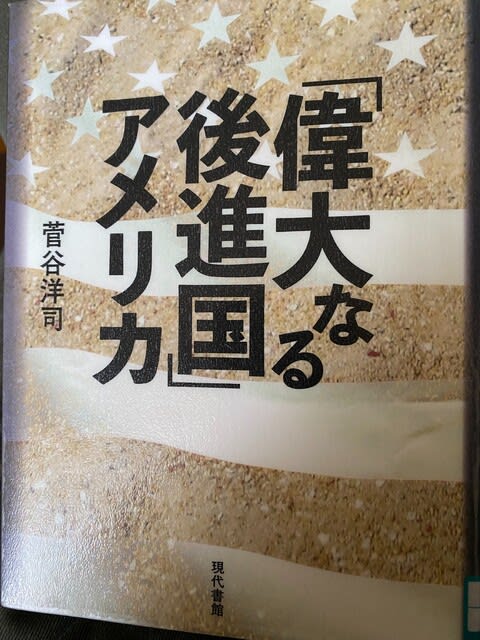最近目を留めた経済関係の新聞記事あるいはNHK番組から
◯東電が来週にも家庭向け3割前後の値上げ申請(6月以降)
電気料金は21年の9月以降値上げが続いている。原因は、①石炭、液化天然ガスなどの輸入価格の高騰、②新型コロナウィルスの感染拡大、③ウクライナ情勢、④円安、⑤新電力の値上げとされる。我家では昨年2月新電力に切り替えたばかりで、使用量はほとんど変わっていないが、大幅な値上げとなった。その傾向は今後も継続する見込みとのこと。また、ガス(田舎ではLPガス)も高くなっている。
◯12月の消費者物価指数は前年同月より4.0%上昇
第二次オイルショック(1981年12月)以来41年ぶりの水準。2月は値上げラッシュが予想されている。滅多にスーパーに行かないおじさんなので実感はわかないが、家内に聞いたところ天ぷら油の値上げをまずあげた。
◯3年ぶりの年金引き上げ1.9%を行う
物価2.5%、名目賃金2.8%の上昇を見込んでいるが、マクロ経済スライドによりそれらを下回る引き上げになり、年金は実質引き下げということになる。
◯26年度の国債費は23年度と比べて4.5兆円増える
0金利政策で国債の金利は低く抑えられていたが、長期金利が上がってきており、利払いが増える。私たちの虎の子の預金の金利は0に限りなく近く、かつての利息がたくさんあった時代を忘れてしまうくらいである。しかし、政府の借金は1029兆円(22年度末、このほかに地方の借金が200兆円)あり、金利が上がると国債費は跳ね上がる。教育費が5兆3000億円と比較しても大きな金額であることがわかる。
政府は企業に対して賃上げを行うよう要請している。安倍政権の時にもあったので2回目?。しかし、企業のほとんどは中小企業(企業数で9割弱、従業者数で7割)で、そのほとんどが賃上げしたくてもできない状況だと言われる。その訳は、赤字企業が6割に達していることからもわかるように賃金を上げるための原資がないからである。これまで物価がほとんど上がらない状態が長く続いてきたために、賃上げしなくてもさほど実質の賃金が下がることがなく、ある意味バランスが取れていたわけである。ところが、物価が上がる一方で賃金が上がらなければ、国民の生活はますます苦しくばかりである。
ここからは、渡辺努「世界インフレの謎」を紹介しながら話を進めたい。2000年代後半から最近まで先進国ではインフレ率が低すぎる(日本はデフレ)状態であった。その理由は、①グローバリゼーション(企業はすこしでも安く生産できるところを求め、原価の上昇があっても値上げしない)、②少子高齢化(働き手の減少=将来の所得の減少=貯蓄を増やし、消費を減らす=インフレ率の下押し圧力)、③技術革新の頭打ちと生産性の伸びの停滞であった。このような状況はなぜ変わったのか。各種メディアではロシアがウクライナに侵攻し、そのためロシアからの燃料、ウクライナからの小麦などの食糧が滞ったからという説明がなされている。
しかし、インフレは21年春から始まっていた。著者によるとインフレを引き起こしたのは、新型コロナウィルス感染の拡大(パンデミック)ではないかと。パンデミックがグロバリゼーションによって構築された世界の物流ネットワーク中の生産設備や物流拠点といった人が「密」となる場所を直撃し、ほうぼうでグローバルな供給網を寸断した。すなわち、供給網の寸断→品薄→価格高騰ということが起こった。しかし、パンデミックは収った22年には経済再開が進みインフレは収るであろうと経済学者たちは予想した。ところが、一過性のインフレと考えていたにもかかわらず、かえってインフレは猛威をふるい始めたのである。
パンデミックは資本や労働に与えた影響よりもむしろ人々の行動変容をもたらし、これが供給を引き上げるのを妨げている。労働者は工場やオフィスに出ることを拒否し、早めのリタイアをする。消費者は人混みを避け、他者との物理的な接触を避ける。この結果、サービス消費(飲食、宿泊、理美容、フィットネスなど)を減らし、モノ消費に重点を置くようになる。この需要のシフトは急であるため、労働と資本の移動が追いつかない。これが世界で起きていることである。この状態は今年中には解消に向かうが、企業はグローバルな生産体制(賃金の安いところで生産する)を見直しし、それがコストアップになるかもしれないと言っている。

パンデミックの「後遺症」が引き起こすインフレ 同書151ページ
以上のことは日本を含め、世界各国で起こっていることだが、日本特有の問題がある。すなわち、90年代からのデフレ傾向の中で国民のインフレ予想が低く、言わば「値上げ嫌い」となっていることである。また、企業は価格を上げないように精一杯の努力を続けていることである。これでは賃金を上げる原資は生まれない。著者は、このあと二つの分かれ道のどちらかに日本は進むと予想する。一つはスタグフレーション、物価が上がると同時に景気が悪化する(欧米でも起きる可能性はあるが、賃金の上昇が日本より高い→消費が落ちない)、二つ目は慢性デフレからの脱却(この道が望ましいことは言うまでもない)、日本の消費者のインフレ予想が上がり、企業が価格を上げると同時に賃金が大幅に上がる。
※賃金上昇しても、それ以上に物価が上がれば、実質の賃金は増えるどころか減ってしまう。増やすためには労働生産性(日本はこれが低い)を増やすことが必要となる。

「ガリガリ君」(赤城乳業のアイスバー)値上げ(2016年)のCM ニューヨーク・タイムズが「日本的」として取りあげた
22年にも値上げしたが、社長の謝罪はなかった
(日本で値上げがいかに大変かを象徴する出来事)
長々と書いてしまった。連合は定期昇給も含めて5%の賃上げを要求しているようであるし、ユニクロなど大幅な賃上げをすると発表している企業もある。賃上げする企業が増えれば、賃上げしない企業から人の移動が起こり、日本全体としての生産性が上がる。こうなればデフレからの脱却ということになる。
◯東電が来週にも家庭向け3割前後の値上げ申請(6月以降)
電気料金は21年の9月以降値上げが続いている。原因は、①石炭、液化天然ガスなどの輸入価格の高騰、②新型コロナウィルスの感染拡大、③ウクライナ情勢、④円安、⑤新電力の値上げとされる。我家では昨年2月新電力に切り替えたばかりで、使用量はほとんど変わっていないが、大幅な値上げとなった。その傾向は今後も継続する見込みとのこと。また、ガス(田舎ではLPガス)も高くなっている。
◯12月の消費者物価指数は前年同月より4.0%上昇
第二次オイルショック(1981年12月)以来41年ぶりの水準。2月は値上げラッシュが予想されている。滅多にスーパーに行かないおじさんなので実感はわかないが、家内に聞いたところ天ぷら油の値上げをまずあげた。
◯3年ぶりの年金引き上げ1.9%を行う
物価2.5%、名目賃金2.8%の上昇を見込んでいるが、マクロ経済スライドによりそれらを下回る引き上げになり、年金は実質引き下げということになる。
◯26年度の国債費は23年度と比べて4.5兆円増える
0金利政策で国債の金利は低く抑えられていたが、長期金利が上がってきており、利払いが増える。私たちの虎の子の預金の金利は0に限りなく近く、かつての利息がたくさんあった時代を忘れてしまうくらいである。しかし、政府の借金は1029兆円(22年度末、このほかに地方の借金が200兆円)あり、金利が上がると国債費は跳ね上がる。教育費が5兆3000億円と比較しても大きな金額であることがわかる。
政府は企業に対して賃上げを行うよう要請している。安倍政権の時にもあったので2回目?。しかし、企業のほとんどは中小企業(企業数で9割弱、従業者数で7割)で、そのほとんどが賃上げしたくてもできない状況だと言われる。その訳は、赤字企業が6割に達していることからもわかるように賃金を上げるための原資がないからである。これまで物価がほとんど上がらない状態が長く続いてきたために、賃上げしなくてもさほど実質の賃金が下がることがなく、ある意味バランスが取れていたわけである。ところが、物価が上がる一方で賃金が上がらなければ、国民の生活はますます苦しくばかりである。
ここからは、渡辺努「世界インフレの謎」を紹介しながら話を進めたい。2000年代後半から最近まで先進国ではインフレ率が低すぎる(日本はデフレ)状態であった。その理由は、①グローバリゼーション(企業はすこしでも安く生産できるところを求め、原価の上昇があっても値上げしない)、②少子高齢化(働き手の減少=将来の所得の減少=貯蓄を増やし、消費を減らす=インフレ率の下押し圧力)、③技術革新の頭打ちと生産性の伸びの停滞であった。このような状況はなぜ変わったのか。各種メディアではロシアがウクライナに侵攻し、そのためロシアからの燃料、ウクライナからの小麦などの食糧が滞ったからという説明がなされている。
しかし、インフレは21年春から始まっていた。著者によるとインフレを引き起こしたのは、新型コロナウィルス感染の拡大(パンデミック)ではないかと。パンデミックがグロバリゼーションによって構築された世界の物流ネットワーク中の生産設備や物流拠点といった人が「密」となる場所を直撃し、ほうぼうでグローバルな供給網を寸断した。すなわち、供給網の寸断→品薄→価格高騰ということが起こった。しかし、パンデミックは収った22年には経済再開が進みインフレは収るであろうと経済学者たちは予想した。ところが、一過性のインフレと考えていたにもかかわらず、かえってインフレは猛威をふるい始めたのである。
パンデミックは資本や労働に与えた影響よりもむしろ人々の行動変容をもたらし、これが供給を引き上げるのを妨げている。労働者は工場やオフィスに出ることを拒否し、早めのリタイアをする。消費者は人混みを避け、他者との物理的な接触を避ける。この結果、サービス消費(飲食、宿泊、理美容、フィットネスなど)を減らし、モノ消費に重点を置くようになる。この需要のシフトは急であるため、労働と資本の移動が追いつかない。これが世界で起きていることである。この状態は今年中には解消に向かうが、企業はグローバルな生産体制(賃金の安いところで生産する)を見直しし、それがコストアップになるかもしれないと言っている。

パンデミックの「後遺症」が引き起こすインフレ 同書151ページ
以上のことは日本を含め、世界各国で起こっていることだが、日本特有の問題がある。すなわち、90年代からのデフレ傾向の中で国民のインフレ予想が低く、言わば「値上げ嫌い」となっていることである。また、企業は価格を上げないように精一杯の努力を続けていることである。これでは賃金を上げる原資は生まれない。著者は、このあと二つの分かれ道のどちらかに日本は進むと予想する。一つはスタグフレーション、物価が上がると同時に景気が悪化する(欧米でも起きる可能性はあるが、賃金の上昇が日本より高い→消費が落ちない)、二つ目は慢性デフレからの脱却(この道が望ましいことは言うまでもない)、日本の消費者のインフレ予想が上がり、企業が価格を上げると同時に賃金が大幅に上がる。
※賃金上昇しても、それ以上に物価が上がれば、実質の賃金は増えるどころか減ってしまう。増やすためには労働生産性(日本はこれが低い)を増やすことが必要となる。

「ガリガリ君」(赤城乳業のアイスバー)値上げ(2016年)のCM ニューヨーク・タイムズが「日本的」として取りあげた
22年にも値上げしたが、社長の謝罪はなかった
(日本で値上げがいかに大変かを象徴する出来事)
長々と書いてしまった。連合は定期昇給も含めて5%の賃上げを要求しているようであるし、ユニクロなど大幅な賃上げをすると発表している企業もある。賃上げする企業が増えれば、賃上げしない企業から人の移動が起こり、日本全体としての生産性が上がる。こうなればデフレからの脱却ということになる。