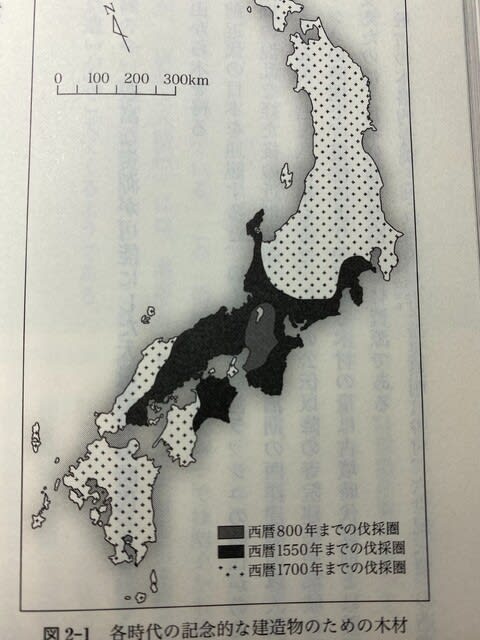昨日朝小雨の中、傘を差し城台山に出かけた。戻ってきて、2階で小田嶋隆「超・反知性主義入門」(昨日県図書館で借りてきたばかり)の本を読んでいたら、家内が深刻そうな顔をして、「お父さん、どこか怪我していない。キッチンの床に血らしいものが付いているよ」と。早速、見に行ったら、血痕がかなり残っている。よく見ると、赤い豆粒のようなものがあった。自分の足をチェックしたら、そこには出血の跡が残っていた。やられた!!明らかに山ヒルにやられた跡で、豆粒はヒルの亡骸だった。3600回、12年以上登っているけれど今までヒルにやられたことはなかった。付近には沢はないので、鹿かイノシシが運んできたものであろう。やはり雨の日には、ヒルはどこでもいると思って、注意したほうがよい。
ところで誰でも好き嫌いはある。政治家の言動には基本的に無関心なことが多いが、安部さんについては、反安部の立場に立つ著者の本をここ10年以上にわたり読んできたこともあり、気になる人物であることは間違いない。安部さんについては、女性による戦犯法廷についてNHKの番組編集に介入したあたりから自民党の右派として知ることになった。もちろん個人的に嫌いであっても、安部さんが国や国民のために良いことをしてくれていたなら政治家として評価しないわけにはいかない。特に国葬ともなると政治家としての安部さんを勉強した方が良いと思って、今回アジア・パシフィック・イニシアティブ「検証 安倍政権ー保守とリアリズムの政治」(文春新書)を買って読んでみた。
この本は、中北浩爾一橋大学大学院教授を始めとした大学の先生によって書かれている。そして安部、菅、岸田さん等54人へのインタビューの結果が織り込まれている。この本の内容を思い切り要約すると意外なことに安倍政権を評価する論考が多いことがわかる。
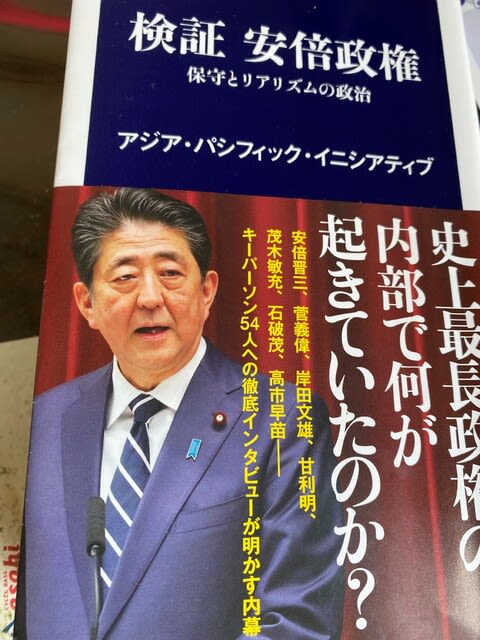
書評ではバランスが取れた本とあった
長期政権になった理由として、中北教授は、①首相官邸を中心に政府与党を含む求心力が強いチームを構築した、②安部首相の政治的リアリズムー右派の政治家であり、それゆえ心情を同じくする政治家や言論人、団体、有権者の強固な支持を受けていた。同時に第一次政権の反省を踏まえて、理念よりもプラグマチックな政権運営に努めた。政権の性格として、政治姿勢は保守そのものでありながら、政策は多分にリベラルな色彩を帯びるケースもあり、評価を難しくしているとしている。安部政権の特徴は、何よりも戦略と統治のありようにある。国のあるべきビジョンを明確にし、積極的にアジェンダ(このアジェンダ、看板の書き換えが頻繁に行われたように思われる)を設定し、それを能動的に遂行しようとした。その過程では現実主義的かつ実務的な取り組みを旨とした。
個別の政策ではまずアベノミックス。前例のない金融緩和と財政支出と規制緩和などであったが、途中の二回の消費税の引き上げなど必ずしもリフレ派の意向にそってはいなかったが、いまだに2%に物価上昇率は実現できていない。欧米ではコロナ後の反動(大幅な金融緩和と財政支出の反動)によりインフレが進んでいるが、日本の物価は2%まで上がっていない(欧米との金利差、日本の衰退?などにより円安が進んでいる。)。非正規労働者の雇用は増えているが、賃金はなかなか上昇せず、相変わらず消費は弱いままである。TPPではアメリカが離脱後も、アメリカ抜きの交渉を進め妥結した。結果日本のFTA(自由貿易協定)でカバーされる貿易量は増大した。
海外では外交・安全保障政策に対する評価が高い。韓国では政権への批判が最後まで強かったが、中国では退陣に際し、中日関係は近年、正常な軌道に戻り、新たな発展を遂げた(おじさんには外交辞令にしか聞こえないが)。選択的夫婦別姓制度についてはアジェンダとして取り上げなかった(支持母体である右派が支持しない)一方で、女性活躍できる環境を整える(「ウーマノミックス」というらしい。人口が減る中で経済を回すためには女性の活躍が必要という少し功利的な政策?)ことに傾注した。また10%の消費税率の引き上げとバーターで幼保無償化を実現した。安部さんが最も実現したかった憲法改正(妥協の末「自衛隊の明記」という一点に絞った)だったが、2012年の野党時代に自民党がまとめた憲法改正案(おじさんには随分復古的、時代錯誤的な改正案にしか思えないが)を支持する党内外の勢力があり、実現できなかった。
最後に反安部の論客を紹介する。今年急逝した小田嶋隆著「日本語を取り戻す」から引用する。この著者は、新型コロナ禍の中にあって安部さん、菅さんどちらも言葉を扱うはずの政治家が言葉を発しないことにあきれかえる。メルケル、ジョンソン、あのトランプさえテレビ演説を行い国民に対し理解を求めた。一方、日本の国の政府の人間は、テレビの画面に出ることを極力避けようとしている。記者会見では質問を打ち切るし、臨機応変な記者との受け答え自体をあらかじめ拒絶している。さらに安部氏の政治手法にいらだつ理由として、私の目から見て、政治家というより扇動家(アジテーター)に見えるからなのだと思っていると。「日本を取り戻す」「戦後レジームからの脱却」などを叫ぶのだが、その内容がはっきりしない。安部さんは保守を自認しているが、このスローガンから見ると保守ではない。これ故に安倍政権への支持率が若年層において高い理由となっている。安倍政権は外交と経済をしくじり、政治的に失敗しただけではない。より重要なのは、彼らがこの国の文化と社会を破壊したことだ。

日本で反政府の立場で発言し続けることの徒労感はますます強くなるばかりである。この著者が急逝したのもこのせいかもしれない。
政府べったりの主張をしているのは楽であることは間違いない。
私は、小田嶋氏の言っていることに全て賛成するわけではないが、国会の委員会で首相でありながら低級なヤジを飛ばしたり、立ち会い演説会で反安部の聴衆を批判するような度量のない人間がするようなことをしたことに失望するのである。かなわないことであるが、多くの国民が尊敬できる(もちろん主張や考えが違っていたとしても)政治家であって欲しかったと思うのである。
ところで誰でも好き嫌いはある。政治家の言動には基本的に無関心なことが多いが、安部さんについては、反安部の立場に立つ著者の本をここ10年以上にわたり読んできたこともあり、気になる人物であることは間違いない。安部さんについては、女性による戦犯法廷についてNHKの番組編集に介入したあたりから自民党の右派として知ることになった。もちろん個人的に嫌いであっても、安部さんが国や国民のために良いことをしてくれていたなら政治家として評価しないわけにはいかない。特に国葬ともなると政治家としての安部さんを勉強した方が良いと思って、今回アジア・パシフィック・イニシアティブ「検証 安倍政権ー保守とリアリズムの政治」(文春新書)を買って読んでみた。
この本は、中北浩爾一橋大学大学院教授を始めとした大学の先生によって書かれている。そして安部、菅、岸田さん等54人へのインタビューの結果が織り込まれている。この本の内容を思い切り要約すると意外なことに安倍政権を評価する論考が多いことがわかる。
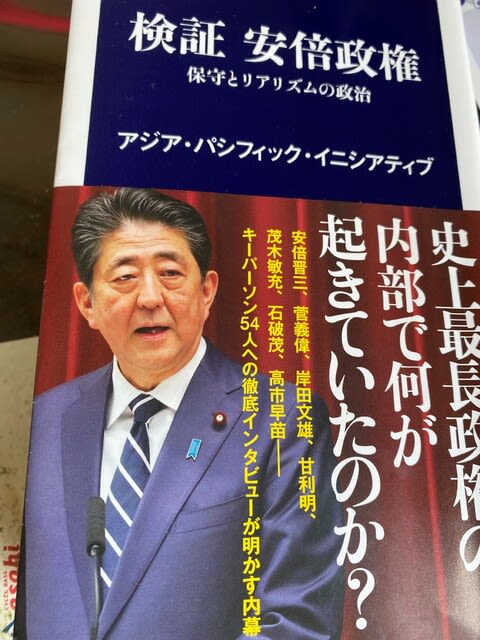
書評ではバランスが取れた本とあった
長期政権になった理由として、中北教授は、①首相官邸を中心に政府与党を含む求心力が強いチームを構築した、②安部首相の政治的リアリズムー右派の政治家であり、それゆえ心情を同じくする政治家や言論人、団体、有権者の強固な支持を受けていた。同時に第一次政権の反省を踏まえて、理念よりもプラグマチックな政権運営に努めた。政権の性格として、政治姿勢は保守そのものでありながら、政策は多分にリベラルな色彩を帯びるケースもあり、評価を難しくしているとしている。安部政権の特徴は、何よりも戦略と統治のありようにある。国のあるべきビジョンを明確にし、積極的にアジェンダ(このアジェンダ、看板の書き換えが頻繁に行われたように思われる)を設定し、それを能動的に遂行しようとした。その過程では現実主義的かつ実務的な取り組みを旨とした。
個別の政策ではまずアベノミックス。前例のない金融緩和と財政支出と規制緩和などであったが、途中の二回の消費税の引き上げなど必ずしもリフレ派の意向にそってはいなかったが、いまだに2%に物価上昇率は実現できていない。欧米ではコロナ後の反動(大幅な金融緩和と財政支出の反動)によりインフレが進んでいるが、日本の物価は2%まで上がっていない(欧米との金利差、日本の衰退?などにより円安が進んでいる。)。非正規労働者の雇用は増えているが、賃金はなかなか上昇せず、相変わらず消費は弱いままである。TPPではアメリカが離脱後も、アメリカ抜きの交渉を進め妥結した。結果日本のFTA(自由貿易協定)でカバーされる貿易量は増大した。
海外では外交・安全保障政策に対する評価が高い。韓国では政権への批判が最後まで強かったが、中国では退陣に際し、中日関係は近年、正常な軌道に戻り、新たな発展を遂げた(おじさんには外交辞令にしか聞こえないが)。選択的夫婦別姓制度についてはアジェンダとして取り上げなかった(支持母体である右派が支持しない)一方で、女性活躍できる環境を整える(「ウーマノミックス」というらしい。人口が減る中で経済を回すためには女性の活躍が必要という少し功利的な政策?)ことに傾注した。また10%の消費税率の引き上げとバーターで幼保無償化を実現した。安部さんが最も実現したかった憲法改正(妥協の末「自衛隊の明記」という一点に絞った)だったが、2012年の野党時代に自民党がまとめた憲法改正案(おじさんには随分復古的、時代錯誤的な改正案にしか思えないが)を支持する党内外の勢力があり、実現できなかった。
最後に反安部の論客を紹介する。今年急逝した小田嶋隆著「日本語を取り戻す」から引用する。この著者は、新型コロナ禍の中にあって安部さん、菅さんどちらも言葉を扱うはずの政治家が言葉を発しないことにあきれかえる。メルケル、ジョンソン、あのトランプさえテレビ演説を行い国民に対し理解を求めた。一方、日本の国の政府の人間は、テレビの画面に出ることを極力避けようとしている。記者会見では質問を打ち切るし、臨機応変な記者との受け答え自体をあらかじめ拒絶している。さらに安部氏の政治手法にいらだつ理由として、私の目から見て、政治家というより扇動家(アジテーター)に見えるからなのだと思っていると。「日本を取り戻す」「戦後レジームからの脱却」などを叫ぶのだが、その内容がはっきりしない。安部さんは保守を自認しているが、このスローガンから見ると保守ではない。これ故に安倍政権への支持率が若年層において高い理由となっている。安倍政権は外交と経済をしくじり、政治的に失敗しただけではない。より重要なのは、彼らがこの国の文化と社会を破壊したことだ。

日本で反政府の立場で発言し続けることの徒労感はますます強くなるばかりである。この著者が急逝したのもこのせいかもしれない。
政府べったりの主張をしているのは楽であることは間違いない。
私は、小田嶋氏の言っていることに全て賛成するわけではないが、国会の委員会で首相でありながら低級なヤジを飛ばしたり、立ち会い演説会で反安部の聴衆を批判するような度量のない人間がするようなことをしたことに失望するのである。かなわないことであるが、多くの国民が尊敬できる(もちろん主張や考えが違っていたとしても)政治家であって欲しかったと思うのである。