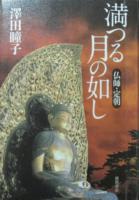最近、仏像鑑賞のための本を数冊読み継いできていたので、たまたまある新聞記事でこの作品名を知り、「仏師・定朝」という副題に関心をもち読んだ。その際、本作品が新田次郎文学賞の受賞(2013年)作品だということも知った。この著者の作品を読むのはこれが初めてである。
この作品は交響曲定朝という感じだなというのが私の第一印象である。平安時代に七条仏所の定朝が若くして卓越した彫像能力を持ちながら、仏像制作という形での彫像に苦悩する。しかし最後は宇治・平等院鳳凰堂の丈六阿弥陀如来座像を世に残す。そして、後の世に「定朝様式」という仏像造形スタイルが確立されていくことになる。ある意味で苦悩から歓喜へのプロセスが描かれて行く。
主旋律は勿論、仏師・定朝の生き様、思いである。彫像能力の才に満ちあふれながら、仏像制作を行うこと、仏像の存在そのものに疑問を抱くという苦悩。そこからあの定朝様式がどのように生まれてきたのか・・・そのプロセスが主旋律である。
この主旋律を際だたせ、サポートし、時には対立する局面をみせながら、副旋律が主旋律に絡まっていく。そして、主旋律を奏でる楽器(定朝)に対して、他の楽器(関係者)が合奏し、重奏し、時には独奏していく。交響曲第九の冒頭のメロディが印象深いようにこの作品も、序章と最終章で鳳凰堂阿弥陀如来坐像に託された定朝の思いがメロディとして奏でられている。
著者は序章で完成した平等院鳳凰堂の絢爛豪華、荘厳さから書き始めている。
「定朝が持てる能力のすべてをつぎ込んだ阿弥陀如来への思いは、余人には理解できないだろう。
養子である覚助は、配下の仏師たちを退け、たった一人で本尊の制作に打ち込む定朝に、苦笑いを隠さなかった。だが、まだ三十歳にもならぬ彼には分かるまい。御仏を作るとは、目に見えぬ仏を彫像として刻みだすだけではない。人の心に秘められた仏性を探り、すべての人々にその在処を告げ知らせる行為なのだ。」(p6)
この文が主旋律の核になるメロディである。若き定朝の中にこのメロディがしっかりと染み渡り鳳凰堂阿弥陀如来に結実していくというプロセスが定朝の苦悩から歓喜への道程である。だが、定朝自身にとって本来の「歓喜」はその一歩手前で未達になったのではないかという印象が残る。それは最終章に次ぎの記述があるからである。
”「隆範さまはいつも、定朝どのはいつか素晴らしい御仏を作られるであろうと、嬉しげに申されておりましたから」
滝緒のすすり泣きを聞きながら、定朝は重荷を下ろしでもしたような寂しい、どこか虚ろな開放感が心を満たしていくのを感じていた。”(p379)
「よく来てくださいました。さあどうぞ、本堂に上がってくだされ。隆範さまの目となって、それがしの畢生の作をしかとご覧くださいませ」(p379)
「なにやら棟梁は平等院の造像が終わって以来、魂が抜けたようになられてしまったのう」(p380)
定朝は、畢生の作を完成させた。そして歓喜とは別の心境に至ったように思う。
年齢16,7の頃の定朝から享年53歳までを描き、定朝の死から3月余り経った冬のある日のシーンで終わる。
定朝の墓の墓前に手向けられた古びた料紙。薄い冬の日に料紙に散らされた金銀の箔が映じて薄い光を放っている。境内を掃き清めていた寺男がそれに気づく。手に取ると、料紙には歌が記されていた。
今ぞこれ 雲間に行かんかりがねの すぐなる道を照らす影かな
「なんじゃ、妙な手向け物じゃのう。同じ供えるのであれば、後ほどわしらに役立つ品がよいのじゃが」・・・・・寺男は料紙をぐしゃりとねじり、懐に突っ込んだ。(p381,382)
鳳凰堂阿弥陀如来坐像を仕上げた定朝の心境とこの料紙の歌一首、平凡な寺男の反応。ここに著者のこの作品へのテーマがあるように思う。
p6の引用箇所の次の行が、「中務さま--それに隆範さま・・・」である。
この隆範が副旋律を奏でる人だ。ある意味、著者は僧侶隆範の人生を反面で語りたかったのではないかという気もする。いわば重要な准主人公。
隆範は、一条帝の東宮学士を務めた学者貴族・高階成忠の子であり、幼くして比叡山に登った。天台座主・院源を師として仕え、24歳の春に学生生活を終えたばかりで、師院源の推挙もあり内供奉十禅師(ないぐぶじゅうぜんんじ)の一人となり、宮中の護持僧の一人となっている。その隆範は、師・院源を戒師として出家した藤原道長が造営を始めた「法成寺」の九体阿弥陀堂に運び込まれてきた仏像を見ることから定朝との関わりができていく。
定朝の父・康尚を棟梁として九体阿弥陀堂に仏像が運び込まれる。だが搬入過程で、その一体の阿弥陀如来像の尊容に傷が付いた。道長の計らいで、御像にまだ直すべきところがあれば直せという示唆・指示を得る。運び込まれた像を眺める道長はじめ参集した人々の居るただ中で、定朝が傷ついた阿弥陀如来の顔に鑿を振るいその尊容を修正してしまう。金泥が剥落し、木地と漆が露わになったままだが、修正されたその尊容は道長はじめそこに居た人々を魅了してしまうのである。
「仏像を福々しく肉感的に作るのは、奈良の昔から行われてきた手法である。しかしいま目の前に現れたそれは、目鼻や頬の丸みを可能な限り薄く作ることで、淡く嫋やかな風情と不可思議な生命感を醸し出していた。」(p27)このとき、定朝16歳である。
定朝が鑿を振るい修正した如来像を見た隆範は、その如来像に己の胸を激しく揺さぶられる。叡山始め諸寺の数多の仏像に接してきている隆範の心を初めて揺り動かした仏像となったのだ。
院源の代理で列席していた隆範は叡山に戻り、この仏像のことを師に伝える。叡山山内には諸像の修理・造営を担当する仏所がある。仏所を監督する老僧朝覚は山外の仏師を侮蔑している。その背景の中で定朝に仏像を造らせたいと院源に進言する。隆範は定朝作の仏像を朝廷をはじめ貴族社会の中に広めていきたいという決意へと進んで行く。そして定朝に活躍の場を与えるため、自らサポートを推進していくことになる。主旋律を引き立てていくための副旋律。しかし、その共振・共鳴も相互に相容れない対立を引き起こす局面を内在し、それが発現される時が来る。それは避けることのできないノイズである。
定朝には天才的な彫像の技量がある。しかし、彼は造像という行為を突き放してみている。御仏を作る行為は嘘っぱちなものと見ている。御仏が居るならば、なぜ盗み、略奪、疫病が日常茶飯事の如く起こるのか。孤児となり飢えて死にそうな子ら数多く存在するのか。美しいと人が褒める仏像を作っても何も救われないではないか。父の如くに、貴族諸賢の意を受けて、期待に沿う仏像を作り、名を成す行為に意義があるのか。
「父はさすが大仏師です。御仏の存在などどうでもよいと言い放ち、如何にすればより尊げな御仏が作れるか、その一事のみに精勤しております。ですが僕には到底、あんな真似は出来ません」。
その思いを基底に抱く若き定朝。その定朝が彫像した仏像が、人々を魅了し癒やしているのも事実なのだ。
内供奉であることを伏せて隆範は七条仏所に定朝を訪ねる。定朝への造像依頼のためである。ここから定朝と隆範がどのように関わりを深めていくか、そして互いに越えることのできない局面がどこにあり、それがどのようにあらわれるかが読ませどころである。
そしてこの二人の奏でる旋律に、様々な人々がそれぞれの旋律を奏でて交響していくことになる。主な登場人物を点描しておこう。
康尚 定朝の父。七条仏所の棟梁、大仏師。貴族の評判を得ている仏師。
だが、若き定朝は父の考え方に反発心を持っている。康尚は打楽器ような役割。
甘楽丸(かんらまる) 叡山の色稚児として生き、そのまま叡山で生活する人物。
幼児期からの隆範を知る。定朝と関わっていく隆範の行動を常に援助する。
副旋律の展開、躍動に重奏していく役割を担う。
滝緒 隆範の従者。牛車を担当する牛飼いの童として仕えるところから始まる。
滝緒もまた、打楽器的役割。隆範の死を鳳凰堂に居る定朝に伝える。
道長 この作品では重要舞台を提供する後見人的存在。要所要所でインパクトを発揮。
交響曲で奏でられる旋律に打楽器が強烈なインパクトをあたえるような存在。
彰子 道長の長女。太皇太后として登場。父道長のやり方に批判的である。
一方で、宮廷の人間関係の面から政治的な配慮、決断をし、関わりを持っていく。
主旋律を引き出し、副旋律を助け、不協和音の発生を打ち消していく調整者的役割
隆範を介して定朝を支援する立場をとる。
敦明 小一条院敦明親王。道長により皇太子位を譲らされた人。道長に悉く反発する。
敦明の行動は、交響曲の中で不協和音を奏で続ける人となる。
ネガティヴな形で定朝や隆範、藤原家との関わりを続ける展開を繰り返す人。
中務 彰子に仕える人。敦明の心情に対する唯一の理解者。悲しみの旋律を奏でる。
敦明という不協和音を緩衝する旋律を奏でようとするが・・・虚しい立場。
この女性が定朝の造像にとってキーパーソンになる。定朝には打楽器的存在。
小式部 和泉式部の子。弘徽殿では中務の唯一の友。中務の心情の理解者でもある。
常に独自の自由奔放なメロディを奏で続ける人として描かれる。
それは敦明、中務との関係で奏でられる独自の協奏。だが主旋律に関わっていく
小諾 女童の頃より彰子の許で宮仕えする人。
時折、副旋律に共鳴する音を奏でていく。定朝の手になる仏像への心酔者となる
隆範へのインパクトは九体阿弥陀堂から御所に戻る際に童の小諾が詠んだ歌
むらさきの 雲路に渡る鐘の音に こころの月を託してもがな
から始まっていく。
道雅 左近衛中将。道長に対する関係では敦明と共通点のある人。対極の生き方を選択
彰子を陰で支えていく役割を担う。副旋律(隆範)を強める旋律を奏でていく。
間接的にに主旋律の響きに共振し、増幅させる役割を担う。
能信 醍醐帝第十皇子・源高明の娘で高松殿(道長の第二夫人)と称される明子の子。
宮人の一人として、隆範と親しい関係を保っていく。副旋律を時に増幅する役割
栄暹 都の孤児を多く保護し、無仏の荒寺・道光寺に住む僧。比叡山から下山した僧。
主旋律(定朝)の苦悩、思いの根元に関わり、底流の旋律を奏でていく人。
生き様として、副旋律(隆範)にインパクトを加える打楽器的存在となる。
こういう人々が鳳凰堂の丈六阿弥陀如来坐像が定朝により生み出されるまでの物語を織りなしていく。あたかも本作品の本文が4章で構成される交響曲のように、様々な人々の思いが音色として響き合い、交わっていく。
ちょっと特異な女性、小式部内侍について付記しておこう。ネット検索していて、ウィキペディアは小式部内侍が「万寿2年、藤原公成の子(頼忍阿闍梨)を出産した際に20代で死去し」と記す。本書著者は敦明親王との間の子として設定している。解けない謎のまま残る一事例なのだろうか。著者の設定が中務の悲劇的な生き様を一層際立たせることにはなる。中務の内奥の思いとは別にして・・・・。
隆範、甘楽丸、滝緒、中務、小諾、栄暹などは、著者の創作による一群の人々であろう。だが、定朝という仏師が生み出されるプロセスをリアルにしていく人々でもある。一読の価値ありと思う。物語の調べとともに、感情移入してしまう高まりを与えられた書だった。
終章に、鳳凰堂の阿弥陀如来を造像する定朝の思いとして、次ぎの一節がある。
「されど頬は丸く、穏やかに--そう、たとえれば満月の如く作らねばならぬ
・・・・・
言うなればそれは地の底から静かに湧き出る泉にも似た静謐さ、身の内に充満した穏やかな生命の息吹の如く、やさしく繊細な丸みでなければならない」(p371)と。
タイトル『満つる月の如し』はここに由来するのだろう。
定朝様式の仏像は数多くあるが、定朝の作と称されるのが平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像だけとは、実に残念だ。しかし、鳳凰堂の修復が終わり、この春からかつての鳳凰堂の姿が蘇ったというのは、うれしい限りである。再公開での拝観ブームが少し低調になった頃に、久しぶりに阿弥陀如来を拝見に行きたいと思っている。
ご一読ありがとうございます。
本作品に出てくる語句と関連事項をいくつかネット検索した。一覧にしておきたい。
法成寺址 :「フィールド・ミュージアム京都」
法成寺 :ウィキペディア
定朝 :ウィキペディア
仏師 定朝 :「神奈川仏教文化研究所」
藤原道長 :ウィキペディア
藤原彰子 :ウィキペディア
敦明親王 :ウィキペディア
藤原寛子 :ウィキペディア
小式部内侍 :ウィキペディア
七条仏所 ← 七条仏所跡 :「京都風光」
康尚 :ウィキペディア
定朝と七条仏所跡 :「平安京探偵団」
上品蓮台寺と蜘蛛塚、定朝の墓 :「京都検定合格を目指す京都案内」
糖尿病と藤原道長 :「古今養生記」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)
この作品は交響曲定朝という感じだなというのが私の第一印象である。平安時代に七条仏所の定朝が若くして卓越した彫像能力を持ちながら、仏像制作という形での彫像に苦悩する。しかし最後は宇治・平等院鳳凰堂の丈六阿弥陀如来座像を世に残す。そして、後の世に「定朝様式」という仏像造形スタイルが確立されていくことになる。ある意味で苦悩から歓喜へのプロセスが描かれて行く。
主旋律は勿論、仏師・定朝の生き様、思いである。彫像能力の才に満ちあふれながら、仏像制作を行うこと、仏像の存在そのものに疑問を抱くという苦悩。そこからあの定朝様式がどのように生まれてきたのか・・・そのプロセスが主旋律である。
この主旋律を際だたせ、サポートし、時には対立する局面をみせながら、副旋律が主旋律に絡まっていく。そして、主旋律を奏でる楽器(定朝)に対して、他の楽器(関係者)が合奏し、重奏し、時には独奏していく。交響曲第九の冒頭のメロディが印象深いようにこの作品も、序章と最終章で鳳凰堂阿弥陀如来坐像に託された定朝の思いがメロディとして奏でられている。
著者は序章で完成した平等院鳳凰堂の絢爛豪華、荘厳さから書き始めている。
「定朝が持てる能力のすべてをつぎ込んだ阿弥陀如来への思いは、余人には理解できないだろう。
養子である覚助は、配下の仏師たちを退け、たった一人で本尊の制作に打ち込む定朝に、苦笑いを隠さなかった。だが、まだ三十歳にもならぬ彼には分かるまい。御仏を作るとは、目に見えぬ仏を彫像として刻みだすだけではない。人の心に秘められた仏性を探り、すべての人々にその在処を告げ知らせる行為なのだ。」(p6)
この文が主旋律の核になるメロディである。若き定朝の中にこのメロディがしっかりと染み渡り鳳凰堂阿弥陀如来に結実していくというプロセスが定朝の苦悩から歓喜への道程である。だが、定朝自身にとって本来の「歓喜」はその一歩手前で未達になったのではないかという印象が残る。それは最終章に次ぎの記述があるからである。
”「隆範さまはいつも、定朝どのはいつか素晴らしい御仏を作られるであろうと、嬉しげに申されておりましたから」
滝緒のすすり泣きを聞きながら、定朝は重荷を下ろしでもしたような寂しい、どこか虚ろな開放感が心を満たしていくのを感じていた。”(p379)
「よく来てくださいました。さあどうぞ、本堂に上がってくだされ。隆範さまの目となって、それがしの畢生の作をしかとご覧くださいませ」(p379)
「なにやら棟梁は平等院の造像が終わって以来、魂が抜けたようになられてしまったのう」(p380)
定朝は、畢生の作を完成させた。そして歓喜とは別の心境に至ったように思う。
年齢16,7の頃の定朝から享年53歳までを描き、定朝の死から3月余り経った冬のある日のシーンで終わる。
定朝の墓の墓前に手向けられた古びた料紙。薄い冬の日に料紙に散らされた金銀の箔が映じて薄い光を放っている。境内を掃き清めていた寺男がそれに気づく。手に取ると、料紙には歌が記されていた。
今ぞこれ 雲間に行かんかりがねの すぐなる道を照らす影かな
「なんじゃ、妙な手向け物じゃのう。同じ供えるのであれば、後ほどわしらに役立つ品がよいのじゃが」・・・・・寺男は料紙をぐしゃりとねじり、懐に突っ込んだ。(p381,382)
鳳凰堂阿弥陀如来坐像を仕上げた定朝の心境とこの料紙の歌一首、平凡な寺男の反応。ここに著者のこの作品へのテーマがあるように思う。
p6の引用箇所の次の行が、「中務さま--それに隆範さま・・・」である。
この隆範が副旋律を奏でる人だ。ある意味、著者は僧侶隆範の人生を反面で語りたかったのではないかという気もする。いわば重要な准主人公。
隆範は、一条帝の東宮学士を務めた学者貴族・高階成忠の子であり、幼くして比叡山に登った。天台座主・院源を師として仕え、24歳の春に学生生活を終えたばかりで、師院源の推挙もあり内供奉十禅師(ないぐぶじゅうぜんんじ)の一人となり、宮中の護持僧の一人となっている。その隆範は、師・院源を戒師として出家した藤原道長が造営を始めた「法成寺」の九体阿弥陀堂に運び込まれてきた仏像を見ることから定朝との関わりができていく。
定朝の父・康尚を棟梁として九体阿弥陀堂に仏像が運び込まれる。だが搬入過程で、その一体の阿弥陀如来像の尊容に傷が付いた。道長の計らいで、御像にまだ直すべきところがあれば直せという示唆・指示を得る。運び込まれた像を眺める道長はじめ参集した人々の居るただ中で、定朝が傷ついた阿弥陀如来の顔に鑿を振るいその尊容を修正してしまう。金泥が剥落し、木地と漆が露わになったままだが、修正されたその尊容は道長はじめそこに居た人々を魅了してしまうのである。
「仏像を福々しく肉感的に作るのは、奈良の昔から行われてきた手法である。しかしいま目の前に現れたそれは、目鼻や頬の丸みを可能な限り薄く作ることで、淡く嫋やかな風情と不可思議な生命感を醸し出していた。」(p27)このとき、定朝16歳である。
定朝が鑿を振るい修正した如来像を見た隆範は、その如来像に己の胸を激しく揺さぶられる。叡山始め諸寺の数多の仏像に接してきている隆範の心を初めて揺り動かした仏像となったのだ。
院源の代理で列席していた隆範は叡山に戻り、この仏像のことを師に伝える。叡山山内には諸像の修理・造営を担当する仏所がある。仏所を監督する老僧朝覚は山外の仏師を侮蔑している。その背景の中で定朝に仏像を造らせたいと院源に進言する。隆範は定朝作の仏像を朝廷をはじめ貴族社会の中に広めていきたいという決意へと進んで行く。そして定朝に活躍の場を与えるため、自らサポートを推進していくことになる。主旋律を引き立てていくための副旋律。しかし、その共振・共鳴も相互に相容れない対立を引き起こす局面を内在し、それが発現される時が来る。それは避けることのできないノイズである。
定朝には天才的な彫像の技量がある。しかし、彼は造像という行為を突き放してみている。御仏を作る行為は嘘っぱちなものと見ている。御仏が居るならば、なぜ盗み、略奪、疫病が日常茶飯事の如く起こるのか。孤児となり飢えて死にそうな子ら数多く存在するのか。美しいと人が褒める仏像を作っても何も救われないではないか。父の如くに、貴族諸賢の意を受けて、期待に沿う仏像を作り、名を成す行為に意義があるのか。
「父はさすが大仏師です。御仏の存在などどうでもよいと言い放ち、如何にすればより尊げな御仏が作れるか、その一事のみに精勤しております。ですが僕には到底、あんな真似は出来ません」。
その思いを基底に抱く若き定朝。その定朝が彫像した仏像が、人々を魅了し癒やしているのも事実なのだ。
内供奉であることを伏せて隆範は七条仏所に定朝を訪ねる。定朝への造像依頼のためである。ここから定朝と隆範がどのように関わりを深めていくか、そして互いに越えることのできない局面がどこにあり、それがどのようにあらわれるかが読ませどころである。
そしてこの二人の奏でる旋律に、様々な人々がそれぞれの旋律を奏でて交響していくことになる。主な登場人物を点描しておこう。
康尚 定朝の父。七条仏所の棟梁、大仏師。貴族の評判を得ている仏師。
だが、若き定朝は父の考え方に反発心を持っている。康尚は打楽器ような役割。
甘楽丸(かんらまる) 叡山の色稚児として生き、そのまま叡山で生活する人物。
幼児期からの隆範を知る。定朝と関わっていく隆範の行動を常に援助する。
副旋律の展開、躍動に重奏していく役割を担う。
滝緒 隆範の従者。牛車を担当する牛飼いの童として仕えるところから始まる。
滝緒もまた、打楽器的役割。隆範の死を鳳凰堂に居る定朝に伝える。
道長 この作品では重要舞台を提供する後見人的存在。要所要所でインパクトを発揮。
交響曲で奏でられる旋律に打楽器が強烈なインパクトをあたえるような存在。
彰子 道長の長女。太皇太后として登場。父道長のやり方に批判的である。
一方で、宮廷の人間関係の面から政治的な配慮、決断をし、関わりを持っていく。
主旋律を引き出し、副旋律を助け、不協和音の発生を打ち消していく調整者的役割
隆範を介して定朝を支援する立場をとる。
敦明 小一条院敦明親王。道長により皇太子位を譲らされた人。道長に悉く反発する。
敦明の行動は、交響曲の中で不協和音を奏で続ける人となる。
ネガティヴな形で定朝や隆範、藤原家との関わりを続ける展開を繰り返す人。
中務 彰子に仕える人。敦明の心情に対する唯一の理解者。悲しみの旋律を奏でる。
敦明という不協和音を緩衝する旋律を奏でようとするが・・・虚しい立場。
この女性が定朝の造像にとってキーパーソンになる。定朝には打楽器的存在。
小式部 和泉式部の子。弘徽殿では中務の唯一の友。中務の心情の理解者でもある。
常に独自の自由奔放なメロディを奏で続ける人として描かれる。
それは敦明、中務との関係で奏でられる独自の協奏。だが主旋律に関わっていく
小諾 女童の頃より彰子の許で宮仕えする人。
時折、副旋律に共鳴する音を奏でていく。定朝の手になる仏像への心酔者となる
隆範へのインパクトは九体阿弥陀堂から御所に戻る際に童の小諾が詠んだ歌
むらさきの 雲路に渡る鐘の音に こころの月を託してもがな
から始まっていく。
道雅 左近衛中将。道長に対する関係では敦明と共通点のある人。対極の生き方を選択
彰子を陰で支えていく役割を担う。副旋律(隆範)を強める旋律を奏でていく。
間接的にに主旋律の響きに共振し、増幅させる役割を担う。
能信 醍醐帝第十皇子・源高明の娘で高松殿(道長の第二夫人)と称される明子の子。
宮人の一人として、隆範と親しい関係を保っていく。副旋律を時に増幅する役割
栄暹 都の孤児を多く保護し、無仏の荒寺・道光寺に住む僧。比叡山から下山した僧。
主旋律(定朝)の苦悩、思いの根元に関わり、底流の旋律を奏でていく人。
生き様として、副旋律(隆範)にインパクトを加える打楽器的存在となる。
こういう人々が鳳凰堂の丈六阿弥陀如来坐像が定朝により生み出されるまでの物語を織りなしていく。あたかも本作品の本文が4章で構成される交響曲のように、様々な人々の思いが音色として響き合い、交わっていく。
ちょっと特異な女性、小式部内侍について付記しておこう。ネット検索していて、ウィキペディアは小式部内侍が「万寿2年、藤原公成の子(頼忍阿闍梨)を出産した際に20代で死去し」と記す。本書著者は敦明親王との間の子として設定している。解けない謎のまま残る一事例なのだろうか。著者の設定が中務の悲劇的な生き様を一層際立たせることにはなる。中務の内奥の思いとは別にして・・・・。
隆範、甘楽丸、滝緒、中務、小諾、栄暹などは、著者の創作による一群の人々であろう。だが、定朝という仏師が生み出されるプロセスをリアルにしていく人々でもある。一読の価値ありと思う。物語の調べとともに、感情移入してしまう高まりを与えられた書だった。
終章に、鳳凰堂の阿弥陀如来を造像する定朝の思いとして、次ぎの一節がある。
「されど頬は丸く、穏やかに--そう、たとえれば満月の如く作らねばならぬ
・・・・・
言うなればそれは地の底から静かに湧き出る泉にも似た静謐さ、身の内に充満した穏やかな生命の息吹の如く、やさしく繊細な丸みでなければならない」(p371)と。
タイトル『満つる月の如し』はここに由来するのだろう。
定朝様式の仏像は数多くあるが、定朝の作と称されるのが平等院鳳凰堂の阿弥陀如来坐像だけとは、実に残念だ。しかし、鳳凰堂の修復が終わり、この春からかつての鳳凰堂の姿が蘇ったというのは、うれしい限りである。再公開での拝観ブームが少し低調になった頃に、久しぶりに阿弥陀如来を拝見に行きたいと思っている。
ご一読ありがとうございます。
本作品に出てくる語句と関連事項をいくつかネット検索した。一覧にしておきたい。
法成寺址 :「フィールド・ミュージアム京都」
法成寺 :ウィキペディア
定朝 :ウィキペディア
仏師 定朝 :「神奈川仏教文化研究所」
藤原道長 :ウィキペディア
藤原彰子 :ウィキペディア
敦明親王 :ウィキペディア
藤原寛子 :ウィキペディア
小式部内侍 :ウィキペディア
七条仏所 ← 七条仏所跡 :「京都風光」
康尚 :ウィキペディア
定朝と七条仏所跡 :「平安京探偵団」
上品蓮台寺と蜘蛛塚、定朝の墓 :「京都検定合格を目指す京都案内」
糖尿病と藤原道長 :「古今養生記」
インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。
↑↑ クリックしていただけると嬉しいです。
(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。
その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。
その点、ご寛恕ください。)