「量的な変化が質的な変化をもたらし、また質的な変化が量的な変化をもたらすというのが『量質転化』の法則です」と弁証法では言っているようです。
さて、世間での一般的な考えでは「量と質」とは全く別な概念のように思われていますね。
ヒトの場合に当てはめてこのことを考えてみましょう。
ここで体が大きく体重の重いヒトと体が小柄で体重の少ないヒトがいたとしましょうか。
この人たちの体型と体重は「量的」な差があると考えることが出来ます。
また、別な側面からその人たちを考察してみましょう。
ヒトAは気が小さくおとなしい性格と仮定しましょう。ヒトBはいい加減でしかも荒々しい性格の持ち主と仮定しましょう。
この場合、両者は性格の異なっている人のように私たちは思ってしまいますね。
ヒトAはおとなしくて一緒にいても気疲れしない「良い人」だと周りからは思われるでしょう。
一方ヒトBは一緒にいるといつ怒りだすのかもわからないので、気疲れするよ、と思われたりしますね。
これを見ると、両者の性格が異なっていると思うのが一般的と思われます
性格や気質の違いは「質の違い」と我々は考えますね。
ですがここで少し見方を変えてみたらどうなるでしょうか。
ヒトAもヒトBも性格と気質には差が無いと仮定したらどうでしょうか。
ただ、人が持っている「気質の量」がそれぞれの場合に、現れる度合いに差異があるのだと考えたらどうなるでしょうか。
「おとなしさ」が多く出る人と「怒りやすさ」が多く出ることの度合いの差が、「性格や気質」だとわたくしには思えるのです。
「おとなしさ」や「怒りやすさ」の度合いがそれぞれに多少の違いはあるにせよ、皆それぞれに同じように持っている「気質」と考えれば、世間で起こる凶悪犯罪もその原因が少しはわかってくるのではないでしょうか。
世間で「凶悪犯罪」が起こった時など、「あの人は普段はおとなしい人なのに、あんなことをしでかすなんて、信じられない」という事を聞くことがあります。
人が思いがけない行動をとるときにはその人の心理的背景などがあるのでしょうが、私がここで述べた「量と質」の観点から見ることもできます。
すなわち、人には様々な要素の心的内実があり、時にはそれらの両極のうち、量的に大きいほうが出現してくることがあるのだろう、と考えるのです。
わたしたちの「生」は実は「紙一重」の所で成り立っているのかもしれません。
さて、世間での一般的な考えでは「量と質」とは全く別な概念のように思われていますね。
ヒトの場合に当てはめてこのことを考えてみましょう。
ここで体が大きく体重の重いヒトと体が小柄で体重の少ないヒトがいたとしましょうか。
この人たちの体型と体重は「量的」な差があると考えることが出来ます。
また、別な側面からその人たちを考察してみましょう。
ヒトAは気が小さくおとなしい性格と仮定しましょう。ヒトBはいい加減でしかも荒々しい性格の持ち主と仮定しましょう。
この場合、両者は性格の異なっている人のように私たちは思ってしまいますね。
ヒトAはおとなしくて一緒にいても気疲れしない「良い人」だと周りからは思われるでしょう。
一方ヒトBは一緒にいるといつ怒りだすのかもわからないので、気疲れするよ、と思われたりしますね。
これを見ると、両者の性格が異なっていると思うのが一般的と思われます
性格や気質の違いは「質の違い」と我々は考えますね。
ですがここで少し見方を変えてみたらどうなるでしょうか。
ヒトAもヒトBも性格と気質には差が無いと仮定したらどうでしょうか。
ただ、人が持っている「気質の量」がそれぞれの場合に、現れる度合いに差異があるのだと考えたらどうなるでしょうか。
「おとなしさ」が多く出る人と「怒りやすさ」が多く出ることの度合いの差が、「性格や気質」だとわたくしには思えるのです。
「おとなしさ」や「怒りやすさ」の度合いがそれぞれに多少の違いはあるにせよ、皆それぞれに同じように持っている「気質」と考えれば、世間で起こる凶悪犯罪もその原因が少しはわかってくるのではないでしょうか。
世間で「凶悪犯罪」が起こった時など、「あの人は普段はおとなしい人なのに、あんなことをしでかすなんて、信じられない」という事を聞くことがあります。
人が思いがけない行動をとるときにはその人の心理的背景などがあるのでしょうが、私がここで述べた「量と質」の観点から見ることもできます。
すなわち、人には様々な要素の心的内実があり、時にはそれらの両極のうち、量的に大きいほうが出現してくることがあるのだろう、と考えるのです。
わたしたちの「生」は実は「紙一重」の所で成り立っているのかもしれません。














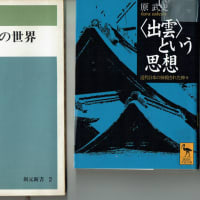






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます