現在、「るつぼ」(クルーシブル)という芝居が都内で上演されているとのことです。友人が東京まで出かけて観てきたそうです。
いつぞや、テレビで堤真一と松雪泰子がこの芝居を宣伝していたのを見たことを思い出しました。
この芝居の原作がアーサー・ミラーだったと知ったのはごく最近です。
アーサー・ミラーと言えばアメリカを代表する劇作家です。
彼の作品では「セールスマンの死」が有名なものとして挙げられます。
私が、学生のころに都内の大学などの学生劇団などでも、上演されていた演目の一つだった記憶があります。
さて、今日は氏のもう一つの代表作と言われている「るつぼ」についてです。
正直言って「るつぼ」については今まで、全く無知でした。
1600年代のアメリカに移住したばかりの清教徒の村で起きた実際の「魔女裁判」を描いた劇作とのことです。
アーサー・ミラーのこの戯曲が上演されたのが1953年と「るつぼ」の公式ページの年表にありました。
1950年代のアメリカはどんな社会状況だったのでしょうか?
政治外交的な面でいえば、冷戦の真っただ中でした。
アメリカ国内では、様々な分野でいわゆる「共産主義者狩り(マッカーシズム)」が行われていました。
映画・演劇界にもその嵐が吹き荒れていました。
このため、ハリウッドを追われた映画人も多くいました。
チャップリンもその一人で、国外に出かけた時、再入国を認めてもらえず、アメリカを去らざるを得なかった事もあったようです。
るつぼの原作者のアーサー・ミラーもその一人で、「非米活動委員会」の対象者リストに挙げられていました。
この「非米活動委員会」の査問は陰湿なもので、「共産主義者」と目された人物が当局(実際の捜査はFBIが行った)に呼び出され、査問を受けます。
この時、自分の意思や信条には関係なく、「共産主義者である」と認めて、さらに思想的な同調者(友人や職場の同僚など)の名前を挙げれば、査問を受けた人の処罰を軽くしてやる、という手法であったようです。
はやい話が、友達を当局に売り渡せばお前の罪を軽くするぞ、と言っていたのでした。
余談ですが、この「赤狩り」に引っかかり、命を落とした歴史学者がいました。
E・H・ノーマンという人物です。
彼はカナダの駐エジプト大使として赴任先の大使館の建物から身を投げて自死をしてしまいます。
自分の良心に従い、友人の名を挙げることを拒否して自殺したものと言われています。
さて、この「非米活動委員会」の手法はまさしく、中世の「魔女裁判」そのものです。
1692年のアメリカの片田舎で実際にあった「魔女裁判」と何ら変わることはありません。
ですから、アーサー・ミラーは自分に降りかかった火の粉を「るつぼ」という戯曲で振り払おうとしたと考えるこができます。
「魔女裁判」は大昔の出来事なのでしょうか?
「魔女」と指摘された人が自分の身を守るためにする行動を、他の人は非難できるでしょうか?
たいへん、難しい問題だと思います。自分にはその答えは出せません。
「魔女狩り」は、いまでも程度の差はありますが、社会の各分野で残っている気がします。
さて、この戯曲をもっと詳しく知りたくて、アマゾンにつぎの本を注文しました。

アーサー・ミラー〈2〉るつぼ (ハヤカワ演劇文庫) というものです。
「るつぼ」の原作の翻訳本です。
いまさっき届いたので、読んでみたいと思います。
最後に「るつぼ」の芝居を知らせてくれた友人に、お礼を言いたいと思います。
ありがとう!!
P・S
私は芝居や映画などを観ても、それが書かれたいきさつや時代背景などの方に眼が行ってしまいます。
テレビドラマの「相棒」の杉下右京の言葉を借りれば、「これは細かいことに眼が行ってしまう僕の悪い癖なのです」という事になります。
追記(11月12日)
「るつぼ」の原作を読んだ感想を書いてみました。興味を持たれた方はこちらもご覧いただければ幸いです。
いつぞや、テレビで堤真一と松雪泰子がこの芝居を宣伝していたのを見たことを思い出しました。
この芝居の原作がアーサー・ミラーだったと知ったのはごく最近です。
アーサー・ミラーと言えばアメリカを代表する劇作家です。
彼の作品では「セールスマンの死」が有名なものとして挙げられます。
私が、学生のころに都内の大学などの学生劇団などでも、上演されていた演目の一つだった記憶があります。
さて、今日は氏のもう一つの代表作と言われている「るつぼ」についてです。
正直言って「るつぼ」については今まで、全く無知でした。
1600年代のアメリカに移住したばかりの清教徒の村で起きた実際の「魔女裁判」を描いた劇作とのことです。
アーサー・ミラーのこの戯曲が上演されたのが1953年と「るつぼ」の公式ページの年表にありました。
1950年代のアメリカはどんな社会状況だったのでしょうか?
政治外交的な面でいえば、冷戦の真っただ中でした。
アメリカ国内では、様々な分野でいわゆる「共産主義者狩り(マッカーシズム)」が行われていました。
映画・演劇界にもその嵐が吹き荒れていました。
このため、ハリウッドを追われた映画人も多くいました。
チャップリンもその一人で、国外に出かけた時、再入国を認めてもらえず、アメリカを去らざるを得なかった事もあったようです。
るつぼの原作者のアーサー・ミラーもその一人で、「非米活動委員会」の対象者リストに挙げられていました。
この「非米活動委員会」の査問は陰湿なもので、「共産主義者」と目された人物が当局(実際の捜査はFBIが行った)に呼び出され、査問を受けます。
この時、自分の意思や信条には関係なく、「共産主義者である」と認めて、さらに思想的な同調者(友人や職場の同僚など)の名前を挙げれば、査問を受けた人の処罰を軽くしてやる、という手法であったようです。
はやい話が、友達を当局に売り渡せばお前の罪を軽くするぞ、と言っていたのでした。
余談ですが、この「赤狩り」に引っかかり、命を落とした歴史学者がいました。
E・H・ノーマンという人物です。
彼はカナダの駐エジプト大使として赴任先の大使館の建物から身を投げて自死をしてしまいます。
自分の良心に従い、友人の名を挙げることを拒否して自殺したものと言われています。
さて、この「非米活動委員会」の手法はまさしく、中世の「魔女裁判」そのものです。
1692年のアメリカの片田舎で実際にあった「魔女裁判」と何ら変わることはありません。
ですから、アーサー・ミラーは自分に降りかかった火の粉を「るつぼ」という戯曲で振り払おうとしたと考えるこができます。
「魔女裁判」は大昔の出来事なのでしょうか?
「魔女」と指摘された人が自分の身を守るためにする行動を、他の人は非難できるでしょうか?
たいへん、難しい問題だと思います。自分にはその答えは出せません。
「魔女狩り」は、いまでも程度の差はありますが、社会の各分野で残っている気がします。
さて、この戯曲をもっと詳しく知りたくて、アマゾンにつぎの本を注文しました。

アーサー・ミラー〈2〉るつぼ (ハヤカワ演劇文庫) というものです。
「るつぼ」の原作の翻訳本です。
いまさっき届いたので、読んでみたいと思います。
最後に「るつぼ」の芝居を知らせてくれた友人に、お礼を言いたいと思います。
ありがとう!!
P・S
私は芝居や映画などを観ても、それが書かれたいきさつや時代背景などの方に眼が行ってしまいます。
テレビドラマの「相棒」の杉下右京の言葉を借りれば、「これは細かいことに眼が行ってしまう僕の悪い癖なのです」という事になります。
追記(11月12日)
「るつぼ」の原作を読んだ感想を書いてみました。興味を持たれた方はこちらもご覧いただければ幸いです。














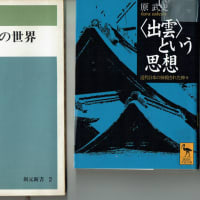






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます