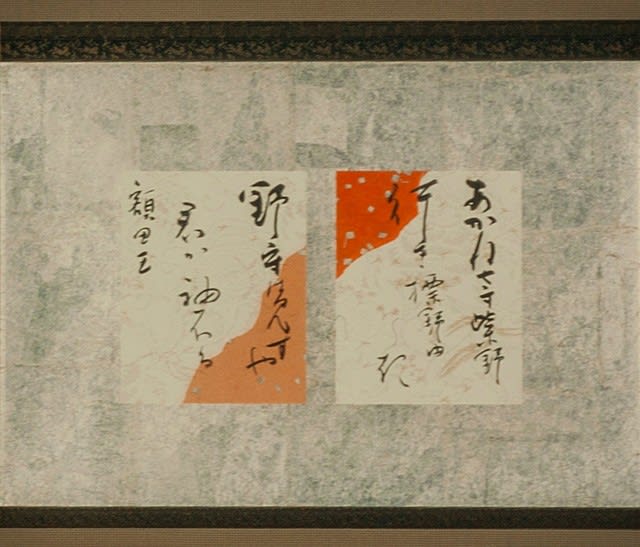【男女同権】(昭和21年12月発表、太宰37歳)
さて戦後です。
この作品は、ある老詩人が、売れなくなって都落ちし、故郷の弟の家に居候しているが、その土地の文化組織から声がかかり、講演をした記録という体裁。
自分は子どもの時から母親を含め、出会った女性にことごとくいじめられてきた。そのさまを縷々語った後、最後に、このたび民主主義の世の中となり、「男女同権」が認められたことはまことに慶賀すべき事であり、これからは言論の自由が保障されるので、女性の悪口を堂々と言うことで余生を過ごそうと思うと結びます。
この作品は戦争直後の浮ついたイデオロギーを徹底的に茶化すと同時に、また、個人どうしの関係では、女性が男よりも常に強いという生活的事実を誇張して表現しています。太宰の真骨頂が出ていると言ってもよいでしょう。
また、彼の一貫した女性観がよく滲み出てもいます。それは、前作『新郎』『十二月八日』にも表れていましたが、女性は日常的現実にとことん根を下ろした存在であり(『皮膚と心』はその典型例です)、男性はそれに支えられて観念の世界に遊ぶことができているという把握です。彼は谷崎のように、女性をそれゆえに崇拝していたのではありませんが、よく女性という存在の本質をとらえていました。このことが男性にとって謎を秘めた女性という存在の内面にうまく入り込めた条件の一つでもあるでしょう。彼自身が多分に女性的な意識・感性の持ち主であったとも言えます。
女権拡張運動の延長としてのフェミニズムは、女性を「男性の支配を受けてきた被害者・弱者」というカテゴリーで一括し、男性の社会的権力に対抗してきました。しかし彼女たちの思想の決定的な欠陥は、意識的にか感性が鈍いせいか、けっしてプライベートな関係における両性のやり取りの構造を見ようとしないことです。エロスの関係では、暴力を用いるのでない限り、諾否の権利はいつも女性が握っています(男が金を支払って女の体を抱かせてもらう売春がその最もよい例)。普通の女性はそのことを必ずわきまえています。一般的な政治的社会的権力関係において、女性がいかに弱者と見えようと、彼女たちは自分たちの「勝利」=「性的アイデンティティ」に自信を持っています。福沢諭吉もその事実を『通俗国権論』の冒頭ですでに指摘しています。
さて最近では、多くの女性たちが「弱者」のレッテルを逆用して、この「隠れていた権力」をあらわに表出するようになりました。何でもセクハラ、痴漢冤罪など。これらはポリコレとして過剰に表通りをまかり通っています。結果、男性たちはますますお行儀がよくなり、女性に対して委縮するようになりました。老詩人の「男女同権」への期待は裏切られたと言えましょう。
何はともあれ、この作品は、硬直した「社会正義」の建前に、搦め手から痛快な一撃をくらわしたもので、思わず吹き出してしまわない読者はまずおりますまい。
【トカトントン】(昭和22年1月発表。太宰37歳)
終戦の詔勅を聞いた時、悲壮な気持ちで死ぬべきだと思ったとたん、どこからか釘を打つ「トカトントン」という音が聞こえ、たちまちその悲壮感が消えて白けてしまった主人公の青年。それから後は、何かに夢中になりかけるたびに「トカトントン」が聞こえて、たちまち情熱が冷めてしまうようになります。この頃では、日常の些細な試みにもこの幻聴が聞こえるようになり、どうにかならないものかと悩んでいます。
こういう人生相談の手紙を受け取った作家は、次のような返事を書きます。
《拝復。気取つた苦悩ですね。僕はあまり同情してはゐないんですよ。十指の指差すところ、十目の見るところの、いかなる弁明も成立しない醜態を、君はまだ避けてゐるやうですね。真の思想は、叡智よりも勇気を必要とするものです。マタイ伝十章、二十八、「身を殺して霊魂(たましひ)をころし得ぬ者どもを懼(おそ)るな、身と霊魂とをゲヘナにて滅ぼし得る者をおそれよ。」この場合の「懼る」は、「畏敬」の意にちかいやうです。このイエスの言に、霹靂を感ずる事が出来たら、君の幻聴は止む筈です。不盡。》
有名な作品ですが、なかなか難解でもあります。この作品の読解のポイントを私なりにいくつか挙げてみましょう。
①一億玉砕も辞さずとまで思いつめた多くの庶民の思いが、一日にしてすかされてしまったその何とも言えない虚脱感が始めに置かれていて、いったいあれは何だったのかというその気分が「トカトントン」という長閑な響きによって象徴されています。これは、死を賭してまで情熱を傾けたことが無意味だったと知らされた時の気持ちをじつによく表しています。この気分が戦後社会の出発点に確実にあったことを太宰は見事に見抜いて表現しました。坂口安吾の『堕落論』『続堕落論』と合わせて読むと、面白い議論ができそうです。
②その後社会、特にジャーナリズムで喧伝されたさまざまな営いやスローガンがすべて空々しい虚妄としか思えないという感慨を、終戦直後の太宰自身は抱いていました。民主国家、文化国家、アメリカに見習え、新生日本・・・・・。
③主人公が情熱を傾けかけた時に「トカトントン」が聞こえる場面は、次の六つ。終戦の詔勅による死の決意、小説の執筆、勤労の神聖さ、恋愛、労働者のデモ行進、マラソン大会。しかし、すべてが外からの影響によって触発された事柄であって、自分から進んで選んだ意思決定ではないことに注意。小説の場合も、もともと太宰らしき作家の作品に長く親しんでいたというきっかけがありました。
唯一の例外は恋愛の場合で、これは勤めている郵便局の窓口にやってきた旅館の女中さんを自然に好きになります。実はこの場合だけは、「トカトントン」という釘打ちの音は、浜辺に二人して座っている時に、幻聴ではなく本当に聞こえてきたとあります。向こうが誘ってくれたのですが、実際には彼女が青年に好意を持っていたわけではなく、自分が定期的に大金を預けに来ることを青年が知っているので、そのことで変な誤解を受けては困ると思って、その秘密を明かして青年の口を封じるために誘ったのでした。
つまり、リアルなかたちで青年の幻想は打ち砕かれたのです。あることがらに情熱を傾けようと思ったときにおのずから白けがやってきて「トカトントン」が聞こえたというのではなく、自分の思い込みが、相手から実際にふられることで勘違いだったことを知らされたのでした。だからこそ、この場合の「トカトントン」は幻聴でなかったのでしょう。
④そこで、「作家」の返事の意味を考えてみます。ちなみに、これがなければこの作品は、戦後社会の上層に漂う虚妄の空気への気の利いたアイロニーだけで終わっていたかもしれません。
近年物故したある文芸批評家は、文学作品に対して奇抜な比喩を仲立ちにしながら社会的解釈を施すことを得意としていた人でしたが、彼がこの作品に触れて、最後の作家の返事は不必要だと唱えたことがあります。なぜ彼がそう言ったのかを私なりに想像してみると、いつもの方法論に従って、文学作品を社会的解釈のほうにことさら引っ張りたかったからなのでしょう。しかし私はそこだけに限定する読み方は不十分だと思います。この結末は不可欠なのです。
この作家の言葉は、青年が何一つ、自分から本気で(命をかけて)取り組んではいないことに関係しています。太宰は(ペンネームからして、堕罪をもじったと言われています)、自分を世間に顔向けのできない恥じ多き人生を送ってきたと常に考えていました。しかし同時に、自分が経てきた苦悩だけは本物だという自恃の念を抱いてもいました。
つまりは、この作品は、戦後の軽佻浮薄な世相の一部に現れた神経症的な傾向の形を借りて、ひそかに自分の魂に救われる余地があるかどうかを問いかけた作品なのだと解釈できます。「トカトントン」に悩まされる青年は、当然、太宰自身の一面でもあるわけです。自分の苦悩など、もしかしたらまだ救済に値しないものなのかもしれない。そう太宰は自問自答しているのです。
ちなみにここにも、他人のあり方の内面に、こっそり自分を忍び込ませる彼の文学的手法が躍如としています。傑作と言っていいと思います。
【小浜逸郎からのお知らせ】
●新刊『まだMMTを知らない貧困大国日本 新しい「学問のすゝめ」』(徳間書店)好評発売中。

https://amzn.to/2vdCwBj
●私と由紀草一氏が主宰する「思想塾・日曜会」の体制がかなり充実したものとなりました。
一度、以下のURLにアクセスしてみてください。
https://kohamaitsuo.wixsite.com/mysite-3
●『倫理の起源』(ポット出版)好評発売中。

https://www.amazon.co.jp/dp/486642009X/
●『日本語は哲学する言語である』(徳間書店)好評発売中。

http://amzn.asia/1Hzw5lL
●『福沢諭吉 しなやかな日本精神』(PHP新書)好評発売中。

http://amzn.asia/dtn4VCr
●長編小説の連載が完成しています。『ざわめきとささやき』
社会批判小説ですがロマンスもありますよ。
https://ameblo.jp/comikot/