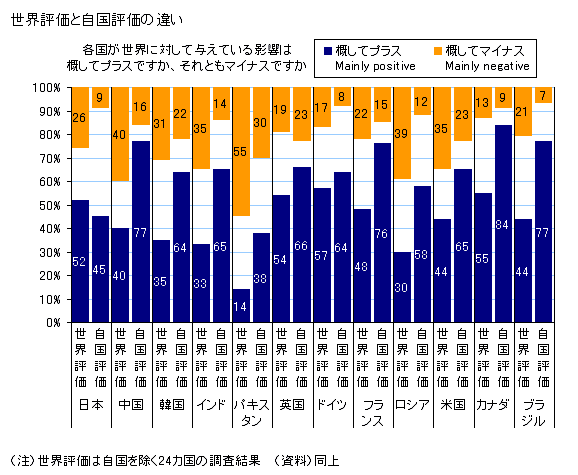日本語を哲学する14
第Ⅱ章 沈黙論

その昔、思想家の吉本隆明が、自らの言語論『言語にとって美とはなにか』を書き上げた後のある講演(「個体・国家・共同性としての人間」一九六八年)で、「沈黙の言語的意味」あるいは「大衆の沈黙の有意味性」を考えることの重要性を指摘していた。
また、ある論文(「沈黙の有意味性」一九六七年)で彼は次のようなことを指摘している。新約聖書に有名な挿話がある。イエスの弟子・ペテロが、群衆から「この人はイエスと一緒にいた」と言われ、それを三度否定する。するとそのとき鶏が鳴く。ペテロは、「あなたは鶏が時を告げる前に三度わたしを否むであろう」というイエスの予言が当たったことを知り、深く自らを苛む。もしここでペテロが「否」と言わずに黙っていたらイエスとともに十字架に架けられていたかもしれない。「沈黙はペテロの全存在とおなじ重さをもっている」……。
じつは、吉本のこの二つの指摘のうち、あとのほうについて私はおぼろげな記憶しかなく、出典を探したが見つからなかった。ところがこのたび偶然にも、詩人の北川透氏から『ひとり雑誌 KYO峡』第2号を恵送していただき、その中に探しあぐねていたくだりが引用されているのを知って、大いに驚いた。以上の記述も、ほとんど北川氏の文章からの孫引きである。氏にこの場を借りて深く感謝いたします。
沈黙の有意味性――この強調は、思想詩人・吉本が、一般の言語学のように、「現に表現されて定着してしまった言葉」だけを扱いうる対象としていたのでは、文学言語の価値の問題が扱えないという強い問題意識を抱いていたことの一つの証拠であろう。発語への思いの高まりとその高まりそのものの現実化(吉本言語論ではこれを「自己表出」と呼ぶ)が、外部の抵抗(音韻規則、統辞法、指示的な意味のひろがり、発話を規定する場面など)に出会い、その抵抗との闘争を通じて、一つの個性的な表出形態を獲得していく過程、そこにこそ、言語の「価値」の実相があらわれる。吉本はそう言いたかったに違いない。北川氏も概略この線に沿ってご自身の言語表現論を書き継がれる構えのようである。
沈黙に有意味性を認めることは、思想としてたいへん大きな意味をもっている。しかし残念ながら吉本自身は、その後このテーマについて追究を続けた形跡がほとんどないように思う(どなたか知っていたらご教示ください)。なお彼の先ほどの二つの指摘のうち、前者の問題、つまり「大衆の沈黙の有意味性」に関しては、彼の言語論の主たる関心対象であった「書き言葉芸術としての文学表現」とは論理を進める枠組み(範疇)が異なり、主として日常世界における言語行為が問題となるはずである(まったく無関係とは言わないが)。しかもこの場合は、講演タイトルを見てもわかるように、生活と政治との関係における言語行為としての「沈黙」に焦点が当てられている。大衆が国家権力の指令に黙々と従ったり、知識人がいくら理想的な思想を説いても「笛吹けど踊らず」の態度をしばしば示すのはなぜか、というように。
ところで私自身は、これまで説いてきたところから明らかなごとく、日常生活者の言葉のやりとりの現場にこそ、言語問題の核心も現れると考えているので、吉本の「大衆の沈黙の有意味性」という言葉を、そういう問題意識に引き寄せたいと思う。もちろんこれは、けっして文学言語を軽視するという意味ではない。文学言語は、哲学言語、法言語などと同じように、またそれぞれ違った仕方で、生活のなかで行われている言語行為から立ち上がり醸成され洗練されたところに現れる「結晶形態」なのである。
日常生活における沈黙の有意味性という概念には、どんな意味と広がりとがはらまれているのか。ここでは、できるかぎりこの問いに応える試みに踏み込んでみようと思う。
これまで私たちは、聞いたり読んだり理解したりすることもふくめて、言語行為であると考えてきた。というよりも、時枝が鋭く見抜いたように、発話者がある場面を前にして素材を概念にまで構成し、それを「話し(書き)」、受話者が自分にとっての場面においてそれを「聞き(読み)」、さらに概念として理解しつつ納得するという、一連の過程(やり取り)そのものが言語行為である。言語行為とは、それぞれの「自己」を投企しあう関係行為である。
したがって、ある人が相手の話を聞くために黙っているという態度をとっていることそのものが、それだけで言語行為を行っていることを意味する。
しかし、前章でも述べたとおり、じつは単に人の話を聴くという機能を果たすために黙っているという態度だけが言語行為であるのではない。人と人とが具体的にかかわっているあらゆる場面で、そのなかのメンバーがさまざまな理由によって黙っているとき、それはすべて一種の言語行為なのである。なぜなら、それらの「沈黙」という様態は、そこにかかわる他者たちに必ずひとつの言語的な「意味」として受け取られるからである。発話をプラスの言語行為とすれば、いわば沈黙とは、マイナスの言語行為である(この「マイナス」という言葉には、価値的な意味を込めていない)。
私たちは、じっさいの言語活動において、多様な形態の「沈黙」をさしはさみ、その「沈黙」の時間と内実とを包含させることによって、総体として、言語活動を行っているとみなすべきである。
このことを示す最もわかりやすい例は、小説における会話表現において、しばしば「……」という表記がなされることである。
「……」とはいったい何か。沈黙それ自体が言語としての意味や価値を何ももたないなら、作家はそんな余計な表記を挿入せず、削ってしまえばよいはずである。しかし作家は削らない。必要不可欠なものとして挿入するのである。
「……」は、相手の発語に対して、返す言葉がなかったということであり、その返す言葉がなかったという事実には、ちょうど、数学において負数や虚数の存在が意味をもっているのと同じように、「言語的な意味」があるのだ。ではそれはどんな意味だろうか。
それは「内語」か、または「内語」にまで構成されることの叶わないさまざまな「思い」であり、「情」である、と簡単に言って済ませることも不可能ではない。しかしこれでは、言語論に限定しただけでも豊かな結論を得たとは言えないし、まして、人間論として「沈黙」や「無言」について何かがわかったとは、到底考えられない。
ここでは、一つの例だけを挙げたが、じつは、たったいま指摘したように、「沈黙」という事態には、まことに多様な意味や価値が含まれている。そして後に示すように、本当をいえば、その意味や価値が何であるかをきちんと探るには、「言語」的な意味という概念の枠内だけで問題とするのでは不十分なのである。そこでまず、「沈黙」という事態には、どんな質的な違いを持った形態がありうるのかを網羅し、その一つひとつの内実について分析してみるのでなくてはならない。とりあえずそれらの形態を列挙してみよう。
【言葉が出されない事態の諸形態】
①聴覚障害者であるための機能不全
②自閉症児のコミュニケーション失調
③統合失調症患者、うつ病患者など、精神病者にしばしばみられる緘黙
④脳の器質的損傷による失語
⑤吃音障害などによるためらいから習慣化してしまう無口
⑥寡黙で事足りる人(話が苦手、あまり必要と感じない、おしゃべりが好きじゃない、など)
⑦人の話をきいたり、本を黙読しながら、感じたり考えたりしている時
⑧現実場面における発語の断念(選択による沈黙)
⑨文学作品における意識的な言葉の捨象
およそこんなところであろうか。本稿では、これらすべてに対して均等な目配りをすることはできない。「言語」一般を思想的にとらえることにとって、「⑧現実場面における発語の断念(選択による沈黙)」の意味を掘り下げることが最も重要と考えるからである。しかしそこに至る前に、それぞれの形態の意味をざっと考察しておこう。
①聴覚障害者であるための機能不全
これについては、前章でやや詳しく論じたので、多くを述べる必要はないだろう。言うまでもなく、聴覚障害者どうしが、発声をほとんどしていなくても、活発な手話を交わしている場合には、彼らは「沈黙」しているのではない。しかし、その場合でも、その手話言語の交換の世界のなかに、健聴者における一般的な「沈黙」と同一の事態が出現していることは疑いない。
ここでの「機能不全」とは、健聴者の集団に参加しながら、言葉をよく聞き取れないために実質的にはコミュニケーションが成り立っていない状態を指している。
②自閉症児のコミュニケーション失調
自閉症児の言語発達の遅れは、基本的な障害の結果であって、原因ではない。早期自閉症の研究者、マイケル・ラターは、自閉症の本質を言語的な認識の発達における障害とみなしたが、この説には納得できない。なぜなら、早期自閉症と診断される幼児は、言語を言語として曲がりなりにも駆使できるようになる二、三歳に達するはるか以前に、言語生活以外の多くの側面で、ふつうの子どもとはどこか異なる特徴を示すことが、今日ではよく観察されているからである(もっとも後述するように、これは、親が子どもの言語発達の遅れに気づいて臨床家のもとを訪れてから、問診の過程で乳児期の状況を思い出すという契機を通してである場合が多いとされている。親自身が誕生直後から気づくのは、感情的理由からしてなかなか困難であるらしい)。
ふつうの子どもは、生後間もなく母親の声を聞き分け(じつはすでに胎児期から漠然と聞き分けていることが実証されている)、母親の接近に喜びと興奮の表情を表わし、また母親の微笑に微笑をもって答えたり、好んで視線を合わせたりする。しかし、早期自閉症と診断される幼児には、乳児期のこうした行動を欠く例が多いと言われている。また、言葉は発しても多くの場合、「対話」として成立していず、単なるオウム返しであったり、養育者の手などを「情のこもった人間の手」とみなさずに、ただの「そこにあるクレーン」として利用したりする。また、厳密な自然規則や機械的な原理に従うもの、時計とか、カレンダーの数字とか、おもちゃの車輪などに異様な執着を示すことも多い。曖昧なもの、見えないがはたらきとしては人間関係にとって不可欠なもの、端的に言えば、他者の「心の表現」と呼ばれるものには、関心を示さなかったり、逃げの姿勢を示したりする。
なお、こうした特徴は、一九四〇年代に「早期幼児自閉症」の概念を初めて確立したレオ・カナーの周到かつ抑制の効いた症例研究ですでに示唆されていることである。
レオ・カナー

カナーの研究が周到で抑制が効いているというのは、症例から安易に「病因」への推論を行っていないという点である。
これに対して同時代のブルーノ・ベッテルハイムは、精神分析学的な観点から、主として乳児に対する養育者の対応のあり方、つまり後天的、経験的、環境的なあり方に「原因」を求める論理に傾いている。しかし、かなり過酷な環境におかれた乳幼児でも、自閉症的な症状を見せずに発達していく多くの例が存在することを考えれば、このベッテルハイムの「病因論」も納得しがたい。簡単に言えば、単純に養育者や養育環境のせいに帰するわけにもいかない。
生後まもなくの時点から、この子はおとなしくて親のかかわりにふさわしい反応を示さないどこか変わったところがあった、という感知は、後に自閉症と診断される子どもたちにかなり普遍的に見られる現象である。しかしこの感知はしばしば曖昧である。多くの親は、当然、自分の子どもが異状を示しているということを直視したがらないものであるから、それを深刻に問題にしないまま、二、三年をやり過ごしてしまうという傾向が強い。そのため、言葉の発達の遅れに気づいた時には、「手遅れ」に近い状態になっているケースも見られるという。したがって、初発の「異状」を放置することで進行を助長し、そのために言語的なかかわりをうまく結べないような関係が固定化してしまうという可能性は考えられるが、そのことを「病因」とみなすことはできない。
そこで現在では、これらの「異状」の「原因」を脳の器質的損傷に求める説が有力視されている。しかし、そういう明瞭な器質的損傷の存在は、機能局在論的な脳科学によっては実証されていないし、そもそも、一義的な「原因」を唯物論的に確定しようとする発想そのものを疑ってみる必要もあるだろう。人間はもともと生物としては多様な偏差と変異をもってこの世に生まれてくるのであり、ある偏差や変異を、「病気」とか「障害」という概念によって切り取り、分節しようとする志向それ自体が、社会的存在として生きなくてはならないという私たち自身の当為や関心から発したものだからである。
だがまた逆に、こういったからと言って、その「異状」の感知を、「病気や障害ではない」などと楽天視することもできない。なぜなら、私たちの大部分が、自分たちは社会存在であるべきだという動かしがたい自己了解をもち、じっさいその自己了解にしたがって文化や社会のシステムを作ってきたのであって、この歴史を、いまさらないものとすることは不可能だからである。歴史はまさに歴史として、常にそのつど、いま・ここに現前しているのだ。
なお、自閉症に関する以上の記述には、精神科医・滝川一廣氏の諸論考に負うところが大きい。この場を借りて滝川氏に感謝します。
自閉症児のコミュニケーション失調の「意味」について現在言えることは限定される。私の推定では、それは、言語活動に先立つ「情緒」的なかかわりの不全を本質としており、養育者との身体接触(肌の触れ合い)や音声のかけあいのもつ人間的な「情緒」の意味を、十分に人間的な「情緒」の意味として受け取れない状態を指している。そして、この推定からさらに次のことが推論される。すなわち、自閉症に関して、「そういえば生まれた時からこの子は何となく変だった」という「異状」が見いだされる事実そのものが、言語活動は言語に「先立つ」情緒的な交流によって支えられるのであって、その逆ではないということを示唆しているのである。
言い換えるなら、やがて言語健常者として育つべきプログラムを内蔵させて生まれてきた乳児に対して、養育者がそうなるべき存在として適切な情緒的扱いを施すことが、いかに大切な意義をもつかということである。乳児の未熟な前言語的表現(泣く、むずかる、微笑みのような表情を示す、抱擁を求める、身体を一定の仕方で動かす、視線を合わせる、喃語を発する、など)を、養育者は、言語存在としての人間に成っていく準備態勢として受け止めるのでなくてはならない。予定された生得的なプログラムを、プログラム通りに解発せしめるのは、養育者と乳児との前言語的、情緒的なやり取りそのものなのである。
第Ⅱ章 沈黙論

その昔、思想家の吉本隆明が、自らの言語論『言語にとって美とはなにか』を書き上げた後のある講演(「個体・国家・共同性としての人間」一九六八年)で、「沈黙の言語的意味」あるいは「大衆の沈黙の有意味性」を考えることの重要性を指摘していた。
また、ある論文(「沈黙の有意味性」一九六七年)で彼は次のようなことを指摘している。新約聖書に有名な挿話がある。イエスの弟子・ペテロが、群衆から「この人はイエスと一緒にいた」と言われ、それを三度否定する。するとそのとき鶏が鳴く。ペテロは、「あなたは鶏が時を告げる前に三度わたしを否むであろう」というイエスの予言が当たったことを知り、深く自らを苛む。もしここでペテロが「否」と言わずに黙っていたらイエスとともに十字架に架けられていたかもしれない。「沈黙はペテロの全存在とおなじ重さをもっている」……。
じつは、吉本のこの二つの指摘のうち、あとのほうについて私はおぼろげな記憶しかなく、出典を探したが見つからなかった。ところがこのたび偶然にも、詩人の北川透氏から『ひとり雑誌 KYO峡』第2号を恵送していただき、その中に探しあぐねていたくだりが引用されているのを知って、大いに驚いた。以上の記述も、ほとんど北川氏の文章からの孫引きである。氏にこの場を借りて深く感謝いたします。
沈黙の有意味性――この強調は、思想詩人・吉本が、一般の言語学のように、「現に表現されて定着してしまった言葉」だけを扱いうる対象としていたのでは、文学言語の価値の問題が扱えないという強い問題意識を抱いていたことの一つの証拠であろう。発語への思いの高まりとその高まりそのものの現実化(吉本言語論ではこれを「自己表出」と呼ぶ)が、外部の抵抗(音韻規則、統辞法、指示的な意味のひろがり、発話を規定する場面など)に出会い、その抵抗との闘争を通じて、一つの個性的な表出形態を獲得していく過程、そこにこそ、言語の「価値」の実相があらわれる。吉本はそう言いたかったに違いない。北川氏も概略この線に沿ってご自身の言語表現論を書き継がれる構えのようである。
沈黙に有意味性を認めることは、思想としてたいへん大きな意味をもっている。しかし残念ながら吉本自身は、その後このテーマについて追究を続けた形跡がほとんどないように思う(どなたか知っていたらご教示ください)。なお彼の先ほどの二つの指摘のうち、前者の問題、つまり「大衆の沈黙の有意味性」に関しては、彼の言語論の主たる関心対象であった「書き言葉芸術としての文学表現」とは論理を進める枠組み(範疇)が異なり、主として日常世界における言語行為が問題となるはずである(まったく無関係とは言わないが)。しかもこの場合は、講演タイトルを見てもわかるように、生活と政治との関係における言語行為としての「沈黙」に焦点が当てられている。大衆が国家権力の指令に黙々と従ったり、知識人がいくら理想的な思想を説いても「笛吹けど踊らず」の態度をしばしば示すのはなぜか、というように。
ところで私自身は、これまで説いてきたところから明らかなごとく、日常生活者の言葉のやりとりの現場にこそ、言語問題の核心も現れると考えているので、吉本の「大衆の沈黙の有意味性」という言葉を、そういう問題意識に引き寄せたいと思う。もちろんこれは、けっして文学言語を軽視するという意味ではない。文学言語は、哲学言語、法言語などと同じように、またそれぞれ違った仕方で、生活のなかで行われている言語行為から立ち上がり醸成され洗練されたところに現れる「結晶形態」なのである。
日常生活における沈黙の有意味性という概念には、どんな意味と広がりとがはらまれているのか。ここでは、できるかぎりこの問いに応える試みに踏み込んでみようと思う。
これまで私たちは、聞いたり読んだり理解したりすることもふくめて、言語行為であると考えてきた。というよりも、時枝が鋭く見抜いたように、発話者がある場面を前にして素材を概念にまで構成し、それを「話し(書き)」、受話者が自分にとっての場面においてそれを「聞き(読み)」、さらに概念として理解しつつ納得するという、一連の過程(やり取り)そのものが言語行為である。言語行為とは、それぞれの「自己」を投企しあう関係行為である。
したがって、ある人が相手の話を聞くために黙っているという態度をとっていることそのものが、それだけで言語行為を行っていることを意味する。
しかし、前章でも述べたとおり、じつは単に人の話を聴くという機能を果たすために黙っているという態度だけが言語行為であるのではない。人と人とが具体的にかかわっているあらゆる場面で、そのなかのメンバーがさまざまな理由によって黙っているとき、それはすべて一種の言語行為なのである。なぜなら、それらの「沈黙」という様態は、そこにかかわる他者たちに必ずひとつの言語的な「意味」として受け取られるからである。発話をプラスの言語行為とすれば、いわば沈黙とは、マイナスの言語行為である(この「マイナス」という言葉には、価値的な意味を込めていない)。
私たちは、じっさいの言語活動において、多様な形態の「沈黙」をさしはさみ、その「沈黙」の時間と内実とを包含させることによって、総体として、言語活動を行っているとみなすべきである。
このことを示す最もわかりやすい例は、小説における会話表現において、しばしば「……」という表記がなされることである。
「……」とはいったい何か。沈黙それ自体が言語としての意味や価値を何ももたないなら、作家はそんな余計な表記を挿入せず、削ってしまえばよいはずである。しかし作家は削らない。必要不可欠なものとして挿入するのである。
「……」は、相手の発語に対して、返す言葉がなかったということであり、その返す言葉がなかったという事実には、ちょうど、数学において負数や虚数の存在が意味をもっているのと同じように、「言語的な意味」があるのだ。ではそれはどんな意味だろうか。
それは「内語」か、または「内語」にまで構成されることの叶わないさまざまな「思い」であり、「情」である、と簡単に言って済ませることも不可能ではない。しかしこれでは、言語論に限定しただけでも豊かな結論を得たとは言えないし、まして、人間論として「沈黙」や「無言」について何かがわかったとは、到底考えられない。
ここでは、一つの例だけを挙げたが、じつは、たったいま指摘したように、「沈黙」という事態には、まことに多様な意味や価値が含まれている。そして後に示すように、本当をいえば、その意味や価値が何であるかをきちんと探るには、「言語」的な意味という概念の枠内だけで問題とするのでは不十分なのである。そこでまず、「沈黙」という事態には、どんな質的な違いを持った形態がありうるのかを網羅し、その一つひとつの内実について分析してみるのでなくてはならない。とりあえずそれらの形態を列挙してみよう。
【言葉が出されない事態の諸形態】
①聴覚障害者であるための機能不全
②自閉症児のコミュニケーション失調
③統合失調症患者、うつ病患者など、精神病者にしばしばみられる緘黙
④脳の器質的損傷による失語
⑤吃音障害などによるためらいから習慣化してしまう無口
⑥寡黙で事足りる人(話が苦手、あまり必要と感じない、おしゃべりが好きじゃない、など)
⑦人の話をきいたり、本を黙読しながら、感じたり考えたりしている時
⑧現実場面における発語の断念(選択による沈黙)
⑨文学作品における意識的な言葉の捨象
およそこんなところであろうか。本稿では、これらすべてに対して均等な目配りをすることはできない。「言語」一般を思想的にとらえることにとって、「⑧現実場面における発語の断念(選択による沈黙)」の意味を掘り下げることが最も重要と考えるからである。しかしそこに至る前に、それぞれの形態の意味をざっと考察しておこう。
①聴覚障害者であるための機能不全
これについては、前章でやや詳しく論じたので、多くを述べる必要はないだろう。言うまでもなく、聴覚障害者どうしが、発声をほとんどしていなくても、活発な手話を交わしている場合には、彼らは「沈黙」しているのではない。しかし、その場合でも、その手話言語の交換の世界のなかに、健聴者における一般的な「沈黙」と同一の事態が出現していることは疑いない。
ここでの「機能不全」とは、健聴者の集団に参加しながら、言葉をよく聞き取れないために実質的にはコミュニケーションが成り立っていない状態を指している。
②自閉症児のコミュニケーション失調
自閉症児の言語発達の遅れは、基本的な障害の結果であって、原因ではない。早期自閉症の研究者、マイケル・ラターは、自閉症の本質を言語的な認識の発達における障害とみなしたが、この説には納得できない。なぜなら、早期自閉症と診断される幼児は、言語を言語として曲がりなりにも駆使できるようになる二、三歳に達するはるか以前に、言語生活以外の多くの側面で、ふつうの子どもとはどこか異なる特徴を示すことが、今日ではよく観察されているからである(もっとも後述するように、これは、親が子どもの言語発達の遅れに気づいて臨床家のもとを訪れてから、問診の過程で乳児期の状況を思い出すという契機を通してである場合が多いとされている。親自身が誕生直後から気づくのは、感情的理由からしてなかなか困難であるらしい)。
ふつうの子どもは、生後間もなく母親の声を聞き分け(じつはすでに胎児期から漠然と聞き分けていることが実証されている)、母親の接近に喜びと興奮の表情を表わし、また母親の微笑に微笑をもって答えたり、好んで視線を合わせたりする。しかし、早期自閉症と診断される幼児には、乳児期のこうした行動を欠く例が多いと言われている。また、言葉は発しても多くの場合、「対話」として成立していず、単なるオウム返しであったり、養育者の手などを「情のこもった人間の手」とみなさずに、ただの「そこにあるクレーン」として利用したりする。また、厳密な自然規則や機械的な原理に従うもの、時計とか、カレンダーの数字とか、おもちゃの車輪などに異様な執着を示すことも多い。曖昧なもの、見えないがはたらきとしては人間関係にとって不可欠なもの、端的に言えば、他者の「心の表現」と呼ばれるものには、関心を示さなかったり、逃げの姿勢を示したりする。
なお、こうした特徴は、一九四〇年代に「早期幼児自閉症」の概念を初めて確立したレオ・カナーの周到かつ抑制の効いた症例研究ですでに示唆されていることである。
レオ・カナー

カナーの研究が周到で抑制が効いているというのは、症例から安易に「病因」への推論を行っていないという点である。
これに対して同時代のブルーノ・ベッテルハイムは、精神分析学的な観点から、主として乳児に対する養育者の対応のあり方、つまり後天的、経験的、環境的なあり方に「原因」を求める論理に傾いている。しかし、かなり過酷な環境におかれた乳幼児でも、自閉症的な症状を見せずに発達していく多くの例が存在することを考えれば、このベッテルハイムの「病因論」も納得しがたい。簡単に言えば、単純に養育者や養育環境のせいに帰するわけにもいかない。
生後まもなくの時点から、この子はおとなしくて親のかかわりにふさわしい反応を示さないどこか変わったところがあった、という感知は、後に自閉症と診断される子どもたちにかなり普遍的に見られる現象である。しかしこの感知はしばしば曖昧である。多くの親は、当然、自分の子どもが異状を示しているということを直視したがらないものであるから、それを深刻に問題にしないまま、二、三年をやり過ごしてしまうという傾向が強い。そのため、言葉の発達の遅れに気づいた時には、「手遅れ」に近い状態になっているケースも見られるという。したがって、初発の「異状」を放置することで進行を助長し、そのために言語的なかかわりをうまく結べないような関係が固定化してしまうという可能性は考えられるが、そのことを「病因」とみなすことはできない。
そこで現在では、これらの「異状」の「原因」を脳の器質的損傷に求める説が有力視されている。しかし、そういう明瞭な器質的損傷の存在は、機能局在論的な脳科学によっては実証されていないし、そもそも、一義的な「原因」を唯物論的に確定しようとする発想そのものを疑ってみる必要もあるだろう。人間はもともと生物としては多様な偏差と変異をもってこの世に生まれてくるのであり、ある偏差や変異を、「病気」とか「障害」という概念によって切り取り、分節しようとする志向それ自体が、社会的存在として生きなくてはならないという私たち自身の当為や関心から発したものだからである。
だがまた逆に、こういったからと言って、その「異状」の感知を、「病気や障害ではない」などと楽天視することもできない。なぜなら、私たちの大部分が、自分たちは社会存在であるべきだという動かしがたい自己了解をもち、じっさいその自己了解にしたがって文化や社会のシステムを作ってきたのであって、この歴史を、いまさらないものとすることは不可能だからである。歴史はまさに歴史として、常にそのつど、いま・ここに現前しているのだ。
なお、自閉症に関する以上の記述には、精神科医・滝川一廣氏の諸論考に負うところが大きい。この場を借りて滝川氏に感謝します。
自閉症児のコミュニケーション失調の「意味」について現在言えることは限定される。私の推定では、それは、言語活動に先立つ「情緒」的なかかわりの不全を本質としており、養育者との身体接触(肌の触れ合い)や音声のかけあいのもつ人間的な「情緒」の意味を、十分に人間的な「情緒」の意味として受け取れない状態を指している。そして、この推定からさらに次のことが推論される。すなわち、自閉症に関して、「そういえば生まれた時からこの子は何となく変だった」という「異状」が見いだされる事実そのものが、言語活動は言語に「先立つ」情緒的な交流によって支えられるのであって、その逆ではないということを示唆しているのである。
言い換えるなら、やがて言語健常者として育つべきプログラムを内蔵させて生まれてきた乳児に対して、養育者がそうなるべき存在として適切な情緒的扱いを施すことが、いかに大切な意義をもつかということである。乳児の未熟な前言語的表現(泣く、むずかる、微笑みのような表情を示す、抱擁を求める、身体を一定の仕方で動かす、視線を合わせる、喃語を発する、など)を、養育者は、言語存在としての人間に成っていく準備態勢として受け止めるのでなくてはならない。予定された生得的なプログラムを、プログラム通りに解発せしめるのは、養育者と乳児との前言語的、情緒的なやり取りそのものなのである。