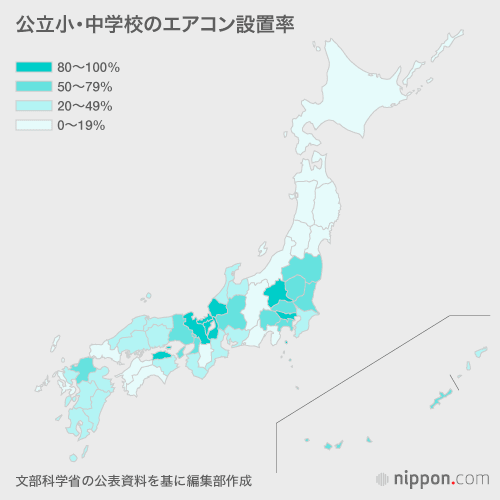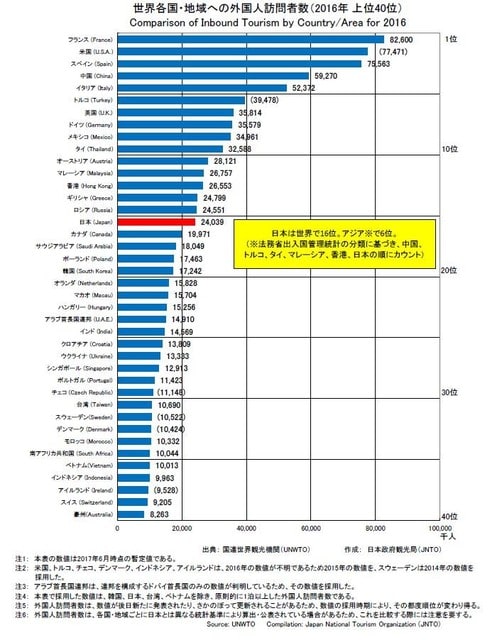あらすじを続けます。
あらすじを続けます。
翔太は施設に入れられ、そこから学校に通うことに。
ゆりは両親の下へ。母親は相変わらずゆりに冷たく、化粧中にゆりが頬を触ってしまうと、「痛ッ!」と言って「ごめんなさいは!」と強く繰り返します。
ゆりは答えません。
頬の傷は明らかに夫の仕業です。
その後すぐ母親は「お洋服買ってあげようか」と懐柔にかかりますが、ゆりは首を横に振ります。
施設から一日外出してきた翔太は、アパート住まいをしている治を訪ねます。
川べりで、翔太がかつて盗んだ高価な釣り竿二本で「父子」は釣りを楽しみます。
治はこの釣り竿を売るつもりでしたが、釣り好きの翔太の希望を受け入れてそのままになっていたのでした。
そのあと、二人は拘置所の信代と面会します。
信代は死体遺棄と誘拐の罪を一人で背負って明るくたくましい調子で二人に接します。
すまながる治に、「いいって。お釣りがくるくらいだよ。あんた前科があるじゃないの。五年は食らうよ」と突き放します。
信代は誘拐容疑も背負うつもりなのです。
翔太に対しては、「あんたを見つけたのはね、パチンコ屋の駐車場。車はビッツ(?)、番号は習志野。本当の両親、その気で探せば見つかるかも知ないよ」と屈託なく情報を伝えます。
治は少し焦り、「そんなこと言うために翔太を呼んだのか」。
「そうよ。私たちではもう無理よ」と信代。
その夜、治と翔太は治のアパートで食事をします。
治がかつてうまい食い方として教えたカップ麺にコロッケ。
翔太は許されていない外泊をすることになり、食後、二人で雪だるまを作ります。
冒頭の場面でコロッケを買った時も冬でしたから、ほぼ一年経ったことがわかります。
およそ一年間の「家族劇」なのでした。
せんべい布団で背中合わせに寝る二人。
「もう『おじさん』でいいよ」と治。
「うん」と翔太。
「僕と別れるつもりだったの」と翔太。
しばらく沈黙した後、「うん」と治。
これは夜逃げの時の心境とはおそらく違っていたでしょう。
でも治は「そんなつもりじゃなかった」とは抗弁しませんでした。
夜が明けて施設に帰る翔太と見送りの治。
バスがやってくる寸前に翔太がぽつりと「ぼく、わざと逃げたんだ」とつぶやきます。
わかってる、わかってるという表情の治。
バスに乗り込んだ翔太を治は追いかけますが、翔太は気張ってなかなか振り向こうとしません。
しかしとうとう振り向いてじっと後ろを見つめます。
ゆりはアパートの通路で、ひとり数え歌をうたいながら破片のようなものをガラス瓶に入れています。
この歌はおそらく初枝に教わったのでしょう。
それから台の上に載って、外をじっと見つめます……。
このラストシーンは、まるで賽の河原で石を積んでいる子どものようです。
「鬼」はやはり壊しに来るのでしょうか。
翔太は生きる希望を暗示させて去っていきますが、ゆりのこの姿には、何とも救いようのないものを感じさせます。
さて長々と筋を追ってきたのですが、この作品に、現代家族の荒廃に対する批判を読み込んだり、血のつながりよりも愛情といった図式的メッセージを読み込んだりするのは、つまらない鑑賞の仕方です。
まずは作品そのものがテクニカルな意味でいかに優れているかを挙げてみましょう。
それを知っていただくためにも、詳しく筋を追いかける必要があったのです。
まず、小道具を中心とした多くの伏線が張ってあって、それらが見事に生きています。
治が初めてフェンス越しにゆりに差し出すコロッケ。これは最後に翔太と食べる場面にそ
のままつながります。
「仕事」の帰りにコロッケを買う時に治が翔太にする、一発でガラスを割れるハンマーの話。これは車のガラスを割る治に同調しない翔太のためらいにつながっています。
スーパーで水着をあてがわれた時のゆりの恐怖や、お風呂での信代とゆりの傷の見せ合いや、万引きした釣り竿が後に重要な意味を持つことについてはすでに述べました。
また前には述べませんでしたが、翔太は国語の教科書に載っていた「スイミー」の話に強く惹きつけられています。
これは翔太の、広い世界への憧れと、力を合わせて大きな敵を追い払う弱者たちへの共感を表現しているでしょう。
解雇された後の信代の妙にセクシーな下着姿とそれを目のやり場に困るようにちらちら見る治。
この後すぐ信代が半ば強引にセックスを求めるのですが、これは仕事の拘束からの解放感を表しているでしょう。
音だけしか聞こえない隅田川の花火大会を六人揃って縁先から見上げるシーン。
直後にズームがぐっと引かれてこの家がビルに囲まれて孤立している様子が強調されますが、しかし逆にこのとき「家族」の絆が海水浴のシーンと同じように象徴的に表現されます。
また、ゆりが髪を短くして名前をりんと変えさせられたとき、亜紀がりんと一緒に鏡に映りながら、「お姉ちゃんももう一つ名前を持っているんだ」と言い、りんが「なんていうの」と聞くと「さやか」と源氏名を答えます。
するとりんは「りんのがいい」とはっきり言います。
まるで愛情の虚実をわきまえているかのように。
新しい名前が与えられるということは、自分が新しい共同性の中でアイデンティティを得たという重要な意味を持っています。
幼いゆり(りん)はこの時、この「家族」の一員であることをついに自覚したのです。
鏡に映った自分をうれしそうに「柴田家」のメンバーとして自己承認する「りん」でした。
さりげなくその事実を示す是枝監督の演出は心憎いの一言に尽きます。
しかしすでに述べたように、何と言っても伏線として決定的なのは、「やまとや」の親父さんの「妹にはさせるなよ」というひとことでしょう。
ここを起点として、この「疑似家族」は「失楽園」への道を歩み始めるのですから。
じつはこの後しばらくして、翔太とりんがもう一度「やまとや」を訪ねるシーンがあります。
ところが入り口には「忌中」と張り紙があり、扉が閉まっています。
「お休み?」とりんが聞くのですが、翔太は答えません。
何かを悟ったようです。
翔太はきちんとお金を払うつもりだったのかもしれません。
しかしそれはかなわず、この世の掟を優しく暗示してくれた親父さんとの別離が、翔太の倫理観をいっそう育てることになったのだと考えられます。
これまで筆者は、治と翔太が万引きを常習としていたり、初枝が金目当てに毎月亡夫の息子の家に金をせびりに行っていたり、夫婦が初枝の遺体を埋めることに大してためらいを感じていなかったり、初枝の死後、信代が年金を平気で引き出していたりすることに、何らかの判断を示してきませんでした。
それには理由があります。
この作品は、たくましく明るく生きようとする庶民の生活を描いてはいますが、貧困の惨めさのようなものはまったく感じられません。
やっていることは反社会的なのですが、そのどれもが、家族の絆をむしろ強める方向に作用しています。
破綻をきたすまでは、だんだんみんなの幸福感が増していくと書いた所以です。
家族とはエロス(情緒)によって結びついて日常生活を共有する集団です。
その共同性の内部では、法社会の約束に反することでも、情緒を支える物語が成立していさえすれば、維持することが可能なのです。
家族は個別的な宗教集団と言ってもいいかもしれません。
この家族の場合、その教義の中心は「万引き」でした。
また治と信代を強く結びつけてきたのが「殺人」であったという事実も付け加える必要があるでしょう。
現代日本を舞台にした映画という枠組みの中ではなかなか気づかないかもしれませんが、法的なルールに反することで家族的な共同性の絆を維持するというあり方は、歴史に思いをはせればさほど珍しいことではありません。
山賊一家、マフィア、現代でもロマ(ジプシー)などいくらでも見つかります。
あるいは昔の遊牧民などは、土地所有や私的所有の観念が希薄ですから、今でなら犯罪と見なされることも平気で行っていたでしょうし、仲間が死ねば彼ら固有のやり方で埋葬していたでしょう。
つまり、エロス(情緒)を絆として結びついた集団は、近代法の支配する社会などよりもはるかに時間性をはらんでいるのです。
『万引き家族』の成員たちは、家族の持つそうした原始性を保存していたのであり、しかも情緒が醸し出す限りでの「人倫性」はしっかりと確保しています。
だれもが互いに対して温かく、特に幼い新参者のゆりには限りなく愛情を注いでいるのですから。
しかし近代社会のルールが自分自身と接触する限りで、そういう人倫性を認めないのは当然です。
存在に気づくことすらないでしょう。
筆者はこの映画を見て、四十年近く前に起きた千石剛賢をリーダーとする「イエスの方舟」を思い出しました。
マスコミの誤解と激しいバッシングによって漂流を余儀なくされたこの教団は、主に家庭的悩みを抱えた若い女性たちを信徒とする小さな情緒的共同体でした。
彼らはじつに真面目な人たちであり、反社会的な行動すら何一つ起こしていません。
マスコミを中心に法社会の「正義」を振りかざす風潮が強まっていますが、もちろん是枝監督は、それを告発する意図などをもってこの映画を作ったのではないでしょう。
監督の意図を忖度することはできませんし、またその必要もありませんが、筆者自身は、この作品は、擬似家族解体の物語であるよりもむしろ、逆説的な家族創造の物語であると考えます。
しかしあらゆる家族は歴史的社会的条件を背負う中で生まれ、その営みを続けますから、ゼロから家族を創造することはできません。
そうかといってありきたりの血縁家族をもってきたのでは創造は果たせない。
そこで一般社会の原理(理性)とは根本的に異なる原理を持つ家族の共同性を際立たせるために、法的には軽犯罪である万引きという絆=教義を出発点に置いたのではないでしょうか。
しかしこの一種の「実験」を長期間にわたって続けるのが不可能であることは、監督の中ではもちろん織り込み済みでした。
渡辺京二氏はかつて「人は必ず共同性に飢える存在である」と述べました。
その飢えが表出される源は、エロスであり情緒なのです。
初めにこの作品を傑作と評しましたが、あえて難を言えば、限られた時間の中にカットを詰め込み過ぎている点でしょうか。
シーンが次々に移りゆくので、一つ一つのカットにはすべて背景があることが一見したところではわかりにくいかもしれません。
しかし逆にこのことは、作品の文学性の高さを示すものともなっています。
説明的部分を極力省いて映像と切り詰められたセリフの展開だけで見せる手法は、この監督の得意とするところでしょうが、おそらく二度、三度と見るうちにその味わい深さがしみとおってくると確信します。
映画が終わって出口に向かった時、二人のお年寄り(私と同年齢くらいか)が、「なんだかよくわかんねえな」とつぶやいているのを耳にしました。映画というものは一般大衆向けに劇場で上映されるということを制約条件としているので、その意味では、劇場向きではなく、DVDなどで一人じっくりと鑑賞するのに適した作品かと思います。
(映画を一度しか見ていないため、セリフその他細かい点で誤りを犯している可能性があります。平にご容赦ください。)