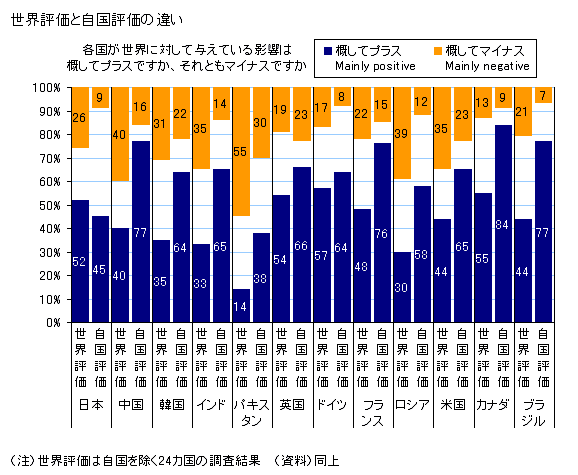「自由・平等・人権・民主主義」とハサミは使いよう(その2)

最後に、最も濫用されている「民主主義」という言葉について触れましょう。自分の立場を正当化し敵対する立場を論難するために、この言葉を盾にしない政治言論は、右から左までほとんどないといってよいくらいです。つまり「民主主義」は現代社会では神聖な葵の印籠と化しているわけですが、しかしそうなると、インフレと同じで、その言葉の価値がどんどん下がってしまいます。どの体制、どの思想が「本当の民主主義」に値するか、まあ、そういう旗の奪い合い、正統争いをやっている光景ですね。
もちろん、この事態に深い疑いを持ち、早くから「民主主義国家」「民主政治」「民主憲法」などの概念を原理的なレベルで批判している数少ない人たちもいます。私はこの人たちを尊敬しています。民主主義はいま、その内的な必然からして、衆愚政治(いわゆるポピュリズム)に堕していく傾向が大いに顕在化しています。そうした状況のなかでは、こうした思想的営みはぜひ必要なことです。というのもこの傾向は、時々の社会経済的条件いかんによって、その急激な危機克服の手段としての全体主義へ結びついていくことが歴史的にも証明されているからです。
しかしながら、他方では、「自由」や「人権」と同じように、相手のやっていることの不当性を指摘するためにこの言葉を葵の印籠として用いざるを得ない局面が多々あることも事実です。繰り返しますが、北朝鮮王朝政府や中共独裁政府の勝手な振る舞いに対しては、これらの体制そのものが民の福利にまったく寄与していないという抗議の意味合いを込めて、「民主化せよ、さもなくば体制転覆を覚悟せよ」と訴えることが必要ですし有効でもあります。
たまたま新聞で目にしましたが、ロシアのプーチン政権も情報統制においてずいぶん強硬手段をとっているようです。報道機関として定評のあった国営ロシア通信社RIAノーボスチの解体を一方的に決めたというのです(産経新聞12月19日付)。同日付の北大名誉教授・木村汎氏の論説によれば、ロシアでジャーナリストが客観的な報道に従事するのは命がけで、過去20年間で341人の記者が殺害され、いまだに一人の犯人も捕まっていないそうです。
こういうお国柄(ツァーリズム時代、社会主義時代を通しての伝統)の政権に対しては、報道の自由や、より開かれた民主主義体制の実現を訴えることは大いに意義があります。
また生活の場面でも、エコ・イデオロギー、効率主義イデオロギー、過剰健康主義イデオロギー、「被差別者」特権イデオロギーなどが、当事者の生活感覚を無視して有無を言わせずじわじわと攻め寄せてくるとき、もっと民主的な議論が必要だろう、と感じることがしばしばあるのではないでしょうか。
さらに、この恐ろしく多様化した大衆社会のなかで、国論を少しでも統一させてまともな政治を行なおうとすれば、だれもが最大限民主的な手続きを取らざるを得ません。政策を一つ一つ実行するにあたっても、世論のマジョリティがどの辺にあるかということに何の配慮もしなくてよいとはとても言えないでしょう。権力がなければ政策を実現することはできず、近代民主主義国家の権力は、世論によってこそ支えられるという点を無視できないからです。
民主主義(デモクラシー)というのはデモス(民衆)自身による民衆の支配・統治を意味しますが、もとよりこれは専制政治(オートクラシー)・貴族政治(アリストクラシー)との関係において成り立つ、統治形態の形式的な概念です。別にはじめから葵の印籠であったわけではまったくありません。よい専制政治、よい貴族政治というのも十分考えられるし、現に歴史上ありました。
民主主義の弊害は、早くから気づかれており、プラトンが『国家』のなかで哲人政治を構想したのも、当時のアテナイ社会の衆愚政治に対する批判意識からです。またアリストテレスは、上記三つの政治体制のうち、一応、理念としては民主政治が最もよいが、それが現実に堕落した時には、他の二つに比べて最悪の事態を引き起こすと見抜きました。
十六世紀イタリアの思想家で、『君主論』の著者・マキャヴェッリは、良い統治を成し遂げるための君主の条件について深く考察しましたが、民主政治などという概念は彼の頭の中のどこにもありませんでした。また徳による統治を説いた孔子も、「小人閑居して不善をなす」と言い放ち、君子たるものの条件を力説しています。ニーチェに至っては、民主主義思想などは端的に奴隷のルサンチマンの上に成り立つものでしかなく、オルテガも大衆の支配がいかに人間を堕落させるかについて力説しています。バークのフランス革命に対する徹底的な否定は有名ですね。
少し論理的に考えてみましょう。そもそも民衆自身による民衆の自己統治という、民主主義の根幹をなす概念はおかしいですね。なぜなら、個々の民衆はそれぞれの生活で忙しく、また識見、能力、視野において限界を持つのが当然であって、政治というものが、自分と直接にかかわらない不特定多数者の意思を統合させる仕事である以上、そんな大仕事を民衆のだれかれに任せるわけにはいきません。政治というのはもともと高度な専門職なのです。
もちろん、近代民主主義がこのことをまったくわきまえないわけではありません。ですから、表看板は民主主義とか、国民主権とか謳いながら、現実には間接民主制あるいは代議制という形をとらざるを得ない。つまり近代民主主義のなかにも、選ばれた優れた専門家が実際の統治に当たるという理念は一応生かされてはいるわけです。選挙制度というのが形式的には、そのことを保障しています。
しかし実際には、この制度も候補者の知名度が高いこと、イメージとして「ステキ」に感じられること、地元で勢力を持っていて人気があること、などの情緒的な要因によって規定されてしまうケースが多い。ことに現代のような情報社会においてはそうですね。集団としての「大衆」の多くは、候補者の政治的な力量や思慮深さ、所属政党の政策理念の是非、などをいちいち詳しく検討せず、単なるムードで選びますから。
このよい例が小泉純一郎元総理であり、近いところでは、さる7月の参院選におけるYT氏やAI氏の当選です。この二人がいかにバカであったかは、その後の行動で白日の下にさらされましたね。こういうことが、間接民主制下においても起きるのは、民主政治の担い手が、最終的には国民による直接の「平等な一票」によって決定されてしまうからです。
世の中には、アメリカで理想とされているような直接民主制こそ、一番進んだ政治の理想なのだと考えている浅慮な人士が絶えません。ことにアメリカに負けた戦後日本は、この考え方を助長しました。別にアメリカだって直接民主制を敷いているわけでも何でもない。一見直接民主制に思える大統領選も、その複雑なシステムによって間接民主制を担保しています。
でもあんなに徹底的に負けると、勝った方がなんだか思想的にも道徳的にも優れていたのだという思いを刷り込まれてしまうのですね。いったんそれを刷り込まれたこの人たちにその信念を覆してもらうのはとても難しい。そこで一つのわかりやすい例を出します。
シドニー・ルメット監督、ヘンリー・フォンダ主演の『十二人の怒れる男』という名作があります。この映画は、アメリカの陪審員制度に材を取ったものです。スラム街で父親を殺したという容疑で被告席に立たされた17歳の少年の法廷での審理が決着し、あとは無作為に選ばれた多様な市民で構成される12人の陪審員たちが、有罪か無罪かを巡って密室で議論を交わすというシチュエーションです。陪審員制度では、全員一致でなければ評決が成立せず、いくら議論しても決着がつかなければ、その陪審員は解任されます。
ご承知のようにこの映画では、はじめに投票で評決をはかると、11人が有罪、ただ一人、8号陪審員(ヘンリー・フォンダ)だけが無罪という結果が出ます。それから騒然とした議論が展開し、冷静な8号陪審員が粘り強い努力によって、ひとりひとり「無罪」を増やしていき、最終的に全員無罪を勝ち取ります。この映画のエンターテインメントとしての魅力はいろいろなところにあるのですが、いまはそれについては語りますまい。
ここで指摘したいのは、この映画を不用意に見ると、アメリカの民主主義はなんて素晴らしいんだというふうに勘違いしがちなことです。陪審員制度は、雑多な市民が重大事の決定に当たるので、たしかに直接民主制の典型です。それが見事に一人の少年の命を救うところまで行き着くわけですから、その感動を、政治形態の理想に結びつけたとしても無理もない、と言えるかもしれません。じっさい、登場人物の一人が途中で「この国の強さは民主主義に宿っている」とスピーチする場面もあります。
しかし、ちょっと考えてみましょう。この映画は、論理的に冷静にものを考えることの大切さを訴えてはいますが、けっして政治制度としての「直接民主主義」を肯定しているのではありません。なぜなら、もし8号陪審員がいなかったら、この審理は何の議論もなく5分間で「有罪」の決着がついてしまっていたからです。8号陪審員は、めったにいるはずのないスーパーヒーローです。すると、雑多な市民によって構成される陪審員制度は、当事者たちの都合、気分、根拠なき信念、偏見などによってひとりの人間の運命を決めてしまう公算が極めて強い、ということになるわけです。この映画はよく見れば、そのことがわかるようにきちんと描かれています。
ちなみに現在、アメリカでは、刑事訴訟全案件中、陪審員制度が適用される事案は、わずか1.2%(1999年)に過ぎず、国内でもこの制度に対する批判が高まっており、適用数も年々減少傾向にあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%AA%E5%AF%A9%E5%88%B6#.E7.B5.B1.E8.A8.88
陪審員制度は、ひとりの見知らぬ人間の運命などに真剣に関心を寄せる気がなく、専門家としての職業倫理も持たない人たち(それはそれで当然のことです)の「人民裁判」の典型です。これをなにか、「より進んだ制度」であるかのように考えた一部の戦後日本人がおバカなのです。このようなおバカな人たちの強引な主張によって、日本でも裁判員制度が施行されてきました(陪審員制度よりはその過激さが薄められているのでまだましですが)。まことに敗戦日本のアメリカ万歳の卑屈な精神には嘆かわしいものがあります。
いまこの国の政治勢力の一部には、地域主権、道州制、参議院廃止、首相公選制などを平然と政策理念に掲げている人たちがいます。こういう政策を掲げる人たちは、ただ何となくこれらが中央集権的な政治体制から脱却して、より個々の住民の利害に結びつくように見えるので、「直接民主主義的な理念の実現に近づく」と考えているだけなのではないでしょうか。これらの政策がどんな現実的結果をもたらすかという長期的見通しが何もありません。人間というものを知らない、また、日本という国の歴史的、文化的なまとまりの良さを正当に評価できない、とんでもなく間違った考えです。間接民主制がかろうじてこの間違いの歯止めになっているのです。
そろそろ結論です。
「民主主義」という言葉が現代先進社会のなかでもっている強大な呪力をいまさらなくしてしまうことはできません。さしあたり、右も左も、方便としてこの葵の印籠を大いに使えばいいでしょう。しかし、よりよい社会制度をどう構想していったらよいかという問題としてこれを捉えるなら、「民主主義」という言葉を少しでも肯定的に用いるために、最低限、次の要件を満たす必要があります。
①この制度を金科玉条と思わず、つねに懐疑の精神を失わないこと。
②政治に携わる人は、多数の多様な民の要求・利害をうまく調整して統合するだけの、専門的な能力、豊富な経験、決断力、公共精神を持った「選ばれた」人であること。
③国民は、どういう人がそれに値するかについて、情実やイメージに惑わされず、できるかぎり理性的な判断力を養うこと。
④適切な人が選ばれるために(YT氏やAI氏のような人が選ばれないために)どういう選抜制度が必要であるかについて、智慧を絞ること。ことに「良識の府」と呼ばれる参議院のあり方について見直すこと。
これは必ずしも、平等・普通選挙を必須としません。また評論家・呉智英氏が提唱しているように、選挙人資格を簡単な試験などによる免許制にするというのも一方法だと思います。
⑤議員の選抜に当たっては、その手続きが透明なものとして開かれていること。
こういう要件が本当に満たされると、実際には、私たちがいま抱いている「民主主義」のイメージとは、だいぶ違ったものとなるはずです。私はこれをあえて、「民主的な手続きによる精神的貴族政治(アリストデモクラシー)」と呼びたい。

最後に、最も濫用されている「民主主義」という言葉について触れましょう。自分の立場を正当化し敵対する立場を論難するために、この言葉を盾にしない政治言論は、右から左までほとんどないといってよいくらいです。つまり「民主主義」は現代社会では神聖な葵の印籠と化しているわけですが、しかしそうなると、インフレと同じで、その言葉の価値がどんどん下がってしまいます。どの体制、どの思想が「本当の民主主義」に値するか、まあ、そういう旗の奪い合い、正統争いをやっている光景ですね。
もちろん、この事態に深い疑いを持ち、早くから「民主主義国家」「民主政治」「民主憲法」などの概念を原理的なレベルで批判している数少ない人たちもいます。私はこの人たちを尊敬しています。民主主義はいま、その内的な必然からして、衆愚政治(いわゆるポピュリズム)に堕していく傾向が大いに顕在化しています。そうした状況のなかでは、こうした思想的営みはぜひ必要なことです。というのもこの傾向は、時々の社会経済的条件いかんによって、その急激な危機克服の手段としての全体主義へ結びついていくことが歴史的にも証明されているからです。
しかしながら、他方では、「自由」や「人権」と同じように、相手のやっていることの不当性を指摘するためにこの言葉を葵の印籠として用いざるを得ない局面が多々あることも事実です。繰り返しますが、北朝鮮王朝政府や中共独裁政府の勝手な振る舞いに対しては、これらの体制そのものが民の福利にまったく寄与していないという抗議の意味合いを込めて、「民主化せよ、さもなくば体制転覆を覚悟せよ」と訴えることが必要ですし有効でもあります。
たまたま新聞で目にしましたが、ロシアのプーチン政権も情報統制においてずいぶん強硬手段をとっているようです。報道機関として定評のあった国営ロシア通信社RIAノーボスチの解体を一方的に決めたというのです(産経新聞12月19日付)。同日付の北大名誉教授・木村汎氏の論説によれば、ロシアでジャーナリストが客観的な報道に従事するのは命がけで、過去20年間で341人の記者が殺害され、いまだに一人の犯人も捕まっていないそうです。
こういうお国柄(ツァーリズム時代、社会主義時代を通しての伝統)の政権に対しては、報道の自由や、より開かれた民主主義体制の実現を訴えることは大いに意義があります。
また生活の場面でも、エコ・イデオロギー、効率主義イデオロギー、過剰健康主義イデオロギー、「被差別者」特権イデオロギーなどが、当事者の生活感覚を無視して有無を言わせずじわじわと攻め寄せてくるとき、もっと民主的な議論が必要だろう、と感じることがしばしばあるのではないでしょうか。
さらに、この恐ろしく多様化した大衆社会のなかで、国論を少しでも統一させてまともな政治を行なおうとすれば、だれもが最大限民主的な手続きを取らざるを得ません。政策を一つ一つ実行するにあたっても、世論のマジョリティがどの辺にあるかということに何の配慮もしなくてよいとはとても言えないでしょう。権力がなければ政策を実現することはできず、近代民主主義国家の権力は、世論によってこそ支えられるという点を無視できないからです。
民主主義(デモクラシー)というのはデモス(民衆)自身による民衆の支配・統治を意味しますが、もとよりこれは専制政治(オートクラシー)・貴族政治(アリストクラシー)との関係において成り立つ、統治形態の形式的な概念です。別にはじめから葵の印籠であったわけではまったくありません。よい専制政治、よい貴族政治というのも十分考えられるし、現に歴史上ありました。
民主主義の弊害は、早くから気づかれており、プラトンが『国家』のなかで哲人政治を構想したのも、当時のアテナイ社会の衆愚政治に対する批判意識からです。またアリストテレスは、上記三つの政治体制のうち、一応、理念としては民主政治が最もよいが、それが現実に堕落した時には、他の二つに比べて最悪の事態を引き起こすと見抜きました。
十六世紀イタリアの思想家で、『君主論』の著者・マキャヴェッリは、良い統治を成し遂げるための君主の条件について深く考察しましたが、民主政治などという概念は彼の頭の中のどこにもありませんでした。また徳による統治を説いた孔子も、「小人閑居して不善をなす」と言い放ち、君子たるものの条件を力説しています。ニーチェに至っては、民主主義思想などは端的に奴隷のルサンチマンの上に成り立つものでしかなく、オルテガも大衆の支配がいかに人間を堕落させるかについて力説しています。バークのフランス革命に対する徹底的な否定は有名ですね。
少し論理的に考えてみましょう。そもそも民衆自身による民衆の自己統治という、民主主義の根幹をなす概念はおかしいですね。なぜなら、個々の民衆はそれぞれの生活で忙しく、また識見、能力、視野において限界を持つのが当然であって、政治というものが、自分と直接にかかわらない不特定多数者の意思を統合させる仕事である以上、そんな大仕事を民衆のだれかれに任せるわけにはいきません。政治というのはもともと高度な専門職なのです。
もちろん、近代民主主義がこのことをまったくわきまえないわけではありません。ですから、表看板は民主主義とか、国民主権とか謳いながら、現実には間接民主制あるいは代議制という形をとらざるを得ない。つまり近代民主主義のなかにも、選ばれた優れた専門家が実際の統治に当たるという理念は一応生かされてはいるわけです。選挙制度というのが形式的には、そのことを保障しています。
しかし実際には、この制度も候補者の知名度が高いこと、イメージとして「ステキ」に感じられること、地元で勢力を持っていて人気があること、などの情緒的な要因によって規定されてしまうケースが多い。ことに現代のような情報社会においてはそうですね。集団としての「大衆」の多くは、候補者の政治的な力量や思慮深さ、所属政党の政策理念の是非、などをいちいち詳しく検討せず、単なるムードで選びますから。
このよい例が小泉純一郎元総理であり、近いところでは、さる7月の参院選におけるYT氏やAI氏の当選です。この二人がいかにバカであったかは、その後の行動で白日の下にさらされましたね。こういうことが、間接民主制下においても起きるのは、民主政治の担い手が、最終的には国民による直接の「平等な一票」によって決定されてしまうからです。
世の中には、アメリカで理想とされているような直接民主制こそ、一番進んだ政治の理想なのだと考えている浅慮な人士が絶えません。ことにアメリカに負けた戦後日本は、この考え方を助長しました。別にアメリカだって直接民主制を敷いているわけでも何でもない。一見直接民主制に思える大統領選も、その複雑なシステムによって間接民主制を担保しています。
でもあんなに徹底的に負けると、勝った方がなんだか思想的にも道徳的にも優れていたのだという思いを刷り込まれてしまうのですね。いったんそれを刷り込まれたこの人たちにその信念を覆してもらうのはとても難しい。そこで一つのわかりやすい例を出します。
シドニー・ルメット監督、ヘンリー・フォンダ主演の『十二人の怒れる男』という名作があります。この映画は、アメリカの陪審員制度に材を取ったものです。スラム街で父親を殺したという容疑で被告席に立たされた17歳の少年の法廷での審理が決着し、あとは無作為に選ばれた多様な市民で構成される12人の陪審員たちが、有罪か無罪かを巡って密室で議論を交わすというシチュエーションです。陪審員制度では、全員一致でなければ評決が成立せず、いくら議論しても決着がつかなければ、その陪審員は解任されます。
ご承知のようにこの映画では、はじめに投票で評決をはかると、11人が有罪、ただ一人、8号陪審員(ヘンリー・フォンダ)だけが無罪という結果が出ます。それから騒然とした議論が展開し、冷静な8号陪審員が粘り強い努力によって、ひとりひとり「無罪」を増やしていき、最終的に全員無罪を勝ち取ります。この映画のエンターテインメントとしての魅力はいろいろなところにあるのですが、いまはそれについては語りますまい。
ここで指摘したいのは、この映画を不用意に見ると、アメリカの民主主義はなんて素晴らしいんだというふうに勘違いしがちなことです。陪審員制度は、雑多な市民が重大事の決定に当たるので、たしかに直接民主制の典型です。それが見事に一人の少年の命を救うところまで行き着くわけですから、その感動を、政治形態の理想に結びつけたとしても無理もない、と言えるかもしれません。じっさい、登場人物の一人が途中で「この国の強さは民主主義に宿っている」とスピーチする場面もあります。
しかし、ちょっと考えてみましょう。この映画は、論理的に冷静にものを考えることの大切さを訴えてはいますが、けっして政治制度としての「直接民主主義」を肯定しているのではありません。なぜなら、もし8号陪審員がいなかったら、この審理は何の議論もなく5分間で「有罪」の決着がついてしまっていたからです。8号陪審員は、めったにいるはずのないスーパーヒーローです。すると、雑多な市民によって構成される陪審員制度は、当事者たちの都合、気分、根拠なき信念、偏見などによってひとりの人間の運命を決めてしまう公算が極めて強い、ということになるわけです。この映画はよく見れば、そのことがわかるようにきちんと描かれています。
ちなみに現在、アメリカでは、刑事訴訟全案件中、陪審員制度が適用される事案は、わずか1.2%(1999年)に過ぎず、国内でもこの制度に対する批判が高まっており、適用数も年々減少傾向にあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%AA%E5%AF%A9%E5%88%B6#.E7.B5.B1.E8.A8.88
陪審員制度は、ひとりの見知らぬ人間の運命などに真剣に関心を寄せる気がなく、専門家としての職業倫理も持たない人たち(それはそれで当然のことです)の「人民裁判」の典型です。これをなにか、「より進んだ制度」であるかのように考えた一部の戦後日本人がおバカなのです。このようなおバカな人たちの強引な主張によって、日本でも裁判員制度が施行されてきました(陪審員制度よりはその過激さが薄められているのでまだましですが)。まことに敗戦日本のアメリカ万歳の卑屈な精神には嘆かわしいものがあります。
いまこの国の政治勢力の一部には、地域主権、道州制、参議院廃止、首相公選制などを平然と政策理念に掲げている人たちがいます。こういう政策を掲げる人たちは、ただ何となくこれらが中央集権的な政治体制から脱却して、より個々の住民の利害に結びつくように見えるので、「直接民主主義的な理念の実現に近づく」と考えているだけなのではないでしょうか。これらの政策がどんな現実的結果をもたらすかという長期的見通しが何もありません。人間というものを知らない、また、日本という国の歴史的、文化的なまとまりの良さを正当に評価できない、とんでもなく間違った考えです。間接民主制がかろうじてこの間違いの歯止めになっているのです。
そろそろ結論です。
「民主主義」という言葉が現代先進社会のなかでもっている強大な呪力をいまさらなくしてしまうことはできません。さしあたり、右も左も、方便としてこの葵の印籠を大いに使えばいいでしょう。しかし、よりよい社会制度をどう構想していったらよいかという問題としてこれを捉えるなら、「民主主義」という言葉を少しでも肯定的に用いるために、最低限、次の要件を満たす必要があります。
①この制度を金科玉条と思わず、つねに懐疑の精神を失わないこと。
②政治に携わる人は、多数の多様な民の要求・利害をうまく調整して統合するだけの、専門的な能力、豊富な経験、決断力、公共精神を持った「選ばれた」人であること。
③国民は、どういう人がそれに値するかについて、情実やイメージに惑わされず、できるかぎり理性的な判断力を養うこと。
④適切な人が選ばれるために(YT氏やAI氏のような人が選ばれないために)どういう選抜制度が必要であるかについて、智慧を絞ること。ことに「良識の府」と呼ばれる参議院のあり方について見直すこと。
これは必ずしも、平等・普通選挙を必須としません。また評論家・呉智英氏が提唱しているように、選挙人資格を簡単な試験などによる免許制にするというのも一方法だと思います。
⑤議員の選抜に当たっては、その手続きが透明なものとして開かれていること。
こういう要件が本当に満たされると、実際には、私たちがいま抱いている「民主主義」のイメージとは、だいぶ違ったものとなるはずです。私はこれをあえて、「民主的な手続きによる精神的貴族政治(アリストデモクラシー)」と呼びたい。