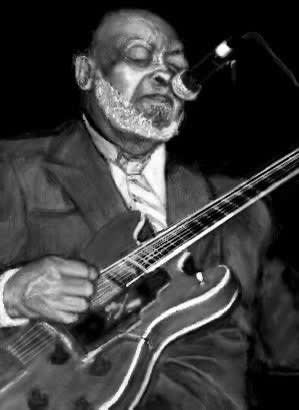2024年6月15日(土)
#436 スリム・ハーポ「Baby Scratch My Back」(Exello)
#436 スリム・ハーポ「Baby Scratch My Back」(Exello)

スリム・ハーポ、1965年リリースのシングル・ヒット曲。ジェイムズ・ムーア(ハーポの本名)の作品。ジョセフ・D・ミラーによるプロデュース。
米国のブルースマン、スリム・ハーポは本名ジェイムズ・アイザック・ムーアといい、1924年11月ルイジアナ州ロプデル生まれ。幼少期よりラジオから流れるブルースに親しみ、ハーモニカを吹くようになる。特にブラインド・レモン・ジェファースンを愛聴していた。
18歳の頃、ムーアは生家を出て同州ニューオリンズに出て港湾労働者をしていた。その後地元に戻って建設作業員をするかたわら、同州バトンルージュのバー、路上などで演奏活動を始め、ハーモニカ・スリムのステージネームを使うようになる。
ムーアはバトンルージュで活動していたブルースマン、ライトニン・スリム(本名・オーティス・ヴェリーズ・ヒックス、1913年生まれ)が義理の兄弟となったことにより、彼のツアーにも帯同する。
また55年にはライトニン・スリムの紹介でエクセロレーベルのプロデューサー、J・D・ミラーとも知り合い、サイドマンとしてライトニン・スリムのレコーディングにも参加する。
57年、ムーアはエクセロで自身名義の初のレコーディングを行う。デビューにあたって、ハーモニカ・スリムという名のアーティストがすでにいることを知らされ、妻ラヴェルの提案によりスリム・ハーポに芸名を変更する。ハーポとはハープ(ハーモニカ)のなまりである。
デビュー・シングルは同年リリースの「I’m A King Bee / Got Love If You Want It」。以降、「Rainin’ In My Heart」(1961年)をはじめとする何枚ものシングルをリリースしたが、最大級のヒットが本日取り上げた一曲「Baby Scratch My Back」である。
レコードデビューしたものの、1960年代前半のムーアはまだ専業ミュージシャンではなく、トラックの運転手をして生計を立てていた。ライブやレコードの売り上げだけでは到底食べていけなかったのだ。
だが、彼の曲は次第に世間に浸透するようになっていた。その顕著な現れは、幾つもの英国のロック・バンドが彼のナンバーをカバーするようになってきたことである。
例えば、ヤードバーズは64年リリースのデビュー・ライブ・アルバムで「Got Love If You Want It」をカバーしている。同曲は、同年キンクスもデビュー・アルバムでカバーしている。また、「I’m A King Bee」はローリング・ストーンズが64年リリースのデビュー・アルバムでカバーしている。
英国の代表的なビート・グループが、こぞってスリム・ハーポという米国のブルースマンに注目するようになってきたのだ。
その機運の中、スリム・ハーポは「Baby Scratch My Back」をリリースする。本曲はほとんど歌らしい歌を含んでおらず、インストゥルメンタルに時おり彼のモノローグとハープ演奏が入るという、ちょっと変わった構成である。トレモロ全開のギター、マラカスといったバックのサウンドが印象的だ。
にもかかわらず、本曲はメチャ受けする。全米16位、R&Bチャート1位を獲得、スリム・ハーポ最大のヒット曲となった。
今思うに、この曲はダンス・ナンバーとして最適だったのだろうな。ほどよく緩いテンポで、踊り易いのが、抜群にウケた理由ではないかと思う。
スリム・ハーポ自身はこの曲について「自分にとってのロックンロールへの試み」と語っていたという。自分の曲が海の向こうで予想外の人気を獲得していることを知り、自分の音楽が単なる黒人のための音楽ではなく、世界的にアピールするのではという野心が生まれて来た、そういうことなのだろう。
その後、この大ヒット曲のカバーは黒人・白人両方から何曲も生まれた。
ブルース畑でいえば、ヒット後間もない66年にフランク・フロスト(ジェリー・ロール・キングスのフロントマン)が「My Back Scratcher」と改題してシングルリリース、R&Bチャートで43位を獲得して、彼唯一のヒットとなった。
ソウル畑にも、流行は波及した。同年、人気ソウル・シンガー、オーティス・レディングはブッカー・T &MG’Sをバックにレコーディングしたアルバム「The Soul Album」の中で「Scratch My Back」のタイトルで本曲をカバーしている。また、MG’S単体でのインスト・バージョンもレコードになっている。
ロック畑の代表格は、ヤードバーズだろう。彼らの66年7月リリースのアルバム「Roger The Engineer」では、「Rack My Mind」というタイトルでオリジナルの歌詞をつけたナンバーとしてカバーしている(クレジットはメンバー5人)。
また同年レコーディングした「BBC Sessions」では、スリム・ハーポの作品として、原曲通りのタイトルでカバーしている。歌詞を持つ「うた」としてこの曲を再構築したのは、彼らと言っていいだろう。
スリム・ハーポの狙い通り、ブルースというよりはロックンロールとして、この曲は世間に認知され、黒人と白人の垣根を越えて幅広くアピールした。
ルイジアナ・ブルースならではのゆるいノリが、英米の人々の好みに見事ハマって、ビッグ・ヒットとなった一曲。
ヒットソングの世界は、どこから伏兵が登場するか、分からない。片田舎のバトンルージュからだって、ニュー・ヒーローは生まれる。これだから、チャート・ウォッチングはやめられない。