
topフォトは楼門 この建物は天正17年(1589年)豊臣秀吉の造営とされています
1月中旬、京都に出かけていた
前日まで京都の積雪状況をTVでみながら、寒さ対策をし雪景色の京の都、神社参詣の旅へ
最強の寒波を肌身に感じながら、早朝の伏見稲荷大社からスタート
千本鳥居に代表される朱の鳥居が観光スポットとして著名になったことから
多くの外国人が稲荷三峯の辺りまでお参りする人が多くなった、そうだ
一ノ峯・二ノ峯・三ノ峯とは
その昔、イナリ神が降臨したとされる峯として、イナリ信仰の原点ともいうべき神蹟で、上社・中社・下社とも呼ばれる
お山巡拝所要時間約2時間とあるが、廻り方では2・3時間を要するらしい
今日は悪路なので慎重にお山巡拝します

本殿

御祭神
宇迦之御魂大神(うかのみたまのおおかみ) - 下社(中央座)
佐田彦大神(さたひこのおおかみ)- 中社(北座)
大宮能売大神(おおみやのめのおおかみ) - 上社(南座)
田中大神(たなかのおおかみ) - 下社摂社(最北座)
四大神 (しのおおかみ) - 中社摂社(最南座)
「お稲荷さん」は、元々は稲の字があることでも分かるように、五穀豊穣を祈ったのではないだろうかと言われています
お狐さんが咥えているアイテムには「玉(宝珠)」「鍵」「巻物」「稲」「子キツネ」・・など色々ありますが、
「玉(宝珠)」は霊の力、「鍵」はその霊力を引出すカギ、
「巻物」は神様からのお言葉、
「稲」は富、子キツネは「子宝」などを象徴しているのではないかと言われています

手水舎


幻想的な雰囲気を味わうことができます千本鳥居方向へ

お山巡り入口
千本鳥居のある辺りは神の降臨地である山の入り口にもあたり
現世から神様のいる幽界へと続く門として多くの鳥居が建てられたのが始まりとされています
また、これらの鳥居は江戸~明治時代、参拝者の奉納により建てられたそうです

千本鳥居
赤い鳥居と言えば、すぐさま人々は「おいなりさん」を連想します
この稲荷の鳥居は社殿と同じく「稲荷塗」といわれ、朱をもって彩色するのが習慣となっている
この「あけ」という言葉は、赤・明・茜など、すべてに明るい希望の気持ちをその語感ににもち
その色はまた生命・大地・生産の力をもって稲荷大神の「みたま」の働きとする強烈な信仰が宿っている
=伏見稲荷大社HP
鳥居を奉納するのは、「願いが通るように」という素朴な願いからといわれ、
千本鳥居をはじめとして稲荷山中の鳥居は大小を問わず信者から奉納されたものという。
鳥居の柱には奉納者の氏名(会社名)・住所・年月日などが墨書されている。
平成になってのそれも多々見うけられ、遠隔地のものもあり、時代・地域を超えた稲荷信仰の広がりを示している。

千本鳥居・内部

奥社社殿
千本鳥居を出た辺りから積雪が目立つようになった


おもかる石
この場所で願いごとをしてから石を持ち上げ
持ち上げたときに感じる重さが想像より軽ければ願い事が叶い、重ければ叶わないとされています

稲荷塚

根上がり松
松の木をご神木とする拝所だったようで、かつて2本の幹が片方がもち上がって連なっていたことから
この松は、ネアガリとの呼称から投資家達から崇敬を集め、また、その下を潜ると神経痛や肩こりに効用があるとの俗信があったという


ややこの辺りから本格的な上り坂になります





新池 谺ケ池(こだまがいけ)

熊鷹社
朱の玉垣の向こうに緑の山影を映す池は新池、谺ケ池(こだまがいけ)との別称があります
行方知れずになった人の居場所を探す時
池に向かって手を打ち、こだまが返ってきた方向に手がかりがつかめると云う言い伝えがあります
池に突き出た石積みに拝所が設けられ、熊鷹大神の御塚が鎮まっています
=伏見稲荷大社HP=

三ッ辻を越え、三徳社あたりでしょうか
まだ早くてお茶屋さんは開いていませんでした




階段は凍って滑りやすく、本格的な山登り?になります(*´Д`)


京都市内が一望

冬登山と同じような・・・のぼり

二ノ峯(中之社神蹟)

ようやく一ノ峯(稲荷山山頂)が見えてきました





一ノ峯山頂(上之社神蹟) 標高233m

足元も悪く信仰心には程遠いいですが、朱の鳥居を目指し階段を上って、、、
早朝でしたので、観光者も少なく独り占めのような参詣でした

= 御朱印 =























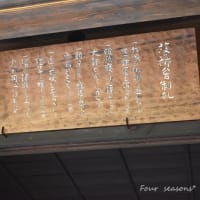







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます