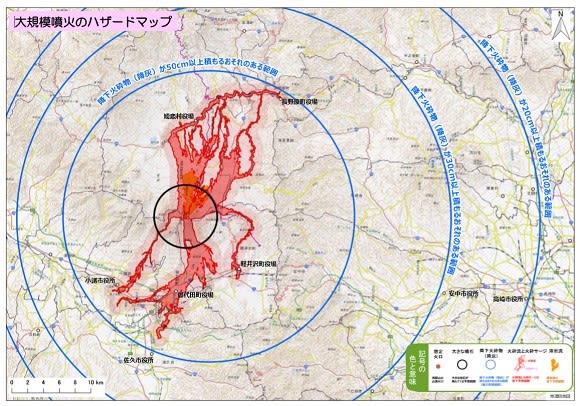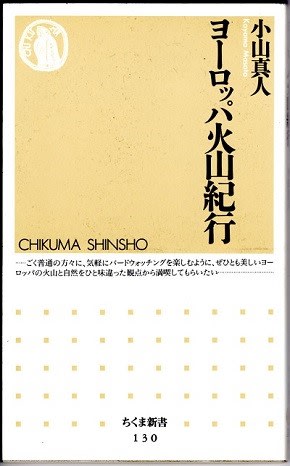前回に続いて北軽井沢で7月下旬に撮影した蝶を紹介させていただく。
最初はトラフシジミ。前翅長16~21mm。本州の寒冷地では年1回の発生、暖地では年2回発生し、春型(4~5月)と夏型(7~8月)があるとされる。食草はフジ、クズ、ハリエンジュ、ウツギ、ノイバラなど。蛹で越冬する。
このチョウにも今回は2日とも出会うことができた。7月17日が私にとっては初めてのトラフシジミとの出会いであったが、その姿は図鑑などでよく知っているものであったので、すぐにそれと判った。その時は、写真を1-2枚撮影したところで、飛び去ってしまい、満足のゆく撮影はできなかった。2回目の24日は複数の個体が見られ、スジボソヤマキチョウや数種類のヒョウモン類などと共に、夢中になってオカトラノオの花で吸蜜しているところであったので、ゆっくりと撮影することができた。
翅はずっと閉じていたので、翅表の写真は撮ることができなかったが、飛び立つ時にチラと青い色を確認することができた。雌雄の判別は、翅表にある性標で行えるとされているが、そのようなわけで、翅裏だけからでは難しく、できていない。
撮影日が7月17日と24日ということで、夏型発生の時期であるが、写真で見ると7月17日に撮影したものの翅裏の色はやや春型に近いように見える。24日に撮影したものは夏型特有の翅色を持っている。
ところで、トラフシジミの2つの型については、いつもの「原色日本蝶類図鑑」(横山光夫著 1964年保育社発行)には次のような興味深い記述がある。
「・・・この2つの型は同じ雌によって産卵されて蛹化し、その一部は第2化の夏型として現われ、残りの一部は蛹のまま夏から秋・冬を越して翌春発生する。・・・本種のように同時に行われた産卵によって発生が1回と2回の混合というのは極めて珍しい例といえる。」
「信州 浅間山麓と東信の蝶」には次のように紹介されている。「長野県ではほぼ全域の山麓部平地から山地にかけ分布し、生息域も比較的広い。東信地方でも普遍的に生息し、樹林地林縁部などで比較的よく見られる。平地、低山地では開発などの影響を受けることもあるが、目立った個体数の増減は認められない。」

葉上で休息するトラフシジミ夏型1/8(2019.7.17 撮影)

葉上で休息するトラフシジミ夏型2/8(2019.7.24 撮影)

草の間を動き回るトラフシジミ夏型3/8(2019.7.24 撮影)

草の間を動き回るトラフシジミ夏型4/8(2019.7.24 撮影)

ヒメジョオンで吸蜜するトラフシジミ夏型5/8(2019.7.24 撮影)

葉上で休息するトラフシジミ夏型6/8(2019.7.24 撮影)

草の間を動き回るトラフシジミ夏型7/8(2019.7.24 撮影)

草の間を動き回るトラフシジミ夏型8/8(2019.7.24 撮影)
次はウラゴマダラシジミ。前翅長17~25mm。年1回の発生で、食草はイボタノキ、ミヤマイボタなど。卵で越冬する。
この種もまた、私には今回初めて見るものであった。
草原を取り巻く林辺の高木の枝の周りを飛び回っている小さい白い蝶を目で追っていると、やがて下のほうの枝先にとまり、長い間そこにとどまってくれたので、じっくり撮影することができた。それがこのウラゴマダラシジミであった。その後枝先から飛び立って、少し離れた場所にある白い花に止まり吸蜜を始めた。
このチョウは、ゼフィルス類の筆頭に挙げられることが多いようであるが、尾状突起もなく他のミドリシジミ類とは外観が大きく異なっていて、何故?と思ってしまう。前出のカラスシジミの方がよほどゼフィルスに相応しい翅裏の紋様を持っている。
このチョウについての「信州 浅間山麓と東信の蝶」の記述は次のようである。「長野県では山麓部平地から山地にかけて、ほぼ全域に生息する。東信地方でも普遍的に見られるが、減少した産地も聞かれる。里山のチョウであり、開発や雑木林の荒廃は、本種の発生にも影響すると考えられる。」
このチョウもまた、翅を閉じたままであったので、翅表の写真はない。前翅の形状の丸みが強いことから雌ではないかと判断している。

枝先にとまるウラゴマダラシジミ1/4(2019.7.24 撮影)

枝先にとまるウラゴマダラシジミ2/4(2019.7.24 撮影)

枝先にとまるウラゴマダラシジミ3/4(2019.7.24 撮影)

花にとまり吸蜜を始めたウラゴマダラシジミ4/4(2019.7.24 撮影)
次は、スジボソヤマキチョウ。前翅長28~40mm。年1回の発生で、6月下旬頃から羽化する。盛夏は活動を休止して越夏し、秋に一時的に活動して成虫越冬する。越冬個体は翌春、4月頃から活動を開始し、産卵行動をとり、5月頃まで見られる。食草はクロウメモドキ、クロツバラ。
この種は、比較的よく見かける種で、これまでにも何度も草原で出会い、撮影もしている。また、白糸の滝に出かけたときに、観光客の周りを飛んでいるのを目撃したこともある。今回は車道を走っている時に道路わきのアカツメクサに止まっている個体を見つけて、その場で車を停めて撮影した。その後、駐車場に車を停めて登って行った丘の上の遊歩道沿いに咲いているオカトラノオの花で吸蜜中の個体を見つけ撮影した。
ヤマキチョウに酷似していて、素人目には両種の区別が付きにくいが、独特の翅形状を持つので、この2種以外との差は明瞭。前出の本「信州 浅間山麓と東信の蝶」には両者がそれぞれ、次のように記されていて、ヤマキチョウの方は減少が顕著である。
「ヤマキチョウは、長野県では中部を中心に低山地から高原にかけて生息するが、東信地方を含め産地、個体数は減少しており、近年の記録も少ない。環境省版、長野県版ともレッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に区分されている。」
「スジボソヤマキチョウは、長野県では全域で山麓部平地から山地にかけて生息している。東信地方でも広く確認されており、比較的普通に見られるものの、開発等で個体数が減少している産地もある。」
両種の幼虫の食草は共にクロツバラが挙げられているので、減少傾向に大きな差があるのは不思議な気もするが、スジボソヤマキチョウの方は、クロウメモドキも食草としているので、食草に対する選択股の多寡が生息個体数の差になっているのかもしれない。

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂1/5(2019.7.24 撮影)

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂2/5(2019.7.24 撮影)

アカツメクサの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂3/5(2019.7.24 撮影)

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂4/5(2019.7.24 撮影)

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂5/5(2019.7.24 撮影)

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂とヒョウモンチョウ1/2(2019.7.24 撮影)

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂とヒョウモンチョウ2/2(2019.7.24 撮影)
スジボソヤマキチョウとヤマキチョウの同定ポイントは、前翅の尖り具合とされている。今回撮影した種は、スジボソヤマキチョウと見てよさそうである。雌雄の別については、ピントははずれてしまったが、飛び立つ姿を捉えることができて、黄色い翅表が見えるので、雄と判定できる。

飛翔するスジボソヤマキチョウ♂(2019.7.24 撮影)
今回はお目にかかることができなかったヤマキチョウの方だが、「信州 浅間山麓と東信の蝶」の巻頭寄稿「舞姫たちよ、永遠に!」の中の、「今、ヤマキチョウに熱い」で故鳩山邦夫氏は次のように記している。
「最近、私が少し熱くなっているのがヤマキチョウ、・・・。東御市地籍の浅間山麓へ車を向かわせたところ、何とヤマキチョウの♀とスレちがう幸運に出会ったのである。ときは2012年5月16日のこと。越冬したヤマキチョウの♂が3頭で広大なテリトリーを全く止まることなく飛翔をくり返す光景に感動した。・・・
ヤマキチョウ。かつて地蔵ヶ原とも呼ばれた軽井沢の湿性草原に、このチョウはそれこそ山ほどいて、越冬前の個体は飛んでもすぐ止まるので、小学2~3年生の私には、もっとも採りやすいチョウであった。
Nさんと知り合った頃は、彼の案内で何ヶ所も佐久地方のヤマキ産地へ行って採集した。もちろん母チョウに産卵させて大量飼育に成功もしている。
では軽井沢町のヤマキチョウはどうなったのだろうか。巨大なゴルフ場が次々とできて、昔の産地は完全につぶれている。そこで1980年ごろ、ゴルフ場の脇を探したところ、たしかに数頭のヤマキチョウを見出したが、減りゆくチョウは採るべきでないと考え全く採集しなかったのが、今では残念に思う。そしてそれが軽井沢地籍のヤマキと私の最後の出会いとなってしまっている。この2年ばかり、南軽井沢や1000メートル林道でクロツバラを見つけて卵や幼虫を探してみたが、成果ゼロが続いている。軽井沢町のヤマキチョウは、かなりシビアーな状況にちがいない。でも、どこかには生き残っていることを祈りたい。」
私はまだ見たことのないヤマキチョウ。軽井沢のどこかで出会うことができるだろうか。
以下、次回。
最初はトラフシジミ。前翅長16~21mm。本州の寒冷地では年1回の発生、暖地では年2回発生し、春型(4~5月)と夏型(7~8月)があるとされる。食草はフジ、クズ、ハリエンジュ、ウツギ、ノイバラなど。蛹で越冬する。
このチョウにも今回は2日とも出会うことができた。7月17日が私にとっては初めてのトラフシジミとの出会いであったが、その姿は図鑑などでよく知っているものであったので、すぐにそれと判った。その時は、写真を1-2枚撮影したところで、飛び去ってしまい、満足のゆく撮影はできなかった。2回目の24日は複数の個体が見られ、スジボソヤマキチョウや数種類のヒョウモン類などと共に、夢中になってオカトラノオの花で吸蜜しているところであったので、ゆっくりと撮影することができた。
翅はずっと閉じていたので、翅表の写真は撮ることができなかったが、飛び立つ時にチラと青い色を確認することができた。雌雄の判別は、翅表にある性標で行えるとされているが、そのようなわけで、翅裏だけからでは難しく、できていない。
撮影日が7月17日と24日ということで、夏型発生の時期であるが、写真で見ると7月17日に撮影したものの翅裏の色はやや春型に近いように見える。24日に撮影したものは夏型特有の翅色を持っている。
ところで、トラフシジミの2つの型については、いつもの「原色日本蝶類図鑑」(横山光夫著 1964年保育社発行)には次のような興味深い記述がある。
「・・・この2つの型は同じ雌によって産卵されて蛹化し、その一部は第2化の夏型として現われ、残りの一部は蛹のまま夏から秋・冬を越して翌春発生する。・・・本種のように同時に行われた産卵によって発生が1回と2回の混合というのは極めて珍しい例といえる。」
「信州 浅間山麓と東信の蝶」には次のように紹介されている。「長野県ではほぼ全域の山麓部平地から山地にかけ分布し、生息域も比較的広い。東信地方でも普遍的に生息し、樹林地林縁部などで比較的よく見られる。平地、低山地では開発などの影響を受けることもあるが、目立った個体数の増減は認められない。」

葉上で休息するトラフシジミ夏型1/8(2019.7.17 撮影)

葉上で休息するトラフシジミ夏型2/8(2019.7.24 撮影)

草の間を動き回るトラフシジミ夏型3/8(2019.7.24 撮影)

草の間を動き回るトラフシジミ夏型4/8(2019.7.24 撮影)

ヒメジョオンで吸蜜するトラフシジミ夏型5/8(2019.7.24 撮影)

葉上で休息するトラフシジミ夏型6/8(2019.7.24 撮影)

草の間を動き回るトラフシジミ夏型7/8(2019.7.24 撮影)

草の間を動き回るトラフシジミ夏型8/8(2019.7.24 撮影)
次はウラゴマダラシジミ。前翅長17~25mm。年1回の発生で、食草はイボタノキ、ミヤマイボタなど。卵で越冬する。
この種もまた、私には今回初めて見るものであった。
草原を取り巻く林辺の高木の枝の周りを飛び回っている小さい白い蝶を目で追っていると、やがて下のほうの枝先にとまり、長い間そこにとどまってくれたので、じっくり撮影することができた。それがこのウラゴマダラシジミであった。その後枝先から飛び立って、少し離れた場所にある白い花に止まり吸蜜を始めた。
このチョウは、ゼフィルス類の筆頭に挙げられることが多いようであるが、尾状突起もなく他のミドリシジミ類とは外観が大きく異なっていて、何故?と思ってしまう。前出のカラスシジミの方がよほどゼフィルスに相応しい翅裏の紋様を持っている。
このチョウについての「信州 浅間山麓と東信の蝶」の記述は次のようである。「長野県では山麓部平地から山地にかけて、ほぼ全域に生息する。東信地方でも普遍的に見られるが、減少した産地も聞かれる。里山のチョウであり、開発や雑木林の荒廃は、本種の発生にも影響すると考えられる。」
このチョウもまた、翅を閉じたままであったので、翅表の写真はない。前翅の形状の丸みが強いことから雌ではないかと判断している。

枝先にとまるウラゴマダラシジミ1/4(2019.7.24 撮影)

枝先にとまるウラゴマダラシジミ2/4(2019.7.24 撮影)

枝先にとまるウラゴマダラシジミ3/4(2019.7.24 撮影)

花にとまり吸蜜を始めたウラゴマダラシジミ4/4(2019.7.24 撮影)
次は、スジボソヤマキチョウ。前翅長28~40mm。年1回の発生で、6月下旬頃から羽化する。盛夏は活動を休止して越夏し、秋に一時的に活動して成虫越冬する。越冬個体は翌春、4月頃から活動を開始し、産卵行動をとり、5月頃まで見られる。食草はクロウメモドキ、クロツバラ。
この種は、比較的よく見かける種で、これまでにも何度も草原で出会い、撮影もしている。また、白糸の滝に出かけたときに、観光客の周りを飛んでいるのを目撃したこともある。今回は車道を走っている時に道路わきのアカツメクサに止まっている個体を見つけて、その場で車を停めて撮影した。その後、駐車場に車を停めて登って行った丘の上の遊歩道沿いに咲いているオカトラノオの花で吸蜜中の個体を見つけ撮影した。
ヤマキチョウに酷似していて、素人目には両種の区別が付きにくいが、独特の翅形状を持つので、この2種以外との差は明瞭。前出の本「信州 浅間山麓と東信の蝶」には両者がそれぞれ、次のように記されていて、ヤマキチョウの方は減少が顕著である。
「ヤマキチョウは、長野県では中部を中心に低山地から高原にかけて生息するが、東信地方を含め産地、個体数は減少しており、近年の記録も少ない。環境省版、長野県版ともレッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に区分されている。」
「スジボソヤマキチョウは、長野県では全域で山麓部平地から山地にかけて生息している。東信地方でも広く確認されており、比較的普通に見られるものの、開発等で個体数が減少している産地もある。」
両種の幼虫の食草は共にクロツバラが挙げられているので、減少傾向に大きな差があるのは不思議な気もするが、スジボソヤマキチョウの方は、クロウメモドキも食草としているので、食草に対する選択股の多寡が生息個体数の差になっているのかもしれない。

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂1/5(2019.7.24 撮影)

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂2/5(2019.7.24 撮影)

アカツメクサの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂3/5(2019.7.24 撮影)

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂4/5(2019.7.24 撮影)

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂5/5(2019.7.24 撮影)

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂とヒョウモンチョウ1/2(2019.7.24 撮影)

オカトラノオの花で吸蜜するスジボソヤマキチョウ♂とヒョウモンチョウ2/2(2019.7.24 撮影)
スジボソヤマキチョウとヤマキチョウの同定ポイントは、前翅の尖り具合とされている。今回撮影した種は、スジボソヤマキチョウと見てよさそうである。雌雄の別については、ピントははずれてしまったが、飛び立つ姿を捉えることができて、黄色い翅表が見えるので、雄と判定できる。

飛翔するスジボソヤマキチョウ♂(2019.7.24 撮影)
今回はお目にかかることができなかったヤマキチョウの方だが、「信州 浅間山麓と東信の蝶」の巻頭寄稿「舞姫たちよ、永遠に!」の中の、「今、ヤマキチョウに熱い」で故鳩山邦夫氏は次のように記している。
「最近、私が少し熱くなっているのがヤマキチョウ、・・・。東御市地籍の浅間山麓へ車を向かわせたところ、何とヤマキチョウの♀とスレちがう幸運に出会ったのである。ときは2012年5月16日のこと。越冬したヤマキチョウの♂が3頭で広大なテリトリーを全く止まることなく飛翔をくり返す光景に感動した。・・・
ヤマキチョウ。かつて地蔵ヶ原とも呼ばれた軽井沢の湿性草原に、このチョウはそれこそ山ほどいて、越冬前の個体は飛んでもすぐ止まるので、小学2~3年生の私には、もっとも採りやすいチョウであった。
Nさんと知り合った頃は、彼の案内で何ヶ所も佐久地方のヤマキ産地へ行って採集した。もちろん母チョウに産卵させて大量飼育に成功もしている。
では軽井沢町のヤマキチョウはどうなったのだろうか。巨大なゴルフ場が次々とできて、昔の産地は完全につぶれている。そこで1980年ごろ、ゴルフ場の脇を探したところ、たしかに数頭のヤマキチョウを見出したが、減りゆくチョウは採るべきでないと考え全く採集しなかったのが、今では残念に思う。そしてそれが軽井沢地籍のヤマキと私の最後の出会いとなってしまっている。この2年ばかり、南軽井沢や1000メートル林道でクロツバラを見つけて卵や幼虫を探してみたが、成果ゼロが続いている。軽井沢町のヤマキチョウは、かなりシビアーな状況にちがいない。でも、どこかには生き残っていることを祈りたい。」
私はまだ見たことのないヤマキチョウ。軽井沢のどこかで出会うことができるだろうか。
以下、次回。